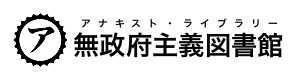大杉栄
意志の教育
マクス・スティルナーの教育論
一
近代個人主義の先駆者マクス・スティルナーの人物およびその中心思想については、僕の『生の闘争』の中に再録された『近代思想』第一巻第三号の「唯一者」によって、すでに大体の紹介をして置いた。そして僕は、その紹介の最後の項に、つぎの意味のことを言った。 スティルナーの名著『唯一者とその財産』は、四十年間図書館の書棚の隅の方に、誰見るものもなく塵の中に埋もれていた。けれども思想は進む。やがてこの知られざりし孤独者が、近代のもっとも強烈なる個人主義思想の先駆者であると、認められて来た。そして今日なお人々の求めている定式の正確な言葉が、彼の中に見出されたと。 この正確な言葉は『唯一者とその財産』のみならず、なおその公けにした最初の論文たる「現代教育の首要原則、人道主義と現実主義」の中にも、同様に見出すことができる。そしてまたこの少年教育論は、やがて一種の青年教育論となった彼の『唯一者』の、はなはだ健全なる嫩芽であった。僕は、この二つの意味から、この教育論を紹介することに、かなり大きい興味を持つ。 「現代教育の首要原則」は一八四二年四月、近世科学的社会主義の祖カール・マルクスの主宰する『ライン新聞』に現れた。 スティルナーはまず、教育学のはなはだ重要なることを説き、Die schulfrage ist eine Lebensfrage(教育問題は人生問題である)とまで論じて、教育学者の間には、まったく矛盾する二個の教育原則、すなわち人道主義と現実主義とが、昔も今も相争われている事実を指摘している。人道主義とは、今日の言葉で言えば、古典教育法である。また現実主義とは近世教育法である。 宗教改革の頃までは、教育と言えば、人道主義の外はなかった。しかし宗教改革から大革命までの間は、主人と奴隷、有力者と無力者、成年者と幼年者の関係が社会を支配した、スティルナーのいわゆる「奴隷の時代」であった。この時代には、教育は一種の権力となって、それを受けたものが、受けないものの上に権威を有する、強者となった。しかし権威はあらゆる人々に持たすことができないので、したがってこの権威の理由であり方法である教育もまた普遍的のものとすることはできなかった。そしてこの権威を倒して、奴隷と主人との制度を破壊し、各人が自らの主人になるという原則を打建てたのが、実にフランス大革命であった。その必然の結果として、教育は普遍的のものとならなければならなかった。しかるに教育を少数者の特権として見る旧い独占論者等は、いきおいこの傾向に対して反抗の声を挙げることとなった。かくしてこの二つの傾向の間の闘争が、今日まで継続されて来たのである。
二
されば十八世紀のいわゆる「光明時代」以前には、教育はまったく人道主義者の掌中にあって、ただ聖書と古典との研究をのみその仕事としていた。人間の生活は、美のモデルや真理の法則を提供するというような、興味深いまた諧調に富んだものではなかった。教育は、ただ社会的優越の方法または支配の道具としてのみ見做され、したがってまったく形式的のものであった。その古典から求めたところのものは、ただ文学や美術の形式であり、図式であった。そしてまた、この教育から求めたところのものは、ただ社会上の形式的優越であった。感情の繊細、趣味の高雅、会話の流麗、動作の端麗、要するにただこれらの形式の上の優越であった。 しかるに「光明時代」以来、一方には、人権の普遍的であることが認められ、したがって教育はあらゆる人々に施さるべきものであると主張された。そして他方には、従来の教育の真価値が疑われて、実用的でなければならぬという議論が出て来た。かくして人道主義の形式教育に対する反抗が現れ出した。芸術の形式などはどうでもいい。生活の材料を得なければならぬ。学校は活動的生活の準備でなければならぬ。いっさいの知識を獲得して、すべての人々が何事にも主人となる能力を与えられなければならぬ。これがこの現実主義の合言葉であった。かくして新しき教育学者等は、人権の原則たる平等が、教育のすべての人に施されるということにおいて、また人権の他の原則たる自由が、あらゆる知識を得て事物の主人になるということにおいて、教育の上にも適用されんことを要求した。
この二個の教育原則は、その性質においてもまた目的においてもかくはなはだ矛盾したものであるが、しかもなおその間にある共通点があった。すなわち過去を理解せんとする人道主義と、現在を左右せんとする現実主義とは、いずれもみな単に一時的事物の上の権力を得させんとするに過ぎなかった。自ら自らを捕える霊のみが永久的のものである。現実主義は人々を互いに平等たらしめんとする。しかし人をして自己と平等たらしめようとはしない。一時的の我れと永久的の我れとを調和せしめようとはしない。一言に言えば、自我の統一と万能との思想を持たない。自我は、そのそとにあるいっさいのものを服従せしめるもので、それ自身だけで充足するものである。 現実主義は、すべての人の自由、すなわちいっさいの権威からの解放を要求する。しかしその自由も自主ではない。現実主義は、彼自らが自由なる人の行為、rucksichtslos すなわち何等の顧慮するところもない精神の発現、ということには思い到らない。したがってこの現実主義によって教育されたいわゆる実用人は、他人との平等の上に、他人の権威からの解放の上に、出ることができない。もっともこの実用人といえども、かの人道主義のいわゆる端麗なシャレものよりは、多少ましかもしれない。しかしこの実用人というのも、「唯物主義の緑青でピカピカと飾り立てている」、無趣味な実業家に過ぎない。
三
現実主義は、いっさいの抽象を嫌って、抽象が生命や自由の仇敵であるかのごとく信ずる。けれども生命や自由は、かえって、この抽象の中にあるのだ。いっさいの物質を滅却して、それを精神化する抽象こそ、本当の解放者なのだ。自由人とは、いっさいの現実に超越して、あらゆる知識を自我の統一の中に帰せしめたものを言うのだ。 されば科学は、その科学としての存在を絶ち、単純な本能に帰し、すなわち意志となって復活して、初めて完成される。この意志になり終るまでに純化されない科学、まったくわれわれの中に溶解し終らないで単にわれわれの一所有物になっているに過ぎない科学、自我を思うままに活躍させないでかえってその重荷になっている科学、さらに換言すれば人格的になり終らない科学は、人の生活を準備するものとはならない。 真理は自我の発現にある。しかるに従来の学校は、かくのごとき自由人を造らんともせず、また造り得なかった。学校はわれわれを事物の主人にした。われわれ自身のいわゆる性質の主人にした。しかし本当に自由な性質の主人にしたのではない。われわれが学校で学んだ科学は、思想や意志の最大の屈辱と妥協する。現実主義者は、生徒がその教わった事物について、よく理解しよく適用することを要求する。けれどもその生徒に教える事物は、要するにある与えられた一事物に過ぎない。そしてさらにその事物を超越して、精神的に活動する新しき人格的知識を得ることを教えない。かくして教育学においても、他のあらゆる科学におけると同じく、屈従と卑劣とが支配している。「現実主義者の奇獣苑から出るものは、実用人、brauchbareburger 有用なる市民、すなわち奴隷人である。・・・学校教育の結実は実に Philistinismus 俗物根性である。」
現実主義は、彼等自らもまた誇らかに、実用人を造ることにのみ努めると言う。しかし本当の実用というのは、ただ生活の通路を開いていくことのみではない、科学は、かくのごとき実用的目的にのみ使用されるには、あまりに高貴すぎる。本当の自由とは、自由人にとっては、その自由を表現することである。そして本当の科学とは、新しき生命を与える、自由そのものである。 動物は、ようやく乳離れをするや否や、森や野を駈けめぐって、その全活動を生活に必要な食物を求めることに献げる。これほど実用的な生活はない。そして実用人の生活はこの動物生活にもっとも近きものである。実用人は、平等や自由の精神たる原則に従わないで、ただその形式たる確信にのみ従って行動する。確信は動かない。心臓に帰っては、絶えず新しくなり、若返りするする血ではない。凝固し腐敗する血である。現実主義の教育は、このいわゆる健全な、強固な性格、動揺するところのない人間を造り上げることはできよう。しかし「不断の自己創造によって、絶えず流動して行くところにその強固があり、瞬間ごとに新しく形成されて、自我の創造精力の尽くることなきところにその永遠がある」、というような性格を造ることはできない。いわゆる健全な性格は凝結し硬直している。性格の完成は、「常に新しく若返り再生することの喜びから、激情の中に揺動し、震動する」ことを堪え忍ぶにある。
四
さればいっさいの教育の中心は、人格の形成であり、発達でなければならぬ。「いっさいの科学は、いかに深くまたいかに広くとも、それがひとたび自我の見るべからざるところに滅尽して再びそこに超感覚的の思惟すべからざるものとなって堂々と再生し激発し来らざる限り、常に外的のものである。」科学がかく完成されんがためには、対象に執着することをやめて、科学そのもの、観念の科学、霊の認識とならなければならぬ。かくして科学は、霊の傾向となり、本能となり、自我の行為を自由に決定する無意識的科学すなわち意志となる。 そしてこの目的を達せんがためには、いっさいの教育が人格的にならなければならぬ。学校が諸々の知識をもって生徒の精神を阻格することをやめて、各生徒の個性を発達せしめ、自由な人間と自主の性格とを築き上げるところになければならぬ。すなわち従来のごとくに、生徒の意志を圧え弱めることをやめなければならぬ。子供の移り気は、普通誤って弱志と称せられているが、その好奇心や知識欲と同様の、存在の理由を持つものである。子供の好奇心を利用しつつも、何故にその意志の自発力をも利用することをあえてしないのか。また子供の自尊心と独立心とを圧えてはいけない。よしそれが倨傲心となったところで、いつでも教師は、それに対する武器として彼自身の自由を持っている。もし自尊心が反抗心に堕落すれば、それは生徒の自我が教師の自我を冒さんとするのだ。やはり生徒と同じく自由人たる教師は、それを堪え忍ぶ要はない。けれども教師は、いかなることがあっても、権威という容易な武器をもって防禦してはいけない。自由人に権威の要はない。独立心が暴慢心になったところで、その暴慢心は、真の女の柔和や、または真の男の剛毅に敵し得るものではない。権威に頼るのは自己の薄弱を告白するものである。 要するにスティルナーは、当時の教育者に対して、Willenloses Wissen 意志のない科学の、旧い原則に執着していることを批難したのであった。そして彼は、意志という新しい原則をもって、それに代わらしめんとしたのであった。旧教育学が科学と生活との一種のKonkordat(和親条約)を結ばんとしたのに対して彼は学校そのものが、生活となり、学校の理想が生命そのものの理想と同じく、人格の自己啓示であり、自己表示であり、自己実現であることを期待した。本当の生命は自由にあるのだから、学校は屈従のところでなく自由のところとならなければならぬ。思索の自由ということだけでは足らない。思索の自由によっては、われわれはただ、内的に自由になるに過ぎない。かくのごとき内的自由があったところで、われわれは依然として外的には奴隷であり得る。むしろこの外的自由の方が、科学から見れば正しく内的自由であり、そして意志から見れば正しく本当の自由なのである。 すなわち人道主義者と現実主義者との上に、さらに人格主義者がなければならぬ。科学を活動的力に変ぜしめ、思索自由の時代を意志自由の時代に移らしめ、そして旧き教育の二個の理想を調和せしめるものは、実にこの人格主義あるのみである。この自由人にして初めて、現実主義の造らんと欲した真に善良なる市民となり、また人道主義の造らんとした真の趣味の人となることができる。
五
以上は、マクス・スティルナーの最初の論文「現代教育の首要原則、人道主義と現実主義」の、きわめて忠実なる略説である。 僕等はここに、なお彼がヘーゲル派哲学の支配から、少しも抜け切らずにいることを、まず認めなければならぬ。すなわち彼は未だ、ヘーゲルのいう意味の霊と自主的意志との間に、超ゆべからざる深淵のあることに気がつかなかった。彼のこの教育論の曖昧な個所は、すべてみなこの欠点から来ると言ってもいい。 つぎに僕等は、スティルナーの後年の中心思想たる個人主義、絶対人格主義が、すでにこの論文の中に十分に啓示されていることを認めなければならぬ。ただ異なるところは、『唯一者』は成年者について語り、「現代教育論」は幼年者について語っていることに過ぎない。そしてここにことに注意して置きたいと思うのは、この「現代教育論」の中には、その個人主義がまだ後年の極端な誤れる利己主義と同一視されていないことである。 最後に僕等は、彼の教育学の原則に十分の根拠があり、今日の教育者等も大いに彼の言に聴くところなければならぬことを認めなければならぬ。スティルナーが当時の教育原則に向けた非難は、今日といえども、しかも遥かに遠く隔たったわが日本においても、等しくまた適用することができる。今日のいたるところの教育は、一個の人を造ることよりも、種々なる知識を注ぎこむことに腐心する。スティルナーの時代と同じく、今日の教育者等は、ただ記憶力の教育、理解力の教育、理性の教育にのみ努めて、意志の教育をまったく無視している。 教育の改革を唱うる多くの学者は、少年の心理状態を解剖して、今日の教育がいかに少年の本能を破砕し、その発意心を抑圧し、その人格を滅絶し、そしてそれらの少年が学校を出ても、いかに生活を知らず、いかに活動に堪えず、人間らしき努力の前にいかに戦慄するかを説いている。 そして僕等自身もまた、常に自ら、かく形成された僕等の腑甲斐なさを、この卑劣を、悔恨し憤懣している。僕等の受けた知育や徳育や体育は、要するに僕等をして、主人のために役立つべき聡明な、温順な、そして強健な小動物としてしまったのだ。 僕等は僕等の弟妹や子女を本当の人間に教育すると同時に、僕等自身もまた、僕等の教育をしなおさなければならぬ。本当に自由な人間とならなければならぬ。本当にみんなが自由な人間となり得るように、僕等の周囲を改造しなければならぬ。