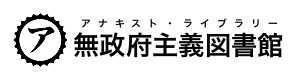石川啄木
日露戦争論
トルストイ
レオ・トルストイ翁のこの驚嘆すべき論文は、千九百四年(明治三十七年)六月二十七日を以てロンドン・タイムス紙上に発表されたものである。その日は即ち日本皇帝が旅順港襲撃の功労に対する勅語を東郷連合艦隊司令長官に賜わった翌日、満州に於ける日本陸軍が分水嶺の占領に成功した日であった。当時極東の海陸に起っていた悲しむべき出来事の電報は、日一日とその日本軍の予想以上なる成功を以て世界をおどろかしていた。そうしてその時に当って、この論文の大意を伝えた電報は、実にそれ等の恐るべき電報にも増して深い、かつ一種不可思議な感動を数知れぬ人々の心に惹起せしめたものであった。日本では八月の初めに至って東京朝日新聞、週刊平民新聞の二紙がその全文を訳載し、九月一日の雑誌時代思潮は英文の全文を転載した。そうしていろいろの批評を喚起した。ここに写した訳文は即ちその平民新聞第三十九号(八月七日)のほとんど全紙面を埋めたもので、同号はために再版となり、後また文明堂という一書肆から四六版の冊子として発行されたが、今はもう絶版となった。翻訳は平民社の諸氏、ことに幸徳、堺二氏の協力によったものと認められる。
平民新聞はこの訳文を発表しておいて、更に次の号、即ち第四十号(八月十四日)の社説に於いてトルストイ翁の論旨に対する批評を試みた。蓋しそれは、社会主義の見地を持していたこの新聞にとっては正にその必要があったのである。そうしてこれを試みるに当って、かの記者の先ず発した声は実はその抑えんとして抑え難き歓喜の声であった。「吾人は之を読んで、ほとんど古代の聖賢もしくは予言者の声を聴くの思いありき。」こういう讃嘆の言葉をも彼等は吝まなかった。想うに、当時彼等は国民を挙げて戦勝の恐ろしい喜びに心を奪われ、狂人のごとく叫びかつ奔っている間に、ひとり非戦論の弧塁を守って、厳酷なる当局の圧迫の下に苦しい戦いを続けていたのである。さればその時に於いて、日本人の間にも少なからざる思慕者を有するトルストイ翁がその大胆なる非戦意見を発表したということは、その論旨の如何に拘らず、実際彼等にとっては思いがけざる有力の援軍を得たように感じられたに違いない。そうしてまた、一言一句の末まで容赦なき拘束を受けて、何事に限らず、その思う所をそのままに言うことを許されない境遇にいた彼等は、翁の大胆なる論文とその大胆を敢えてし得る勢力とに対して、限りなき羨望の情を起さざるを得なかったに違いない。「而して吾人が特に本論に於て、感嘆崇敬措く能わざる所の者は、彼が戦時に於ける一般社会の心的及び物的情状を観察評論して、露国一億三千万人、日本四千五百万人の、曽て言うこと能わざる所を直言し、決して写す能わざる所を直写して寸毫の忌憚する所なきにあり。」これ実に彼等我が日本に於ける不幸なる人道擁護者の真情であった。
しかしながら彼等は社会主義者であった。そうしてまた明白に社会主義者たる意識をもっていた。故にかの記者は、翁の説く所の戦争の起因及びその救治の方法の、あまりに単純に、あまりに正直に、そうしてあまりに無計画なるを見ては、「単にかくのごときに過ぎずとせば、吾人豈失望せざるを得んや。何となれば、これあたかも『如何にして富むべきや』という問題に対して、『金を得るにあり』と答うるに等しければ也。これ現時の問題を解決し得るの答弁にあらずして、ただ問題を以て問題に答うる者に非ずや。」と叫ばざるを得なかった。「人はことごとく夷斉に非ず。単に『悔改めよ』と叫ぶこと、幾千万年なるも、もしその生活の状態を変じて衣食を足らしむるに非ずんば、その相喰み、相摶つ、依然として今日の如けんのみ。」これまた唯物史観の流れを汲む人々の口から、当然出ねばならぬ言葉であった。かくてかの記者は進んで彼等自身の戦争観を概説し、「要するにトルストイ翁は、戦争の原因を以て個人の堕落に帰す、故に悔改めよと教えて之を救わんと欲す。吾人社会主義者は、戦争の原因を以て経済的競争に帰す、故に経済的競争を廃して之を防遏せんと欲す。」とし、以て両者の相和すべからざる相違を宣明せざるを得なかった。
この宣明は、しかしながら、当時の世人から少しも眼中に置かれなかった。この一事は、他の今日までに我々に示された幾多の事実と共に、日本人--文化の民を以て誇称する日本人の事物を理解する力の如何に浅弱に、そうしてこの自負心強き民族の如何に偏狭なる、如何に独断的なる、如何に厭うべき民族なるかを語るものである。即ち、彼等はこの宣明をなしたるに拘らず、単にトルストイ翁の非戦論を訳載し、かつ彼等もまた一個の非戦主義者であったが故に、当時世人から一般にトルストイを祖述する者として取り扱われ、甚だしきに至っては、日本の非戦論者が主戦論者に対して非人道と罵り、悪魔と呼んで罵詈するのは、トルストイの精神とは全く違うのだというような非難をさえ蒙ったのである。そうしてこの非難の発言者は、実に当時トルストイの崇拝者、翻訳者として名を知られていた宗教家加藤直士氏であった。彼は、あたかもかの法廷に於ける罪人が、自己に不利益なる証拠物に対しては全然関知せざるもののごとく装い、あるいは虚構の言を以て自己の罪を否定せんと試むるがごとく、その矛盾極まる主戦論を支持せんが為には、トルストイ翁が如何に酷烈にその論敵を取り扱う人であるかの事実さえも曲庇して省みなかったのである。
もしそれこの論文それ自身に加えられた他の日本人の批評に至っては、また実に畢竟「日本人」の批評であった。日本第一流の記者、而して御用紙国民新聞社長たる徳富猪一郎氏は、翁が露国を攻撃した点に対しては、「これ恐らくは天がトルストイ伯の口を仮りて、露国の罪悪を弾劾せしめたるの言なるべし。」と賞讃しながら、日本の行為を攻撃した部分に対しては、「ここに至りて伯もまたスラーヴ人の本色を脱する能わず候。」と評した。またかの高名なる宗教家海老名弾正氏も、翁がロシアの宗教家、学者、識者を罵倒し、その政治に反対し、延いて戦争そのものに反対するに至った所以を力強く是認して、「彼が絶対的に非戦論者たらざるを得ないのは、実にもっとも千万である。」と言いながら、やがて何等の説明もなく、「彼はロシア帝国の予言者である。しかも彼をして日本帝国の予言者となし、吾人をしてその声に傾聴せしめんと欲するは大なる謬見である。」という結論に達せねばならなかった--しかり、ねばならなかった。また他の人々も、あるいは右同様の筆法を以て、あるいは戦争功用論を以て、あるいは戦争不可避論を以て、あるいは戦争正当論を以て、各々、日本人にして翁の言に真面目に耳を傾くる者の生ぜんことを防遏するに努めねばならなかった。実際当時の日本論客の意見は、平民新聞記者の笑ったごとく、何れも皆「非戦論はロシアには適切だが、日本にはよろしくない。」という事に帰着したのである。そうして彼等愛国家の中の一人が、「翁は我が日本を見て露国と同一となす。不幸にして我が国情の充分にかの地に伝えられざりし為、翁をして非難の言を放たしめたるは吾人の悲しむ所なり。」と言った時、同じ記者の酬いた一矢はこうであった。曰く、「否、翁にして日本の国情を知悉せば、更に日本攻撃の筆鋒鋭利を加えしことならん。」
ただその間に於て、ひとり異色を帯びて、翁の理想の直ちに実行する能わざるものなるを首肯しつつ、なおかつ非常の敬意を以て之を弁護したものは、雑誌時代思潮であった。
予の始めてこの論文に接したのは、実にその時代思潮に転載された英文によってである。当時語学の力の浅い十九歳の予の頭脳には、無論ただ論旨の大体が朧気に映じたに過ぎなかった。そうして到る処に星のごとく輝いている直截、峻烈、大胆の言葉に対して、その解し得たる限りに於て、時々ただ眼を円くして驚いたに過ぎなかった。「流石に偉い。しかし行なわれない。」これ当時の予のこの論文に与えた批評であった。そうしてそれっきり忘れてしまった。予もまた無雑作に戦争を是認し、かつ好む「日本人」の一人であったのである。
その後、予がここに初めてこの論文を思い出し、そうして之をわざわざ写し取るような心を起すまでには、八年の歳月が色々の起伏を以て流れて行った。八年! 今や日本の海軍は更に日米戦争の為に準備せられている。そうしてかの偉大なロシア人はもうこの世の人でない。
しかし予は今なお決してトルストイ宗の信者ではないのである。予はただ翁のこの論に対して、今もなお「偉い。しかし行なわれない。」という外はない。ただしそれは、八年前とは全く違った意味に於てである。この論文を書いた時、翁は七十七歳であった。