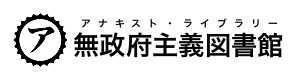ピョートル・アレクセーヴィチ・クロポトキン, 大杉栄訳
革命の研究
革命の研究
これは主としてフランス大革命の事実にもとづいて述べたものであるが、僕等はさらにこれをロシアの現状に照らし合せて見て、そのますます真実なことにむしろ驚くものである。
ボルシェヴィキの謀反人バンクハスト女史も、その機関誌『ウォーカース・ドレッドノート』にこれを掲載して、共産主義者の反省を求めている。
革命の時に、どんな奴がどんなことをするかは、だまされまいと思う労働者のよく知っていなければならんことだ。(訳者)
一
革命という言葉は、今では、被圧制者の唇にも、また所有者の唇にすらも、しばしば上る。すでにもう、時々、近い将来の変動の最初の顫えが感ぜられる。そして、大なる変動や変化の近づいて来る時にはいつもそうであるが、現制度の不平者は――その不平がどんなに小さくてもいい――かつては実に危険であった革命家という肩書を争って自分につける。彼等は現制度を見限って、何等かの新制度を試みようとする。それで彼等には十分なのだ。
あらゆる色合の不平家の群が、こうして活動家の列の中に流れこむことは、勿論革命的形勢の力を創り、革命を不可避にする。多少でもいわゆる輿論に支持されていれば、宮殿や議会の中でのちょっとした陰謀でも政権を変え、また時としては政府の形式をすらも変えることができる。
しかし革命は、それが経済組織にもある変化を及ぼそうというには、多数の意志の協力がいる。幾百万の人の多少活発な支持と協力とがなければ、革命はとうてい不可能である。いたるところに、どこの村にも、過去の取壊しに従事する人がいなければ駄目だ。そして他の幾百万の人は何かもっといいことが起るという望みの下に黙ってやらしていなければ駄目だ。
大きな事変の前夜に起って来る、ぼんやりした、曖昧な、そして多くは無意識的なこの不平があり、現制度に対する不信用があって、それで初めて本当の革命家が広大無辺の勤め、すなわち幾世紀かの存在によって神聖なものとされて来た諸制度を数年間にもつくりかえる勤めを成就することができるのである。
しかしまた、これが多くの革命が、その上に乗りあげて、そして倒れた暗礁なのである。
革命が来て日常生活のきまった順序がひっくり返された時。いっさいの善悪の情熱が自由に爆発して真昼間にさらけ出された時。失神のそばに非常な熱誠を見、臆病のそばに勇敢を見、つまらぬ反感や個人的陰謀のそばに非常な自己犠牲を見る時。過去の諸制度が倒れて、新しい制度が相続く変化の中にぼんやりと描き出された時。その時に、さきに自ら革命家と名のったものの大多数は、秩序の守護者の列の中に急いで走って行く。
街の騒ぎや、試みられる諸制度の不安定や、明日の不安やは、もう彼等を疲らせたのだ。彼等は、一方にすでに成就された些細な変化が暴風の中に滅んでしまうのを恐れる。そしてまた彼等は、経済制度のごく小さな変化も、すでにその社会のいっさいの政治的概念の深い変化を必要とし、そしてごく小さな政治上の変革も、経済界でのもっと大きな変化を経なければ行われない、ということが分らない。
そして彼等は、反革命の来るのを見て、急いでそれと一致しようとする。民衆の情熱や、また時としては無遠慮なその表現は、彼等に厭がられる。やがて彼等はもう革命にあきる。そして休息や緩和を促がすものの中に走って行く。
過去がそのもっとも熱心な守護者を集めるのは彼等の間である。彼等はその過去の一部分、勿論それは何でもないものであるが、それを犠牲にしただけ、それだけ熱心な過去の守護者になる。彼等はもっと遠くへ彼等を引きずって行こうとするものを憎む。
そして彼等は、革命的のいろんな手段をその手に握っているところから、それを過去のお役に立てようとするので、いよいよ危険になる。彼等は断行する。反革命も彼等がいなければあえてすることができないほどに断行する。そして彼等は、旧い制度をもっと根深く覆えそうとするものや、将来の中にもっと根深く進んで行こうとするものを捕まえる。彼等は革命を救うという口実の下に、実はそれに轡をはめるために、「狂犬ども」を死刑にしたロベスピエールやサン・ジュストの輩の真似をする。
で、革命の騒ぎの間は、その革命の味方と敵との区別がつかない。そしてまた、これはことに言っておかなければならないことだが、過去の革命の歴史家等は、この点についての考えに混雑を来たさせるよう、その全力を尽して来た。
今、フランス大革命だけを例にとって見る。ある歴史家の理想は、ルイ十六世の立憲内閣に一椅子を占めてすっかり満足したミラボーであった。またある歴史家の理想は、ドイツ人に対しては勇敢な愛国者であるが、しかし経済問題には少しも大胆でないダントンであった。彼は実に、外寇を斥けるためには、立憲君主とも妥協し、ブルジョワ地主に圧迫されている農民とも妥協し、また不動産の投機師とも妥協した執政官であった。そういったいろんなものが不思議にも彼の革命的精神と調和していたのだ。
また他のある歴史家にとっては、その理想は、財産の平等や無神論を主張して革命家等を死刑にした「義人」ロベスピエールであった。彼は一七九三年の夏、パリ市民が饑饉に苦しんでいる時、イギリス憲法の特徴を議論することをジャコバン党に迫った男だ。
最後にまた、他のある歴史家にとってはマラーが理想であった。ある時彼は、二十万の貴族の首を要求した。しかし彼はフランス国民の三分の二を熱中させた問題、ことに農民によって耕作されて来た土地が何人に所有さるべきかの問題の代弁者となることをあえてしなかった。
そしてさらにまた最後に、ある道化者にとっては、その理想は、公爵夫人等やその腰元どもの首を熱心に要求した――それも公爵夫人等はコブランツに行っていたので、実は腰元どもの首にすぎなかったのだ――検事であった。そしてその間に、ブルジョワの泥棒どもはフランスを掠奪し、労働者を飢餓に陥らしめて、その莫大な財産を造ったのである。
そして今日の革命家等の大多数は、過去の諸革命については、不幸にして、歴史家等が一生懸命になって語ったその戯曲的方面しか知らない。彼等は一七八九―一七九三年間に幾百万の無名の民衆がフランスでやり遂げた[#「やり遂げた」は底本では「やり逐げた」]大事業、一七九四年のフランスをして五年以前のフランスとまったく違った国にしてしまった大事業はほとんど知らない。
私が今この研究を企てたのは、この混雑の中を多少迷わずに辿って行こうとする今日の革命家の手助けにしたいためである。
私はまず、本当の革命家と、今はわれわれの味方だと言っているがやがてわれわれの敵になるだろうものどもとを、あらかじめよく区別しておく必要を力説しておきたいと思う。それから私は、革命家等にそのなし遂げなければならないだろう広大な勤めを説いて、もし彼等が、歴史家等が過去の革命についてわれわれに語ったことをモデルにしてつぎの革命を想像しているならば、そのなめなければならないだろう悔恨を、彼等に予告しておきたいと思う。
そして最後にまた、どれほどの精力の発揮、どれほどの猛烈な激しい仕事を、革命がその子等に要求するかを彼等に説きたいと思う。これは革命の成功のためには、危機のさいの相交換される銃丸と等しく、あるいはそれ以上に肝要なことである。
二
思想の大胆と、その考えていることを実行させるように民衆を引き入れて行く自発力と――これがいつでも今までの革命に、革命家等が欠いたところのものである。そしてこれが、またつぎの革命にもやはり欠けそうなのだ。誰か、過去の諸革命を研究して、つぎのような痛恨の言葉を発しなかったものがあろう。「あれほどの努力があり、あれほどの崇高い熱誠があり、あれほどの血を流し、あれほどの家族に喪服を着せ、あれほどの顛覆をして、そしてこんなちっぽけな結果しか得られなかったのか」――この言葉は文書の中にも、対話の中にも、また革命の宣伝の中にも絶えず繰り返されている。
これは、一部分は、革命が盲目的なあるいは無意識的な過去のともがらの間に出会う大きな障礙について、一般に人はよく知らないからである。彼等が後もどりしてその過去の特権を救おうとする、彼等の力と頑固さとを、とかく人は軽く見すぎようとする。そして、彼等がもう正々堂々として戦いができなくなった時、なお彼等にその過去の特権を救おうとする陰謀や蔭での仕事があることを忘れるからだ。一言でいえば、革命がいつも少数者によって行われることを忘れるからだ。
そしてまた人は、革命家等は一般にその行為では非常な勇気と大胆とを現すが、その思想やその目的や、その将来についての考えには、いつも大胆を欠いていることを忘れる。この将来を革命家等は、彼等がそれに対して叛逆して起った過去の形の下に、それを夢みている。過去は将来への彼等の飛躍にまでも彼等をゆわいつけているのだ。
彼等は旧制度に対してその本当の力を作っているもの、すなわちその宗教とか、法律とか、国家とか、国家に対する服従心とか、宮殿とか、監獄とかに決定的打撃を与えて、それを殺してしまうことをあえてしなかった。新しい生活に大きな門を開くために十分破壊することをあえてしなかった。そしてこの新しい生活についての彼等の考えはごく漠然としたもので、したがって遠慮深くそして範囲が狭くて、その夢においてすらも、彼等がその奴隷の過去に崇め祭っていた礼拝物に触れることをあえてしなかった。
勇敢な心臓を臆病な脳髄の用に立てようとしたところで、それで大きな結果が得られるだろうか。
実際、フランス大革命の諸事業を考えて見ると、われわれの祖父の行為の大胆なのと、その思想の臆病なのとに驚かされないわけに行かない。極端な革命的方法と臆病で保守的な思想とだ。自分の生命も享楽も投げ棄てた豪胆と果断との浪費と、ごく近い将来についての考えには信ずることのできないほどの臆病とだ。
民衆がそのかつて尊敬をもってめぐらしていた操り人形の一つに触れることをあえてするまでには、そしてまた民衆がその尊敬し服従する首領等に過去の制度のただ一つを犠牲にすることを余儀なくさせるまでには、幾月も幾年もかかった。
これがフランス大革命の特徴なのだ。ちょうどこれは敵の砲台を取るには非常な勇気と大胆とを示す兵隊が、その砲台の向うを見ようともせず、またその戦争の原因とか目的とかについての全体の観察をしようともしないのと同じようなものだ。
武器を持たない民衆がバスティーユの厚い城壁と大砲とに向って進んで行く。女どもがヴェルサイユへ走って行って王を捕虜にして連れて来る。いたるところに、各々の小都市に、丸太棒を持った若干の男が、あしたは自分等が「秩序に復した」市会によって死刑に処せられることなぞは少しも思わずに市役所を占領する。武器もない民衆がテュルリー宮殿に侵入して、赤い帽子をかぶった王を捕まえる。そしてさらに二カ月たって、彼等はスイスの雇兵やブルジョワの国防軍に不信を抱いて、このテュルリーを襲い取る。無名のものらは政府を軽んじて、自ら九月の虐殺に責任を負う。軍隊を持たない共和政府が、内に王党と闘いながら連合諸王と対立する。ダントンは革命を救うための至上の方法として大胆不敵を要求する。革命議会の断頭台も、ヴァンデの溺死も、車裂きの刑も、何ものもこの革命家等がその革命的方法を取ることを止めることはできない。そしてしかも、この雄大なドラマに伴うものは、思想の臆病、いっさいのものの上に天がける思想に大胆のないことであった。思想の臆病なことは、高貴なる努力をも非常なる情熱をも、無辺の熱誠をも、いっさい殺してしまうものである。
八月十日近くなって王室が倒れかかった時、ダントンやロベスピエールやコルドリエの輩は、彼等が王を恐れたよりも以上に共和政治を恐れた。そしてテュルリー宮殿の奥から呼び寄せられ指揮されていた外国軍の侵入によって、初めて彼等は、フランスは王冠を戴いた操り人形がなくなってもすむということを考えるようになったのだ。
坊主どもが新制度に対するその広大な陰謀によって全フランスを蔽うていた時、そしてこの陰謀がフランスの三分の二をその掌中に握っていた時、革命家等はうやうやしく教会を取り囲んで、それを革命の保護の下に置き、そして旧教を侮辱する「無政府主義者」等を断頭台に上ぼせた。
経済問題では、彼等の臆病はもっともっと大きく、そしてもっともっと醜劣なものだった。封建制度はもう事実上存在しない。領主は百姓どもに逐われて国外に走った。領主の森は荒されて、そこの鳥獣は退治された。封建の課税はもう払わない。しかるに革命の指導者等は国民議会の時まで封建制度の最後の遺物を保存して、それをつぎの世紀にまで残そうと努めた。そして、名声嚇々たる[#「名声嚇々たる」はママ]ジロンド党の徒や謹厳なロベスピエールは、財産の平等などという言葉を聞くと、民衆がもう私有財産を尊敬しないのかという考えだけで慄えていた。何故なら、彼等はそれを過去から伝えて来た。国家はこの私有財産の上にもとづくものだからである。
実際彼等指導者等はこれらのあらゆる点において遅れていた。そして民衆は彼等よりも過去からの解放に進んでいて彼等よりももっと遠くを見ていた。が、この将来の幻が実に漠然とした曖昧なふらふらしたものだったのだ。そして民衆それ自身の中にも、この曖昧とぐずぐずとが革命全体に伝わって、その思想がいろいろと分れていた。六月二十日に民衆をテュルリー宮殿に走らした肉屋のレジャンドルも、王を廃するということは夢にも考えなかった。王はその槍の下に押えている民衆がみんなそうであるように、さらにその槍の先きを打ちこんで王権をおしまいにしてしまうことができなかった。そしてその後、バブーフの共産的陰謀が起った時には、山岳党ですらもびっくり仰天してしまった。彼等は民衆の漠然とした社会主義的平等の憧憬をよく知っていた。しかし彼等はそれがはっきりした綱領になって現れると、びっくりしてしまったのだ。
一八四八年でも同じことだ。それまでの十五年間のあらゆる社会主義的宣伝の後に、フーリエやカペーの後に、共産主義について幾千の演説会で話され、また幾多の小冊子で説かれた後に――生存の権利とか幸福の権利とかいうことがすでにそれらのものの中に論ぜられていた――これらいっさいの宣伝の後に「民主的」革命家等は、すなわち自ら革命家であると信じ、また世間でもそれで通り、彼等の間のもっとも進歩したものとすらいわれていたものらが、共産主義を主張するものはすべて銃殺しようとした。彼等が思い切って考えていることはようやく民主的共和制であったのだ。国家が保護金を下付する組合であったのだ。そして彼等は、ボナパルトの輩に、自ら王位につくべく民衆の漠然とした共産的憧憬を利用させたのだ。
一八七一年のパリ・コミューンの時にでも、やはり同じことだ。彼等が闘わなければならない反動の恐るべき力の前にはその膝を曲げない猛烈な革命家達も、革命思想は持たなかった。革命については、彼等はただその方法しか知らなかった。しかもその方法というのも、彼等によれば、政府が今日までのその敵に対して使った武器を、こんどはその政府に向けるだけのことだ。
彼等は、彼等が倒した国家を小さくして再現したコミューンを夢みているのだ。そして彼等は、経済的革命という考えがぼんやりと民衆の頭の中にできかかっている間に、経済上の改革はその後でのことだといいながら、コミューンの政治的独裁を建てることしか考えないのだ。
コミューンの旗印の下に労働者の大衆を集める唯一の方法は、経済的革命を始めることだ、などということは夢にも思わない。またもし一八七一年のコミューンが失敗したら、少なくともそれは、他日再びその事業を始めるだろう人々に、金持に対する貧乏人の、なまけものに対する労働者の民衆的革命という考えを伝えなければならない、とも考えなかった。
何等の新しい思想も、旧い世界を革命するというような何等の思想も、この人々にはなかったのだ。その行為においては実に革命的であったこの人々も、その欲するところには実に臆病であり、そして彼等自身がそれに戦いを宣言している過去のモデルそのものの上に錬えられていたのだった。
しからば今日われわれは、来たらんとする革命の前日にあって、それよりももっと進んでいるかどうか。革命をやる大胆な思想と自発力とを持っているか。
われわれが憤慨するこの過去に対して、その従順に対して、その強権的組織に対して、その偽善に対して、その瞞着に対して、はたしてわれわれは、この過去をその総体においてのみでなく、さらにその毎日のあらゆる表現においても否認するところの、革命的思想を持っているか。現在の制度の上のみでなく、さらにそれらのものの発達を導く思想そのものの上にも、斧を加えることができるか。
これを一言すれば、はたしてわれわれは、われわれの行為や方法におけると同じく、われわれの思想においても革命的であるか。われわれの精力が革命的思想のために使われているだろうか。
三
われわれの父祖の持たなかった思想の大胆さを今日の人々に与えたのには、いろんなことが与かって力あったことは確かだ。
われわれの時代の人がそれに与かり加わった自然科学の非常な目ざめは、思想にも前例のない大胆さを与えた。きのうできたばかりの全科学が、われわれの父祖の夢にも思うことのできなかった広大な地平線を、われわれの前に開いた。
物質上いろんな力が一つのものとされて、動物や人間の精神生活をも含む自然現象の総体が説明され、われわれはこの自然現象の総体についてのごく大胆な考えを持つことができるようになった。宗教の批評は、深刻に、未曽有のそしてまた不可能だった大胆さで行われた。人間社会のいろんな制度の起原を神に帰するようなことや、また奴隷制度を説明し永続させて行くことに使われたいわゆる「摂理の法則」についての、神聖な迷信のいっさいの土台は、科学的批評の下に打ち倒された。そしてこの批評はすでに民衆の奥深くにまで浸みこんだ。
人間は自然におけるその地位を知ることができた。彼自身がその制度を造ったものであり、そして彼のみがまたそれを造り直すことのできることを知った。
一方にはまた、人が自然の中に見るいっさいのものにかつて結びつけていた不変という考えが、ぐらつかされ毀されて無にされてしまった。自然の中のいっさいのものは変化する。絶えず変化する。太陽系も、遊星も、気候も、動植物も、人種も。人間社会の諸制度がどうして不朽のものであり得よう。
何ものもそのまま継続するものはない。いっさいのものは変化する。動かないように見える岩も、大陸も、またそこに住んでいるものも、その習俗も、その習慣も、その考えも、われわれがわれわれのまわりに見るところのものは、ただちに変って行かなければならない一時的現象に過ぎない。不動は死だ。こういった考えに近代科学はわれわれを馴らした。
が、この考えはまだほんの昨日からのことだ。アラゴはわれわれとほとんど同時代の人だ。それでも、ある日彼が大陸のことについて話して、それがある時には海の中から浮び出し、ある時には波の底に沈んでいたともいうと、やはり学者の一友人が彼に言った。「すると、その大陸はやはりきのこのようにして生えるんですか。」それほどまでに、当時ではまだ、自然の不変という考えが人心に深く根をはっていたのだ。今日では、大陸の変化とか進化とかいうことはもうごく通俗な言葉の一つとなった。
そして人は、革命は進化の主要な一部分に過ぎないものだということを、おぼろげながらも分り始めた。自然の中のどんな進化でも、変革なしに行われることはないのだ。ごくゆるやかな変化の時期のあとに加速度的の急激な変化の時期が来る。されば革命は、それを準備するゆるやかな変化やまたその後に来る急激な変化と同じように、進化のために必要なものである。
生命は不断の発達だ。植物も動物も個人も社会も、同じ状態に長くいれば、枯れて死ぬ。これが進化哲学の根本思想なのだ。そしてこの思想が、いっさいの変化のために必要な大胆さをどれほど励ますであろうかは、すぐに分ることだ。
なおこの外でも、この世紀の間の人知の侵略の迅速さを見よ。またその大胆さを見よ。
「思い切ってやって見ろ」というのが近代の機械術の合言葉だ。高さ百メートルの海の入江に架けた長さ六百メートルの橋を考えて見ろ。やって見れば、実際はフォス湾でそれが成功したようにできるのだ。三百メートルの塔を考えて見ろ。やって見ればできるのだ。スエズやパナマの海峡を掘って見ろ。やれば、二つの大洋がつながるのだ。アルプス山に穴をあけて見ろ。やれば、中央ヨーロッパの平野を地中海の岸に結びつけるのだ。
近代機械術の歴史は、「大胆、そしてまた大胆に!」というダントンの言葉の一連の変遷に過ぎない。
そしてこの大胆さはすでに文学や美術や戯曲や音楽にも及んだ。心が諸君にいうままに、大胆に話せ、書け、描け、作曲しろ。
諸君が思想を持ち知識を持ち才能を持っているならば、諸君はその形式の新しさにもかかわらず聴かれ、また了解されるだろう。
四
これらいっさいのことは、われわれの時代に、またその革命に、莫大な利益を与える。これらいっさいのことは革命家の思想の大胆さを刺激する。しかるに不幸にしてこの同じ大胆さが、今日までのところ政治や社会経済の方面に欠けていた。そこでは、思想においても、またその適用においても、まだ臆病が支配している。
もっとも、前世紀の間は、政治史は敗北のことしか書くことができなかった。あちこちで勝利は得られていても、その勝利はやはりまったく敗北の性質を持っていた。
一八四八年の革命前に、イタリアや、ハンガリーや、ポーランドや、アイルランドの愛国者等が、その民族的独占を得ようとして示した壮烈な行為を思い出して見ても、それが失敗に終ったことを思えば、そこに何等の元気づけさえも見出すことはできない。そして、イタリアやハンガリーの独立がついにどうして得られたかということを思うと、その理想がそれによって実現せられるに至ったその帝国主義に対する譲歩や、その後戻りについて、彼等愛国者のために赤面せざるを得ないのだ。
四八年六月や七一年五月の犠牲者等の殺戮や、ドイツの軍国主義や、帝国主義時代のフランスの侵略や、ロシアの青年の無駄な努力や、ロシアの革命の失敗や、またロシアの反動主義がその勝利を歌った虐殺、これらいっさいのことは、社会事実の表面しか見ることのできないものには、大胆な心を呼び起すようにも、また養うようにもできていなかった。
また、国際労働者同盟(インターナショナル)が、その最初にやった大きな約束、労働者の心に呼び起した希望について考えて見ても、その後継者であると自負している諸労働党の堕落を思えば(これはサンジカリズムの勃興以前に書いたものだ)、労働者がその約束について信仰を失って、その心に絶望を抱くようになるのももっともなことだ。
しかし、政治の落胆者どもによって拡げられ養われたこの見解ほど、間違ったことはないのだ。何故なら、前世紀の失敗や敗北の原因を考えると、何がその敗北を持ち来たしたかは、すぐ分るのだ。それは前に進むことを十分あえてしなかったからだ。いつでも目をうしろの方へ向けていたからだ。
いろんな個人や国民が、荒れ狂うような革命党となった時、彼等はその理想を将来の中に求めず、それを過去の中に求めた。新しい革命を夢みるかわりに昔の革命にあこがれていた。
一七九三年には、ローマかあるいは古代スパルタをさえ再建しようと夢みていた。一八四八年にはこの一七九三年のやり直しをしようとした。一八七一年にも、一七九三年のジャコバン党をひそかに崇めていた。ドイツ革命もやはりこの一八四八年を再現しようとした。一八八八年にはペテルスブルグの執行委員会はブランキーやバルベスをそのお手本とした。そして一九〇五年には、ロシアの社会主義革命家は、ロシアの新聞でいつも一つの革命として彼等に教えられていたところの、ベルリンの一八四八年三月十八日を想像していた。
技師や科学者や芸術家が過去を投げ捨てている時、政治家と経済学者とはその霊感を過去に求めている。実際、もし技師がその材料を古代技術に求めるとしたなら、その技術はどんなものになるだろうか。その新しい考えを得るのに、その手許にある新しい力や新しい材料を使わなかったら、ローマの橋や堀割以上のものができたろうか。フォルス橋の技師等は、この新しい材料を使わなかったら、海の入江を遮って橋弧を積み重ねるのにシクロペアンの技術しか考えることができなかったろう。もし彼等に大胆さがなかったら、彼等はその建築の新時代を開くことはできなかったろう。
また、もしウォーレスやダーウィンが古い書物の中に事実と思想とを探すことに固執していたとしたら、植物や動物の進化という学問はどんなになったろうか。この先駆者等は新しい学問には新しい観察がいるということが分っていた。そして彼等は大自然を訪ねて、熱帯のほとりにその秘密を探りに行った。その新しい帰納的結論を得るために新しい基礎を求めに行った。
しかるに、政治や経済の方面ではこういうことがないのだ。そしてこれがその考えの臆病なわけなのだ。十九世紀の一揆叛乱の敗北したわけなのだ。
その目をうしろの方へ見はって新しい社会を建設するなどということができるものでない。プルードンがすでに勧告していったように、今日の社会の傾向を研究して、それによって明日の社会を推断するほかは、新しい社会の建設に達することはできない。人心に芽ぐんでいる新しい思想、これが根本だ。そしてこの唯一の根本によって、プルードンが勧告したように、今日の社会の傾向を研究して、そこから革命の成功に必要な革命的狂熱と思想の大胆さを引き出して来ることができるのだ。
五
今、マルクスシストや、ポシビリストや、ブランキストや、またブルジョワの革命家等を一瞥して見ると――何故なら今日芽ぐんでいる革命にはこれらのすべてのものが顔を出すであろうから――そして同じような政党が名は違っても同じ特徴を持ってどこの国にもあることを考えて見ると、そしてまた、その根本思想や目的や方法を解剖して見ると、驚くことには、彼等はみんな過去に目をつけていて、誰一人将来を見ようともしないで、そしてその政党がみんなつぎのような一つの思想しか持っていないのだ。すなわち、その思想というのは、政府の力としてははなはだ強い、しかし世界を革命することのできる唯一の思想を生みだすにははなはだ無力な、ルイ・ブランかブランキーか、あるいはロベスピエールかマラーを復活させることなのだ。
みな独裁を夢みている。「無産階級の独裁」とマルクスはいった。詳しくいえば、その執政官どもの独裁だ。ほかの政党の参謀等は、社会党以外のわが党の独裁だというだろう。が、それはみな帰するところは同じだ。
みなその敵の合法的虐殺による革命を夢みている。革命裁判、検察官、ギロチン、およびその雇人すなわち死刑執行人と獄吏とを夢みている。
みな国民をその臣下として、国家の叙任を受けた幾千幾万の官吏によってその臣下を支配しようとする、全知全能の国家の政権獲得を夢みている。ルイ十四世もロベスピエールも、またナポレオンも、ガンベッタも、要するにこういった政府以外のものを夢みてはいなかったのだ。
みなこの独裁時代の後に革命から生れ出る「建物の冠」として、代議政治を夢みている。みな独裁者の造った法律に対する絶対的服従を教えている。
みなその権力の首領等と違ったことを考えているものはすべて虐殺するという、公安委員会の夢ばかり見ているのだ。自分自身の意志するままに思索し行為することをあえてする革命家等は殺されなければならない。もっと遠くへ行こうというものは、なおさら殺されなければならない。もしマラーがまだ許されるとすれば、マラー以上の共産主義者や、また「気違い」だと呼ばれているものは殺されなければならない。
みな何等かの形式の下に、あるいは私有かあるいは国有かの所有権の維持を欲している。財産を使用し濫用する権利の維持を欲している。仕事による報酬、国家によって組織された慈善を欲している。
みな個人や民衆の発意心を殺すことを夢みている。考えるということは、と彼等はいう、それは科学であり技術であって、民衆には不向きのものである。そしてやがて、民衆に発言することが許されても、それは彼等のために考え彼等のために法律をつくる首領を選ぶために過ぎないだろう。そして思想の指導者によって論ぜられない解決を、自ら求め、自ら試みるためではないだろう。マルクスやブランキーは、ルソーが十九世紀のために十分考えたように、今日の世紀のために十分考えた。そして、首領が先見しなかったことは存在の理由がないことになるのだ。
これが革命家という名を僭称している百人中九十九人の夢なのだ。
六
さればもし諸君が、いわゆる革命的だという、しかし無政府主義的宣伝には染っていない、教育を受けた労働者の集会へ行って、そして革命の時にはどうするかと聞いてみるなら、富豪の家へ坐りこむとか、食料を分配するとか、銀行や倉庫に鍬や鉄鎚を打ちこむとか、監獄をぶち毀すとか答えるものがどれだけいることだろう。そして一言でいえば、労働者が搾取者にその労力を売って、その金でまたほかの搾取者の家主や食料品屋や銀行屋などに支払う、というようなことのもうない新生活を始める企てをするというものがどれだけあることだろう。いわゆる革命家の中に、まずその首領等にそれを謀るということをせずに、自らその思想を発表することのできるものが、どれだけいることだろう。みんなが異口同音に答えることはたった一つだけある。それは「革命の敵」を虐殺するということだ。そして、それをもっとも多く虐殺すると約束するものは、それが革命をやるごく小さな手段について語るのに赤ん坊のように臆病であっても、ただちに本当の革命家と見做される。
きのうは機関銃の餌食となり、あすは機関銃の主人となる。民衆はそれ以上に出てはいけないのだ。そのほかのことはいと高いところで考えてくれるのだ。
私はほかのところですでにこのことを言った。民衆が長い間そのために圧迫されて来たものどもに復讐する場合には、何人にもそれを非難する権利はない。ただ民衆の苦しんだいっさいのことを彼自身も苦しんだものだけが、そうした場合にその中へ立ち入る権利がある。その子供等が餓えに泣くのを聞き、餓え疲れて死ぬのを見たものだけが、橋の下に寝ね、貧窮のあらゆる危惧とあらゆる屈辱とを受けたものだけが、紳士どもがホテルで寝ている間に、家もなくパンもなくして大道にぶらつき、または将軍どものやすやすと退却する間に雪の中に餓え凍えてうろついたものだけが、立ち入る権利があるのだ。民衆の復讐を審いて、きのうは穢多非人であった彼が、その圧制者のためにそこへ立ち入る権利があるのだ。それにそれだけではない。民衆は幾千年以来、この復讐を教えられているんじゃないか。この復讐ということは、宗教によって神聖にされ祝福され、そしてまた加害者のからだを傷つけることによってその加害者が乱した正義を恢復する法律という女神の手で強いられているんじゃないか。誰も彼も合法の殺人によって復讐を賛同しているんじゃないか。死刑執行人の獄吏に金を払っているのではないか。
また、今日の制度の下に、死刑執行人や裁判官に反抗する勇気のあり、そして事実の上で反抗した人だけが、それについて論ずる十分な権利があるのだ。それをすることのできなかったものは黙っているほかはない。その復讐は彼等が授けた教育の結果なのだ。合法的復讐という彼等が教えた主義の結果なのだ。彼等が人命を軽んじた結果なのだ。この復讐の語るところのものは、キリスト教やローマ教の幾千年間の教育、貧窮の幾千年、いっさいの歴史なのだ。いっさいの歴史に対する叛逆だけがこの復讐に反対して立つ権利があるのだ。
しかし、この復讐という性質を否認して、国家の原則として立って、そして革命の原則のような顔をして威張っている暴力は、これとはまったくわけが違う。それはジャコバン党(中央集権派の典型)お得意の暴力だ。なぜなら、彼等は、民衆の狂熱がその最初の犠牲とともに消えて、すぐそれが後悔に変ってしまうことを知っているからだ。そして彼等はまたその革命的思想の空虚を補うために、革命の具体化としての合法的暴力を行わなければならないのだ。
彼等は、革命に反対することに利益を持つ人間どものごく少部分でも殺すことのできないことを知っている。ブルジョワが、国民の大多数であることを知っている、少数ブルジョワによって支配されている無産者の大衆しか、もうその想像の中に残らないほど、資本の集中ということを信ずる馬鹿者どもにはお気の毒であるが、これは事実なのだ。現に、フランスに今、ブルジョワと賃金労働者とがどのくらいいるか。いっさいの賃金労働者をかぞえて、それには官吏だの、従僕だの、大商店や大銀行の香水の香のぷんぷんする雇い人だの、鉄道の金ボタンをつけた雇い人だの、その他もっとも悪いブルジョワよりももっとブルジョワであるいっさいの賃金労働者を入れて、一八八一年の国勢調査では、フランスの三千七百万の全人口の中に、いっさいで七百万しかいなかった。それにその家族を加えても二千万足らずにしかならない。そしてその残りの一千七百万は、農民と地主とブルジョワとその家族とだ。そこから、地主というよりもむしろ無産者である農民の五百万を引くと、他人の労働で食っている千二百万のブルジョワ――その従僕どもは入れずに――が残る。フランスは千二百万のブルジョワだ。そしてイギリスには千五百万のブルジョワだ。
今日のジャコバンもやはりブルジョワの虐殺のことはあえて言い得ない。「そのいっさいのものを黙らしてしまうには」と彼等は言う。「数千の頭を切るだけで十分だ。その恐怖でみんな地の下にもぐってしまう。」
さて、この理屈はある一事を証拠だてることになる。それは、フランス革命の時にジャコバン党のブルジョワが言いふらしたこのお伽噺のために、民衆は彼自身の歴史から何にも学ばずにいるということだ。
まずジャコバン党の革命が、もっと遠くへすなわち民衆の押して行くところへ行くことをあえてしなかった間違いから、すでに死につつある時に、いわゆる恐怖時代が始まったのだ。そしてハイカラどもや遊冶郎どもが隊を作って民衆を侮辱し、赤い拍車の生活に戻って、すでにフランスの四分の三を支配していた反革命を叫ぶようになったのも、まさにこの恐怖時代の下のことだ。
エドガー・キネェはそれをこう説明した。それは民主政治が恐怖政治を使いこなすことができないからだ。カトリックの教会や封建諸王がそれをやったのと同じ結果をもって、それを使いこなそうとするには、民主政治はルイ十一世や暴王ジャンやロシアの諸皇帝について学ばなければ駄目だ。民主政治はそれを大騒ぎしてやる。が、民衆は槍の先きに突き刺さった頭のまわりでカルマニヨル(共和党の歌舞)を踊っている時にでも、実に頑是ないいい児である。
封建諸王やロシアの皇帝はそんな騒ぎをしない。彼等はただ一人を打ち倒して他のものどもをそれと同じ運命に陥る恐れで戦慄させる。彼等はその犠牲者を街の中に引きずり廻すようなことをしない。牢屋の中で絞め殺してしまう。ロシアのアレクサンドル三世は[#「アレクサンドル三世は」は底本では「アレクサドンル三世は」]、王位につくとすぐ、五人――しかもその一人は女――の犠牲者を選んで、それを絞め殺した。それでも彼はまだそれを公共の場所の広場でやったことを後悔した。そんなことをしたので、ヴェレスチャギンはそれを画布の上に不朽のものにしたのだ。その後はすべてシュルツセンブルグの牢獄に鎖づけにして、十年間もその囚人等の一語をも聞えなくし、生きているのか死んでいるのかも分らないようにしておいた。彼は、広場だの真昼間の死よりも、どうしたのか分らない恐怖の方がもっと人心に強く響く、ということを知っていたのだ。
そしてキネェがなお、この恐怖政治はとても民衆には使いきれないと言ったのは実にそのとおりだ。恐怖政治というようなことは民衆は嫌いなのだ。民衆はかえってそれを恐れているのだ。民衆自身はすぐそれにいやになる。パリ・コミューンの検事や、犠牲者等の満載された車や、断頭台などは、すぐ民衆におぞ気を立たせる。そして民衆はまた、すぐ、この恐怖政治が独裁を準備することを知り、そしてその断頭台をぶち毀しに行く。民衆は恐怖政治によって統治はしない。恐怖政治は鎖を鋳るために発明されたもので、ことにそれで合法の皮をかぶった時には、民衆を結わえるための鎖を鋳るものである。
七
敵に打ち勝つためには、断頭台よりももっと以上のもの、恐怖政治よりももっと以上のものがいる。革命的思想がいる。本当に革命的な、広大な、敵が今までそれによって支配して来たあらゆる道具を麻痺させて無能のものにしてしまうほどの、思想がいる。
もし、敵に打ち勝つためには恐怖政治しかないということであったら、革命の将来はどんなに悲しいことであろう。が、幸いに、革命には、それと違った有力な他の方法があるのだ。そしてこの方法はすでに、どんな方法が彼等に勝利を確かめるかということを求めている革命家等の新しい世代の中に芽ざしているのだ。彼等は、それがために、何よりもまず、旧制度の代表者からその圧制の武器を奪い取らねばならないことを知っている。あらゆる都市、あらゆる農村において、あらゆる圧制の主要機関をたちどころに廃止しなければならぬことを知っている。ことにはまた、かくして解放された都会や農村に、住宅や生産機関や運輸の方法や、また食料その他生活に必要ないっさいのものの交換を社会化して、社会生活の新しい型を始めなければならないことを知っている。