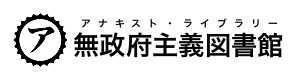シンディ=ミルスタイン
民主主義は直接的
最近、言葉が小銭のように投げ散らかされているように思う。民主主義も例外ではない。
世界銀行・IMF・WTOを「民主化」せよという要求を耳にする。「民主主義」は良い政府の基準だと主張する人もいる。「もっと多くの」民主主義・「より良い」民主主義・さらには「参加型民主主義」なるものが私達の苦悩に必要な解毒剤だと断言する人々もいる。こうした善意から出た見当違いの意見の直中で、自分達の生活を掌握するという本物の願望が打ち砕かれている。
私達が生きている世界を考えれば、このことは確かに理解できる。名前も分からず、多くの場合は遠く隔たった場所の出来事や機関--記述することもほとんどできず、ましてや対決することもできない--が、私達の仕事・飲料水・住居を決定する。ほとんどの人が、人生はそうあるべきようにはなっていないと感じている。多くの人々は「政府」や「大企業」について不平を言いさえする。しかし、それにもまして、社会的悲惨の源泉はあまりにも覆い隠されているために、親しみやすく見えかねない程なのである。ベン&ジェリーズのアイスクリームコーンの「思いやり」資本主義や、西洋超大国の「人道主義的」素振りがそうだ。
真の原因が聖域で理解できないもののように思われる以上、人々は、顔を持つ架空の標的に非難の矛先を向けるものだ。諸機関ではなく個々人に、権力ではなく人々に向けるのである。スケープゴートのリストは長い。黒人からユダヤ人まで、シングルマザーからゲイまで、といった具合である。私達同様にほとんどもしくは全く権力を持っていない人々を厳しく非難するのは容易い。一見して不可視のシステムに対する社会闘争は、目に見える「他者」への憎しみに置き換えられる。コミュニティ--自分達自身の生活を確立し、他者とそれを共有し、自分達自身の選択で何かを作り上げる場所--の熱望は、ナショナリズム・原理主義・分離主義へ、そしてそれらに伴うヘイトクライム・大量虐殺・民族浄化へと世界中で歪められている。コミュニティは、もはや、自己と社会との豊潤な認識を意味してはいない。この認識はちっぽけな「私達」と同じようにちっぽけな「彼等」との死闘へと翻訳され、その間、支配機構が私達全員を打ち負かす。力無き者が力無き者を踏みつぶし、力ある者はほとんど無傷のままでいるのだ。
私達に残っているのは、権力者がでっち上げた幾つかの悪い選択肢だけである。「ネイション」の記事において、Slavoj Zizekは、前年のコソボ紛争との関連でこれを「二重脅迫」だと名付けた。空爆に反対すれば、ミロシェヴィッチの権威主義的民族浄化体制を暗黙に支援することになる。ミロシェヴィッチを非難すれば、グローバル資本が形成した世界を支持することになる。この選択の余地のない選択は、他の多くの現代的危機にも当てはまる。大量虐殺は国民国家の介入を余儀なくさせているように見える。過剰な自由貿易は国際的監督機関を必要としているように見える。もし、この像全体の外部に倫理的観点からの正しい答えがあるなら、それはどのようなものなのか?人々が死につつあり、環境が破壊されつつあるときに、そんなものははったりでしかない。少なくとも、これが、政府の役人からニュースのコメンテーター、街路にいる一般人まで、一般的な知恵が意味していることなのである。
多くの左翼でさえ、高いところから私達に示される選択肢と同じ、制御不能な世界を制御するための「現実的」選択肢しか理解できていない。このことを考えると、左翼主義の視野は達成可能だとされていることに限定されている。つまり、国際的意志決定機関へのNGOや「三分の二世界」の参加・国民国家の説明責任と開放性・資本主義の誤りの訂正に限定されているのだ。こうしたものやそれに類する要求は、現行体制内での最低限の要求に過ぎない。しかし、これらは、いかなる解放的意見とも似ても似つかない。限局的で中立化された民主主義概念に働きかけるものの、その「民主主義」は民衆のものでも、民衆によるものでも、民衆のためのものでもない。むしろ、民衆という仮想の名においてのものに過ぎない。そして、「民主主義」というあだ名の付いているものは、単なる代表制であり、進歩主義者と左翼がこの予めひとまとめにされた定義の範囲内で擁護できる最良のものといえば、根本的に誤ったシステムのヴァージョン改善に過ぎないのだ。
「国民が代表者を立てた瞬間、その国民はもはや自由ではない。」よく知られているように、ジャン-ジャック=ルソーは「社会契約論」でこのように宣言した。自由、特に社会的自由は、確かに、国家に対する明確なアンチテーゼである。それが代議制国家であったとしてもだ。最も基本的なレベルで、代議制は私達の自由を他者に譲ることを「求める」。本質的に、誰かが権力を持つべきで、その他大勢は持つべきではないということを前提としている。万人に平等に分配された権力がない以上、私達は、他の人々と共に自分達の社会を有意義に形成する能力を放棄している。私達は、自己決定能力を放棄し、従って自由も放棄している。そのため、指導者がどれほど啓蒙されていようとも、暴君として支配する。私達--「国民」--が指導者の決定に盲従しているからだ。
だからといって、代議制政府がもっと権威主義的な支配形態と同様だというわけではない。例えば、代議制システムが普遍的人権の約束を果たせないとしても、そうした主張を全く行わない政府よりは明らかに望ましい。しかし、最も寛容な代議制システムであっても、必然的に自由の喪失を引き起こす。資本主義同様、成長か死かの至上命令は国家構造そのものに組み込まれている。カール=マルクスが「資本論」で説明していたように、資本主義の目的は「絶えざる利潤形成運動」である--実際、そうでなければならない。同様に、そうした目的は国家の根底にも存在する。絶えざる権力形成運動なのだ。利潤を求める動きと権力を求める動きは、それぞれ、それ自体が目的となる。こうした動きがなければ資本主義も国家もないからだ。これらの「ゴール」はその組織構造(body constitution)の一部である。従って、多くの場合、搾取と支配という二つの連結したシステムは、システムを維持するために必要なことであれば何でも行わなければならない。さもなくば、絶えざる勢いを全うできなくなる。
従って、国家が行うことは何であれ、それ自体の利害関係の中にあるはずである。もちろん、時として、国家の利益が様々なグループや人々の利益と一致することもある。正義や思いやりのような概念と重なり合うことさえあるかもしれない。しかし、こうした一致は、国家の円滑な機能にとって何ら中心的なことではなく、不可欠なことですらない。国家がその権力を維持し、凝固し、強化すべく継続的に動く際の単なる道具的踏み石に過ぎない。
好むと好まざるとに関わらず、全ての国家は権力を独占しようとせざるを得ない。ミハイル=バクーニンは「国家主義とアナーキー」で書いていた。「経済分野が莫大な資本の利益になるように小規模な資本や中規模の資本さえをも死滅させ、使い尽くしてしまうのと全く同じ競争が、(中略)国家の生においても作用している。帝国の利益になるように小規模・中規模国家を破壊し、吸収しているのである。」バクーニンが記しているように、国家は「破滅しないために他者を破滅する。」こうした権力奪取ゲームはほとんど常に、中央集権化、覇権、次第に洗練されていく命令・強制・統制方法に繋がっていく。明らかに、このように権力の独占を追求する中で、支配される対象が常に存在することになる。
従って、制度化された支配システムである以上、国家にせよ資本にせよ制御することなどできない。修正することも緩和することもできない。つまり、国民国家や資本主義の条件を受け入れている左翼や進歩的活動家の集合的叫びは、いかなるものであれ、究極的には次のようなものに過ぎない。「代議制なき搾取はやめろ!代議制なき支配はやめろ!」
一方、直接民主主義は完全に国家とも資本主義とも敵対する。「民衆による支配」(民主主義の語源)である以上、民主主義の根底にある論理は、本質的に、自由を構築する絶えざる運動である。そして、既に目にしているように、自由は、最良の代議制システムであっても放棄されるに違いない。
直接民主主義の反対者が一般に権力者であることは偶然ではない。「民衆」が話した--公民権を剥奪され、権能を奪われ、餓死しさえしている人々の大多数のように--時には、常に、民主主義の価値に関する「対話」を通じて作用する革命となった。従って、直接的統治形態として、民主主義は、他者を支配したいと望んでいる少数者グループにとって--君主であろうと、貴族であろうと、独裁者であろうと、米国のような連邦政権にとってさえも--脅威に他ならない。
実際、私達は、米国革命を含めた過去の大革命において民主主義がその急進的先鋭性を見出していることを忘れている。米国の政治主体として、こうした急進化した民主主義の諸傾向に耳を傾けることは非常に適切であろう。こうした諸傾向は、米国革命において、非常に勇敢に戦われ、圧倒的に失われてしまった。私達が支配それ自体に異議を唱えることに何らかの希望を持っているのなら、この未完成のプロジェクトを取り上げねばならない。
だからといって、米国の始まりに関わる様々な不公正を無視すべきだとか、それらを誤魔化すべきだとか述べているのではない。原住民族・黒人・女性などが排除され、惨たらしく殺され、搾取された(今もされ続けていることが多い)という事実は、この国を創り出した歴史的出来事にとって二次的な問題などではなかった。直接民主主義を求めるいかなる運動も、この抑圧と米国革命の解放的瞬間との関係に取り組まねばならない。
同時に、革命をその時代の文脈で見て、「それがどのような進歩だったのか?それは、最終的に万人に拡大しなければならない新しい自由を垣間見させたのか?」と問わねばならない。近代の全ての大革命同様、米国革命は都市内部と都市間での顔を付き合わせた集会に基づく政治を生み出した。
「米国の民主的政治形態は本物のコミュニティ生活から発展した。(中略)群区やそれほど大きくない地域が政治ユニットであり、町民会は政治的媒体であり、道路・学校・コミュニティの平和が政治目的だった」とデューイは「公衆とその諸問題」で述べていた。自治の要綱は1776年に突然出現したのではない。文字通り最初の入植者と共に到着した。入植者達は、旧世界当局の拘束から逃れ、メイフラワー協定で自分達の社会ルールを新たに制定することを決めた。この協定とその後に続く一連の協定はコミュニティに対する個々人の相互約束--権利も義務も--だと見なされていた。当初は、新しく発見された平等主義的宗教の価値観から生じた約束だった。この考えが定着し、多くのニューイングランド村落は自身の憲章を改訂し、町民会を通じた直接民主主義を制度化した。市民はコミュニティの公的政策と公的ニーズを決定するために定期的に会議を持った。
コミュニティの討議・審議・決定に参加することは、十全で活力ある生活の一部となった。これは入植者達(たとえその大部分が男性だったとしても)に経験を与え、後に米国革命を支援することになる諸機関を示しただけでなく、闘うに値する具体的自由をも示した。だからこそ彼等は自分の日常生活の管理を保持すべく闘争した。最初は独立を求めて英国と、その後に、相反する統治形態をめぐって自分達同士で闘った。もちろん、最初の憲法は、直接民主主義ではなく連邦共和国を創設した。だが、革命前・革命中・革命後に、幾度となく、町民会・連邦集会・市民義勇軍のいずれかが、確立した自主管理権力を行使したり、妨害された際に新しい自主管理権力--合法的諸機関と超法規的諸機関双方--を創り出したりし、この過程の中でさらに急進的になっていったのである。
私達は、ニューハンプシャー州のモットー「自由に生きるか、さもなくば死ぬか」やヴァーモント州の年に一度の「タウンミーティングの日」のように漠然とした残響に過ぎないにせよ、この独学の直接民主主義を受け継いできた。しかし、こうした制度的・文化的断片は、合州国にいる多くの人々が今も大切にしている根深い価値観を反映している。つまり、独立・発意・自由・平等である。これらは草の根自治とトップダウンの代議制との現実的緊張関係を作り出し続けている。現代の革命家として私達はこうした緊張関係を足場としなければならない。
これらの価値観は、19世紀のユートピアコミュニティ実験から、社会的自由を求めた公民権運動闘争、1960年代に参加型民主主義を求めた「民主的社会を求める学生達」、1970年代の反核運動におけるアナキズムに刺激された親和グループの組織化、昨年のシアトル行動まで、北米左翼史全体に鳴り響いている。諸原則と諸実践双方において、合州国左翼は特に戦後に独創的で活動的だった。私達は、旧来の特権と危険な排斥に疑問を呈しながら、様々な「主義」に挑戦してきた。常に上手く行くとはいかないにせよ、内部的に民主的なプロセスをほぼ義務づけているような文化を自分達の組織内部で創り出してきた。私達は、デモから対抗機関まで全てのことを組織するのが得意なのである。
だからといって、過去や現在の左翼の活動を美化しようとしているのではない。むしろ、この国誕生の土台を作っている様々な価値観を得るための奮闘を私達も欠いたことはない、と指摘しようとしているのである。だが、当時も今も、私達の最大の誤りの一つは、政治それ自体--つまり、自由が出現するよう保証された場所の必要性--を無視しようとしてきたことにある。
クラッシュは、「空中で踊る(絞首刑になった)叛逆者」(「サンディニスタ!」収録の「叛乱ワルツ」より)について数年前に歌っていた。私達の政治闘争はこれを手本にしてきたようだ。街路や自分達のインフォショップ、コレクティヴの会議では力強く感じるかも知れないが、それは瞬間的であり、私的な感覚である場合が多い。公的政策に対処したり、敵対したり、対抗したり、その外部で活動しようとしたりするときでさえ、私達は政治的になることができる。だが、それは、公的政策それ自体を作り上げる場合のような政治を行わせない。自分が好まないこと「からの自由」に過ぎない。もっと正確に言えば、解放なのである。
「解放と自由は同じではない」とハンナ=アレントは「革命について」で主張していた。確かに、解放は基本的に必要である。人々は、危害・飢え・憎しみから自由にならねばならない。しかし、解放が自由に達することはまずない。自分のニーズと願望とを満たそうとするなら、自分の生活を管理しようとするなら、私達一人ひとりには、自己発達「への自由」--個人的に・社会的に・政治的に--が必要なのだ。アレントは付言している。「(解放)は、革命の中核的思想である自由の樹立を実現することはもちろん、理解することすらできない。」
全体としての社会に影響を与える決定は何処でなされるのか?これが革命的質問である。何故なら、これが権力が存在する場だからだ。今や、この場の扉を万人に開放する時である。何故なら、私達皆が平等で、公的政策が作られる場所--公的領域--に継続的に参加できて初めて、自由が足掛かりを得るための闘争機会を手にするからだ。
米国革命家にとって最も影響力のある理論家、モンテスキューは、その画期的な「法の精神」において「政治的自由の制定」に取り組もうとした。彼が到達した結論は、「権力が権力をチェックしなければならない」であった。革命後の合州国において、この考えは、最終的に、抑制と均衡のシステムとして合州国憲法に取り込まれた。しかし、モンテスキューの概念は遙かに発展的であり、権力それ自体の本質に触れている。問題は権力それ自体ではなく、制限のない権力である。つまり、モンテスキューの概念を徴用すれば、それ自体で目標となる権力こそが問題なのだ。権力は永久に自由と結び付かねばならない。自由は権力に課せられた制限でなければならない。少なくとも、トーマス=ペインは、「人間の権利」において米国革命にこのことを痛感させた。「旧制度における統治は、それ自体の肥大化のための権力占有である。新制度における統治は、社会の共通利益のための権力移譲である。」
自由が社会目的であれば、権力は水平的に保持されねばならない。私達は皆、支配者であると同時に支配される側でもなければならない。つまり、統治者かつ被統治者というシステムが唯一の代案なのだ。自由が権力と共存するのであれば、私達は、自分の手中に平等に権力を持たねばならない。言い換えれば、自由を維持できるのは政治権力の共有を通じてのみであり、この共有が生じるのは政治的諸制度を通じてである。権力は、独占されるのではなく、皆に分配されねばならず、そのことで私達の多様な「力」(理性・信念・意志決定などの)が開花できるようになる。これは支配の力ではなく、創造の力である。
もちろん、直接民主主義を制度化することは、自由社会の最低限を保証するに過ぎない。自由は既成事実ではなく、固定概念でもない。多分、新しい支配形態が常にその醜悪なる頭をもたげるであろう。しかし、最低限、直接民主主義諸制度は、万人がそのように望むなら誰もが審議・意志決定機関に集まることができる公的空間を開放する。それは誰もが説得し、説得される機会を持つ空間であり、いかなる議論も決定も隠されることのない空間であり、精査・説明責任・再考のために常に戻ってこれる空間なのである。真に開放的な政策決定メカニズムとして機能するとすれば、直接民主主義の中に萌芽として残っているのは、平等・多様性・協力・人間的価値の尊重といった価値観である。願わくば、こうした価値観が、連邦市民集会の範囲が永続的に拡大する中で、自分達のコミュニティ・経済・社会を自主管理し始める際に、解放的倫理の基礎となって欲しい。
実践として、直接民主主義は学ばれねばならないだろう。原則として、全ての意志決定を補強しなければならないだろう。制度として、勝ち取られねばならないだろう。魔法のように一夜にして出現することはないだろう。むしろ、マレイ=ブクチンが表現していたように、「共和国を民主化し、民主主義を急進化する」ための闘争から少しずつ出現するであろう。
私達は、全ての政治活動に政治を注入しなければならない。第二の米国革命を求める時期であるが、今回は、国民国家の絆を破壊する革命であり、国境も主人もない革命であり、民主的に行動する力で万人を十全に解放しながらリバータリアン自治の潜在的可能性をその限界まで駆り立てる革命である。これは民主主義という言葉それ自体--より良い代議制ではなく、世界を直接再構築する徹底的プロセスとしての--を奪還することから始まるのだ。
最終更新日:2006年2月6日