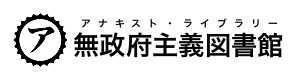マレイ・ブクチン
ディープエコロジー・アナルコサンジカリズム・アナキズム思想の将来
ブライアン=モリスがディープエコロジーに対して行った傑出した批判に私が付け加えることなどほとんどない。実際、エコ神秘主義を取り巻く議論へのモリスの貢献は、総じて、痛烈であると同時に洞察を持ったものであった。私は彼の著作を読むことは優れた教育経験だと考え、英国だけでなく合州国の幅広い徴収の耳に届くことを希望するものである。
また、アルネ=ネスのエコロジー・コミュニティ・ライフスタイルに対するモリスの書評が、「ディープエコロジーの父」の知的貧困と、全てのディープエコロジー「運動」の馬鹿さ加減を明らかにしてくれることを望んでいる。ロドニー=アイチェティのディープエコロジー:人間と乖離していないは、どちらかと言えば軽はずみで、不適切な箇所も多く、神秘主義的なのだが、私には、これまで長い間見てきたディープエコロジーに対する反論の中では多分最良のものだと思われる。だが、ここ数年間、北米のディープエコロジストとやり取りした後に、私は、ネスたちの従者は信念に突き動かされているのであり、理性的衝動ではなく神学的衝動に基づく忠誠心に動機づけられているのだ、という結論に残念ながら到達した。そこには、この種の信念システムを揺るがすような理性的議論など全くない--したがって、この思慮のないドグマを扱うだけのエネルギーを未だに持っている人々にこの問題の論議をお任せすることにしたのである。
モリスが行った痛烈な観察にもう一つだけ付け加えさせてほしい--と言うよりも、多分それを強めることになるのだろう。全ての生物はその「内在価値」という点でお互いに公平で有り得るというディープエコロジーの生物中心的格言は、人間が出現する以前の長期にわたる有機的進化の中で何か意味を持っていたのだろうか、ということを疑問に思っている人がいるかも知れない。ディープエコロジーの概念的枠組み全ては、完全に人間的媒介--自然界で人間種にユニークな立場を与えている事実--の産物なのである。全ての倫理システム(生物的進化に基盤を持ちうるものを含めた)は、明らかに文化的諸状況の中で人間が形成したものなのだ。このシーンから人間的媒介を剥ぎ取ってしまえば、動物が、散漫だとか、有意義だとか、道徳的だだとか見なすことのできる行動を示す、という最小限の証拠すらなくなるのだ。アナキスト地理学者だったエリゼ=ルクリュが、猫は(マリー=フレミングによるルクリュ伝のイントロダクションでジョージ=ウッドコックが引用しているところによれば)「自然のアナキスト」だとか、もっと悪いことに、「それら(つまり、猫)が、時として理解したり分かち合ったりしていない人間感情など、見抜いていない考え(原文のままだ!)など、予見していない願望など一つもない」と書いている。ルクリュは動物行動学的にも生態学的にもナンセンスを書いているのだ。アナキスト著作者が、こうした神人同型同性説的戯言を述べている著者を「エコロジカルだ」などと褒めそやすことは、少なく言っても残念きわまりない。「内在価値」が近代エコロジー思想で心地よい直感的洞察以上の何かであるとすれば、それは、人間が自分の精神の中で形成した「属性」なのであり、人間が動物などの他の生命体に授与することを決めた「権利」なのだ。人間精神や人間の社会的価値観を操作することとは別個に存在してはいないのである。
ディープエコロジーのあほらしさから、グラハム=パーチェスが押し進めているアナルコサンジカリズムの途方もない説明へと目を転じたところで、報われそうにない仕事である。それが本の形で出版されることになっていなければ、私は無視したであろう。パーチェスの一編、社会生態学・アナキズム・労働組合主義は、私が好戦的に文章を書いており、「北米アナキストと労働組合主義者を侮辱」しているとして私を非難することで始まり、私がこれまで長い間出会った中でも最も罵倒的で、感情的な人格攻撃を私に浴びせかけている悪意に満ちたエッセイである。私は、『良くて非建設的、悪くて全く有害な』だけでなく、さらに悪いことに、私は『飽くことを知らない論争への欲求』に身を焦がしている、とパーチェスは読者に警告しているのである。パーチェスは、アナキスト運動の中での私の役割について、確かにバランスがとれ挑発的ではない客観的な評価を押し進めながらも、自分の精神分析的慧眼をひけらかしている。私は、『「新しい」エコロジー運動の知的指導者・創設者になるという不健康な願望』に冒され、『知的な精神分裂病』の兆候を示し、最終的に、私は、『アナキズム理論と実践が持つ主要な生態学的洞察全てを盗み、ネオヘーゲリアンの外観を伴った社会主義フェミニスト(!)の様相をそれらにまとわせ、それらを(私)自身のものだと多かれ少なかれ主張し続けている』と断言されているのだ。あたかも、この程度の罵倒では充分ではない--まさしく、私自身の『飽くことなき論争の欲求』を鎮圧しようとしてくれているのだろう!--かのようにして、それに続けてパーチェスは、私が一ダースほどの著書と数多くの論文で押し進めていた見解の総体を、『知的暴行』だと特徴づけているのである。
私の観点がどのように進化してきたかについてパーチェスの混乱していることが多い説明--1960年代後半と1970年代には「アナキスト=エコロジスト」で、1980年代と1990年代に「乱暴な」反サンジカリストそして反アナキストの「社会的エコロジスト」へと変化しただけだと仮定しているが--を正そうとしたところで、それはくだらないだけでなく、退屈なものにもなろう。彼の説明のばかばかしさを整理することは私の著作を真面目に読んでいる方にお任せすることにしたい。ここでは、いくつかの点を指摘することで充分であろう。あらゆる種類のプロレタリア階級と労働者の支援を抜きにして社会を根本的に変革できるなど、誰も信じてはいないし、中でも私が最も信じていないのだ。だが、マルクス主義者が伝統的に産業労働者に割り当てていた--アナルコサンジカリストは単にそれをオウム返しにしていた--「覇権的」役割を産業労働者が演じると仮定することは、急進主義思想と実践を徹底的に窒息させることなのである。アナキスト社会を求めた闘争でプロレタリア階級に覇権的役割を割り振っている諸理論--労働史家は「プロレタリア社会主義」と総称的に示しているが--に対する私の批判は、単に、それらは廃れている、ということなのである。プロレタリア社会主義の時代が歴史へと推移した理由は、私自身だけでなく、あらゆる種類の真面目な急進主義理論家--アナキストも含めてだ--によっても探求されてきた。私は、私自身の人生の数十年の経験から、産業労働者は、男性・女性、夫・妻、父親・母親、兄弟・姉妹、実際、隣人・市民としての方がもっと容易く接することができる、ということを学んだ。産業労働者は、自分を無情に搾取している工場を「管理する」かどうかについてよりも、地域の諸問題・公害・公教育・民主主義・道徳・自分の生活の質についてもっと関心を持っているものだ。実際、私が鋳造場と自動車工場で長い間共に働いていた労働者と労働組合員の大多数は、労働時間が終わると、生産スケジュールや職務割り当てについて熟考するよりも、工場の外に出たいと熱望していたのだった。
我々が、革命的覇権階級としてのプロレタリア階級の歴史的性質を誤解していた(付け加えれば、これは伝統的アナキストの失敗ではなくマルクス主義の失敗である)ということは有り得ないだろうか?工場システムはプロレタリア階級を組織し、急進化することなどなく、命令と服従という産業システムにプロレタリア階級を一貫して吸収していた、ということは有り得ないだろうか?資本主義と労働者階級は、19世紀と20世紀初頭以来、停滞してはいないだろうか?それとも、資本主義と労働者階級は、伝統的マルクス主義者だけでなくアナルコサンジカリストにも大きな挑戦を提起している--そして、その主張をはっきりと無効にしている--根本的変革を共に経験してきたのだろうか?優れた先見の明を持って、バクーニンは、労働者階級が「ブルジョア化」する可能性について自分の恐怖を表明し、そして、もっと一般的に、『大衆が、中央集権的で国権主義的な腐敗した文明の有害な影響力によって、骨抜きにされることは言うまでもない。それ以上に、深く混乱し、無感動になることもあったのだ。』と述べていた。バクーニンの恐怖は、単にその時代にだけ適用される戦略的見解の表明ではなく、今でも、言い逃れよりも説明を必要とする歴史的判断なのだ。今日、いわゆる「進歩的」資本主義事業は、雇用・解雇・生産分配率の設定を労働者と共有することで、プロレタリア階級を自分自身の搾取との共謀関係に持ち込みながら、非常に見事に成功しているのである。
パーチェスは、こうした重大な発展と、私や他の人々が行ってきた分析を無視しているだけでない。彼は、社会主義、実際、労働組合主義に対する批判を、アナキズムそれ自体に向けられた敵対の表明だとして、莫大に誤解し扇動的に再定義しているのである。パーチェスがアナキズムとサンジカリズムの歴史について非常に良く知っていると仮定すれば、この論法は誤魔化しであり、全くの歪曲なのだ。だが、ここでは寛大に考えて、これはある程度の無知と、精力的に非難されて然るべき偏狭さの現れなのだと言っておこう。事実はといえば、19世紀後半に、サンジカリズムがアナキストの間で問題になったとき、猛烈に議論がなされたのである。世紀の変わり目のアナキスト運動にいた傑出した人物--エンリコ=マラテスタ・エリゼ=ルクリュ・エマ=ゴールドマン・セバスチャン=フォールなど--は、当初、サンジカリズムに様々な理由で反対したのだった。その理由の多くが、彼らが持っていた多くの先見の明を示していた。やがて、彼らがサンジカリズムを受け入れるようになったとき、その多くは非常に用心深く受け入れたのだった。マラテスタはサンジカリズムに対する根本的批判の中で、革命的精神の発生は『労働組合の機能に関わる標準的で自然な定義にはなり得ない』と論じていた。マラテスタは最終的に、はっきりと不本意ながらもアナルコサンジカリズムを受け入れたものの、多くのサンジカリストが受け入れる覚悟がある以上に、もっと広範なアナキスト組織と実践の必要性を継続して要求していたのだった。
実際に、アナキスト集団は、アナルコサンジカリスト組織--アナキズムを避けていたサンジカリスト組織は言うまでもなく--とはっきりと対立するようになることが多かった。今世紀初頭、スペインの無政府共産主義者は、Tierra y Libertad 誌の編集者ヒュアン=バロンとフランシスコ=カルディナルに主として影響され、後年CNT形成したアナルコサンジカリストを「逃亡者」であり「改良主義者」だと激しく非難した。同様の対立は、イタリア・フランス・合州国でも発展し、多分、それも理由なきことではなかったのだろう。アナルコサンジカリズム運動の記録は、アナキズム史全般の中でも最も酷いものの一つであった。例えば、メキシコ革命で、Casa del Obrero Mundialのアナルコサンジカリスト指導者は、恥ずかしくも、プロレタリアからなる自身の「赤の大隊」を、この革命で最も血に飢えたごろつきの一人であるカランサの指揮下に置き、真に革命的だったサパタの義勇軍と戦わせたのである。結果として、いくつかのほんの僅かな改良を得たが、共同行動でサパティスタの挑戦を打ち負かすと、カランサはその改良を撤回したのだった。メキシコの偉大なるアナキスト、リカルド=フローレス=マーゴンは、アナルコサンジカリストの行動を裏切りだと正当に非難したのだった。
同じことが、スペインのCNT指導者を弁護する時にも言える。CNT指導者は、1936年後半にマドリー政府の「大臣」になることで、そのリバータリアン原理を取り消してしまった。このことについて、CNT信奉者の多くが反対したわけではないのだ。もう一つ付け加えなければならないが、1937年5月に、バルセロナのプロレタリア階級がカタルーニャの首都でスターリニスト反革命に抵抗しようとしたときに、CNT指導者は威信を使って彼らを武装解除させたのである。合州国については、今日のアナルコサンジカリストたちが世界産業労働者(IWW)のような伝説的運動に夢中にならないように、このサンジカリスト運動は、他の国々同様、決してアナキズムにコミットしていなかったとアドバイスしておかねばなるまい。最も有名な指導者「ビッグ=ビル」ヘイウッドはアナキストではなかった。それでも、他のIWW指導者の多くはアナキスト的見解に傾いていたが、1920年代には共産党員になっただけでなく、1930年代とその後は熱心なスターリン主義者になったのだった。真面目なスペイン=アナキストが、CNTに参加したものでさえも、FAI(イベリア=アナキスト連盟)に対するCNTの労働組合メンタリティの影響を有害で、究極的には破滅的だと見なしていたのだった。市民戦争の終わりに近づくと、FAIがCNTをコントロールしていたのかどうか、逆に、もっとありそうなことだが、CNTが、その強力な労働組合メンタリティを持って、FAIのアナキスト原理を本質的に水増ししたのかどうかが問題になった。欧州において成長していたサンジカリスト運動の圧力下でアナキスト原理がサンジカリスト原理と併合されてしまうことを注意深く受け入れていたときでさえ、マラテスタは非常な洞察力を持って宣言していた。『労働組合は、生来、改良主義的であり、革命的になることはない』(強調は筆者)と。大言壮語を持ってサンジカリズムをアナキズムと同等視し--無知なだけでなく馬鹿げている傲慢な行為だ--、そして続けて、労働組合主義とサンジカリズムを本質的に同等視しているグラハム=パーチェスのような無骨者は、軽蔑するだけの価値しかないのだ。
過去におけるアナキストの正真正銘の焦点は、コミューンや自治体であって、工場ではなかった。工場は、決定的要素ではなく、もっと広いコミューン構造の一部でしかないと一般に認識されていた。サンジカリズムは、プロレタリア階級と産業的環境をその焦点として抜擢することでこの幅広い見地を狭めてしまったという意味で、伝統的アナキズムが創り出したもっと全般的な社会的・道徳的風景を重大に狭めてしまったのである。大部分、このイデオロギ-的後退は、フランスとスペインで19世紀の終わり数年間で工場システムが勃興したことを反映していた。だが、特に卑俗な経済優先主義的マルクス主義(その名誉のために言っておくが、マルクスは労働組合主義をそれほど重んじてはいなかった)の優位性を反映してもいたのである。多くの素朴なアナキストとノンポリ労働組合主義者はそれに屈服してしまったのだ。スペインのアナルコサンジカリズム実力者の一人、アバド=デ=サンティリャン著、革命の後では、プラグマティックな経済優先主義へのこのシフトを映し出している。それは、彼自身の見解を、スペイン社会主義者の経済優先主義と何ら区別できないほどにまでしてしまう形でなされたのだった--そして、もちろん、カタルーニャ政府との共謀へと、そして文字通りスペイン=アナキズムの墓堀人の一人へと彼を導いたのである。サンジカリズム--それがアナルコサンジカリズムであろうと、それほどリバータリアン的ではない変形物であろうと--は、アナキズムが持つ大規模な辺境的で無能な個人主義的諸傾向を除けば、アナキズム運動史におけるいかなる要因よりも、アナキズムの倫理的内容を変質させるために数多くのことをなしたのであろう。実際、アナキズムがサンジカリストの遺産を振り払い、その共同体連合論的で共産主義的な遺産を拡大しなければ、アナキズムは、卑俗なマルクス主義に美辞麗句をかぶせ、思慮をなくした物真似であり、歴史の中に消え去った時代の亡霊以外の何者でもなくなるであろう。
だが、ドイツ人が、genug!と言うように、私はパーチェスとその類に対して同じことを思っている。自身の信念が持つ知的・実践的軌道の酷い無知さ加減を露呈している愚劣さを持ったまま一足飛びに本を出版する前に、彼らにアナキズムの理論と実践が持つ歴史的・原文的基盤を徹底的に吟味させてやらねばなるまい。そして、私自身の見解を批判することを企てる前に、私が歴史と、労働者運動の失敗について書いてきたことを彼らに骨を折って読んでもらわねばならない。だが、私が酷く恨みがましく思っていることは、私が自分の生態調和的観点を『アナキズム理論と実践』から『こそ泥している』という馬鹿げた示唆--もっと分別のあるアナキストでさえもが時として示すことがある示唆だ--なのである。事実、私は社会生態学(エコアナキズムの見解と私は呼んでいる)のためにアナキストの先人たちを過剰に引用しようとしてきたし、できる限りあらゆる場所でそうしてきた。1982年に--つまり、パーチェスによれば私が社会生態学のためにアナキズムの見解を放棄した時期に--書かれた自由の生態学は、クロポトキンの倫理学からの題銘で始まっている。この本の謝辞で、私は、『相互扶助とアナキズムに関するピョトール=クロポトキンの著作は永続的な伝統を保持している。これが、私がコミットしているものなのである。』と書いた。クロポトキンに関する限り、私がこれから説明する様々な理由で、少々大げさであるが、テキストには、私の心からの賛同を表明している相互扶助論からの広範囲の引用を含め、好ましく、多くの場合賞賛を持って、少なくとも彼文章を9つ参照しているのである。私がエリゼ=ルクリュに言及していなかったとすれば、それは、私が、マリー=フレミングにより1988年に出版された自伝を、ほんの数週間前に初めて読むまで、彼の著作と見解について何も知らなかったからなのだ。だが、今振り返ってみても、私がどのような場合であれルクリュを引用していたとは思えないが。
過去のアナキスト著述家と私との親和性を私が引用しなければならないほど、アナキスト墓守は非常に重要な点を見過ごしていることが多いのだ。社会生態学は充分に統合され一貫した見解である。それは、自然進化とその進化プロセスにおける人間の場所に関する哲学、生態学の方向性にそった弁証法の再案出、ヒエラルキー出現の説明、支配と自由の遺産と認識論との間にある弁証法の歴史的検証、歴史的・倫理的・哲学的見地からのテクノロジーの評価、マルクス主義・フランクフルト学派・正義・合理主義・科学主義・道具主義の広範囲にわたる批判、そして最後に、相補性(complementarity)という客観的倫理に基づいたユートピア的で権力分散型で連邦主義的で美学的基盤を持った未来社会のヴィジョンの推論を包含している。私は、これらの考えを、単なる主題目録として示すのではなく、高度に一貫した見解として示している。それ以上に、社会生態学が部分部分の総和以上のものであるということを認識しようとするのなら、自由の生態学は、Green Perspectivesに主として掲載された数編の重要なエッセイは言うまでもなく、その後に出版された都市のない都会化・社会生態学の哲学・エコロジーと社会で補完されねばならない。
適切であろうとなかろうと、こうした著作が持つ全体調和論的(ホリスティックな)総体は、私の知る限り全く私の著作の結果として存在するようになった言葉「エコアナキズム」を、急進主義社会理論における最良の体系だった著作と、理論的・知的に同等の位置に置こうと努めていたのだ。この集成をバラバラにするために、私がこの総体へと発展させた思想に対して、著名な19世紀アナキストの諸著作の中から先人一人を引用し、その結果、私が、現代にとって有意義で、関連した総体へと統合しようとしてきたことの一部だけを扱うことは、単に馬鹿げているだけだ。同じようにすれば、いかなる社会理論体系、科学理論体系さえもの、体系だった説明を、歴史的先行者を引用することで、様々な断片的構成要素へと還元してしまうこともできるだろう。何らかの「こそ泥」が行われているとすれば、それはアナキスト墓守が行っているのではないだろうか。彼らは、社会生態学との関連という点で過去数十年間にわたりアナキズムがいかなる名声を獲得してきたにせよ、その名声から自分自身は利益を得ているくせに、「それはずっと前に私たちが言っていたことだ」というどちらかと言えば独りよがりの自慢を万能産業へと変質させているのだ。私が彼らと出会ったときに、こうした擁護者たちの傲慢さとドグマティズムに触発されなければ、私はこのような主張などしなかったであろう。事実はといえば、クロポトキンは私がマルクス主義からアナキズムへと転向することに何の影響も持っていなかったのだ--この点に関して言えば、バクーニンからもプルードンからも何も影響されなかったのである。私が、リバータリアン系譜の中で、50年代と60年代に充分入ってからゆっくりと発展させた諸見解を定着させるために最も有効だと思ったものは、ハーバート=リード著アナキズムの哲学だった。したがって、私の1964年のエッセイエコロジーと革命思想においてリードに重大な注目を向けていたのだ。奇妙に思えるだろうが、初期のエッセイで私が示した諸見解を勃興させたのは、マルクスとエンゲルスによるアナキズム批判に対する私の反応・アテネのポリスに関する読み込み・情報が豊富なジョージ=ウッドコックのアナキズム史・生物学者としての私自身の副業・テクノロジーの研究だったのであり、初期アナキストの著作を包括的に読んだことではなかったのだ。独善的アナキストの中にはそのように主張するものもいるが、もし私がアナキズムの伝統の「中で生まれて」いたのなら、私は当然プルードンの交換志向的契約主義が癪に障り、労働運動での長い経験の後に、グラハム=パーチェスとその類が押し進めているサンジカリズムの戯言に悩まされていることだろう。
1980年以降の社会生態学に関する私の著作を、それ以前の「忠実な」アナキズムだと思われている著作と区別するというパーチェスの愚かな試みは、社会生態学の発展について多くの事実を説明せずに放置している。私は、資本主義が生み出した生態系混乱に関する、初めての、ほとんど一冊の本ほどの長さの著作食物に混在する化学物質の問題を1952年に書いた。当時、私はネオ=マルクス主義者であり、アナキスト思想家からは何ら影響を受けていなかった。マルクスの見解の多くが、私の欲望充足(post-scarcity)という概念に重大に寄与し、それは私が未だに頑なに守っている正にその「1980年以前」の見解なのである(付け加えておけば、1930年代にスペインのアナキストの中には、同様の見解を持っているものもいた、ということを私は数十年後にスペインのアナキストを著したときに発見した)。私のアナキズム的見解がマルクスの諸概念のいくつかによって「質を悪く」されているのかも知れないという懸念を少しも持たずに、私はこのこと全てを述べているのである。バクーニンと共に、私は、マルクスが急進的理論に貴重な貢献をしたという見解を共有しているのである。その貢献は、彼の権威主義的政治や見解を受け入れずとも、容易に評価できるものなのである。アナキストがマルクス--この点について言えば、ヘーゲルさえをも--を愚かなほどに悪魔的に扱うことは、リバータリアン思想に役立てるために持ち込まねばならない考えが持つ芳醇な遺産を放棄することなのである。丁度、多くの生物学者の優れた著作が生物学思想に役立つように持ち込まれねばならないのと同じである。だからといって、マルクスの中央集権主義・「労働者の党」へのコミットメント・国民国家の支持といったマルクスの莫大な誤りを受け入れねばならない、などと言っているのではない。ヘーゲルの弁証法を学ぶことが、「絶対者」・厳格な神学システム・混成している企業議会君主制・ヘーゲルが「絶対的観念論」と広く呼んでいたものを必ず受け入れねばならないということを意味していないのと同じである。
同じ理由で、我々が伝統的アナキズムの洞察を、その欠点を率直に扱うことなく賞賛するならば、自分自身以外の何者をも騙すことに他ならないであろう。国民国家に対する連合主義的社会組織概念を発展させ、産業資本主義--マルクスがその著作のほとんどでドグマ的に賞賛していたシステム--の攻撃に晒されていた職人と農民の権利を擁護したことについては、プルードンに正当な名誉が与えられてしかるべきである。だが、契約的経済諸関係に対するプルードンのコミットメントを無視することは単なる近視眼であろう。それは、「各人へは能力に応じて、各人からは必要に応じて」という共産主義の格言とは区別されるものなのである。プルードンの契約主義は、その連合主義的諸概念に浸透し、ブルジョア概念である「権利」と区別することなどできないものであった。契約的交換へのプルードンの傾向を「社会契約」という疑似哲学的概念へ向ける試みがなされてきているにも関わらず、私はこのことを述べているのだ。
プルードン主義が本当に社会契約だったとすれば、私の目には、それは非常に不満足なものだったと思われる。プルードンの連合主義の原理に対するイントロダクションでリチャード=ヴァーノンが、プルードンは、連合主義を、自身の初期の非常に私事本意主義的アナキズムを抜粋したものだと見なしていた、と述べていることを無視することも出来はしない。注意深く考察してみれば、プルードンの見解は、自由奔放で、一見して「主権を持った」個々人・職人・コレクティブさえもの存在を前提としているように思われる。それらの存在は、共産主義的「所有」システムとモノの分配にではなく、契約的で交換的な諸関係と財産所有を中心として構築されていたのだった。
さらに、バクーニンは共産主義者ではなく集産主義者だと公言し、特にその組織に関する見解は、それ自身で矛盾していることが多かった(ここで、パーチェスに思い出してほしいのだが、フーリエは、その多くの芳醇な洞察にも関わらず、いかなる意味でも社会主義者でもアナキストでも革命家ですらなかったのである)。「科学的アナキズム」という題目の元でバクーニンの多くの著作のほんの一部をマキシーモフが組み合わせたものは、バクーニンの洞察の多くが今日の正統派アナキストにショックを与えるのと同じように、多分、バクーニンを仰天させることだろう。私はといえば、大部分バクーニンに同意している。例えば、『自治体選挙はいつでも民衆の真の態度と意志を最もよく反映するものだ』という点などについてである。ただ、この点については、彼の公式を、自治体選挙は国会選挙よりも民衆の意志を正確に反映できる、という意味に言い直したいが。しかし、どれほどの正統派アナキストはバクーニンの見解--もしくは私の制限付きの見解--に同意するのだろうか?この問題についてアナキスト伝統主義者と「ピュアリスト」から私が出会った極度の抵抗が、今日、アナキズムの伝統の一部としてのリバータリアンで、参加型で、自治体主義的で、連邦的政治を発展させる可能性を実質的に排除してきたのである。
時代と場所を考えれば、クロポトキンは、私がリバータリアンの伝統で出会った中でも最も先見の明がある理論家の一人であろう。60年代後期になるまで、クロポトキンの著作の重版は北米書店に現れることはなく、そのときになって、私が田園・工場・仕事場に(そしてその後には、この本についてコリン=ワードの素晴らしい要約に)に親しむようになり、60年代中期になるまで、私は相互扶助論の一部--つまり、中世諸都市をあつかった中核の部分--を読んだことはなかった。ざっくばらんに言って、これらの本が私の見解にかなりの影響を及ぼしたわけではなかった。むしろ、私の見解を確認し、アナキズムに対する私のコミットメントを強めたのだった。同様に、1974年の拙著都市の限界は、私が1958年に書いた非常に長いエッセイを中心に纏められ、1960年代になるまで私が英訳本を見たことがなかった経済学批判要綱で示していた街と国との関係に関するマルクスの観察のいくつかに知らず知らずのうちに対応していた。実際、マルクスの資本論に強く影響された著作、都市の限界を育成していたのは、歴史の方向性に及ぼす都会の発展に関する私の研究だったのである。この本では、その後の付記ページで都市設計の歴史で示しているように、偶然にクロポトキンを引用していただけだったのである。私がこのバックグラウンドを引いたのは、1980年以前と1980年以後の私の発展というパーチェスの区別がどれほどナンセンスなのかを示し、そして、パーチェスがどれほど私の著作について、ましてや私の著作を育成してきたイデオロギー的・哲学的・歴史的源泉の「系譜」と多様性について、知らないのかを指摘するためである。
クロポトキンなどのアナキスト著作者から略奪することとはほど遠く、私は、繰り返し言うが、過去に彼らに対する恩義を誇張しがちであった。私はアナキズムの持つ海賊的諸概念に同意したことはない。その諸概念は市民的団結と民衆集会に基づいたコミューンという幅広い概念だけでなく、通常の専門的・科学的協会にも依拠しているのだ。それ以上に、「革命的本能」(バクーニン)に主として根差している革命主義や、「社会的本能」(クロポトキン)に主として根差している相互扶助主義は、真面目な説明に対する曖昧模糊とした代替物以外の何者でもないのだ。本能理論は、非常に注意深く扱われねばならないものであって、さもなくば、全くの社会生物学へとゆだねられてしまう。相互扶助論を妥当なものにするためにクロポトキンが動物全般に対して「社会的本能」をどちらかといえばルーズに帰属させたことは、私の観点では、特に問題がある。その理由は、それが非常に選択的な動物の研究に基づいていた--クロポトキンは、非常に進化した哺乳類にも孤独を好む動物が数多くいることを無視しがちだった--ということだけではない。もっと問題なのは、クロポトキンが、動物の群れや一時的コミュニティを、社会--つまり、自分の関心と意志によって、その諸制度を形成・発展・転覆・廃止するという明らかに人間的能力という点で変更可能な、非常に変化しやすい諸制度--と混同しがちだったのである。
エリゼ=ルクリュに関しては、彼は、クロポトキンの見解のある種の要素を馬鹿げていると思われる点にまで拡大したのだった。猫がどれほどまでに我々の「感情」・「願望」・「思想」を「理解したり共有したりする」とか「予見する」のかを理解することなど私にはできない相談だ。ルクリュは、私がこの論文の冒頭近くで使った引用において、猫はそうしていると主張しているのである。ルクリュのような非常に聖人のようで心優しいアナキストについて私が疑いをはさむことで、私が猫を飼っている人々から嫌な目で見られることは確実だ。だが、私はそうした神人同形同性説を素朴だと思うのである。「地球と人間との間に秘密のハーモニーがある」、それを破壊すると「無分別な社会」は必ず後悔するだろう、といったルクリュの観点は、あまりにも曖昧すぎ、時として神秘的すぎて、寛大な感情以上の何かであるとは見なせないのである。確かにそうした感情を尊重することはできる。だが、数え切れないほどの著作者(非常に反動的な自然浪漫主義者たちを含めた)は、これまで、本来的にエコアナキストだと自身を見なすために、もっと断固としてそれを繰り返し述べてきたのだ。ディープエコロジー・エコ神学・空っぽ頭の心霊主義者どもは、どう扱えばよいのか私が知っている以上に、人間性と非人間的自然との「秘密のハーモニー」をもっと多く見いだしてきたというわけだ。私は、アナキスト・断固たる革命家としてのルクリュを確かに賞賛するが、自然界に対する彼の特殊な見解が、エコアナキズムと共に、その善意とは別に認められてしまうのなら、私は不安になるだろう。
そう、プルードン・バクーニン・クロポトキン・ルクリュ・マラテスタなどの主導的アナキスト思想家に、当時彼らが行ったこと・彼らが我々に提供していることに対する正当な栄誉と尊敬を与えよう。だが、アナキズムは、彼らが一世紀前に海図で示した部分を越えて進んではいけないのだろうか?我々の中でそうしようとする人がいれば、グラハム=パーチェスのような共同墓地守護者の暴政下に生きねばならないのだろうか?パーチェスは、棺桶から骨になった指を持ち上げ、生態学調和を志向した社会的諸関係と人間性の自然に対する関係について、現在にはそぐわず、取りかかりとして始めるには非常に誤りの多い公式を持っている19世紀アナキストの文章を無視している、と我々を非難する--ここにヒントがある、そこに先人の断片がある、かなりの長さの一節さえもがある、というわけだ--と思われる。我々は確かに、過去の偉大なるアナキスト思索者が押し進めた見解の上に立つことができる。だが、我々は、彼らが押し進めた諸概念よりももっと洗練された諸概念、連邦主義・反国権主義・権力分散主義・自由の定義・自然界に対する感性の必要性を無視しなければならないのだろうか?彼らの諸見解の中心となっていた多くの概念で、我々が無視せざるを得ないものも数多くある。こうした進歩と、そして望むらくは、その進歩が示している一貫性が、全体としての文化発展史の一部なのである。アナキズムは、その墓守のために、さらなる発展と改訂ができないように免疫をつけられてしまうのだろうか?私は、そうならないことを望んでいる。特に、アナキズムとは、ほとんどその定義になってしまうのだが、社会的領域だけでなく、思考領域での自由の行使でもあるからだ。アナキズムを地下室に閉じこめ、聖地から「こそどろした」戦利品だとしてリバータリアン思想の革新的一群を非難することは、リバータリアン精神と、リバータリアンの伝統が示している全てに対する侮辱なのだ。時代は確かに変わるのだ。アナルコサンジカリズムが「歴史的主題」もしくは革命の行為者として頼りにしていたプロレタリア階級とほんの僅かばかりの農民は、最良の場合でも数の上で激減しており、最悪の場合には既存システムに統合されてしまっている。資本主義が持つ最大の矛盾は、システム内部のものではなく、システムと自然界との間にある。今日、全ての抑圧された人々の中で--厳格に産業労働者だけではなく--大きなコンセンサスが成長している。それは、生態系の混乱は、途方もない問題を、我々が知っている生物圏を破滅させてしまってもおかしくないほどの問題を生み出している、というものだ。人間一般の懸念・目に見える生物圏を維持し保全する必要性・背景と社会層が全く異なる人々が持っている一つの懸念が出現すると共に、アナルコサンジカリズムは、運動としても思想体としても、単に廃れたものになったのである。社会的・文化的・道徳的風景全体を一変させ、伝統的アナキズムを発展させた世界の良質な部分を消してしまった歴史的変化に、アナキズム理論と実践が歩調を合わせる--それを乗り越えることはともかくとして--ことができなければ、アナキズム運動全体は、確かに、テオドア=アドルノが呼んだもの--亡霊--になり果ててしまうだろう。アナキズムの伝統を首尾一貫して近代的に解釈するという全ての試みが分断され、切り刻まれ、小分けにされて先祖(その見解は現代よりもそれぞれの時代に適していることが多いものだ)に配られてしまうなら、リバータリアンの伝統は、アナーキー的な再洗礼教徒が消え失せたように、確実に、歴史の中に消え失せてしまうであろう。そして、資本主義と右翼が、確かに、社会を完全にその統制下におき、自称リバータリアンの考えは、イデオロギー博物館の中で遺跡になり果てても当然であろう。それは、ジャコバン主義が現代そうなったように、次の世紀ほども遠くはないことであろう。
Murray Bookchin
July 11, 1992
Institute for Social Ecology
P.O. Box 89
Plainfield, Vermont 05667 USA
(802) 454-8493