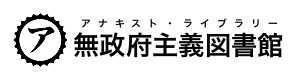マレイ・ブクチン
連邦主義の意味
顔をつきあわせた参加型民主主義の主張に異議を唱える論法の中で最も有効なものは、我々が「複雑な社会」に生きているというものである。近代の人口密集地域は、あまりにも大きすぎ、あまりにも集中しすぎていて、直接的意志決定を草の根レベルでできないようになっている、と言われる。さらに、我々の経済は、あまりにも「グローバル」過ぎて、多分、生産と取引の複雑さを解体することなどできないだろうとされる。そして、現代の多国籍で、多くの場合非常に中央集権的な社会システムでは、政治・経済生活の民衆管理というユートピア的な「地域型の」枠組みよりも、国家の代議制を整備し、官僚制度的諸機関の効率を高める方が良い、と忠告されるのである。
結局のところ、そうした主張は次のように進む。中央集権主義者は、「さらなる権力を民衆に」、少なくともその代表者に渡す、ということを信じているという意味で、本当は「地方主義者」である。確かに、良い代表者は、その「有権者」(「市民」という言葉の傲慢な言い換えの一例であるが)の望みをいつも知りたいと思っているのである。
だが、顔をつきあわせた民主主義だと?この「複雑な」現代世界で、国民国家に対する民主的代案を手に入れることができるなどという夢は忘れてしまえ!多くの実際的な人々は、社会主義者も含めて、この種の「地方主義」を望ましいとする主張を、この世のものだとは思えないとして片づけてしまうものだ--良く言って悪気のない恩着せがましさであり、悪く言えばあからさまな嘲笑だ。事実、もう数十年前になるが、1972年に、民主社会主義者、ジェレミー=ブレッカーの雑誌Root and Branchで、私は次のように挑戦されたのだ。一例を挙げれば、ハドソン川はニュージャージー州パースアンボイのようなその下流諸都市が飲料水として利用しているわけだが、私の著書欲望充足のアナキズム(Post-Scarcity Anarchism)で示した地方分権主義者の見解は、ニューヨーク州トロイがハドソン川に未処理廃棄物を捨てることをどのようにして防ぐのか説明してほしい、と。
状況の上っ面だけを見れば、ブレッカーのような中央集権政府賛同の論法は、少々抵抗しがたいもののように思える。ある地域が他の地域を生態学的に苦しめることを防ぐためには、確かに「民主主義的」ではあるが、それでもなお大規模にトップダウンの構造が必要だと仮定されているのである。だが、地方分権に敵対する慣例的な政治的・経済的主張は、パースアンボイの飲料水の運命から、証拠なしに言われている我々の石油「中毒」まで幅広いが、数多くの非常に問題ある諸前提に依拠している。最も気がかりなのは、そうした論法が、現状の経済体制を無意識に受け入れている、ということである。
地方分権と自給自足
現在存在しているものは必ず存続するはずだ、という仮説は、あらゆる空想的思考を腐食させる酸である(近年の急進主義者の傾向として、国家社会主義の欠点と市場経済の欠点を扱うのではなく、「市場社会主義」を支持していることが見られるように)。疑いもなく、今後も、朝の食卓で朝のリフレッシュを必要としている人々のためにコーヒーを輸入しなければならないだろうし、意図的に仕組まれた使い捨て経済が産み出すジャンクではなく、もっと長持ちする品物をほしいと思っている人々のために外国製の金属を輸入しなければならないだろう。だが、過密した、実際息苦しい地帯にぎゅうぎゅう詰めにされた数千万人の全くの非合理性はさておくとしても、現在のように労働を過度に国際分業させることが人間の欲求を満足させるために絶対必要なことなのだろうか?それとも、これは、多国籍企業に莫大な利益を提供するために創り出されているのだろうか?我々は、石油(その究極の産物は大気汚染物質と石油によって生成された発癌物質である)が豊富な地域と近代の経済生活をきちがいじみたほど連結させながら、第三世界からの資源の略奪という生態学的諸結果を無視しなければならないのだろうか?この「グローバル経済」は、急速に拡大している産業官僚制度と、成長か死かの競争市場経済の結果なのだ。この事実を無視するなど途方もない近視眼なのだ。
自給自足の尺度を確立するために、充分な生態学的根拠を探求する必要などない。大部分の環境保護志向的な人々は、労働の大規模な国内分業と国際分業が、言葉の文字通りの意味で、極度に無駄だということに気がついている。労働の過剰分業は、巨大な官僚制度型の過剰組織化を助長し、遠く離れた場所まで物資を輸送する時の資源の莫大な消費を助長するだけではない。廃棄物の有効なリサイクル・非常に中央集権的な産業と人口集中地がその源泉である公害の回避・地元原料や地方原料の十全な利用、これらの可能性を剥奪するのである。
一方、比較的自給自足のコミュニティが、個々人が晒される諸機会と諸刺激を芳醇にし、自己と能力について豊かな感覚を持った円熟した人格を助長することを無視することはできない。こうしたコミュニティでは、工芸・農業・工業が、連邦的に組織された機能限定的なコミュニティ=ネットワークの役目を果たしている。円熟した環境における円熟した人格というギリシアの理想は、チャールズ=フーリエのユートピア的著作に再び現れているものだが、19世紀のアナキストと社会主義者によっても久しく大切にされていたのだった。
当時は、個人が、若干の週間労働時間(フーリエの理想社会においては任意の一日とされている)の中で、自分の生産活動を様々な仕事に当てる機会があることは、肉体活動と精神活動との分断を克服し、莫大な労働分業が創り出している社会的地位の違いを超越し、工業・工芸・食物耕作を自由に行き来することで得られる豊富な経験を促す上で、極めて重要な要因と見なされていた。故に、自給自足は、雑多な経験・能力・確信(assurances)によって強化された、より豊かな個人を促すと見なされていたのだ。嗚呼、このヴィジョンは、今日、左翼主義者と多くの環境保護主義者が実用的なリベラリズムへとシフトしてしまったことで、そして、急進主義運動が自身の空想的過去について悲劇的に無知であることによって、失われてしまったのだ。
私は確信している。我々はこのヴィジョンが意味していることを忘却してはならないのだ。このヴィジョンの持つ意味は、単に健全な生態調和実践に従うだけでなく、生態調和的生活方法で生きるということなのだ。「生態系に責任を持った」やり方で保全し、投資し、食事し、購入する方法について教えてくれる数多くのハンドブックは、もっと基本的な欲求を曲解している。それは、言葉の十全な意味で生態学的に考え--そう、推論し--、生活することの真意を中傷しているのである。私は、有機的園芸は、きちんとした農業や良い栄養源以上のものだと考えたい。結局、それは、自分が生きるために消費する正にそのものを私的に耕作し、自分が環境から引き出したものをその環境に帰すことで、食物網の中に直接自分の身をおく方法なのだ。
このようにして、食べ物は、肉体的栄養素の一形態という以上のものになっている。自分が耕す土壌・自分が育て消費する生き物・自分が準備する堆肥、これら全ては、我々の周囲にある人間以外の世界と人間の世界とに対する感性を研ぎ澄ましながら、肉体だけでなく精神をも養う生態系連続体の中で結びついているのである。熱狂的「スピリチュアリストたち」のおかげで、私はよく楽しませてもらっているものだ。彼らの多くは、一見して「自然」に見える風景を受動的に見ているだけか、儀式や魔法や多神教の神々(もしくは、これら全て)の愛好者たちである。最も著しい人間活動の一つ--つまり、食物耕作--の方が、生態系に対する感受性を(お望みならば、スピリチュアリティと呼んでもよいが)促すために、エコロジカル=スピリチュアリズムという名前で考案されている呪文やマントラよりも、もっと多くのことをできる、ということを彼らは実感できないでいるのだ。
国民国家を解消し、参加型民主主義で置き換えるという画期的変革は、政治構造だけが変革され、心理的には真空だという状態の中で生じることはない。私はジェレミー=ブレッカーに対して次のように反論した。地方分権で、参加型民主主義で、コミュニタリアンと生態学の諸原則に導かれた方向へと根本的に転換している社会では、民衆は、ハドソン川の水をこれほどまでに汚染することを許すといったでたらめな社会的処理を選択することはないと仮定することだけが道理にかなっている。地方分権主義・顔をつきあわせた参加型民主主義・コミュニティの価値観に対する地方主義的強調は、一つのもの(all of one piece)として見なされねばならない--私が30年以上も擁護してきたヴィジョンに確固として存在してきたのである。この「一つのもの」は、新しい政治だけでなく、自然界を経験する様々な方法を含めた新しい思考方法・新しい感性・新しい人間諸関係を包含している新しい政治文化も含まれているのだ。ここで、「政治」や「市民権」といった言葉は、それが過去に獲得し、現在拡大されている芳醇な意味によって再定義されるであろう。
労働の国際分業は、地元と地方の資源を使い、エコテクノロジーを導入し、理性的(実際、健康的な)方向にそって人間の消費を封じ直し、長持ちする(使い捨てではなく)生活手段を提供する質の高い生産を強調することで、大幅に弱めることができる。不運なことに、これらの可能性の非常に重要なリストを、私は1965年のエッセイ「解放的テクノロジーに向けて」で一部だが組み立て、評価したのだが、これはあまりにも昔に書かれているため、今の世代のエコロジー志向の人々に入手しやすくなっていないという重荷を背負っている。実際、このエッセイの中で、私は同時に地域統合とエココミュニティ間で資源を連結させる必要性についても論じているのだ。地方分権型のコミュニティは、必ずお互いに相互依存的になるのである。
地方分権主義の諸問題
多くの実用的な人々が地方分権主義の重要性を全く見ていないとすれば、エコロジー運動にいる多くの人々は、「地方主義」が持っている極めて現実的な諸問題を無視しがちである。それは、世界規模で経済・政治生活をトータルに連動させることを促しているグローバリズムの諸問題と同じぐらい厄介な諸問題である。私が支持している全体調和論的な文化変革・政治変革がなければ、地方主義的孤立とある程度の自給自足を強調している地方分権主義の諸概念は、文化的な地方根性や愛国主義を導く可能性がある。地方根性は、文化の特異性・生態系や生態地域の特性・参加型民主主義を可能にする人間規模のコミュニティの必要性を無視している「グローバル」なメンタリティと同じぐらい重大な諸問題を導く可能性がある。エコロジー運動において、このことは小さな問題ではない。エコロジー運動は、全くの善意ではあるがどちらかといえば愚直な極端へと振れる傾向を持っている。我々は、世界を、他の人間と人間以外の生命形態とで共有する方法を見つけなければならない。これは断固として繰り返しても繰り返しすぎることはない。だが、この見解は、過度に「自給自足的」コミュニティでは多くの場合獲得しにくものである。
地域の自立と自活を擁護している人々の意志を私は尊重したいのだが、こうした概念は、非常に誤解されやすいものである。もちろん、例えばコミュニティがそこで必要としているものを生産できるならたいていの場合はそうすべきだ、ということについて「地域自立研究所」(Institute for Local Self-Reliance)のデヴィッド=モリスに同意できる。だが、自立的コミュニティも、コミュニティが必要とするもの全てを生産出来るわけではない--伝統的にコミュニティの男女に若いうちから重労働をさせて早々と老けさせ、コミュニティそれ自体の現前の範囲以上に政治生活をする時間をほとんど持っていなかった過酷な村落生活様式に戻らない限りは。
エコロジー運動に、石器時代の神々は言うに及ばず、非常に労働集約な経済へと回帰することを確かに擁護している人々が実際にいることは残念だ。明らかに、我々は、地域主義・地方分権主義・自給自足という理想にもっと大きな、もっと十全な意味を与えなければならないのだ。
今日、我々は、質が高く有用な物品の生産に焦点を当てながら、生態調和社会での基本的生活手段--それ以上のことをも--を生産することができる。だが、未だに、エコロジー運動にいる他の人々は、結局のところ、ある種の「共有的」資本主義を擁護することに終わってしまうことが余りにも多い。「共有的」資本主義では、一つのコミュニティが、その資源を所有しているという感覚を持って、一つの企業のように機能する。協同組合が「ブルジョア的諸権利」の網に--つまり、他者に配達するものと「交換」してコミュニティが受け取る正確な料金額に焦点を当てた、契約と経理の中に--巻き込まれてしまったことを見れば分かるだろうが、協同組合のようなシステムは市場型の分配システムが始まる兆候なのである。この堕落は、労働者管理の企業でも生じていた。1936年7月に労働者が収用した後、労働者管理企業は、バルセロナで資本主義企業--スペイン革命初期にアナルコサンジカリストCNTは、この事業実践と戦ったのだが--と同じように機能したのだった。
厄介な事実なのだが、地方分権主義や自給自足それ自体は、必ずしも民主主義的になるとは限らないのである。プラトンの「共和国」における理想都市は、確かに、自給自足的になると考えられていたが、その自給自足性は、哲学のエリートだけでなく戦士をも扶養するためのものだった。事実、その自給自足性を保護するための都市の能力は、スパルタ同様、外部の諸文化が持つと見なされていた「堕落した」影響力に抵抗する腕力に依存していたのだった(東洋にある数多くの閉鎖的社会では未だに見られる特徴だと言えよう)。同様に、地方分権は、それ自体で、生態調和社会が構築されることを保証などしてくれない。地方分権社会は、極度に厳格なヒエラルキーと容易く共存できる。その顕著な例は、欧州や東洋の封建主義である。封建主義の社会秩序においては、非常に地方分権的なコミュニティが、君主・公爵・男爵ヒエラルキーの基盤だったのである。フリッツ=シューマッハー様には失礼ながら、小さいことは必ずしも美しくはないのである。
同様に、人間的規模のコミュニティと「適正テクノロジー」それ自体も、支配的な社会に対抗することを保証してくれるわけではない。実際、数世紀にわたり、人間は村落や小規模な街に暮らしてきた。多くの場合、堅く組織された社会的結びつきを持ち、共産主義的所有形態さえをも持ちながら暮らしていた。だが、これらが、非常に専制的な帝国主義国家の物質的基盤を提供したのである。経済的・財産的条件について考察するならば、ハーマン=デイリーのような経済学者の「ゼロ成長」という見解において高い地位を獲得するかもしれない。だが、それらは、インドや中国に見られた最も恐ろしい東洋的専制政治を構築するために使われた強固な土台だったのだ。こうした自給自足的で地方分権型のコミュニティが、コミュニティを破壊する軍隊と同じぐらい恐れていたことは、コミュニティを略奪する帝国の徴税人だったのである。
地方分権型で自給自足的で小規模で「適正テクノロジー」を使用していたからという理由でそうしたコミュニティを大絶賛するなら、我々は、それらは同時に文化的に停滞し、外来エリートに支配され易かったということを無視しなければならなくなる。そうしたコミュニティが持つ一見して有機的だが、伝統に拘束された労働分業が、世界の様々な場所で非常に抑圧的で下劣なカースト制度の基盤を形成していた可能性が高い。このカースト制度こそ、正に今日までインドの社会生活を苦しめているのだ。
一見して逆に見える危険はあるが、私は、地方分権・地方主義・自給自足・そして連邦さえもを、個別に取り上げることは、理性的な生態調和社会を確立することを保証しはしない、ということを強調しなければならないと思う。実際、これら全ては、地方根性を持つコミュニティ・寡頭政治・専制的政治体制を支援してきたことが多いのだ。はっきりさせておくが、こうした言葉の使用を中心として構成されている制度諸構造抜きにして、そして、これらの言葉をお互いに組み合わせて受け取らずに、自由な生態調和志向的社会を確立することなど望み得ないのである。
連邦主義と相互依存性
地方分権主義と自給自足は、単なる地方主義以上のもっと幅広い社会組織原理に含まれていなければならない。地方分権・おおよその自給自足・人間規模のコミュニティ・エコテクノロジーなどと共に、民主主義的で、真にコミュニタリアンな相互依存形態が必ず必要なのだ。つまり、連邦主義のリバータリアン諸形態である。
私は、多くの論文と著書(特に、The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship、現在はFrom Urbanization To Citiesと題名を変えた)で、古代・中世・近代の連邦が持つ連邦諸構造の歴史を詳細に詳述してきた。例えば、16世紀初頭のスペインでコミュネロス(Comuneros)や、1893年のパリ地区運動(sectional movement)、そして最近の様々な連邦の試みの中でも特に、1930年代のスペイン革命時にアナキストが試みていたもの、についてである。今日、多くの場合に地方分権論者の間で重大な誤解を引き起こしているのは、連邦の必要性を理解できていないことが多すぎるという点にあるのだ。少なくとも、連邦は、地方分権型コミュニティが排他性と地方根性に向かって変化していく傾向に歯止めをかける傾向を持っているのである。連邦主義が何を意味しているのか--地方分権主義の鍵となる原理を形成し、地方分権主義に十全な意味を与えている事実だ--を明確に理解していなければ、リバータリアン自治体連合論の政治課題など、容易く、良くても空虚になるだろうし、最悪の場合非常に偏狭な目標のために利用されてしまうだろう。
ならば、連邦主義とは何だろうか?結局、行政評議会のネットワークなのである。その評議会のメンバーや代理人は、村・町・大規模都市の町内会で行われる顔を付き合わせた民主主義的民衆集会から選出される。こうした連邦評議会のメンバーは、集会自身で策定した政策を調整し、実施するために自分を選んだ集会に対して責任を持ち、厳密な委任を受け、リコール可能なのである。従って、その機能は、純粋に行政的・実際的なものであり、共和制政府システムにいる国会議員の機能のような政策決定ではない。
連邦主義の見解には、政策決定と、採用された政策の調整・実行との明確な区別が含まれる。政策決定は、もっぱら、参加型民主主義の実践に基づいた地域民衆集会の権利なのである。行政と調整は、連邦評議会の責任なのであり、村・町・町内会・都市を連邦的ネットワークに連結させる手段となる。従って、権力は、トップダウンではなく、ボトムアップに流れ、連邦においては、ボトムアップで流れてくる権力は、連邦評議会の範囲が、局所的なものから地方的なものへ、そして、地方からもっと広い範囲まで領土的に広がるにつれて減少するのである。
連邦主義を実現させる上で重要な要素は、資源・生産・政策決定の共有に基づいた本物の相互扶助のための、コミュニティ間の相互依存関係である。あるコミュニティが、重要な物質的欲求を満足させ、共通の政治的諸目標を実現するために、別なコミュニティや他の諸コミュニティ一般に頼る必要がなかったならば、排外性と地方根性が出現して当然である。連邦は参加型行政の一形態を--連邦ネットワークという手段によって--拡充したものだと認識されねばならないことを理解してはじめて、地方分権と地域主義は、さらに大きな連合体を構成している諸コミュニティがもっと大きな人間的コンソシエーションの領域を犠牲にして偏狭的に引きこもることを未然に防ぐことができるのである。
つまり、連邦主義は地域と地方の中に存在しているべき相互依存性を永続化する方法なのである。実際、地元管理の原則を放棄することなく、相互依存性を民主化する方法なのだ。自給自足という道理にかなった指標は全ての土地と地方に望ましいものの、連邦主義は、一方では地元偏狭主義を回避し、他方では全国や地球規模にわたる過度の労働分業を回避する手段なのである。つまり、バランスのとれた生態調和社会を作り上げているより大きな全体に分担的なやり方で参画しながら、コミュニティがその独自性と円熟性を保持できる方法なのだ。
社会組織原理としての連邦主義がその十全なる発展に到達するのは、経済それ自体が地元地域の農場・工場・その他必要な事業を地域自治体の手にゆだねることで連邦化したとき--つまり、どれほど大きかろうと小さかろうと、あるコミュニティが、他のコミュニティと連結したネットワークの中で、そのコミュニティ自身の経済資源を管理し始めたとき--なのである。自給自足か市場交換システムか、という選択を強いることは、極度に単純化した無用な二分法なのである。私は、連邦的生態調和社会は共有の社会、その欲求に応じてコミュニティ間で分配するときに感じる快楽に基づいている社会になる、と思いたいのであって、見返りを期待した交換諸関係の中に「協働的な」資本主義コミュニティがはまり込むといった社会ではないのだ。
不可能だろうか?我々が、国有化された財産(中央集権的国家の政治権力を経済権力を使って強化することだ)や、個人取引経済(その「成長か、死か」の法則が惑星全体の生態的安定性を破壊するぞと脅しているのだ)が適当だと考えている場合を除き、私には経済の連邦型自治体化以外のいかなる実行可能な代案があるのか分からない。いずれにせよ、この場合、コミュニティの諸問題に直面しているのは、特権を持った国家官僚でも、意地汚いブルジョア事業主でも--いわゆる労働者管理企業という「共有的」資本家たちですら--(こうした人々は皆お奨めの特別メニューを持っているわけだが)なく、市民なのであって、職業や仕事場とは無関係であろう。この場合、仕事・仕事場・社会的地位・所有関係に関わる伝統的な特殊利権を超越し、そのコミュニティに共通の諸問題に基づいた一般的関心を創り出すことが必要となろう。
つまり、連邦は、地方分権・地域主義・自給自足・相互依存のアンサンブルなのだが、それ以上でもあるのだ。このそれ以上とは、かけがえのない道徳教育と人格形成--古代ギリシア人がパイデイアと呼んでいたことだ--である。これが、今日のような受動的有権者・消費者とは異なり、参加型民主主義の中で理性的で能動的な市民権を促すのである。結局、人間同士の関係と、自然界と人間との関係とを意識的に再構築する以外に方法はないのである。
社会の再構築と、自然界と人間との関係の再構築は、地方分権や地域主義や自給自足だけで達成できると論じることは、様々な解決策の不完全な集積とともに我々を取り残してしまう。連邦した自治体に基づく社会に対するこうした諸前提の中のどれを無視しても、確実に、創造したいと望んでいる社会という織物全体にぽっかりとあいた穴を残すことになるだろう。この穴は次第に大きくなり、最終的には織物それ自体を破壊してしまうだろう。ちょうど、市場経済が、「社会主義」や「アナキズム」など、良い社会に関係するいかなる概念であれ、それと結合する(cojoined)ことで、全体としての社会を最終的に支配してしまうのと同じである。また、我々は、政策決定とその実施との区別を無視することもできはしない。なぜなら、政策決定が民衆の手から滑り落ちてしまえば、それはその代理人によって吸い上げられ、すぐさまその代理人は官僚になってしまうからだ。
要するに、連邦主義は、全体として意識されねばならないのである。自治体における参加型民主主義を、几帳面に監督された調整システムと統合した、意識的に形成された相互依存体なのだ。自立性と依存性から、もっと十全に明言された相互依存形態への弁証法的発展を含んでいるのである。ちょうど、自由社会にいる個人が、幼児期には依存的で、青年期には独立的になり、その二つを否定することではじめて、個々人間の・個人と社会との間の意識的な相互依存形態へと成長するのと同じである。
従って、連邦主義は、流動的で絶え間なく発展し続ける社会的新陳代謝なのである。そのことで、生態調和社会の独自性は、相違を通じて保持され、絶え間なく拡大する分化に向かう潜在的可能性のおかげで維持されるのである。事実、連邦主義は、(近年観念論者たちが、リベラル資本主義について私たちを信じ込ませようとしている「歴史の終焉」のような)社会の歴史の終わりを特徴づけているのではなく、むしろ、社会内部での、そして、社会と自然界との参加型進化を特徴としている新しい生態-社会の歴史に向かう出発点なのである。
二重権力としての連邦
結局、私がこれまで著書の中で示そうとしてきたことは、自治体に基づく連邦は、中央集権国家全般と、そして、近年では国民国家との激しい緊張状態に存在してきた、ということなのである。これまでも強調してきたことだが、連邦主義は、単に、行政に関する無類の社会的形態、特に市民的・自治体的形態だというだけではない。人間に関する諸事における力強い伝統なのであり、その背後には数世紀にわたる歴史を持っているのだ。連邦は、代々、中央集権化と国民国家の創造に向かうというほとんど同じぐらい長い歴史を持った傾向に対抗しようとしてきたのだ。
これら二つ--連邦主義と国権主義--をお互いに緊張状態にあるものとして見ないならば、連邦の概念はその意味を全く失ってしまう。この緊張の中で、国民国家は、カナダや合州国の州政府のような様々な仲介者を使って、「地元管理」の幻想を創り出してきた。カナダの州の自律性と合州国の州の権利など、「ソヴィエト」つまり評議会がスターリンの全体主義国家で緊張状態に存在していた民衆管理に対する媒介だったなどと言うのと同じ程度の連邦でしかない。ロシアのソヴィエトは、ボルシェヴィキに乗っ取られ、10月革命の1年か2年後にはその政党によって奪われてしまったのだ。「連邦主義の」候補者を日和見的に州政府に擁立する--もしくは、もっと悪夢のようなことなのだが、一見して民主主義的に見える州知事職へと擁立する(合州国「緑の党」のいくつかが計画していたように)--ことは、国民国家に対抗する権力としての自治体連邦の役割を弱めることになり、連邦と国民国家との間に緊張が必要だということの重要性を暈してしまう--実際、これら二つが長期にわたって共存することなどできないという事実を隠してしまうのである。
全体として--地方分権・参加型民主主義・地域主義の構造として--の、そして、新しい発展の方向性にそって絶え間なく増大する分化の潜在的可能性としての連邦主義について述べる上で、私は次のことを強調したい。全体調和性というこの同じ概念は、諸自治体間の相互依存性に適用されるだけでなく、自治体それ自体にも当てはまるのである。初期の著作で指摘したように、自治体は、個人にとって最も即時的な政治的土俵である。家族というプライバシーと私的友人関係という親密さを越える、文字通り、戸口の上り段の世界なのだ。この最初の政治的土俵では、政治は、文字通り世論つまりコミュニティを管理するという古代ギリシャ的意味で理解されねばならず、個人は、単なる人間から能動的な市民へと、プライベートな存在からパブリックな存在へと変換されうるのである。代議制統治形態が示すレベルでは、一個人もしくは少数の個々人が具現化する権力に集合的力が変形されるわけだが、市民を社会の将来について直接参画できる文字通り機能的存在にするこの重要な土俵を前提とすれば、我々はもっと基本的な(家族それ自体とは別個の)人間的やり取りのレベルを扱うことになる。つまり、自治体は、歴史の流れの中でどれほど歪められていようとも、公的生活の最も本物の土俵なのだ。
逆に、委任的・権威的「政治」レベルは、程度こそあれ、自治体権力・市民権力の放棄を前提としている。自治体は、いつでも、この真の正真正銘の公的世界として理解されねばならない。市長のような管理職的立場を、代議制権力の領域にいる州知事と比較するなど、その全くの奇形性にもかかわらず、市民生活の基本的な政治的性質を莫大に誤解しているのである。従って、「緑の党」が純粋に形式的で分析的なやり方で--近代論理学が主張しているように--「執行的」のような言葉はこれら二つの立場を交換できるようにしていると述べるなど、その文脈から執行的権力という概念を完全に引き剥がし、具象化し、我々がこの言葉に関連づけている外的虚飾のために、この概念を死んだカテゴリーに入れているだけなのだ。都市を全体として見なし、参加型民主主義を創造する潜在的可能性を十全に認識するのであれば、カナダと合州国の州政府は、最良の場合でも代議制に、最悪の場合は寡頭政治支配を専ら中心として組織された、確立した小規模共和国だとはっきりと見なさねばならない。それらは、国民国家に向かう言い回しに道筋を提供し、本来の公的領域の発展を疎外しているのである。
リバータリアン自治体連合論プログラムの中で「緑の党」の党員を市長候補に擁立することは、結局のところ、リバータリアン自治体連合論らしきプログラム中で州知事候補を擁立することと質的に異なっている。それは、自治体・州・国民国家それ自体に存在する諸制度の文脈を無視し、従って、これら三つの執行的立場全てを純粋に形式的な規定の下に置くことと等しいのだ。これはちょうど、人間も恐竜も共に脊髄を持っているから、同じ種やさらには同じ属にさえ属しているなどと述べることと同じぐらい不正確なのだ。どの場合でも、制度--それが市長的なものであれ、議員的なものであれ、都市行政委員であれ--は、全体としての自治体の文脈で見られねばならない。ちょうど、大統領・首相・連邦議会議員・国会議員が、同様に、全体としての国家の文脈で見られねばならないのと同じである。この観点からすれば、「緑の党」が市長に候補者を擁立することは、州政権に候補者を擁立することとは根本的に異なっている。何故市長の権力が、州の官公吏の権力よりも、遙かに規制され、もっと民衆に近しい範囲下にあるのかということについては際限なく詳細な理由を調べることができるだろう。
しつこいようだが、この事実を無視することは、政策・行政・参画・代表といった諸問題が置かれねばならない文脈と環境に関する感覚を単に放棄することになる、ともう一度言わせていただきたい。市役所や町役場は、断じて、その地方・州・国民国家の首都ではないのだ。
疑いもなく、現在、あまりにも大きすぎて、それ自体で疑似共和国になる寸前の都市が存在する。ニューヨークシティやロスアンジェルスのようなメガロポリタンエリアがその例として考えられるだろう。そうした場合にも、緑の運動が持つ最小限プログラムならば、連邦は、都市部同士の間だけでなく、都市部の中でも--つまり、諸町内会の間やはっきりと区別できる地区間で--確立されねばならないと要求することができる。本質的には、このように、人口が非常に多く、スプロール現象を起こし、必要以上に大きい存在は、究極的に、人間的規模に調整され、参加型民主主義に尽力する本物の自治体へと制度的に解体されねばならない。こうした存在は、制度的にも現実的にも、人口がまばらな米国の諸州にさえ見られるような国家権力をまだ十全に形成してはいない。市長は、未だに、莫大な強制権限を持った州知事でもないし、市議会は、今日合州国で生じているように死刑執行の法案を文字通り制定できる国会でも州議会でもない。
自身を疑似国家へと転換しつつある諸都市においては、政治家がリバータリアン的方向に導かれ得るだけの多くの余裕が未だにある。既に、こうした都会の諸団体の行政部門は、非常に不安定な基盤となっている--莫大な官僚主義・警察権力・課税変更権・司法制度に重荷を負わされ、これらがリバータリアン自治体連合論アプローチに対する重大な諸問題を引き起こしているのである。我々は、いつも非常に率直に自問しなければならない。具体的な状況はどのような形をとるのか、ということを。大都市における市議会と市長オフィスが、次第に強力になっている国家や州行政、もっと悪い場合には多くの都市に影響を与える可能性のある地方司法権における権力集中の闘争の場を提供している所では、市議会に立候補することは、実際、次第に権威主義的になる国家諸機関の発展を妨害し、制度的に地方自治化された民主主義を回復する手助けをするために我々ができる唯一の頼みの綱なのかも知れない。
ニューヨークシティのような都会的存在を本物の諸自治体へ、究極にはコミューン群へと物理的に地方分権化するには疑いもなく長い期間がかかるだろう。そうした努力は、緑の運動の最大限プログラムの一部なのである。だが、そうした大規模な都会的存在が、ゆっくりと制度的に地方分権化されることはないという理由などどこにもないのだ。物理的地方分権化と制度的地方分権化の区別は、いつも念頭に置いておかねばならない。これまで幾度となく、こうした大規模な都会的存在の中で民主主義を地元化し、文字通り民衆により大きな権力を与えようとして、急進主義者や都市計画者さえもが優れた計画を押し進めてきた。だが、皮肉なことに、中央集権主義者がこうした試みに物理的妨害を行使することにより阻止されてしまっていたのだった。
地方分権の擁護者が、制度的地方分権化が生じるためにはこうした大規模実体の物理的崩壊が条件だ、と論じるのは混乱している。これら二つのまったく別個の発展の方向性を同じだとか、お互いに絡み合っているなどとするのは、中央集権主義者の側に立ったある種の裏切り行為なのだ。リバータリアン自治体連合論者は、制度的地方分権と物理的地方分権の区別をいつもはっきりと心の中に留めておき、後者の確立に時間が掛かろうとも、前者は完全に確立できると認識していなければならないのである。
November 3, 1990