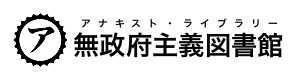大杉栄
クロポトキン総序
一
雑誌編集者の無知と無謀とには今さらながら呆れる。クロポトキンの著書全部を、わずか数日の間にしかも数十枚の制限で、総評してくれないかという註文だ。
そんな馬鹿なことができるものじゃない。僕は即座に「よし、よし」と答えながら、実はほんのちょっとした手引、それもまるっきりの素人のための、くらいのものを書くことに内緒できめていた。
しかしよくよく考えて見れば、内緒でそうきめた僕の方がよっぽど無知で無謀であったのだ。せっかく註文主が、えらそうな題目の下に、いい加減に、えらそうな与太を飛ばさせようとしたのを、実際近来の無政府主義論、クロポトキン論などというものはみんなそうなんだからね、それを真面目にわざわざ小面倒なものを引き受けてしまったのだ。
三、四百ページ以上の大きな本だけでもちょっと十冊近くある。そのほかに小冊子が二、三十はある。しかもその小冊子というのが、いずれもみな、大きな本と同じように四、五年ないし七、八年の研究と思索との結晶であるほかに、それを非常な苦心の下に数十ページの中に書き縮めたものだ。クロポトキン自身も実はこの小冊子の方がよっぽど骨が折れていると言っている。学問にはまるっきり素人の、そして大きな本なぞ読むひまのない、労働者のため、ということがクロポトキンのこの苦心の目的であった。したがってそのどの小冊子といえども、一つとして、見逃しのできるものはない。その大がいは大きな本よりかえって重要なくらいなのだ。
片輪者の学者にとっては、学者という奴は西洋でも日本でもみんな片輪者だ、ことに日本の学者なぞはその片輪者の中にすらはいらんかも知れない、この素人のためということが何よりも面倒なのだ。クロポトキンだってやはりそのお他聞に洩れない。一時は学者になって見ようかという馬鹿げた考えを大切にして、そういった片輪者にばかり教えを受けて来た僕も、やはりその、片輪者の仲間にすらもはいれない片輪者に仕込まれてしまった。
クロポトキンの著書にもったいをつければまだまだ幾らでもつくんだが、とにかくその数十冊のものの総評、あるいは総解説、あるいは総手引を、わずか数日の期限の中のわずか一晩か二晩かでやってのけようというんだ。何ができるものか。まあ、諸君が僕のうちへ遊びに来て、「クロポトキンの本を読みたいんだが、どんなものがありますか」という質問を出して、そして僕が「そうですな」と山羊鬢をいじくりながら旧い記憶をたどって思い出すままにぽつぽつと吃り出す、ぐらいのことに想像して読んでくれ給え。
実際、ずいぶん旧い記憶なんだ。
こないだも神戸で賀川君と会って、僕の留守中に出た有象無象どもの無政府主義論、クロポトキン論を十ぱ一くそにしてやっつけるつもりだという話から、「それでも日本ではアナーキズムのオーソリティなんだからな」と大いに威張って見たところが、「そうだ、少なくとも旧いことにおいてはね」とさっそくあべこべに一本やっつけられてしまった。
僕がクロポトキン大明神でおさまっていたのはもう十年も十五年も昔のことだ。はたち前からクロポトキンのものを読み出して、十年近い間クロポトキンかぶれしていた。少なくとも書物の形で出たクロポトキンのものは片っ端から買い集めて読み耽った。二度も三度も、四度も五度も、どうかすると六度も七度も、繰返し繰返し読んだ。どんなことが、どの本の、どの辺に書いてあるか、ということまでも大がいは知っていた。クロポトキンの著書全部のよほど詳しい索引が自然に、僕の頭の中にできあがっていた。
僕はこのクロポトキンかぶれのために、どれほど僕の知識的発達に、とともに僕の全人格的発達にも、利益を享けたか知れないが、それと同時にまたどれほど損害を蒙ったか知れない。そしてその損害に気がついたのは、ようやく年二十七の時の、千葉監獄の独房の中でであった。それ以来僕はクロポトキンの書物にはいっさい目を触れなかった。クロポトキンのばかりじゃない。いっさいの無政府主義文書からできるだけ遠ざかることに定めた。そしてただ手当たり次第に、範囲にも順序にもまったくお構いなしに、もっとも主としては社会学と生物学との、諸学者に親しんでいた。
さきに「一時は学者になって見ようかという馬鹿げた考えを大切にして」と言ったのはその時のことだ。クロポトキンから独立しようと思ったのはいい。しかしその独立をやはり書物でやろうと思った僕は大馬鹿だったのだ。
が、お蔭で、クロポトキンの書いたことは大がい忘れてしまった。無政府主義も大がい忘れてしまった。大骨折って買い集めた無政府主義文書も、水難、火難(これは本当の)、貸難、盗難(これはちょっと込みいった陰謀の)、諸難に遭って全部無くしてしまった。
お役人様々や世間のお利口者どもは今でもまだ僕を無政府主義者だと思いこんでいる。僕もまたそいつらにそう言って嚇かしてやっている。人の厭がることや恐がることをことさらに言ったりしたりすることの好きなのが、僕の持って生れた厄介な病気なんだ。常にはなはだ相済まんとは思いながらも、如何とも仕方がない。で、せめての申訳けにこうして白状して置くが、僕は決してクロポトキン大明神のもうし児でもなければ、またいわゆる無政府主義者なぞという至極量見の狭い狂信者でもない。ただちょっと気違いじみた一人の人間様であるだけのことだ。
その人間様がお気に召さずに、世間の奴等は、きのうまでは友人だとか仲間だとかいっていた奴等までも、寄ってたかって撲殺しにかかった。ことにこの世間の奴等の阿呆と卑怯とを食いものにしている新聞雑誌どもは、その撲殺軍のお先棒に立って騒ぎ廻った。
その新聞屋、その雑誌屋がだ。図々しいにもほどがある。世態人情が少々変わり、物騒な無政府主義が流行りものになったとなると、急にぴょんぴょん頭をさげて「どうぞ、先生・・・」てなことでやって来る。そしてそのご本人がとうの昔に無政府主義なぞを廃業していることはご存じない。忘れていることはご存じない。
どいつでもこいつでも、僕のこういった物の言いかたに、怒る奴は怒れ、笑う奴は笑え。破って棄てたかったら、こんな原稿は、勝手にどこへでもうっちゃるがいい。また、読むのがいやなら、こんな雑誌は、勝手にどこへでもほうってやるがいい。どうとでも勝手にしやがれだ。
が、念のために言って置くが、こういった物の言いかた、少々気違いじみた人間様の言葉が、可笑しかったり癪にさわったりするようでは、無政府主義の精神はとても分かりませんよ。クロポトキンの著書の神髄はとても掴めませんよ。それから、これはことにこの雑誌の発行者や編集者にごく内々で言って置くが、たまにはこういうものを載せる方が雑誌がよく売れますよ。そして、これはまた、僕自身にとっては、いろんな奴等へのいろんな意味での多少の腹いせになるんです。実に一挙幾得か知れません。
その大がいは忘れてしまった旧い記憶を思い出すために、二、三日近所を遊び廻って、ようやくクロポトキンの著書五つ六つを借り集めて来た。
それをたねにして、ことに近日中出版される筈の大杉栄訳クロポトキン自叙伝『一革命家の思い出』を盛んにひねくり廻して、このクロポトキン総序を書く。それは、クロポトキン自身をしてもっとも多く語らしめる便宜と利益とを与えるほかに、自然の避雷針にもなることだろうから。
不十分な点は、ご質問さえあれば、できるだけの補いをする。直接お会いしてでも、手紙でも、また雑誌の上ででも、お互いの都合のいいようにして。
二
ダーウィンを本当に知るには、その名著『種の起原』や『人間の由来』やを読むよりも、何よりもまず『一博物学者の航海記』を繙かなければならない。『種の起原』によってあらゆる科学界から哲学界までをも一挙にして根本的に変革させた、ダーウィンの生物学上および地質学上の知識、というよりもむしろその全人格的基礎は、その二十三歳から二十七歳にわたる満四カ年の世界一周の間にできあがった。彼は一博物学者として軍艦ビーグルに便乗し、南アメリカ、南洋、オーストラリアの諸国諸島を遍歴跋踏した。そして一人で各地の植物史、動物史、地質史を調査研究した。この自分一人での実地に当たっての調査研究ということが後年のダーウィンを造りあげたのだ。現に『種の起原』の中に、またそれによって初めて、その萌芽と発達のあとを十分窺うことができる。もしこの航海がなかったら、あるいはダーウィンは、至極平凡な一田舎牧師として世を終ってしまったかも知れないくらいだ。
クロポトキンを本当に知るのにも、やはりその名著の『パンの略取』や『相互扶助論』やを読むよりも、何よりもまずその自叙伝『一革命家の思い出』を繙かなければならない。この自叙伝については、森戸君が詳細な紹介をする筈だし、それに追々僕の全訳が出る筈だから、別に解説はしない。
僕がこの自叙伝の翻訳をしたいと思ったのはずいぶん旧いことだ。明治四十一年の春、巣鴨の獄中から幸徳に宛てて出した手紙の中にも、「兄の健康は如何に。『パンの略取』の進行は如何に。僕は出獄したらすぐ多年宿望のクロポトキンの自伝をやりたいと思っている。今その熟読中だ」(大杉栄著『獄中記』六五-六六)と書いている。それが五、六年前にようやくある本屋と話がついて、内務省へお伺いを立てて見たが、どうしてもお許しが出ず、ついそのままになっているうちに、一昨昨年の暮れに例の有名な誤訳家三浦関造君にさきをこされてしまった。僕はさっそく内務省へ出かけて、その不信を責めて、僕の翻訳の出版許可を迫った。内務省では「あんまり滅茶苦茶な翻訳なので、あんなものなら出さしても差支えあるまい」とのことで許したのだそうだが、「どうもあなたにあれをうまく翻訳された日にゃ」なぞとうまいことを言ってなかなか許してくれなかった。が、とうとうお許しが出た。そして僕は、「多年の宿望」と三浦君のクロポトキンに対するはなはだしい冒涜に対する憤慨とを、ようやくのことで果たすことができるようになった。
この自叙伝の中で、僕が今特に注意したいのは、その第三章「シベリア」の巻だ。
ダーウィンの世界一周は、主として一博物学者としての、今日は此処明日は彼処と転々として移って行くほんの通り一ぺんの旅行に過ぎなかった。もっともその間に、アメリカ・インディアンや東洋諸島の蛮人とも会い、メキシコの革命騒ぎをも見、チリの鉱山労働者にも接して、人間の生活の上に純真な人道的感情を養ってもいる。しかし彼は、その感情をどこまでも育てあげることをせずに、むしろその学説の「生存競争」で晦ましてしまった。
クロポトキンはその十九歳から二十五歳までの五カ年間をコザック士官としてシベリアで暮した。が、このコザック士官としてというのは、決して単なる一軍人としてではなく、むしろ一行政官、しかも社会改良の一委員としてであった。彼は東シベリアの首府イルクーツクに着くとともに、総督コルサコフの下に、参謀長クウケルの副官となった。コルサコフはその部下に自由思想の人々を持っていることを誇りとするほどの人であった。クウケルはまだ年三十五にも達しない若い将官で、その書斎にはロシア最善の新聞雑誌と一緒にゲルツェンのロンドン版革命的文書の全集が揃っていた。
クウケル将軍はその頃臨時トランス・バイカリア県知事の職にあった。数週間の後彼は県の首府チタという小都会にまで行った。そしてそこで彼は、一刻の猶予もなく、当時盛んに議論されていた大改革に身も魂も打ちこんでしまった。当時セント・ペテルスブルグの諸省は地方官憲に命じて、県の行政や、警察の組織や、裁判所や、監獄や、追放制度や、町村自治などについて、ごく自由な基礎にもとづいた根本的改革を施すことを求めていたのだ。
クウケルはペタシェンコ大佐という聡明なかつ実際的な人と、誠実な数名の文官との補佐の下に、終日、時としては夜の大部分までも働いていた。クロポトキンは二つの委員会--監獄と追放制度の改革、および町村自治制の立案と--の幹事となった。彼は十九歳の青年の熱心をもってこれらのことに当った。まずロシアにおけるこれら諸制度の歴史的発達や、また外国におけるその現状について多くの書物を読んだ。しかし彼等のトランス・バイカリアでの仕事は決して机上の空論のみではなかった。クロポトキンは地方の実際の要求と可能性とに通じた実際家について、まず大体の輪郭を論じ、次に一々事実について仔細に調べて行った。
「なおその外にも臨時のいろいろな仕事があった。地方の農業展覧会の報告書とともに、県の経済事情調査書も書かなければならなかった。その他いろいろと重要な調査をしなければならなかった。『われわれは重大な時代に生活しているのだ。働きたまえ、君。君は現在および将来のあらゆる委員会の幹事だということを忘れないようにして。』クウケルはよく私にこう言った。私はますます精を出して働いた。」
クロポトキンのこの努力は、実際の上には、まったく水泡に帰した。官僚政治の組織そのものが邪魔をしたとともに、やがて中央政府に反動の波が来た。あらしが来た。クウケルは免職されて、二人の憲兵の護衛の下にセント・ペテルスブルクに送られ、セント・ピーター・ポールの要塞に幽閉されようとまでした。
しかしクロポトキンの人間や社会についての理解は、そしてまたその全人格的基礎は、まったくその間に築きあげられた。「私がシベリアで送った五カ年は、私にとっては、人間と人間の性質についての純正な教育であった。私はあらゆる性質の人々と、最善の人とも最悪の人とも、社会の上流に立つ人ともまたどん底に蠢いている人とも、宿なしやまたはいわゆる済度しがたき罪人とも、あらゆる種類の人々と接触した。農民の日常生活における風俗習慣を観察する上に十分な機会を得た。ことにはまた、政府者がよし最善の動機から行ったことでも、その農民に益するところのいかに少ないかを観察するいっそう多くの機会を得た。」
「私がシベリアで暮した数年間は、他では容易に学び得ない多くの教訓を私に教えた。まず私は行政機関の方法によっては本当に民衆のために有益な何事をも絶対にできないことを悟った。私は永久にこの妄想と別れた。次に私は人間とその性質との外に、なお人類社会の生命の内的源泉をも分かりはじめた。書物の中には滅多に出て来ない無名の民衆の建設的作用、およびこの建設的作用が社会の種々なる様式の生長発達にいかに重要な役目を勤めているかということが、私の眼の前にはっきりと現れて来た。」
「農奴使用者の家に育った私は、当時のあらゆる青年と同じく、指揮や命令や叱責や懲罰などの必要ということを信じ切って実際生活にはいった。しかし私は種々なる大事業を取扱い、また多くの人間と交渉するに及んで、命令や紀律の原則の上に行動するのとお互いの理解を原則として行動するのとの差異が分り出して来た。前者は軍隊の謁兵などには立派に役立つ。しかし実生活のことにかけては、そしてその目的が多くの輻合的意志の厳格な努力を通じてのみ達せられるところでは、何の値打ちもない。」
「かくして私はシベリアで従来抱いていた国家的規律の信仰をまったく失ってしまった。すなわち当時すでに私は無政府主義者となるべく準備されてあったのだ。」
「発意の人はどこにでも要る。しかし一度このはずみが与えられた以上は、その事業は軍隊式にではなく相互の理解にもとづく自治団体式に経営されなければならない。国家的紀律の設計組立家等はその国家的理想郷を組立てる前に実際生活の学校を通過して来て欲しい。そうすれば、軍隊的ピラミッド的社会組織の諸案を今日ほどに聞かなくても済んだに違いない。」
クロポトキンがこのシベリアで書いたといういろんな調査書や報告書が、今まだどこかに保存されているかどうかはまったく分らない。
かくして社会改良にまったく絶望した彼は、その後は主としてシベリアや満州の地理学的探検の旅行に日を送った。
彼はまず、当時ロシアが占領したばかりのアムール下流植民地に食糧を送るために、アムール州を数千マイル下った。その時にも、諸植民地の地理的事情や経済的事情についての報告書がセント・ペテルスブルグの政府に呈出されてある筈だが、どうなったか。
次に彼は、満州の、こんどは本当に純粋の地理学的探検に出かけた。
アジアの地図を一瞥すると、大体において北緯五十度に沿うて走っているシベリアのロシア境がトランス・バイカリアで急に北の方に曲がっているのを見る。この国境線は三百マイルのアルグン河に沿うて行って、それからアムール河のところまで行くと東南に曲って、アムール地方の首都ブラゴヴェシチェンスクがちょうど再びまた北緯五十度のあたりになる。トランス・バイカルの東南端新ツルハイツとアムール河畔のブラゴヴェシチェンスクとの間は、東西の距離わずかに五百マイルであるがそれをアルグン河とアムール河と沿うて行くと千マイル余りになる。それにアルグン河は船も通わず、その沿岸の交通もきわめて困難だ。ことにその下流ではごく険しい山路があるばかりだ。
トランス・バイカリアは牛馬にすこぶる豊富な地方である。この地方の東南隅に占拠して富裕な牛馬飼養者であるコザック等は、その牛馬の好市場たるべき中部アムールとの直接の交通を求めていた。このコザック等は従来蒙古人と交易していた。そしてかねがね彼等から、大興安嶺を越えて東に行けば容易にアムールに達せられる、ということを聞いていた。東にまっすぐに行くと、興安嶺を越えて、メルゲンという満州町、スンガリーの支流ノンニ河に通ずる支那の旧道に出る筈だ。そしてそこからは立派な道が中部アムールに通じているという。
「コザック等はこの通路発見のために一隊をを組織して、私にその隊長になってくれと言うのだ。私は喜んで承諾した。ヨーロッパ人でこの地方に行ったものはまだ一人もなかった。数年前にロシアのある地理学者がこの道を行ったことがあったが、途中で殺されてしまった。ただかつて、高宗帝時代に二人のジェスイット僧侶が南方からメルゲンまではいり込んでその緯度を測定したことがあった。しかしそれから北の縦横五百マイルの広漠とした地域は、まったく絶対的に未知のものであった。私はこの地方についてのあらゆる参考書を調べて見た。誰一人として、支那の地理学者すらも、この地方については何にも知らない。それに中部アムールとトランス・バイカリアとの連絡はそれ自身重大な性質を帯びていた。ツルハイツは外満州鉄道の主駅になる筈であった。かくして私達はこの大事業の先駆者となるのであった。」
クロポトキンの一隊は難なくこの探検に成功した。彼等はその目的の直通路を発見したほかに、大興安嶺の境界的性質や、その山越えの容易なことや、または久しく地文学上の謎になっていたユウン・ホルドンチ地方の第三期火山などについての、多くの興味ある事実を発見した。
それが済むと、すぐまたアムール河畔を旅行して、その河にというよりもむしろ入江になっているニコラエウスクまで行って、そこからさらにウスリー河を溯った。
それから彼は満州の中心であるスンガリーを吉林まで溯ってもっと面白い旅行をした。
アジアの多くの河は同じ大きさの二つの河の合流したもので地理学者はその二つのどれを本流、どれを支流と言っていいか苦しむくらいだ。インゴダとオノンとが合してシルクとなり、シルクとアルグンとが合してアムールとなる。そしてこのアムールはまたスンガリーと合してかの洋々たる大河となり、東北に流れて韃靼海峡の無人境で太平洋に注いでいる。
その年すなわち一八六四年までは、満州のこの大河もあまりよくは知られていなかった。初めていろいろと知られたのは、前にも言ったジェスイットの時代からであるが、それもごくいい加減なものであった。
クロポトキン等は総督に迫ってスンガリー探検の急務を説いた。総督は吉林州総督に友交を求めるという口実の下に、その秋一隻の汽船を送ってスンガリーを溯らせることにきめた。クロポトキンもその一行に加わった。この探検も立派にその目的が達せられた。河口から吉林までの詳細な河流図も作られた。
「私達の探検はその後忘れられてしまった。天文学者のウソルツェフと私とがシベリア地理協会の『会報』の中にその報告を発表した。しかるに数年後イルクーツクの大火で、その『会報』の残部もスンガリーの原図もすべて焼失して、ようやく昨年(一八九八年)になって外満州鉄道の敷設が始まった時に、ロシアの地理学者等が私達の報告書を探し出して、この大河がすでに三十五年以前に探検されたことを発見したのであった。」
かくして彼はだんだんその精力を科学的探検に向けるようになった。一八六五年には西サヤンを探検して、そこでシベリア諸高原の地勢についての新見地を得、またそれが支那辺境の重要な一火山地方であることを発見した。そしてついに、その翌年再び長途の旅行を企てて、ヤクーツク州の諸金鉱とトランス・バイカルとの間の直接通路を発見した。
シベリア探検会の会員等は多年この通路の発見を試みて、それらの鉱山とトランス・バイカルの平野との間にあるごく険しい岩質のしかも幾列にも平行した山脈横断に努めたのであった。しかしこの探検家等は、南方から進んでこの陰気な山岳地方に到着し、そしてさらに幾百マイルも北方に延びている物凄い山脈を目の前に見た時、ことごとくみなもと来た南へ引返してしまった。
クロポトキンはそれと反対に北から南へと行った。まずレナ川を下って北方の金鉱地に行き、そこで遠征の仕度をして、三カ月間の糧食を持って二百五十マイルにわたる山岳地方を南へ南へと横断して行った。
「とうとう私達は目的の通路を発見した。三カ月の間ほとんどまったく無人の山中と陰湿な高原とをさまよって、ついに目指すチタに着いた。聞けば今ではこの道が南方から金鉱地へ牛馬を送る重宝な道になっているそうだ。私自身にとっては、この旅行は後日シベリアの山岳と高原との地勢を研究する要石を見出す上に非常な助けとなった。」
これらの旅行と探検とは、地理学者としてのクロポトキンを大成させるとともに、その間に見聞した諸動物の社会的習性によって後年の名著『相互扶助論』の萌芽を得しめたのであった。
三
クロポトキンの著書の一々を思い出すままいい加減に紹介して見ようと思ったのが、書き始めるとやはり持前の凝性が出て来て、書物の内容よりもむしろクロポトキンをしてそんなものを書かせるに至った事情の方が明らかにしたくなった。どうもその方が本当のやり方らしい。それに面白いのは、初めや中ほどにちょいちょい書いた僕自身の腹いせや何かが、その時には是非ともそれを言わなければ済まない気持ちであったのが、もうそんなことはどうでもいいことになってしまった。クロポトキン大明神が復活した訳ではないが、クロポトキンという一個の偉大な人間の、その思想や感情の科学的研究の前には、僕というちっぽけな人間の、しかもそのきわめて些々たる私事なぞに構っておれなくなったのだ。
一八六七年、クロポトキンはセント・ペテルスブルグに帰った。ポーランドの政治犯人等がシベリアで暴動を起こしたのに対する、ロシア軍隊の残虐が、ついにクロポトキンをしてその軍職を見棄てしめたのであった。
クロポトキンは大学にはいった。数学の十分な素養が今後のいっさいの科学的研究や思想の唯一の健全な基礎であるという考えから数学科の中の物理数学科にはいった。そしてその間に主として地理的研究に耽った。
クロポトキンの最近の探検報告書が印刷された。しかしその間に彼にはもっと大きな問題が起っていた。シベリアでの彼の旅行は彼に次のようなことを信じさせた、すなわち当時北部アジアの地図の上に描かれていた山脈は大部分とりとめのない空想的なもので、その地方の地勢についての何等の観念をも与えない。アジアの一大特徴であるかの大高原は、当時の地図を描いた人々にはその存在をすらも想像されていない。そしてこの高原の代りに、幾多の大山脈、たとえば、地図の上では普通に黒い毛虫が東の方へ匐って行くように描かれてあるスタノボイ山脈の当方の部分などが、実際にはそんな形勢もなく、またL・シュヴァルツなどの探検家の報告とも違っているにもかかわらず、測量局でのさばっていた。こんな山脈は自然の上にはまったくないのだ。一方には北氷洋に流れ、他方には太平洋に流れこむ幾多の河の源泉は、広大な一高原の上で入りまじっている。すなわちその源泉は同じ沼の中から出て来るのだ。しかるに、ヨーロッパの測量家どもの想像では、高大な山脈が首要分水界に沿うて走っていなければならないものとされていた。で、彼はそこに実際には何の形跡もない大高山を描き出していた。そしてこういった多くの空想上の山脈が北部アジアの地図の上を四方八方に入り乱れていた。
そこでアジアの山脈の配置を知る本当の首要原則、すなわちその山脈構成法の調整を見出すということが、幾年かの間クロポトキンの注意を集中させた一問題となった。しばらくの間は、かの古い地図と、それからアレクサンドル・フォン・フムボルドが久しく支那の原著を研究してアジアの全体を子午線とその並行線とに沿うて走る幾多の山脈の網の目で蔽うてしまった推論とが、クロポトキンの研究の邪魔をした。が、ついに彼は、このフムボルトの推論ですらも新しい研究の刺激にはなるものの、事実とは一致していないことを知った。
初めて彼は、実際当時ではこれがまったくの初めてであるが、彼は純粋の帰納的方法で従来の探検家のあらゆる気圧的観察を蒐めて、それによって幾百カ所の高度を測って見た。次に彼は、いろんな探検家によってなされた、仮定上ではない事実上のあらゆる地理学的および物理学的観察を、大きな地図の上に書き記して見た。そして彼はどんな地形線がこの観察の事実ともっともよく適合するだろうかを見出そうとした。この予備的研究が二年余りかかって、なお数カ月の間彼は、このあちこちに散らばっている観察の、如何とも手の下しようのない混乱の理由を見出そうとして考えぬいた。
するとある日のこと、まったく突然に、ちょうど一閃の光明に照らされたように、すべてがはっきり分かって来た。アジアの首要地形線は、北から南へでもなくまた西から東へでもなく、ちょうどアメリカのロッキー山脈や高原の地形線が西北から東南に進んでいるように、西南から東北に走っているのだ。そしてただ第二次的の諸山脈が西に跳び出しているだけのことだ。それにアジアの諸山脈は、アルプス山脈のように独立した山脈の集合ではなく、すべてみなかつてはベーリング海峡の方に向っていた古大陸であったところの一大高原に隷属しているのだ。高い分水山脈がその高原のふちに沿うて屹立し、そして幾年月かの間にその後の沈殿物によって生じた台地が海の中から浮かび出て来て、アジアの古い背骨であるこの高原の幅を両側に拡げて行ったのだ。
「この研究は、私は科学に対する私の主なる貢献だと考えている。最初私は、大きな書物を出して、北部アジアの山岳や高原についてのこの新しい観念を各々別々の地方の詳細な調査によって証拠立てて見ようと思った。しかし一八七三年になって、私がすぐにも拘引されそうなことが分かった時に、ようやく私の考えを表した地図を描いて、その説明書を書いただけであった。」
「これは両方とも、私がセント・ピーター・ポールの獄中にある間に、兄の監督の下に、地理学協会によって出版された。当時アジアの地図を書きかけていて、私の研究のことをも知っていたペーテルマンという人が、まずその地図に私の案を採用し、それ以来大多数の製図家もそれを採用した。このアジア地図は、今日ではすぐに理解されることであるが、アジア大陸の外形上の首要諸特質と、その気候や動植物の配布と、およびそれらのものの歴史までをも説明したものだ。」
「今日では製図家でもいつアジア地図にこんな変化が来たのかを知っているものはほとんどない。しかし科学の上では新しい観念はそれに結びつけられた何人かの姓名とは構わりなしに進んで行く方がいいのだ。最初の概論には免れることのできない誤謬も、そのほうが修正しやすくなる。」
クロポトキンはまたロシア地理学協会の地勢地理課の幹事としてずいぶん働いた。
当時は全ヨーロッパにわたって猛烈に探検熱の昂まった時代であった。ロシアの地理学協会も盛んに活動した。したがってまたその地勢地理課、およびその幹事たるクロポトキンが熱心に取扱った地理学上の問題もずいぶん多かった。ことに協会が北極探検の計画を立てて、その探検隊によって行わるべき諸科学上の研究を指定するための一委員会が設けられ、クロポトキンは例によってまたその委員会の幹事となった。そしていろんな専門家が各々その専門とする一科学の項を受持ったのであるが、海棲動物学だとか、潮流学だとか振子観察だとか、または地球磁気などという多くの厄介な項目は間に合わずに、仕方なしに幹事たるクロポトキンが書かなければならない羽目になった。それはクロポトキンにはまったく新しい学問であった。しかしクロポトキンはそれすらをもきわめて短日月の間に立派に仕あげた。
が、その間に彼はまた、その専門の地理学についてのまったく新しい一大著述を企てる野心を養っていた。ロシアの地理に関するあらゆる有益な材料は、すべてみなクロポトキンの手を通して協会にはいった。世界のこの広大な部分についての遺漏のない、一大地理書を書いて見たら、という考えがだんだん彼につのって来た。彼のつもりでは、さきに彼がヨーロッパ・ロシアについて発見した首要地形線にもとづいて、この国の詳細な地理的記述をなし、さらにその記述の中に各々その地勢を異にする諸地方に行わるべき経済生活の種々なる様式を略記して見たいと思った。
そして彼はこの野心を充たすための十分な時間と自由とのために協会幹事の職を渇望していた。しかし彼は、その後間もなくフィンランドとスエーデンの周遊を命ぜられて、氷河時代の堆積物調査に派遣され、地質学と動植物分布学との上に新地平線を開こうとしていた間に、その目撃した悲惨な農民の生活が彼をしてせっかくすすめられた協会幹事の地位をも辞せしめ、同時にまたその科学者としての野心をまったく放擲させた。
が、その一大地理書著述の野心は、後年彼が同志エリゼ・ルクリュの『大地理学』編纂に与かった時、その第五巻『スカンジナヴィアとヨーロッパ・アジア』および第六巻『アジア・ロシア』の中に十分に果し得たことと思う。かつて僕はこの第六巻のロシア訳を丸善で見たことがあるが、最近にはその第七巻のフランス文『東部アジア』が四、五冊丸善に来ているのを見た。
僕はクロポトキンのロシアやシベリアの地理学的発見について、大部分の読者には大して興味のなさそうなことを少々長すぎるほど書いて来た。しかしこうした自然科学上の研究が、同時にまた、後年のクロポトキンの社会科学の基礎になっているのだ。過激派征伐の軍人どもは、戦さのひまひまには今言ったような地理学書でも繙いて見て、少しは「土地と人間」(これはルクリュの本のサブ・タイトルだ)のことを考えて見るがいい。
四
アジアの新地図を作り、新地理を書くことについての、クロポトキンの科学的研究の態度は大抵これで分かったことと思う。が、クロポトキンのこの科学的研究の素養については、さらに遡ってその少年時代に受けた教育を見なければならない。
クロポトキンが近侍学校--日本の幼年学校と士官学校とを合わせたようなもの--で受けた教育ほど羨しいものはない。先生はみな当時ロシアで第一流の学者であった。実際、ごく年少の生徒にある課目の一番の初歩を教えるのには、どんな先生でも決して善すぎるということはない。ただ書物だけで講義をするのではない。すべて実地について、生徒自身をしてその実験をやらせた。
書物で初等幾何学を教わると、すぐに野外に出て、初めは棹や測量用の鎖で、やがては観象儀やコンパスや測量台などで、その復習をした。そしてやや進んで測量学や築城学を教わる時には、反射羅針盤をあてがわれて、「この羅針盤で角度を量り、歩測で距離を計って、某々の湖、某々の道路、某々の公園の見取図を作って来い」と命ぜられる。生徒等は軍服の大きなポケットにライ麦のパンの幾きれかを詰めこんで、毎日朝早くから数マイル隔たった公園へ出かけて、地図を引きながら美しい木影の路や小川や湖の畔を歩き廻る。かくしてできあがったみんなの地図はやがて正確な地図と対照される。
「私にはこの測量が深い悦楽の泉であった。その独立の仕事、幾百年を経た老樹の下の孤独、何ものにも妨げられずに楽しむことのできる森林生活、および仕事そのものの興味--これらのすべてのものが私の心に深い痕跡を残した。私が後にシベリアの探検家になり、また友人の幾人かが中央アジアの探検家になったのも、その基礎はすでにこの測量によって準備されていたのだ。」
それに生徒の方でもまた、この方針に従いかつそれに促されて自己教育をした。独立的研究をすらもした。
クロポトキンは年十五の時にはもう経済学の独立的研究をやっている。それは当時経済学熱の絶頂にあった兄アレクサンドルの勧めで、村の教会のお祭りである「カザンの聖処女祭」の市を研究して、そこへどれだけの商品が持ちこまれどれだけの商品が売れたかの統計を作ったのだ。クロポトキン自身もそれを「平民生活の探検者として最初の自立」だと言い、「この小事業は私を農民等にさらに一歩近づかせて、新たな方面から彼等を観察させ、なお後年シベリアでこれが非常な助けになった」と言っている。そしてその統計そのものについては、「自分ながら驚くほど成功した。今から考えて見て、私のその統計は多くの同じような統計に勝るとも劣るところはなかった」と自讃している。
この兄がクロポトキンの知識的発達にどれほど与っているか知れない。しかしそのことはここでは省く。
そしてクロポトキンは十六の時にもう歴史の著述と独立研究とをしている。彼は授業時間中に作ったノートの助けをかりて、またいろんな書物の助けをもかりて、自己用の初期中世史の一講義を書きあげた。その翌年彼はローマ法王のボニファス八世と王権との争いに特殊の注意を持って、無理やり帝室図書館にはいりこんで、古代チュートン語と古代フランス語との豊富な古文書的源泉に親しんだ。
「まったく新しい社会の構成法や、錯雑した関係のまったく新しい世界が、私の前に現れた。それ以来、近代的見解によって演繹された著作よりも、歴史の古文書的源泉に溯る方が遥かにいいことを覚った。近代的見解には、近代政治学の偏見や、または単なる一時的思潮の信条が、その時代の実生活を覆いかくしている。」
クロポトキンのこの中世史研究は、その後彼にまったく独創的な史的観察を抱かせて、『相互扶助論』の中の最傑作「中世都市における相互扶助」二篇を形づくらせる基礎となった。
クロポトキンはまた十八の時に学校用の物理学教科書を編纂している。陸軍の学校で使う大がいの教科書はその当時の第一流の学者によって特別に書かれたものであった。クロポトキン等の物理学の教科書もかなりいいものであった。が、どちらかと言えば、それは少し旧式のものになっていた。で、クロポトキン等の先生はその独特の教授法でやって行って、教室で使うその教材の摘要を作り始めた。そして数週間たつと、先生はクロポトキンにその摘要を書く役目を仰せつけた。先生は本当の教育家としての態度に出て、そのいっさいをクロポトキンに任せて、自分はただ校正刷りを読むだけだった。熱や電気や磁気の章は全然書き直さなければならなかった。クロポトキンはそれを書きあげた。そして彼は学校用に印刷されたほぼ完全な教科書を作った。
その年にクロポトキンはまた化学の研究をはじめた。先生はやはり第一流の学者で、すでに有益な独創的研究を遂げていた人であった。クロポトキン等は五、六人で組んで、一友人の家に実験室をつくって、ステックハルトの教科書の中に初学者に勧めている簡単な機械を備えた。そして日曜日や祭日の全部をその実験に暮した。
当時、すなわち一八五九年から六一年にかけては、諸正確科学に対する趣味の世界的勃興の時代であった。グローヴやクロージァスやセガン等は、熱およびその他のあらゆる物理的力が運動の変態に過ぎないことを証明した。ヘルムホルツは音響についてのその劃時代的研究をはじめた。チンダルはその通俗講演の中で分子や原子についての暗示をした。ゲルハルトとアヴォガドロとは元素交換の法則を発表した。メンデレーフ、ロタール、マイヤーおよびニューランズは諸元素の周期律を発見した。ダーウィンはその『種の起源』によっていっさいの生物学的科学を革命した。また、カール・フォクトとモレショットとは、クロード・ベルナールのあとをついで真正の心理学の基礎を生理学に置いた。科学勃興の大時代であったのだ。そして人心を自然科学に向わしめたこの大潮流はとうてい不可抗的のものであった。クロポトキンもやはりこの潮流の中に巻きこまれた。そして彼は、「あとで何の研究をするにしても、自然科学の深い知識とその方法に習熟することがすべての基礎にならなければならぬということを覚ったのであった。」
クロポトキンの著書のすべてに一貫するもっとも深い特徴は、この「自然科学の深い知識とその方法との習熟」である。本当に正直な近代科学的精神の横溢である。
ぼくはさきにクロポトキンはその科学者としての野心をまったく放擲したと言った。しかしそれは単なる科学者としての野心を棄てただけのことで、科学そのものを見放した訳ではない。また、自分の人間の一部分を形づくっている科学者を殺してしまった訳ではない。その後といえども自然科学の研究にはできるだけ尽くしている。そしてその研究とともに、諸社会科学の新見地の上に自然科学の方法そのままを適用することに全力を尽くしている。
が、そのことはまたあとで言うとして、もう少しクロポトキンの自然科学について説こう。
一八七四年、クロポトキンが初めてセント・ピーター・ポール要塞に投獄される数日前のことだ。彼はフィンランドとロシアとの地質的構成についての報告書を書き終って、それを地理学協会で朗読しなければならないことになっていた。厚い結氷の層が中部ロシアをまでも蔽うていた、というクロポトキンの新発見は、当時の多くの学者等にあまりに極端な仮説だと考えられた。で、いったんきまった朗読の日を一週間延ばして、十分な討論に附することになった。
「盛んな討論があった。そして少なくともある一点だけは私が勝った。ロシアの洪積時代についてのいっさいの旧い学説はまったく根拠がない、で、その全問題を調査し直して、新しい出発点を求めなければならない、ということは認められた。そして私はわが国一流の地質学者バロボ・ド・マルニイの次のような言葉を聞いて満足した。『氷堆が蔽うていたか否かは別として、とにかく流氷の作用について従来われわれの言ったいっさいは、実際のいかなる探検にも根拠のなかったことを認めなければならない。』」
その日彼は地勢地理課の課長になるようにと勧められた。しかし彼は内心その晩は「第三部」の牢屋で寝なければなるまいと決心していたのであった。はたしてその翌日彼は拘引された。
そして彼は要塞の独房の中で、この報告書を訂正増補して、二冊の大きな本になるほどの原稿を書きあげた。その一冊はさきにも言ったごとく、兄アレクサンドルの監督の下に地理学協会から出版された。その後クロポトキンが脱獄してイギリスに亡命し、レヴァショフという匿名で雑誌『ネェチュア』と新聞『タイムズ』とに科学上の雑報や新刊批評を書いて生活の資を得ていた時、『ネェチュア』の副主幹ケルシイからそうとは知らずにこの自分の著書の評論を頼まれて、ひどく当惑したという面白い話もある。
遠い過去の、人類が生れ出たばかりの頃に、スカンジナヴィアやフィンランドの向うの北方の諸群島に、年々氷が積り積っていた。そしてこの積り積った広大な氷の層が、漸次ヨーロッパの北部に襲うて来て、やがては徐々としてその中部地方にまでも拡がった。生物はこの半球のこの部分にも住んでいた。が、この広大な氷原から来る氷の息に吹かれて、惨憺たる不安な生活を送りながら南へ南へと逃げた。憐れな弱い無智な人間もその覚束ない生存をを続けるのにあらゆる艱難辛苦を嘗めた。幾千万年かが過ぎ去った。氷が解け始めた。湖水時代が来た。無数の湖が凹地にできた。みすぼらしい亜北植物がそれらの湖のまわりの底も知れない沼地をおずおずと侵し始めた。再びまた、幾千万年かが過ぎ去った。ごく緩慢な乾燥作用が始まった。諸生物が南の方から徐々としてその侵冦を始めた。そして今日ではわれわれはその乾燥作用がよほど迅速になった時代にいるのだ。乾燥した平野や草原ができて来た。人類はこの乾燥作用を妨げる方法を見出さなければならなくなった。現に中央アジアはこの乾燥作用の犠牲となり、東南ヨーロッパもそれに脅かされている。
この氷原が中央アジアにまで及んでいたという確信は、当時多くの学者の間に異端視されていた。が、今日では、クロポトキンのこの新発見は大体において認めないものはない。
その後クロポトキンは『エンサイクロペディア・ブリタニカ』にも多くの科学上の論文を書いているが、それにもまして彼自身の科学上の研究ともなりまた科学界の貢献ともなったのは、一八九二年から一九○三年に至る十年間、彼が雑誌『十九世紀』の「最近科学」欄を受持ったことだ。
これはその後は誰が担任しているか知らないが、クロポトキンの前にはハクスレーがやっていた。さすがのクロポトキンもそのあとを引受けるには多少の躊躇があったようだ。しかしクロポトキンのその諸論文は最近に一まとめにして出版されるという話があったが、その後戦争や何かで立消えになっているらしい。
とにかくクロポトキンは、そのお陰で、最近科学のいっさいの発見、いっさいの新説に通ずることができた。そしてそれらの発見や新説の研究の結果、ますます科学的方法の上に深い確信を抱くようになった。そのことは『近代科学と無政府主義』の再版の序文にも言っているし、その本文の中にも詳しく論じている。
五
クロポトキンの著書全部の大体の単なる解説、というのが中途でクロポトキンをしてそれらの著書を書かしめた頭の出来具合の説明に変り、それが同時にまたうまくクロポトキンの無政府主義以外の科学的著述の自然の解説になってしまった。クロポトキンの生涯をフィンランドでの改宗を境として、前後の二期に分ければ、その前期のほとんどすべての著述、もしくは著述の卵が紹介されてしまった訳だ。
革命家としてのクロポトキンの著述、それはもとよりすこぶる重要なものだ。しかしその本当の重要さは、やはりその科学者としての著述の重要さが分らない間は、本当には分らない。
さきには僕は巣鴨の獄中から幸徳に宛てた手紙の一節を書き抜いたが、その一節の前にはこんなことが書いてある。
「この頃読書をするのにはなはだ面白いことがある。本を読む。バクーニン、クロポトキン、ルクリュ、マラテスタ、その他どのアナーキストでも、まず巻頭には天文を述べている。次に動植物を説いている。そして最後に人生社会を論じている。」
「やがて読書にあきる。眼をあげてそとを眺める。まず眼にはいるものは日月星晨、雲のゆきき、桐の青葉、雀、鳶、烏、さらに下っては向うの監舎の屋根。ちょうど今読んだばかりのことをそのまま実地に復習するようなものだ。そして僕は、僕の自然に対する知識のはなはだ浅いのに、いつも恥じ入る。これから大いにこの自然を研究して見ようと思う。」
「読めば読むほど、考えれば考えるほど、どうしてもこの自然は論理だ。論理は自然の中に完全に実現されている。そしてこの論理は、自然の発展たる人生社会の中にも、同じくまた完全に実現されなければならない。」
「僕はまた、この自然に対する研究心とともに、人類学や人類社会史に強く僕の心を引かれて来た。こんなふうに、一方にはそれからそれへと泉のように学究心が湧いて来ると同時に、獄中の強制的無為無活動はいよいよますます:叛逆: 心をそそってくる。この学究と:叛逆: との二つの野心、僕等はそれを一つは監獄で一つは社会で満足させて行くんだね。」
この「自然は論理だ」の項は少々可笑しいが、とにかくクロポトキンの無政府主義文書には自然科学を説いていることがすこぶる多い。しかしここに注意して置かなければならないのは、それがヨーロッパの多くの自然科学者がやったような、また日本でも丘浅次郎博士や石川千代松博士がやっているような、いわゆる生物学的社会学では決してなかったことだ。クロポトキンは自然科学の事実もしくは原則をそのまま人類社会学の上に適用する、幼稚きわまるそしてまた危険きわまる類推法なぞには決して依らなかった。彼はどこまでも本当の科学者であった。彼が社会科学を論ずる上に自然科学を説いたのは、一方には自然科学の帰納的方法をそのまま社会科学の上に適用せんとし、他の一方にはかくして自然科学の傾向と社会科学の傾向との上に一致を求めて、そこにその一大世界観を建てようとしたのであった。
そしてこの一大世界観が、クロポトキンにとっては、その無政府主義そのものなのである。
「無政府主義は自然全体を包括する。--すなわちその中の人類社会の生活とその経済的政治的道徳的問題をも含む--いっさいの現象の機械的説明に基礎を置く世界観である。その目的は一個の概括的結論の中に、自然のいっさいの現象--したがってまた社会生活の--を包含する総合哲学を建設することである。」(クロポトキン著『無政府主義の哲学と理想』)
『無政府主義の哲学と理想』は、まず最近の諸自然科学の傾向および諸社会科学の傾向を述べて、そこに立脚する宇宙の科学的概念すなわち総合科学としての無政府主義を論じ、さらに進んで「自然科学的帰納法によって得られた概括的結論を人類諸制度にも適用しようとする試み、また人類社会の各単位に対して最大量の幸福を実現する目的をもって自由平等友愛の途上における人類の将来の歩武を予見しようとする試み」(クロポトキン著『近代科学と無政府主義』)で、社会哲学として無政府主義を説いたものである。そしてその『近代科学と無政府主義』はそれをさらにいっそう詳細にしたものということができよう。
六
近代の哲学にはまったく相反するがごとき方向に流れる二大潮流がある。
その一つは、実験科学の著しい進歩につれて、その方法にまったく安住している人々の一派である。この人々といえども自ら全真理を捉えているとはもとより信じていない。彼等自らも、きわめて小さな、しかもあちこちに散らばっている断片を持っているに過ぎないことは、十分に承知している。しかし彼は、真理であると認められたまた認めらるべきいっさいが、すなわち彼等の精神を満足せしめ得べきいっさいが、科学的方法によってしかもそれによってのみ得られると堅く信じている。しかるに他の一方に、この科学を無視しているのではなく、むしろそれに非常な注意と敬意とを払いつつ、いわゆる科学的方法に十分な満足を感じ得ない人々の一派がある。すなわちこの人々の精神ことに情感は科学的方法によっては満足され得ないある要求を持っている。
今僕がこの二大潮流の簡単な説明の中に、その一方に対しては精神、他の一方に対しては精神ことに情感と言ったごとく、前者は理知もしくは理性を重んずるとともに、後者は本能もしくは感情を尚ぶ傾向がある。そしてこのいずれもの傾向に濃淡強弱の度のいろいろあることは言うまでもない。しかし概括して、前者を科学派(サイエンティズム)、もしくは主知派(インテレクテュアリズム)、後者を実際派(プラグマティズム)、もしくは非理知派(アンチ・インテレクテュアリズム)と呼ぶのに差支えはあるまい。
実際派は科学派の主知主義と主理主義(ラショナリズム)とを非難して、科学を利用しつつ、科学のそとにまたは時として科学に反対して真理を得ようとする。科学派の重んずる理知や理性を人間の皮相の能力であると見做して、さらにその根本のものであると認める感情や本能や傾向や欲望やまたは憧憬を尚ぶ。この実際派に拠れば、理知や理性の所産たる科学は、自然に対するわれわれの能力を確かめるものに過ぎない。事物の利用をわれわれに教えるものに過ぎない。その本質については何事をも教えない。われわれ自身がいかなる本質のものであり、われわれが何処から来たり、何処に行き、また行かんとしつつあるかは、われわれ自身の非理知的根抵または時としては無意識の中に求めなければならない。われわれの暗い憧憬や本能は、われわれの理性の明るい判断よりも、遥かによくそれらのことを教えてくれる。科学は無視し蔑視すべきものではないが、しかし第二義的の知識に過ぎない。第一義の本当の知識はわれわれの情感的直覚の中に求めなければならないと言う。
科学派と実際派とを比較する時、すぐわれわれの頭の中に浮かんで来るのは、科学の破産という言葉である。この科学の破産によって実際派が産れ、実際派の勃興によって科学の破産が確かめられた、としばしば言われている。
このいわゆる科学の破産は、既成科学そのものの不完全と、およびある科学者等の態度の愚昧と不遜とから生じたものである。すなわちある学者等は科学の急速な進歩に酔わされて、科学の万能を信じまた科学の既成法則をもって一定不変の真理であるかのごとく説いた。けれども科学そのもののさらに新しい進歩は、その既成のしかも根本の、多くの法則を打破った。
すなわちさきのいわゆる法則は、数学者の常に用いる、第一近似価であったのだ。そしてこの第一近似価は、それが発見されたのと同じ科学的方法で、必然にかつ当然にさらに第二もしくは第三の近似価に移ろうととしているのだ。そしてまた、この第一近似価の破滅に乗じて、従来の科学の不完全とある科学者の愚昧と不遜とまたいわゆる科学的方法のある方面における無能とを批評しつつ、さらに異なれる方法によって第二もしくは第三の近似価を求めようとしているのが、かの実際派の哲学論者であるのだ。
しかるに、科学派の学者は、精神と物質との一元論から出発して、この二つの世界のいずれの研究にも科学的方法をもって進もうとする。また、実際派の哲学者は、そのいわゆる事物の皮相たる物質界の研究を科学者のなすがままに委ねて、そのいわゆる事物の本質たる精神界の研究に特殊の方法をもって自ら任ぜようとする。されば問題は、この精神界において、科学派の帰納法と実際派の直覚法とのいずれが、第二もしくは第三の近似価を得ることに成功するかにある。
以上は科学派と実際派とのいずれにもできるだけ善意なしたがってもっとも公平な大体の比較であるが、しかし実際派の起原をを見るに、それは精神界というよりもむしろ社会界における真実を求めるために、いわゆる科学的方法の訂正として現れたものだ。
物理学や化学などのいわゆる正確科学では、従来の科学的方法で十分であるかも知れない。しかしそれらの科学に馴れた科学者等は、とかくに人間の本能とか意志とか感情とか憧憬とかを無視して、ただ知力と理性とに重きを置く傾向があった。そしてこの知力や理性の上にのみ築かれた体系をもって、真実である法則であると見做し、なおそれを一定不変の絶対的のものであるとまで断定した。この主知主理的真実の中には、、本能や意志や感情や憧憬を無視したところに全的人間味が欠け、また不完全な人間の知力や理性を過重したところに必然の誤謬があった。したがっていわゆる社会的法則や真実はただ理屈攻めのもので、実際において人間離れのしたまた実際の生活と適合しない場合が多かった。そこでこの欠点を補い、この誤謬を正さんがために、等しく観察と実験とによる科学的方法を用いつつ、ただその観察や実験を知力や理性の上よりもむしろ本能や行為の上にもとづかせたプラグマティズムすなわち固有の意味の実際主義が生れたのであった。
この意味の実際主義は、一八七七年十一月および一八七八年一月の『ポピュラー・サイエンス』に初めてこのプラグマティズムという言葉を用いた、アメリカの科学者パースの創見であった。
この実際主義とは行為の哲学、結果の哲学、利益の哲学である。ある思想の真偽を判断するのに、ただちに理性や理論に走ることなく、まず行為に赴いて見る。すなわちその思想を実際問題とぶつからせて見る。そしてその行為のもたらす結果により、利害によって、その思想の真偽を決定する。かくあらゆる思想を夢みながらではなく生かして、抽象から具体に移して、試して見るという方法には、第一の条件として意志を要求する。精力を要求する。教えられたいっさいの理屈を排斥しもしくは忘却して、ただ本能の奔るがままにあらゆる事実にぶつかって行く、意志と精力とを要求する。
パースのこの実際主義は、ジェームスによって多くの解釈を加えられて著しく宗教的となり、またシラーのいわゆる人本主義となり、さらにまたベルグソンの創造論となり、種々に発展し変化してついにさきに述べた今日の実際派的大勢を形づくるに至った。しかし要するに固有にいう実際主義の起原と根本とは、この行為とその要求する意志と精力とによって、主知主理派の科学的方法の訂正を企てたものであった。
けれども従来のいわゆる社会的法則もしくは真実が、多くの場合に虚偽でありあるいは容易にその真実を判断され得ないのは、社会科学そのもののまたはその研究方法の今言った意味での不完全であるというほかに、実際派の哲学者輩のまったく知らないしかしわれわれの忘れてはならない一大理由がある。すなわち科学者や哲学者もまたわれわれと同じ人間であって、その属する社会的階級の定心を持っている。彼等の多くは少なくとも有閑階級に属しまた直接間接に権力階級に附随している。社会が利害のまったく相反する征服階級と被征服階級との両極に分離し、学者がその隷属する征服階級に定心を持っている時、そのいわゆる社会的真実が多くの場合において被征服階級の生活事実に適合しないことは言うまでもない。
労働運動は、さらに広く言えばいっさいの民衆運動は、この征服階級のいわゆる社会的真実に対する、実生活の上からの最初は無意識的の叛逆であった。そして実際主義は、社会のこの階級的区別を少しも考察の中に入れずに、ただ主知主理的のいわゆる社会的真実に対する最初から意識的の叛逆であった。
C・G・Tすなわち労働総同盟のサンジカリズムは、労働運動におけるこの無意識的実際主義のもっともよく具体化されたものである。
サンジカリズムは、無知なる労働者の日常生活の間に、その日々の資本家との闘争の間に、ほとんど自然にできあがった運動である。理論である。もっともサンジカリズムはその長い間の形成の行程の間に、社会改良主義から無政府主義に至る幾多の社会的学説の影響を受けてもいるが、それらの学説の指導の下に形成されたというよりも、むしろ労働者がただ生きんとする本能に駆られて、右往左往の間にそれらの学説を行為によって吟味しつつ、ついに彼等の生活そのものの経験と直覚とから不断の流転を経て創造されたものである。彼等は最初から理想を持たなかった。また定まった運動方法を持たなかった。もとより何等の社会的学説を持っていよう筈もなかった。彼等はただ盲滅法に、その目前の死から逃れんがために、さらによりよく生きんがために彼等の能うだけの全力を尽くした。かくして彼等は彼等自分の力をもって彼等自身の真実を築きあげようとしたのであった。
彼等はその長い努力の間に、種々なる社会的学説にたよってことごとく失敗した結果、いっさいの社会的理論を斥けて、ただ彼等自身の経験にのみよることとなった。よりよく生きんとする意志から、その障碍となるべきいっさいの事物にぶつかって行って、その結果の中から彼等自身に利益のあるものだけを選び出した。彼等の運動方法も、彼等の団体の組織も、彼等の将来の理想も、彼等の道徳も哲学も、すべてみな理屈でこねあげたものではなくただあらゆる事業とぶつかって見て、その結果として現れたものである。
しかるにこの実際的方法によって形成されたサンジカリズムと、まったく科学的方法によって形成された無政府主義とが、すなわち別個の方法によって獲得された各々の社会的真実が、その最後の結論においてほぼ相合致したのは何故か。
それはクロポトキンの科学的方法が、いわゆる実証派(ポジティヴィズム)の偏狭杜撰な科学的方法ではなく、「人類社会の各単位に対して最大量の幸福を実現する目的をもって、自由平等友愛の途上における人類の将来の歩武を予定しようとする試み」の科学的方法であったからである。人間の本能や感情や意志や憧憬やを蔑視する、また社会の階級的分離を無視する、いわゆる主知主理派の科学的方法でなかったからである。実生活の上の観察と実験とによって幾多の事実を帰納しつつ、また人間を全人的に取扱いつつ、社会的真実を求めんとした純正な科学であったからである。ことにその社会進化の最大要素を人類の社会的憧憬に求め、社会的創造に頼って、新勃興階級たる労働者中のもっとも活力ある分子の実際生活にその結論を得て来たからである。
七
しからば、かくして得たその一大世界観、すなわち無政府主義の哲学とはどんなものか。
クロポトキンはそれをまずその『無政府主義の哲学と理想』の中に論じ、さらにその『近代科学と無政府主義』の中に詳論している。それを今、僕はその前者の巻頭数ページをそのままに翻訳して、大体の瞥見をして見ようと思う。
自然の事実についての知識と、社会現象についての概念とは、常に少なからず相交渉するところあるものである。すなわち宇宙の総体についての思想の変化と、社会現象についての思想変化とは、常によく相反映する。
かつてわれわれの先祖は信じていた。地球は宇宙の中心である。太陽も月も星も、すべてこの地球を中軸として、その周囲を廻転する。そして日月星晨をはじめ、万有ことごとく、この地球の上に棲息する万物の霊長たる人間のために、神の御手によって創られた。されば神は常に人間の上を見守って、あるいはその徳行を賞せんがために、あるいはその罪悪を懲さんがために、時に野に雨を降らし、時に街に雷を鳴らすと。そしてこの科学と哲学との支配していた史上のもっとも暗黒な時代を、もっとも雄弁に物語るものは、すなわちかの東方諸国の神権政治であった。
けれども、やがて十六世紀の頃になって、ようやく人間とその思想とが宗教の桎梏を脱しかけようとした時、われわれの祖先は従来地球と人間とにあまりに過大な役目を帯ばしめていたことに気がついた。地球はもはや宇宙の中心ではなく、他の諸遊星よりもずっと小さい一小塊、太陽系中の一粒の砂に過ぎないと知った。そしてこの地球に代って宇宙の中心となった、しかもこの地球に較べれば広大無辺なほどのかの太陽も、これと同じ大きさあるいはさらに大きな、天の河の中に閃いて見える無数の他の太陽の一つに過ぎないと分った。かくして、今までは神のいとし児と誇っていた人間も、この宇宙の無窮に対しては、九天の上から突如として九天の下に蹴落とされた形となった。
哲学史を繙いて見れば、この天文学上の知識の変化が、どれほど社会事実の思想の上に影響を与えたかについて、必ず幾ページかの絢爛たる文字を見出す。実にこの時代のあらゆる思想は、その純理的なると応用的なるとを問わず、一としてこの反動を蒙らざるはない。そしてこの時代から、初めて、今日のいわゆる自然科学の芽が吹き出して来た。
しかるに今日また、それと同様のことが起って来ている。すなわちわれわれは科学的概念の総体と哲学的概念の総体との上に、すでに前にもまして、さらに深いさらに大きな変化の起りつつあるのを見る。
十八世紀の終りから十九世紀の初めにかけて、天文学は正にニュートン説の全盛時代であった。その哲学は言う。太陽はわれわれ太陽系の主人である。王である。支配者である。心である。魂である。この太陽から、その諸衛星の運動を指揮しその間の調和を維持する、力が出て来る。すなわち太陽の強大な引力が地球や諸遊星やまた諸彗星をすらも、各々その軌道に安んぜしめるのだ。それらのすべてのものはこの太陽から分れ出た枝葉だ。みんな太陽から生れて来たのだ。そしてそれらの土塊に生気を与えかつその装飾となっている諸生物もまた、みんなこの太陽のお陰で育っているんだ。この支配者の権威によって、初めて宇宙の間に、完全な秩序と調和とが生れる。よし多少の不秩序が起ることがあっても、それはほんの一時の変動で、すぐに太陽の引力がすべてをもとの秩序に帰らしめる。しかもこの秩序たる、実に万世不易のものである。何となれば、いっさいの変動は、その命ぜられた秩序に復帰せんがために、互いに相補整し相壊滅するが故であると。かくしてそこに新しい太陽崇拝教が起った。
しかしこの概念もまた、前のと同じようにすぐに打ち毀されてしまった。諸遊星と諸太陽との間の無限の空間には、数限りのない極微物質の群が飛び廻っている。その群の中には、時々地上に落下して人間を戦慄させる大きなものもあれば、ようやく幾グラムか幾センチグラムに過ぎない小さなものもある。そして、このごく小さな土塊にも、その周囲には、顕微鏡でなければ見えないほどの無数の塵埃が空間をとりかこんでいる。これらの極微物質は各々それ自身の生を有し、恐ろしい速度で四方八方に突進し、いたるところに、そして常に相衝突して相離合して、その間にある偉大な力を生ぜしめる。その力は、それを一つ一つに離して見ればもとより言うに足りない微弱なものであるが、それが相重なり相積んでついに恐ろしい強大なものとなる。そして太陽系そのものも、その中の無数の星も、またそれらのものを動かす運動もその調和も、すべてみなこの極微物質の集合的作用に過ぎないことが分った。さらに一歩を進めて言えば、ニュートンが太陽の力であると言った引力そのものも、実はこの空間に充ち満ちている極微物質の自主的運動の結果に外ならないことが分った。 これを一言に言えば、従来は常に統計と結果とのみを見て、その統計を成す各単位や、またはその結果を導く起原については、ほとんど顧みられなかった。それが今日では、反対に、むしろ単位であり起原である極微物質の方に注意を傾けるようになった。そして、統計の中に積み重なっている各個体の微かな作用が分らなければ、その結果は分るものでないと考えるようになった。
さらに言葉を換えて言えば、宇宙にはもはやただ一個の支配力というようなものはない。あらかじめ定められた法則はない。あらかじめ計画された調和はない、ただ無数の極微物質が、各々自由自在にその向うところに突進して、そしてその間に自然と均勢ができる。それが宇宙の力だ。法則だ。調和だ。
これが最近天文学の結論である。宇宙の総概念、すなわちコスモロジイの結論である。
天文学上のこの新しい結論は、さらにあらゆる自然と人類社会との諸科学の上にも、それと同じ変化を及ぼした。
まず物理学上では、かつて実体として取扱われていた光とか、熱とか、電気とか、または磁気とかいうものが、よほどその性質の解釈を変えられて来た。すなわち、熱を加えられたあるいは電気の通ぜられたある物体に対して、それがもともと、自分では何の力も持たない死んだ物体であったのが、そとのある未知のものからそれらの力を与えられて生きて来たのだ、というようには見なくなった。物理学者はまず、その物体および周囲の空間の中に、あらゆる方向に突進し活躍し廻転している無数の極微物質の運動に注意し、そしてそれらのものの運動と衝突と生気とによって光や、熱や、電気や、または磁気が生じたのだと説明する。
生物学においてもまた、種の創造とか現出とかいうことはもはや昔の物語となって今日では各個体そのものの生活とその周囲ということとが、動植物学者の研究主題となった。この周囲の影響とか、また毎日のように変って行くその諸条件に各器官が適応して行く状況によって、個体の上に起る変化を研究するようになった。気候の寒暖乾湿や、食物の多少や、またはその外界の力に対する感受性の厚薄強弱等によって、各個体の上に起る変化が、やがて新種の起原になるのだ。すなわち、種の変化は各個体の上に別々に起る変化の総計もしくは結果である。各個体がその生存する周囲の無数の影響を受けつつ、各自がその個性に従ってそれに適応する、その統計が、相集まって新しい種を造り上げるのだ。
しかし、この個体そのものもまた、無数のそしてそれ自身の生を持っている極微物質の集合体である。生物の各器官は有機体たる無数の細胞より成り、その各細胞はそれ自身の個性を保存しつつ相集合して、そこにある一個体を組織する。人間はもはや唯一者ではない。分離することのできない完体ではない。微生物の集合団である。細胞の群体である。器官の部落である。かくして生物学者は、人間を知ろうと思うなら、まずその各単位を究めなければならないと言うようになった。
そして十八世紀の唯物論者すらもなおその概念に囚われていた、いわゆる人間の霊魂なるものも、孤立した特別の存在物ではなく、要するにはなはだ複雑した、すなわち各自が別々に自治し独立しつつ、自由な行動をとっている諸種の官能の群体である。総計である。これらの官能の各々には、それぞれの神経中枢がある。それぞれの種々なる器官がある。かくしてついに心理学は一個人の心理的作用の学問ではなくなって、その個人の生命を組成する諸種の官能の別々の研究となった。
社会科学にもやはり同じ変化が来た。むしろさらに明白にこの変化が現れている。
歴史はもはや王朝の歴史ではない、民衆の歴史である。さらに適切に言えば、各個人の歴史である。歴史の見解はもはやいわゆる英雄崇拝を許さない。そして史上における民衆の大きな役目が、その研究の進むに従って、ますます重大な意味を持って来た。過去の大事件はすべてみな幾千万の個人の意志が積み重なった結果として見られるようになった。すなわち歴史はまず、ある時代に生存して一国民を組織する各個人が、どんな信仰を持ち、どんな生活を送り、どんな社会的理想を抱き、そしてどんな方法をもってその理想に進んで行ったか、ということを調べて見る。そして、それらのすべての力の集合的作用によって史上一切の大現象を解釈しようとする。トルストイの描いた『戦争と平和』の中の、一八一二年の戦争のごときは、実にその好適例である。
法律学者もまた、単にある法典を研究するだけでは、もはや満足ができなくなった。ちょうど人種学者と同じように、いろいろな制度の起原を尋ねて、時代を追うてその進化のあとを究めて行く。そしてこの研究を進めるにも、成分法などよりもむしろ各地方の習慣、またはいわゆる習慣法にたよって行く。かくしてそこに無名の社会的創造、建設的天禀を発見する。
また、経済学はかつて国家の富の科学であった。されば、この科学の始祖たるアダム・スミス自身も、その名著に題して『富国論』と言った。そしてその取扱った主題は、国家の生産であった。輸出入であった。交換であった。しかるに今日の経済学はもう、国家の富を研究するだけで満足ができなくなった。そして各個人がその欲望を充たしているかどうかを知ることが、そのもっとも重大な研究主題となった。
今日の経済学はもう、一国の富を測るのに、その交換の総額によるようなことはしない。まずその一国の中に、窮乏の中に蠢いている個人の数に比較して、幸福を享けている個人の数がどれほどあるかを調べて見る。すなわち一軒一軒と歩き廻って、食物に事を欠いていやしないか、子供にさっぱりとした夜具を着せているか、明日のパンに困っているような家はないか、と探して見る。これを要するに、個人の欲望とその満足ということが、最近経済学のまず第一に知ろうとするところである。
政治学ではやはり、各国の法典に記されたいろいろな形式、すなわち国家の看板などはもうさほど重大な問題ではなくなった。ただ政治学者が知りたいのは、各個人がどれほどまでに自由を享けているか、地方自治の欲望がどれほどまでに満足されているか、各個人の知識的水準がどれほどまでに進んでいるか、どこまでその思想を表白する自由があるか、そしてまたその情意の衝動によって行動の自由がどこまで許されているか、ということである。すなわち、政治学の研究主題は、やはりその国民を組成する単位の個人であって、一国の政治的状態などという結果は、その起原たる各個人の状態さえ分れば、自然に分って来るものとされている。
かく物理界にも、生物界にも、また人類界にも、すべての科学にわたって、時代の一大特徴たるこの傾向が容易に見られる。かつては総計と結果のみを見て、それに満足していたのが、こんどは逆に、その総計なり結果なりを組成する各単位の上に注意を向けるようになった。
八
さきにもちょっと一言したように、近代科学のこの傾向は一つの大きな概念を近代思想の上にもたらした。それは、調和とか秩序とかいう思想についての、最近科学の結論である。
自然は実によく秩序が行き届いている。激変などということは滅多にない。どうして日月星晨は、いつもその空間の同じ道を往来して、互いに衝突したり打ち毀し合ったりすることがないのだろうか。どうして火山の爆発や不意の地崩れなどが起こって、時に大陸を打ち崩し、または地の底の洞や海の凹地などを埋めてしまうことがないのだろうか。どうしてまた、人間の社会はこんなに固定しているのだろうか。どうして時々その内部に転覆というようなことが起らずに、長い間こうして無事に続いて行くのだろうか。これらの疑問に対しては、いつの時代にも必ず何等かの解答が出ている。そしてその解答は、その時代によって、いろいろと違っている。
昔の解答はごく単純なものであった。すなわち創造主がその創造物の保存に努めているのだ。 けれどもやがてこの思想が法則という概念に変った。もっともその法則というのは、最近科学のいうそれとは、だいぶその意味が違う。すなわちそのいわゆる自然法は、かくかくのことが生ずれば必然にこれこれのことが起るという、物と物とのただの関係、言い換えれば、因果の条件的法則を指すのではない。その諸現象の上に遥かに優れた、そしてそれらのものを指揮し命令して行く、何か特別なもののように思われていた。
十九世紀の諸科学は多くこの思想の下に支配されていた。自然科学もそうだった。社会科学もそうだった。そしてこうした法則とか、規律とか、または秩序とかいう思想が、大学にも、議会にも、官衙にも、商館にも、いたるところで、そしてまた日常生活の間にすらも浸みこんでしまった。
けれども最近科学の傾向はさらにその道を転じかけて来た。自然界に多少の調和があるのは、大きな激変の滅多に起らないのは、そして生物や無生物がよくその周囲の事情に適応しているのは、それらのものがこの周囲の事情そのものの産物であるからである。この周囲の事情そのものがそれらのものを造り出したのだ。したがってこの周囲はそれらのものを滅多に打ち毀すようなことをしない。建設力と破壊力との自由な働きそのものが、それらのものを創造し、かつそれらのものの調和を維持しているからである。されば、自然に調和がありとすれば、それはそれらの力の自由な働きの結果に外ならない。そしてまたこの結果は、その時の必要に応じて、それらの力によって常に変化され得べきものである。
調和や秩序は神の御心によるものでもない。また、ある一個の大きな力によって課せられた法則によるものでもない。調和や秩序はただ次の条件によって維持されて行く。すなわちある同一の点に働くあらゆる力の間に自由に生ずる均勢ということである。そして、これらの力の中のあるものが、何ものかによって障碍される時、その力はしばらく表面には現れずにしかしその間に蓄積されて、やがてはその障碍物を打ち破る。かくしていわゆる激変が起る。
また、調和や秩序は永遠無窮のものではない。必ず断えず改修され変化されて行くという条件の下でなければ維持されない。自然界にもまた人類界にも、一物たりとも一瞬時も変化しないで済ませるものはない。不断の進化、これが自然の生命である。そして自然界に多少の調和があり、よし変動があっても、それはごく稀れでしかも常に部分的であるのは、自然界の衝動と軋轢との結果、互いに相均勢して、互いにその間に密接なソリダリテを結ぶ。
もっともこの自然の調和というのは、勿論ある範囲内でのことで、従来の生理学者や哲学者のように誇張することはできない。星とか大陸とかいうものは、幾百千万年かかって成長して来たもので、その間にほとんど信ずることのできないほどの緩慢な変化を続けている。かく幾百千世紀かをそのリズムとする天体の調和と、それに較べれば無限の加速度で進行するものの調和との間には、当然区別して考えなければならないあるものがある。
動植物の種は、従来考えられていたよりも、よほどの急速度で変化する。地質の変化もそうだ。そしてこれらの変化に対しては、従来の博物学者が使ったような、一様なそして緩慢な進化などという言葉はもう許されなくなった。進化と激変とが常に入混って、そしてこの二つとも等しく自然の大調和のためにその力を寄与している。
九
クロポトキンの世界観、(十字削除)というのは、ざっとまずこんなものだ。誰にでもちょっとはうなずけるほどの、至極平凡な、また至極温健なものだ。ただそれが(八字削除)社会観になると、急に誰でもなかなかうなずけない、至極突飛な、また至極過激なもののように見えて来る。
しかしまあ、そんなことはどうでもいい。また、僕はかくながながとクロポトキンの世界観を説いて来たものの、実のところ、そんなこけ嚇しの世界観なぞはどうでもいいんだ。クロポトキン自身だって、この世界観があって、初めてその社会観ができたのじゃない。世界観の前に社会観があったのだ。そしてその社会観の前にもまた何ものかがあったんだ。それはクロポトキン自身だ。クロポトキン自身の強い感情だ。クロポトキンの世界観や社会観は、この強い感情にもとづいて、それをただ科学的に理屈づけたものだ。クロポトキンの社会哲学の本当の値打ちはそこにある。
僕はさきに、クロポトキンの科学的方法は人間の本能や感情や意志や憧憬やを蔑視する、また社会の階級的分離を無視する、いわゆる主知主理派の科学的方法ではなかった、と言った。クロポトキンの社会哲学には、クロポトキン自身の深い感情や憧憬が、その基調になっている。そしてその感情や憧憬の共鳴を同代人の生活や人類の歴史の中に求めた。
社会進化の行程は、いわゆる「科学的」社会主義の主張するがごとき、生産方法云々を土台とする必然的のものではない。その社会およびその中の各個人が持っているいろんな意志、いろんな憧憬、いろんな傾向の、自由な闘争を土台とする蓋然的のものだ。
だから、社会哲学はあるが社会学はないと言って、社会学の科学としての価値を否認する学者すらもある。しかしこの社会哲学の中に本当の社会学があるんだ。
しからば、クロポトキンがその社会哲学の基調としたクロポトキン自身の深い感情、深い憧憬というのは何か。それは自由発意と自由合意とである。個性の尊重である。自他の個性の尊重である。そして、その各個性の自由なる合意、自由なる団結である。自由と平等と友愛である。
クロポトキンがまだ十四、五の時であった。彼は近侍学校にはいった。
学校には古木の茂った美しい庭園があった。第五級の生徒はそこへはいって遊ぶことができなかった。第一級の生徒等がその中で寝ころんだりお饒舌りしている間に、新入生等はその周囲を駈足させられたり、また古参生等が六柱戯をやっている間にその球拾いをさせられたりしていた。クロポトキンは学校にはいった数日間、庭園のそうした事情を見て、そこへは行かずに自分の室に籠っていた。そして本を読んでいた。すると、人参のような髪に雀斑だらけの顔の一人の近侍がやって来て、すぐ庭園へ下りて駈足をするようにと命じた。
「いやです、僕は今本を読んでいるんじゃありませんか。」とクロポトキンは言った。
近侍は怒った。たださえ面白くない顔をいっそう不格好にして、今にもクロポトキンに飛びかかろうとした。クロポトキンも防禦の身構えをした。近侍はその帽子でクロポトキンの顔を打とうとした。クロポトキンはうまくそれをはねのけた。近侍は帽子を床板の上に投げつけた。
「拾え。」
「自分で拾うがいい。」
こんな不従順な振舞いは学校では未曾有のことであった。翌日も、またその次の数日も、クロポトキンは同じような命令を受けた。が彼は頑固に二階のその室に籠っていた。そのたびに、ますます迫害は嵩じて来た。普通の子供なら絶望してしまうほどひどくなった。それでも彼は平気で古参生等を茶化していた。
第一級の近侍等は下士官の資格を持っていて、下級生等に対する全権を与えられ、校内の厳重な紀律を保つことに任ぜられていた。そしてニコラス一世時代には、この近侍等の命令に反抗したものは、そのことが公けになれば、兵卒(農奴)等の子供を集めた学校に送られることにきまっていた。また、近侍等のちょっとした出来心に少しでも背こうものなら、彼等は重い樫の木の定規を持って、室に集まって、その不従順な生徒に手痛い制裁を加えるのであった。そしてクロポトキンは、この長い間の悪習に反抗して、それを打破する先頭に立ったのだ。
僕はこのただ一事にだけでもクロポトキンの個性の強さを見る。そして彼はこの個性の強さとともに、やはり子供の時から、その母から譲り受けて農奴どもの間に養われた深い友愛を持っていた。
クロポトキンは彼自身のこの強い感情の現れを、やがて西ヨーロッパへのその初旅の間に、国際労働者協会内の一大傾向の中に見た。そしてそこから無政府主義を教わった。このことは、クロポトキン自叙伝『一革命家の思い出』の中に、彼自らが詳細に語っている。
十
クロポトキンは、いつもこの一大傾向を説いている。彼は、彼が再び西ヨーロッパに旅して、スイスのジュラ同盟にはいり、そこで無政府主義の機関誌『謀叛人』を創めた時のことを語って言う。
「社会主義の新聞はとかく現存諸制度に対する泣言の年代記に過ぎなくなる傾向がある。鉱山や工場や田園の労働者の圧迫されていることが書かれている。同盟罷工の際の労働者の窮迫や苦痛が目に見えるように語られている。労働者がその雇主と闘争する孤立無援のありさまがくどくどと記されている。そして毎週毎週この孤立無援の努力が続けざまに書かれるということは、その読者をしてはなはだしく意気銷沈させる。そこでその新聞の記者等はそれを防ぐために、主として熱烈燃えるような文字を使って、それによってその読者に元気と信仰とを鼓吹しようとする。しかし私は、それと反対に、革命的新聞は何よりもまず、いたるところに新時代の到来と新社会生活の芽生えと旧制度に対するますます激しくなって来る叛逆とを告げる種々なる兆候の記録でなければならないと考えた。この兆候はよく注意して見て、その間の密接な連絡をつけて分類類集し、そして思想の復活が社会に起きた時に、なお躊躇している多くの人々に、その進歩的思想がいたるところに見出すべき、目に見えないそして往々無意識な論拠を与えるようにしなければならない。かくしてその読者をして全世界の人々の心臓の鼓動と共鳴せしめ、長い間の不正不義に対するその叛逆と共鳴せしめ、新しい生活様式を造り出すその企てに共鳴せしめる、というのが革命的新聞の主とする義務でなければならない。革命を成功させるものは希望であって絶望ではない。
歴史家は往々われわれに語って、これこれの哲学が人類の思想に、したがってまたその制度に、ある変化を生ぜしめたと言う。しかしこれは本当の歴史ではない。偉大なる社会哲学者等は、ただ来たるべき変化の兆候を捉えて、その間の内的関係を察し、そして帰納と演繹とによって将来を予言したに過ぎないのだ。社会学者はまた若干の原則から出発し、それをあたかも若干の定理から幾何学上の結論を引出すように、その必然の結果にまで推論して、社会組織の設計をつくる。しかしこれも本当の社会学ではない。精確な社会的先見というものは、新生活の幾千の兆候に目をとめて、その一時的事実と有機的の本質的事実とを区分し、そしてこの基礎の上に概括論を建てなければできるものでない。
私は明晰な分りやすい言葉を使って、読者をしてこの思索方法に親しませ、そのもっとも遠慮がちなものにもなお社会が何処へ進みつつあるかを自ら判断させ、思想家等が誤った結論に達した時には自らそれを矯正させるよう馴れさせようと努めた。」
かくしてクロポトキンが一八七九年から一八八二年までの間に、『謀叛人』のために書いた幾多の論文は、一八八五年すなわちフランスでの入獄中に、友人エリゼ・ルクリュによって『謀叛人の言葉』という題の下に出版された。もっともその中の大部分は、その以前もしくはその以後に、一つ一つ小冊子となって出版されている。
クロポトキンはその小冊子について言う。「私は、実際白状するが、自分の思想を述べるのにどれほどのページを使ってもいい人達、すなわちタレイランの有名な『私は短く書くひまがなかった』という言訳けを許される人達が、折々うらやましかった。数ヵ月間の研究の結果を --たとえば法律の起原についての-- 一ペンスの小冊子に縮めて書くには、それを短くするのに非常な時間がかかった。しかし私達は労働者のために書くのだ。そしてこの労働者にとっては、一冊の小冊子に二ペンス払うのでも、高すぎるくらいなのだ。その結果私達の一ペンス半ペンスの小冊子は数万部も売れて、なお各国の国語に翻訳された。」
なお当時のクロポトキンは、ルクリュの『大地理学』の編纂を助けるために、『謀叛人』の発行所のジュネーブから少し離れたクラランに住んでいた。「そこで私は、妻の助力の下に私が『謀叛人』のために書いた一番いいものを書き上げた。妻はいつも私とあらゆる出来事や問題について議論をし、かつ私の文章の厳格な文学的批評をしてくれた。その中の『青年に訴う』のごときはあらゆる国語に翻訳されて数十万部も拡がった。実際私はその後私の書いたほとんどすべてのものの基礎をそこで築きあげたのであった。」
この小冊子の中でも、ことに『法律と強権』は、その後に出た『国家論』と『裁判論』(詳しく言えば『裁判と称する復讐制度』)とともに、非国家論の三部作として有名なものだ。
そしてクロポトキンはこの『謀叛人の言葉』の出版された翌年、すなわち一八八六年に出獄するとすぐ、『監獄論』(詳しく言えば『ロシアとフランスの監獄について』)を書いた。クロポトキンはロシアの旧式監獄とフランスの新式監獄とをいずれも親しく囚人として経験した。『監獄論』はこの経験の結論である。
十一
やがて『謀叛人』は、その非軍国主義伝道のために発行を禁止され、『謀叛』の名の下にパリでその発行を続けることとなった。
クロポトキンは出獄後イギリスに行って、二、三の同志と一緒に『自由』という月間新聞を創めた。そして同時に入獄のために中止した無政府主義論の著述に取りかかった。
『謀叛人の言葉』は主として無政府主義の批評的方面を扱ったものであった。で、こんどは、無政府主義そのものの説明とともに、無政府主義の建設的方面を予想し得る限り画き出すことに努めた。
その前者は、一八九一年の『無政府主義の道徳』、一八九五年の『無政府主義、その基礎と主張』、一八九五年の『無政府主義、その哲学と理想』等となって現れた。
そしてその後者は、初め『謀叛』に連載され、後さらに詳述されて、一九○六年の『パンの略取』となって現れた。
「これらの研究は私をして今日の文明諸国の経済的生活についてのある点をさらに十分に研究させた。従来多くの社会主義者等はこう言っていた。今日の文明社会では、実際われわれはすべての人に十分な幸福を保証するに必要な以上に生産している。ただいけないのは分配だ。で、もし社会革命が起れば、社会は今資本家の手にはいってしまう『剰余価値』や利潤を自分の手に収めることとなるので、各人はただその工場に帰りさえすればいいのだと。しかるに私はそれと反対にこう考えた。今日の私有財産制度の下では、生産そのものが間違った方向に進んで、十分な生活のためにもっとも必要なものの生産を忽ろにしまたは往々妨げている。そのいかなる必要品もすべての人の幸福を保証するに要する以上には生産されていない。よく話に出る生産超過というのは、民衆が今日その相応な生存のために必要だと見做されているものすらも買えないほどに貧乏だ、ということを意味するに過ぎない。あらゆる文明国では、その農工業のいずれの生産もすべての人の充足を保証するようにさらに大いに増さなければならず、また容易に増すことができるのだと。そして、この研究は、近代農業の可能性と、何人にも手工労働と頭脳労働とを同時に行わせるようにする教育の可能性とを考えさせるに至った。私はこの考えを雑誌『十九世紀』に連載した論文の中に詳述し、今それは『田園、工場、製造所』という題で単行本になっている。」
要するにこの『田園、工場、製造所』(一八九八年)は、現代社会の農工業におけるある傾向を説いて、その傾向の助長の上に無政府主義の経済的可能性を論じたものである。
「なお、もう一つの大問題が私の注意を集中させた。ダーウィンの『生存競争』という定式が、その多くの祖述者によって、しかもハクスレーのごときその中のもっとも聡明な人によってまでも、どんな結論に導かれているかは、誰でも知っていることである。文明社会におけるどんな醜悪事でも、白人といわゆる劣等人種とのまたは『強者』と『弱者』との関係のどんな醜悪事でもこの定式の中にその口実を見出さないものはない。
すでに私はクレールヴォー(監獄)滞在中に、動物界における『生存競争』の定式そのものとその人類社会への適用とを全部修正する必要を考えた。この方面についての二、三の社会主義者がやった企てはどうも不十分だと思われた。その時に私は、ロシアの動物学者ケスレル教授の一講演の中に、この生存競争の法則についての本当の説明を見出した。ケスレルはこの講演の中に言う。『相互扶助は相互闘争と等しく自然の一法則である。そして一種の進歩的進化のためには、前者の方が後者よりも遥かに重大である。』この数言--それは不幸にもわずかに二、三の実例で証明されただけで、さきに話したことのある動物学者シェフェルソフがそれに二、三の例証を加えたに過ぎないものであった--が私に取っては全問題の鍵となった。そして一八八八年にハクスレーがその凶暴な論文『一宣言、生存競争論』を公けにした時、私は動物界および人類社会における生存競争についてのその見方に対する駁論と、数年間貯えていた材料とを、人の読めるような形にまとめようと決心した。私はそのことを私の友人等に話した。しかし『弱者は禍なるかな』という喊声の意味に『生存競争』を解釈することが、科学によって啓示された自然の命令のようになって、それがほとんど宗教のように深くこの国に根ざしていた。ただ二人だけが自然事実のこの誤認に対する私の反抗に賛成してくれた。『十九世紀』の主幹ジェームズ・ノールズ氏はその優れた烱眼からすぐに問題の要点を捉えて、本当の若い元気で私にそれを始めるよう勧めてくれた。もう一人は、ダーウィンがその自叙伝の中に彼のかつて会ったもっとも聡明な人の一人だと書いているH・W・ベーテスであった。地学協会の幹事をしていた。それで私も彼を知っていた。私がその話をすると彼は喜んで言った。『そうです、本当にしっかりとお書きなさい。それが本当のダーウィニズムです。“彼等”がダーウィンの思想から造りあげたことは考えるだけでも恥ずかしいことです。お書きなさい。それが発表される時には、あなたが公表してもいいようなふうに手紙を書いて上げましょう。』私にはこれほどいい奨励はなかった。で、すぐに仕事を始めて、『動物界の相互扶助』、『蒙昧人の相互扶助』、『野蛮人の相互扶助』、『中世都市の相互扶助』、『現代の相互扶助』の題で『十九世紀』に発表した。」
この諸論文は、一九○二年に、『相互扶助論』の名の下に一まとめになって出版された。『相互扶助論』はクロポトキンのいろんな著述の中でも恐らくは彼がもっとも骨を折った、そしてその無政府主義論の科学的根本基礎をつくったものである。
クロポトキンはこの研究によって、その社会哲学の基調とする自由発意と自由合意とが、動物の相互扶助の中に、また人類史の民衆生活の中に、常にもっとも有力な進化の要素となっていることを見た。無政府主義が人類史を一貫する一大傾向であることを見た。
「なおこの研究の間に、野蛮時代や中世自由都市の諸制度と親しむための研究が、さらに重要な一問題、すなわち国家がヨーロッパに最近体現されて以来三世紀間歴史の上に勤めた役目の上に私を導いて行った。そしてまた、文明諸国の間の相互扶助的諸制度の研究は、人間の正義感および道徳感の進化論的基礎の研究に私を導いた。」
この国家の研究は、さきに言った『国家論』(詳しく言えば『国家、その歴史的役目』)および『裁判論』の中に、また人間の正義感および道徳感の研究は、やはりさきに言った『無政府主義の道徳』の中に発表された。(七行削除)
十二
最後に僕は、クロポトキンが国際労働者協会内の一大傾向から学んだという、その傾向の実際的および理論的方面について、クロポトキン自身が『一革命家の思い出』の中に語るところを取次ごう。
新しい社会が文明諸国に萌生えつつある。それが旧い社会に代らなければならない。新しい社会とは平等人の社会だ。その平等人は自分の腕や頭を、彼等をいい加減に選んで雇う人間どもに、売らなければならぬようなことはないだろう。すべての人の最大限の幸福を得るために、あらゆる努力を協力させるよう組立てられた組織の中で、自分の知識や能力を生産に応用することができるだろう。そして各人の個人的発意のための広い自由な余地が残されるだろう。
この社会は、各々の連合の要求するあらゆる目的のために結合した、多くの団体に組織されるだろう。あらゆる種類の--農業上、工業上、知力上、芸術上の、--生産のための連合。住宅や、ガスや、食料や、衛生品などを供給する消費のための自治町村。この自治町村の連合。自治町村と同職団体との連合。および最後に、ある一定の土地に限られていない経済上、知力上、芸術上、道徳上の欲望を満足するために協力する人々より成る、全国内もしくは数カ国内にわたる大団体。そしてこれらすべての団体は、今日ヨーロッパ諸国の鉄道会社や逓信省が、あるいは単なる利己的目的に駆られ、あるいは往々仇敵同士の違った国家に属していながら、中央鉄道政府とか中央逓信政府とかいうものなしに協力しているよう、または気象学者等やアルペン倶楽部やイギリスの水難救済会や小学校教師や自転車乗りなどが、科学上の目的やあるいは単に娯楽上の目的のためにあらゆる仕事を協力しているよう、互いに自由合意の方法で直接に協力するだろう。新しい生産や発明や組織の発達はまったく自由であるだろう。個人的発意は奨励されるだろう。統一や中央集権の傾向は排斥されるだろう。
それにこの新社会は、変えることのできない一定の様式に結晶することなく、絶えずその光景を変えて行くだろう。生きた、進化して行く、有機体であるだろう。統治団の必要は感じられないだろう。自由合意と連合とは、統治団が今日自分の仕事と見做しているいっさいの仕事を、代ってすることができるだろう。そして各団体間の衝突の原因が著しくその数を減じて、なお生じ得べき衝突は仲裁裁判に附することができるだろう。
私達の中の誰も、私達が求めているこの変化の大きさや深さを小さくは見なかった。土地や工場や鉱山や住宅などの私有制度が工業の進歩を保証する手段として必要であり、また賃金制度が人間を働かせる手段として必要であるとする今日の学説が、所有権や生産を社会化するというようなもっと高い理想に、すぐに譲歩する気づかいはない、ということは私達も分っていた。私有財産についての今日の思想が変る前に、くどくどしい伝道と、長い間の引続いての闘争と、今日支配する財産制度に対する個人的および集合的の叛逆と、自己犠牲と、社会改造の部分的企図と、部分的革命とを経なければならない、ということも私達は知っていた。また今日われわれがみなそれに養われている強権の必要についての思想は、文明人がみなすぐに棄ててしまうこともあるまいし、またそんなことはできもしない、ということは私達もよく分っていた。本当は自分等の社会的感情や習慣から出たものをその支配者の法律から出たものと思い違えていた、ということが人間に分るまでには、長い年月の伝道や、強権に対する幾度もの叛逆的行為や、今日歴史から引出して来るいろんな教義の全部の修正を経なければならない。私達はそんなことはみなよく知っていた。が、私達はまた、この二つの方面の改造を説きつつ、自分が人類の進歩の潮流にのっているのだ、ということも知っていたのであった。
私は労働階級の人達やまたそれに同情する知識階級の人達と親しく交わって、その人達が自分の自由をその一身の幸福よりも重く見ているということを、すぐに知った。五十年以前には労働者はその物質的幸福を与えられるという約束と交換に、あらゆる種類の支配者に、専制的暴君にですらも、その一身の自由を売った。しかし、今はもうそんなことはない。選挙された支配者に対する盲目的信仰というようなことも、ラテン諸国の労働者の間には、その支配者が労働運動のもっともいい首領等の中から選挙される時にすらも、だんだんに消滅しつつあった。「われわれが何を要求しているかは、まずわれわれ自身が第一に知らなければならない。そうすればわれわれはわれわれ自身でそれをもっともよく成就することができる。」というのが、彼等の間に広く拡がっている--普通に人の思っているよりも遥かに広く--思想であった。国際労働者協会の規則の中の、「労働者の解放は労働者自らが成就しなければならない」という言葉は、一般に共鳴されてその心の奥深くに根を張っていた。
一八七一年三月二十五日に選出されたパリ・コミューン政府委員ほどに、あらゆる進歩した政党を明白に代表した政府は、いまだかつてなかった。ブランキー派も、ジャコバン派も、国際労働者協会派も、みなそこにうまく権衡して代表されていた。しかるに労働者自身はまだ、その代表者等に強要するほどの明白な社会改革の思想を持っていなかったので、コミューン政府はこの方向には何にもしなかった。されば社会主義の成功そのもののためにも、個人の自主、自恃、自由発意の思想、すなわち無政府主義の思想が、所有権や生産を社会化する思想と相並んで説かれざるを得なくなった。
各個人の思想や行為の表現をまったく自由にすれば、主義の多少の誇張が生ずる、ということは私達も確実に予想していた。しかし私達はまた思想や行為の腹蔵のない正直な批評に支持される社会生活そのものがいろんな思想を脱殻させて、避けがたい誇張を免れしめるもっとも有力な方法になると信じていた。そして経験はその正しいことを証拠立てている。実際私達は、自由はその一時的弊害のもっとも賢明な治療法だ、という古い言葉に従って行動していた。
人間には、まだその本当の値打ちは世間に分っていないが、、無理強いに維持されて来たのではない、そしてその無理強いには屈しない社会的習慣の神髄がある。過去からの遺伝がある。人類のいっさいの進歩はそれにもとづいている。人類が肉体的にも精神的にも堕落し始めない限り、この習慣と遺伝とはどれほど非難されまたどれほど一時的の反抗に出遭っても破滅されることはないだろう。
それと同時にまた、これほどの変化は一人の天才の臆測から生じ得るものでもなく、一人の人の発見でもあり得ず、民衆の建設的行為から出なければならない、ということも私達は考えていた。ちょうど中世初期にできた訴訟法や、財産共産制度や、ギルドや、自由都市や、国際法の基礎などが、民衆によって創り出されたように。
多くの先輩は、あるいは強権の原則にもとづく、あるいはごく稀れに無政府の原則にもとづく、理想の社会を画こうとした。ロバート・オウエンとフーリエとは、ローマ帝国やローマ教会に型どったピラミッド式社会の理想に反して、有機的に発達する自由社会の理想を発表した。プルードンはこの事業を続けた。そしてバクーニンは、その歴史哲学についての広い明晰な理解を現社会制度の批評に適用して、いわゆる「破壊しつつ建設した。」しかしこれはみな要するに準備的事業に過ぎなかった。
しかるに国際労働者協会はこの実際社会学の諸問題を労働者自身に訴えて解決する新方法を始めた。協会に加わっている知識階級の人々は、労働者に世界各国の事情を知らせ、労働者の獲得した結果を分析し、そして後には労働者がその結論をつくるのを助けるだけの仕事をした。私達は「社会はこうでなければならない」というような私達の理論的見解から理想社会を画き出そうとはしなかった。私達はただ労働者に勧告して現在社会の諸弊害の原因を探究し、その討論会や大会でわれわれが今生活している社会よりももっといい社会組織の実際的状況を考察するよう、促しただけだ。国際大会で起った問題はあらゆる労働団体の研究題目として選ばれた。すなわちその年中に、その問題は全ヨーロッパに、各支部の小集会で、各自の職業やその地方の十分な知識をもって討論された。そしてこの各支部の結論が各連合の次の大会に提出された。しこうして最後に、それがさらに緻密なものとなって、次の国際大会の討議に附せられた。
私達の憧れている新社会の構造というのは、かくして理論においても実際においても、上からではなく下から造り出されたのだ。
私自身は、こうした都合のいい事情の下に置かれてあったので、この無政府主義が自由社会の単なる概念や単なる行動方法よりもより以上のものを含んでいる、ということがだんだん分るようになった。無政府主義は、人類社会についての諸科学に用いられて来た形而上的もしくは弁証法的方法とはまったく違った方法で進まなければならない、自然哲学および社会哲学の一部分である。すなわちそれは諸自然科学と同じ方法で取扱われなければならない。しかしそれは、ハーバート・スペンサーがやった単なる類推法の瓢箪鯰のような基礎の上にではなく、帰納法を人類社会の諸制度の上に適用した、健全な基礎の上にでなければならない。そして私はこの方面に私のできるだけの最善を尽した。