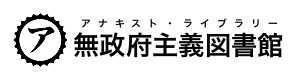マレイ・ブクチン
社会的アナキズムかライフスタイル=アナキズムか
掛け橋不可能な亀裂
ここ二世紀で、アナキズム--非常に普遍的な反権威主義的考え方の一群--は二つの根本的に相反する傾向間に緊張をはらみながら発展してきた。二つの傾向とは、個々人の「自律」に対する私事本位主義的コミットメントと社会的「自由」に対する集産主義的コミットメントである。これらの傾向がリバータリアン思想史の中で調和したことなど一度もなかった。事実、前世紀の大部分では、これらの傾向はアナキズムの中に単に共存していただけだったのだ。その共存の仕方も、その場に造りだされるべき新たな社会を明確に述べたマキシマリスト的信条表明ではなく、国家に対する反対というミニマリスト的信条表明に過ぎなかったのである。
個別に見ればさまざまな違いが明確にありはしても、言うまでもなく、アナキズム諸派は特定形態の社会組織を擁護していなかった。しかし、基本的にアナキズム全体として提起していたのは、アイザイア=バーリンが「ネガティブ=フリーダム」と呼んだ、形式的な「~からの自由」であって、本質的な「~への自由」ではなかったのだ。事実、アナキズムはその多元論、イデオロギー上の寛容性、創造性、さらにはある近代ポストモダニスト信奉者が論じたように、論理の支離滅裂性さえもその現れだとして、ネガティブ=フリーダムに対するコミットメントを賛美していたものであった。
アナキズムがこの緊張を解決できず、個人の集産集団に対する関係をはっきりと述べることができず、無国家無強権社会を可能ならしめる歴史的背景を明言できなかったことが、アナキスト思想の中で今日まで解決されていない諸問題を生み出したのだ。ピエール=ヨセフ=プルードンは、当時の多くのアナキストよりも、リバータリアン社会の充分な具体像を描き出そうとしていた。基本的に小規模生産者・消費者協同組合・共同体間の契約に基づいたプルードンのヴィジョンは彼の生まれた地方職人世界の芳香を漂わせるものであった。しかし、「a patroniste」を混合した彼の試みは、契約的社会構造を持った、リバティという族長主義的概念となることが多く、深みを欠いていた。プルードンの職人・協同組合・共同体は、職人が持つ個人的自律への偏向を映し出しており、能力と欲望といった共産主義の言葉よりも、平等や正義といったブルジョア契約用語にそれぞれが関連しており、集産集団に対するいかなる道徳的責任もその成員の良心程度にしか定義していなかったのだ。
確かに、プルードンの有名な宣言である、『私を支配しようと手を差し出す人は誰であれ強奪者か暴君だ。宣言しよう、奴は敵である。』は、個人主義的なネガティブ=フリーダムに強く偏向しており、抑圧的な社会制度に対するプルードンの反対と彼が意図していたアナキスト社会のヴィジョンとを覆い隠してしまっている。彼の言明は、ウィリアム=ゴドウィンの明快な個人主義宣言、『私が心の底から服従できる唯一の力とは、私自身の理解による意思決定、私自身の良心の命令しかない。』、と簡単にブレンドできる。ゴドウィンの自分自身の理解と良心という「権威」に対する宣言は、プルードンが「自分の」リバティを制限する恐れのある「手」を非難したように、アナキズムに巨大な個人主義的推進力を与えたのだった。
このような宣言は人をつき動かす力を持っているのであろう。北米合州国において、これらの宣言は、その「自由な」事業の是認とともに、いわゆるリバータリアン(もっと正確に言えば、有産主義者)右翼から絶大な賛美を勝ち取ることとなり、アナキズムがそれ自体で全く一貫性のないものだと明らかにされたのである。逆に、ミハイル=バクーニンとピョートル=クロポトキンは基本的に集産主義的見解を持っていた。クロポトキンの場合、明らかにそれは共産主義のものであった。バクーニンは個人よりも社会を強く優先していた。彼によれば、社会は、『全ての人間個々人より先にあり、同時にすべての人間よりも生き長らえる。ちょうど自然それ自体のようなものである。自然のように永遠、というよりもむしろ、自然のようにこの地球上に生まれていたのであり、地球と同じぐらい長く生き残りつづけるであろう。したがって、社会に対する革命的反逆は、人間が自然に反逆するのと同様、不可能なものとなろう。人間社会はこの地球上における自然の最後の偉大なる出現物、もしくは創造物以外の何物でもないのだ。社会に対して反抗したいという個人は、(中略)実在の範囲外に自身の身を置くことになろう。』[1]
バクーニンは幾度となく、議論上の重大な焦点を当てながら、自由主義とアナキズムにおける個人主義的傾向に対する反対を表明していた。バクーニンは比較的穏やかな調子で書いている。社会は『個人に借りをしている』のだが、個人を形成するのは社会なのだ。
『我々の現存社会にいる最も酷い状態にある個人でさえ、数えきれないほどの世代からなる累積的な社会努力なしには存在も発達もできなかったのだ。したがって、個人・その自由・存在理由は、社会の産物なのであり、その逆などありえはしない。社会はそれを形成している個々人の産物ではない。より高次な社会になればなるほど、個人がもっと十全に発達し、その自由はより大きくなる。人が社会の産物であればあるほど、人は社会から多くのことを受け取り、社会により大きな借りをしているのである。』[2]
クロポトキンは、驚くべき一貫性を持って、この集産主義的強調点を堅持した。多分彼の著作の中で最も広く読まれていたであろう、「エンサイクロペディア=ブリタニカ」の「アナキズム」という項目に載せたエッセイでは、アナキズムの経済概念を『全ての社会主義』の中でも『左翼』に位置すると明確に述べ、『中心から円周へという現在のヒエラルキーに「とってかわる」、地域と個人の独創力、単純なものから複雑なものまでの自由な連合という精神』において、私有財産と国家の徹底的な排除を要求したのである。事実、倫理学に対するクロポトキンの著作は、社会に対して個人を対立させ、実際に個人やエゴに対して社会を低く見積もるような自由主義的試みを一貫して批判していたのだった。彼は社会主義の伝統にはっきりと身を置いたのである。彼の無政府共産主義は、テクノロジーの進歩と生産性の増大に基づき、1890年代における圧倒的なリバータリアン=イデオロギーとなり、平等に基づいた分配という集産主義概念を一貫して推進していた。『大部分の社会主義者と同様』、アナキストは、『地域の生産者と消費者集団からなる各郡区や各コミューン』の連合に基づいた社会を最終的には生み出すことになる、『革命と呼ばれる加速度的な進化の期間』が必要だとクロポトキンは強調し、認識していた。[3]
19世紀後半と20世紀前半にアナルコサンジカリズムと無政府共産主義が出現すると、個人主義傾向と集産主義傾向との緊張を解消する必要性が本質的な論争の的となった(原注)。無政府個人主義は、大規模な社会主義的労働者運動によって全く問題外だとされた。その運動に関わっている大部分のアナキストは自身を左翼だと考えていた。1930年代とスペイン革命において絶頂に達した大規模な労働者階級運動の勃興に特徴づけられる嵐のような社会動乱期において、アナルコサンジカリストと無政府共産主義者は、マルクス主義者と同様、無政府個人主義を風変わりなプチブルであると考えていた。彼らは無政府個人主義をアナキズムではなく自由主義に断然多くの根を持つ中産階級の道楽だとして非常に直接的に攻撃していたのだった。
(原注:実際、アナルコサンジカリズムは、英国国教会が企図した「グランド=ホリデイ」つまり、ゼネストの概念にまで辿ることができる。スペインのアナキストの中では、1880年代までに既に受け入れられた実践となっており、これは、フランスにおける教義としてアナルコサンジカリズムが詳細に述べられるようになる十年ほど前のことである。)
その時代は、個人主義者が、その「唯一性」という名の下に、人を動かさずにおかない一貫したプログラムを持ったエネルギッシュな革命組織の必要性を無視することを許しはしなかったのだ。マックス=シュチルナーの自我とその「唯一性」という形而上学への耽溺とはまったく別個に、アナキスト活動家は、理論的で、多方面を取り扱い、実行計画を示しているような基本的書物を必要としていた。そうした書物の中には、クロポトキンの「パンの略取」(ロンドン、1913)、ディエゴ=アバド=サンティジャンの 「革命の経済機構」(バルセロナ、1936)、 G=P=マキシーモフの「バクーニンの政治哲学」(英語版は1953年、マキシーモフの没後3年で出版された。元々の編纂日は英訳本には載っていないが、多分その数年前かあるいは数十年前だと思われる。)がある。私の知る限り、シュチルナー主義者の「エゴイストの組合」がこれまでに目立って出現したことはなかった--そうした組合は確立可能で、その自我中心主義的参加者の「唯一性」を存続させることができたと仮定すればの話しだが。
個人主義アナキズムと反動
確かに、イデオロギーを持った個人主義はこの徹底的な社会動乱期に消滅しはしなかった。個人主義アナキズムの相当大きな貯蔵庫が、特に英国系アメリカ世界で、シュチルナー自身の思想だけでなく、ジョン=ロックとジョン=スチュワート=ミルの思想によっても成長していた。リバータリアンの見解に対するコミットメントは様々なレベルではあったものの、自家製個人主義者達がアナキストの地平を埋め尽くしていた。事実、無政府個人主義はまさしく「個人」を引きつけていたのだった。自由競争の風変わりなバージョンに固執していた合州国のベンジャミン=タッカーから、自分の支離滅裂なシュチルナー主義的信条を大切にしていたスペインのフェデリカ=モンツェニーまでいた。その無政府共産主義イデオロギーをはっきりと公言していたにもかかわらず、エマ=ゴールドマンのようなニーチェ主義者は個人主義の精神を深く留めていた。
いかなる無政府個人主義者であれ、労働者階級の勃興に影響を与えることはなかった。彼らは自分達の反抗をユニークで個人的な形で表現していた。特に、激しい論調の小冊子、乱暴な行動、ニューヨーク・パリ・ロンドンの退廃的な文化的ゲットーにおける常識では考えられないようなライフスタイルという形で表現していたのであった。一信条として、個人主義アナキズムは大部分が依然としてボヘミアン的ライフスタイルをとっており、性の自由(「フリーラブ」)の要求と、芸術・行動・服装における革新への専心に最も顕著に現れていた。
個人主義アナキストがリバータリアン活動の前面に出ていたのは、重大な社会的抑圧と死にかけた社会的無活動の時期であった。そしてその活動は主としてテロリズムとして現れたのだった。フランス、スペイン、合州国において、個人主義的アナキストはテロ行為を犯し、このことがアナキズムは暴力的で不穏な陰謀だという評判を与えたのだった。テロリストになった人々は、多くの場合、リバータリアン社会主義者や共産主義者ではなく、自暴自棄になった男女だった。彼等は武器と爆弾を手に、おそらくは「行為による宣伝」の名の下に、当時の不公正と俗物根性に抵抗したのだった。しかし、ほとんどの場合、個人主義アナキズムの表現は文化的に反抗した行動だった。これは、アナキストが実行可能な民衆活動とのつながりを失うほどはっきりとアナキズムの中で突出するようになっていった。
欧米アナキズムにおいて無視できないほどの現象、つまり個人主義アナキズムの広がり、が出現しているのは、今日の反動的社会文脈によるところが大きい。社会主義の中で尊敬できる形態さえもが、何らかの形でラジカルだと解釈可能な諸原理から大あわてで退却している時代に、ライフスタイルの問題が再びアナキズムの社会行動と革命政治を補完しているのである。個人主義-自由主義の伝統がある合州国と英国の1990年代は自己流のアナキストの波に洗われている。その色鮮やかでラジカルなレトリックは置いておくとしても、それらが近頃の無政府個人主義を培養しているのである。私はそれらを今後「ライフスタイル=アナキズム」と呼ぶことにする。エゴとその唯一性への没頭、そして、その多様な抵抗の概念が、リバータリアンの伝統にある社会主義的特長を着々と腐食しつつあるのである。マルクス主義やその他の社会主義と同様、アナキズムはそれが反対していると明言しているブルジョア環境に深く影響を受ける可能性を持っている。それは、ヤッピー世代に育まれた「内面」と自己陶酔とが、ラジカルだと公言している多くの人々にその痕跡を残している結果なのである。その場限りの冒険主義・個人の大胆で華麗な演出・反理性主義のポストモダニズムと奇妙にもよく似た、理論に対する嫌悪・理論的一貫性の無さの賛美(多元論)・想像力、願望、恍惚に対する本質的に反政治的で反組織的なコミットメント・日常生活の極度に自己指向的な魔術化。これらは社会的反動が過去二十年にわたり欧米アナキズムを扱って来た代価なのだ(原注)。
(原注:その欠点にもかかわらず、熱気にあふれた1960年代初頭のアナキズム的カウンターカルチャーは、非常に政治的であることが多く、願望と恍惚のような表現を明らかな社会用語の中に投げ込み、後のウッドストック世代の持つ個人主義的傾向をあざ笑っていることが多かった。市民権運動と平和運動の誕生から、「享楽」の純粋な自己満足的形態に強調点を置いているウッドストックとオルタモントまでの「若者文化」(元々そう呼ばれていた)の変遷は、ボブ=ディランの「風に吹かれて」から「ローランドの悲しい目の乙女」までの退化に反映されている。(訳注:「風に吹かれて」は、ディランのセカンド=アルバムの最初の曲であり、「ローランドの悲しい目の乙女」は7作目の最後の曲である。この間に、ディランの唄は、社会問題を唄うプロテスト=フォークから大衆受けするフォーク=ロックへと堕落した。))
個人の心理発達テクニック概論の編纂者であるカティンカ=マトソンは、1970年代には『私たちが世界の中での自分自身を知覚するやり方に大きな変化が』起こっていた、と書いている。『1960年代には』、彼女は続けている、『政治的活動主義、ヴェトナム、エコロジー、ビ-=イン、共同体、ドラッグなどへの没頭が見られた。今日、私達は内側に目を向けている。私達は、自分自身の定義、自分自身の改善、自分自身の業績、自分自身の啓発を探し求めている。』[4] 。マトソンの不健全な動物寓話小集は、「サイコロジー=トゥデイ」誌に編纂され、鍼灸から「易経」まで、エストからゾーン=セラピーまで、全てのテクニックを網羅している。今考えると、彼女はライフスタイル=アナキズムを、内面を覗き込む催眠剤概論にうまく含めることができたと思われる。その催眠剤の大半は社会的自由ではなく私的自律という考え方を育てているのだ。心理療法はその亜種全てが、情動的に自己充足した静かな心理条件の中で、自律を探し求める内面に向けられた「自己」を養っているのであって、自由によって示される社会に参画した自己ではない。心理療法におけるものとしてのライフスタイル=アナキズムでは、エゴは集団と、自己は社会と、個人は共同体と対峙させられているのである。
エゴは--もっと正確に言えば、様々なライフタイルにおけるエゴの具体化は--1960年以後の多くのアナキストにとって「強迫観念」となってしまった。そうしたアナキスト達は、既存の社会秩序に対して組織立ち、集産主義的で、計画性のある抵抗の必要性との接触を失ってしまっている。脊椎のない「抗議」(既存システムの変化を引き起こそうとせずに単に私的スリルのためだけになされる抗議)、方向性のない脱出、自己主張、非常に個人的な日常生活の「再植民地化」は、退屈し切ったベビーブーマーとジェネレーションXの持つ心理療法的、ニューエイジ的、自己指向的なライフスタイルと歩調を合わせている。今日、合州国におけるアナキズムを通過し、次第に欧州で増えて来ていることは、責任ある社会的コミットメントを侮蔑した内省的な私事本位主義、「コレクティブ」とか「親和グループ」のように名前をいろいろと変えているエンカウンターグループ、構造・組織・公的な参加を傲慢にもあざけっている心理状態、風変わりな青年どもの遊び場以外の何物でもないのだ。
意識していようといまいと、多くのライフスタイル=アナキストは、社会革命ではなく、ミシェル=フーコーの「私的暴動」アプローチを明瞭に表現している。その前提は、民衆集会・評議会・同盟における抑圧された側の「制度化された」権能の要求ではなく、権力自体の曖昧で表面的な批判にある。この傾向は社会革命の実現可能性を、「不可能だ」とか「空想的だ」として否定している限りにおいて、本質的な意味で社会主義的もしくは共産主義的アナキズムの価値を下げているのだ。実際、フーコーは、『抵抗は権力に対して外側に位するものではない(中略)権力に対して偉大な拒絶の場が一つ(不変的にとも読める)--反抗の魂、すべての反乱の中心、革命家の純粋な掟といったもの--あるわけではない。』(邦訳書、123ページ)という観点を促している。フーコーの誇張と言い逃れは置いておくとしても、反抗が完全に多種多様な形になるほどに、非常に大きな、いたるところにある権力の抱擁の中に皆がとらわれているため、我々は『孤独』と『奔放』の間を役に立たないまま漂っているというわけだ[5] 。あちこちをさまよっているフーコーの考えは、抵抗はいつでも現前にあるゲリラ戦に必ずなってしまい、絶対に負けてしまう、という考えにまでおちぶれている。
ライフスタイル=アナキズムは個人主義アナキズムと同様、理論を軽蔑している。一般に余りにも曖昧で、直感的で、直接分析を行うには反理性的でさえある、神秘的で原始的素性を持っているのだ。これらは、既存の社会不安からの逃げ場として自己の神聖化に向かう一般的傾向の適切な症状なのであって、その原因ではない。だが、多くの私事本位主義的アナキズムは、それ自体を批判的検証に役立つほどの泥まみれの理論的前提を未だに持っているのである。
そのイデオロギー的系図は基本的に自由主義であり、それは十全で自律した個人という神話に根差している。その自己主権の要求は、公理となっている「自然の権利」、「内在価値」によって、そして、もっと洗練されたレベルでは、全ての知覚可能な現実を生み出している直感的なカント主義的超越的エゴによって正当だとされているのである。これらの伝統的観点は、マックス=シュチルナーの「我」、つまりエゴ、に表面化している。それは、あたかも世界は自己指向的個人の選択如何によるかのような、現実全てをそれ自体へと吸収する傾向を実存主義と共有しているのである。(原注)
(原注:このエゴとその財産という哲学的系譜は、フィヒテからカントまで辿ることが出来る。シュチルナーのエゴの観点は、カント主義、特にフィヒテ主義のエゴの粗雑な突然変異でしかなかった。それは洞察よりも空威張りで特徴づけられていた。)
ライフスタイル=アナキズムに関する最近の著作は一般に、エゴ中心主義的強調点を残してはいるものの、全てが「我」を指し示したシュチルナーの主権者を回避し、実存主義・リサイクルされたシチュアシオニズム・仏教・道教・反理性主義・原始人主義、もしくは非常に普遍的に、様々な変異前のそれら全てに向かう傾向がある。これから見ていくように、その共通性には人類が堕落する前の、原始的で、拡散していることも多く、短気で幼児的でさえあるエゴ、歴史・文明・洗練されたテクノロジーよりも、多分言語それ自体よりも、表向き優先されているエゴへの回帰の臭いがする。そして、これらは前世紀を支配していた一つの反動的政治イデオロギー以上に成長しているのだ。
自律か、自由か?
全てのカテゴリーを所与の社会秩序の産物と見なす社会的構造主義の罠に陥ることなく、「自由な個人」の定義を求めねばならない。個性はどのようにして存在するようになったのだろうか?そして、どのような条件下で個性は自由になるのだろうか?
ライフスタイル=アナキストが自由ではなく自律を要求するとき、彼等はそのために自由の持つ豊潤な社会的含蓄を失っている。実際、社会的自由よりも自律を求める今日のアナキストが鳴らす一様の太鼓の音を偶然だとして、特に、自律という概念が私的リバティと密接に対応しているリバータリアン思想の英国系アメリカ的変種の中で現れたものだとして見過ごすことはできない。そのルーツは「libertas」というローマ帝国的伝統にあり、そこでは拘束されていないエゴは、「自由に」その私的所有物を持つ--そして私的肉欲を満足させる--というものであった。今日、「主権者の権利」を賦与された個人は、多くのライフスタイル=アナキストによって、国家に対するだけでなく、社会それ自体に対するアンチテーゼとしても見なされている。
厳密に定義すると、ギリシャ語の「autonomia」は「独立」を意味している。それは、その維持のために他者に対して何者にも依存もしていない、自己管理しているエゴを暗示している。私の知識では、これを広く使っていたのはギリシャの哲学者達ではなかった。実際、F=E=ピートの歴史的語彙目録「ギリシャ哲学用語集」ですら言及されていない。「自律」は、「リバティ」と同様、プラトンならば皮肉を込めて「自身の主人」と呼んだであろう男(女)のことを差しているのであって、それは「人間の魂の持つましな原則が悪しき原則を統御している」状態なのだ。プラトンにとってさえ、自己の主人となることを通じて自律を確立しようという試みは、パラドックスを作りだしていたのだ。『なぜなら、主人はまた召使でもあり、召使は主人でもあるからであり、いかなる種類の対話をしようと、同じ人間が叙述しているからなのである。』(共和国、第4巻、431ページ)。特に、本質的に個人主義的アナキストであるポール=グッドマンは、『私にとって、アナキズムの主要原則は自由ではなく、自律である。仕事を開始し、自身のやり方でこなす能力なのである。』を堅持していた--美学者としては価値があるが、社会革命家としては価値のない観点である[6] 。
「自律」は自己主権を推定している個人に関連している一方、「自由」は個人と集産集団とを弁証法的に織り混ぜている。「自由」という言葉はその類同語としてギリシャ語の「eleutheria」があり、「ゲマインシャフト(gemeinschaftliche)」やチュートン族の生活と法における共同体的系譜を今でも保っているドイツ語の「Freiheit」から派生している。したがって、個人に適用されると、「自由」は、その個人の起源と自己としての発達の社会的・集団的解釈を保持しているのである。「自由」において、個人の自己性は、集団に対抗したり集団から離れていくような点に立脚しているのではなく、自身の社会的存在性によって大きく形成される--そして理性的社会においては実現されるであろう。したがって、自由は個人のリバティを包含しているだけでなく、その実現も意味しているのである。(原注)
(原注:不幸にして、ロマンス言語の「自由」はラテン語の「libertas」から派生した言葉だと一般には説明されている--フランス語では「liberte」、イタリア語では「liberta」、スペイン語では「libertad」。英語は、ドイツ語とラテン語が混ざっているため、自由 Freedom とリバティ Liberty との区別を行うことが出来、他の言語では出来ない。私はこのことに関して、他言語で書いている人々は、それらの区別をきちんとする必要がある場合に英語を使うことをお勧めする。(訳注:本翻訳では、「Liberty」をリバティ、「Freedom」を自由と訳した。))
自律と自由の混乱は、L=スーザン=ブラウンの「個人主義の政治学」(The Politics of Individualism: POI)に全く明らかである。この書物は基本的に個人主義アナキズムを明確に述べ詳細に検討しているのだが、無政府共産主義との派生関係も残している[7] 。もしライフスタイル=アナキズムに学問的系譜が必要ならば、それはバクーニンとクロポトキンを、ジョン=スチュワート=ミルに混ぜ合わせたブラウンの試みに見出せるであろう。ブラウンの書物は、私的自律に関わる諸概念が社会的自由の諸概念とどれほどうまくなじまないのかを示している。本質的にグッドマンのように、彼女はアナキズムを社会的自由の哲学としてではなく、私的自律の哲学として解釈している。そこで、彼女は「実存的個人主義」という概念を示し、リバータリアンの殿堂の中で最も才能ある思索者であったエマ=ゴールドマンからの多くの引用をしながら、「道具的個人主義」(つまり、C=B=マクファーソンの「所有的(ブルジョア)個人主義」)と「集産主義」の双方と鋭く区別している。
ブラウンの『実存的個人主義』は、自由主義の『個人の自律と自己決定へのコミットメント』を共有している、と彼女は書いている(POI、2ページ)。彼女は以下のように述べている。『多くのアナキズム理論が、アナキストによる共産主義と非アナキストによるそれとを同様に見てきているが、アナキズムをその他の共産主義哲学者達と区別しているのは、個人の自己決定と自律に対する非妥協的で容赦のない賛美なのである。アナキストになるということは、--共産主義者であれ、個人主義者であれ、相互主義者であれ、サンジカリストであれ、フェミニストであれ--個人の自由の第一位性に対するコミットメントを断言することなのである。』(POI、2ページ)。ここで彼女は「自由」という言葉を自律の意味で用いている。アナキズムの『私有財産批判と自由な共同体的経済関係の擁護』(POI、2ページ)がブラウンのアナキズムを自由主義よりも超越させているにもかかわらず、集産集団の権利よりも--そしてそれに対抗して--個人の権利を持ち上げているのである。
ブラウンは次のように続けている。『(実存的個人主義を)集産主義の観点と区別していることは、個人主義者は』--自由主義者に他ならないアナキスト達は--『内的に動機づけられた権威ある自由意志を信じている、ということである。一方、大部分の集産主義者は人間個人を他者によって外的に形成されている--他者に対する個人は、集産集団によって「作り上げ」られている--と理解している。』(POI、12ページ、強調は筆者)本質的にブラウンは集産主義--国家社会主義だけでなく、集産主義それ自体も--を、集産主義社会が個人に集団への従属を課すという自由主義的流言を使って却下しているのである。彼女の法外な示唆は、『「大部分の」集産主義者』が個人を『歴史の流れに流されている単なる人間漂流物』(POI、12ページ)と見なしているというものであるが、これは、ある点においては事実である。スターリンは明らかにこの観点を持っていたし、多くのボルシェヴィキもそうだった。彼らは、個人の願望と意図に及ぼす社会的力という仮説を持っていた。しかし、集産主義「それ自体」もそうだというのだろうか?我々は、理性的で、民主的で、調和した社会を捜し求めていた集産主義の豊潤な伝統を無視しようとしているのではないだろうか?例えば、ウィリアム=モリスやゲシュタフ=ランダウアーのヴィジョンはどうなのか?ロバート=オーエン、フーリエ主義者、民主的なリバータリアン社会主義者達、初期の社会民主党、カール=マルクスやピョトール=クロポトキンはどうなのか?私は、『「大部分の」集産主義者』が、それがアナキストであったとしても、ブラウンがマルクスの社会解釈に帰した粗雑な決定論を受け入れるとは思えない。強行路線の機械論者達である偽の「集産主義者」を作りだすことで、ブラウンは言葉巧みに、一方では神秘的で自然発生的に作りだされた個人を、他方ではどこにでもおり、圧制的だと仮定され、全体主義でさえある集産集団を対峙させている。その結果、ブラウンは、「実存的個人主義」と「大部分の集産主義者」の信念とのコントラストを誇張しているのである--彼女の論法が良くて思い違いを助長し、悪くて陰険に見える点まで。
ジャンジャック=ルソーの「社会契約論」の名高い始まりにもかかわらず、人間は明らかに自律しているわけでもなければ、「自由に生まれ」たのでも「ない」。実際、全く逆で、人間は「非常に」不自由で、非常に依存的で、明らかに他律的なのである。人間がある歴史的時期にどのような自由、独立、自律を持つのかは、長期にわたる社会的伝統、そう、「集産的」発展の産物なのである。それは、個々人が、その発展の中で重要な役割を演じ、実際自由になりたいと願うならば、最終的にはそうする義務があるということなのだ。(原注)
(原注:人間が自由に生まれたという神話を味わい深く冷やかす中で、バクーニンは抜けめなく宣言している。『ジャンジャック=ルソー学派個人主義者の思想とプルードン主義相互主義者の思想は何と馬鹿げていることだろう。彼等は社会を、お互いに絶対独立している個々人の自由契約の産物と見なし、相互関係を作るのは、単にそれが人間間でこれまで行われて来た慣習だからだというのである。まるで、こうした人間達は空から振って来て、そのときに話言葉・意思・最初の思想を持って来たとでも言いたげだ。まるで、人間は地上のいかなるものに対しても、つまり、社会的起源を持っているいかなるものに対しても何の関わりも持っていないと言っているようなものだ。』マキシーモフ著、「バクーニンの政治哲学」、167ページ。)
ブラウンの論法は、驚くほど単純な結論を導いている。『個人を形成しているのは集団ではない』と我々は述べられる。『むしろ集団に形と中身を与えているのは個人なのである。集団は「個人の集積なのであってそれ以上でもそれ以下でもない」のだ。集団には生命も無く、それ自身の意識もないのである。』(POI、12ページ、強調は筆者)この驚くべき公式は、マーガレット=サッチャーの、社会なるものは存在せず個々人がいるだけである、という悪名高い発言によく似ているだけでなく、世界は具体的なことから完全に引き離されているという実証主義的で、確かに素朴な社会的近視眼を宣言しているのである。既に思い起こしている人もいるだろうが、アリストテレスは、プラトンが言語に絶した「形式」の王国を作り上げ、その具体的で不完全な「コピー」から離れて存在させたと叱ったときに、この問題を解決していたのだ。
個人が単なる「集積」を作りだすことはない、これが依然として真である--電脳空間は多分例外であろう。逆に個人は、ばらばらにされ密封されているように見える時であっても、社会的存在としての正にその存在により、個々人が確立する関係や、お互いに確立しなければならない関係によって大きく定義される。集産集団--そしてそこから推定される社会--が単なる『個人の集積であり、それ以上でもそれ以下でもない』は、人間関係の性質に対する「洞察」を示しているが、それは自由主義的どころか、特に今日においては、潜在的に反動的なのだ。
集産主義を執念深い社会決定論だと強く特定することで、ブラウン自身は、抽象的な「個人」を「創りだして」いる。それは個人という語の厳密に慣習的な意味には実在してさえいない。人間経験は、最低限、生命・衛生・知性・対話を維持するのに必要な社会的条件と物質的条件を「前提としている」。そして、ケア・関心・共有といった感情もそうであり、これらはブラウンが自分の任意主義形態の共産主義にとって不可欠だと見なしている性質なのだ。誕生から成人へそして老年へと至るまで人間に埋め込まれている社会関係の豊潤な言及がないため、ブラウンが前提としている「個人の集積」は、乱暴に言ってしまえば、「社会」では全くないであろう。それは、着脱自在で、自己探求的で、エゴイスティックな単細胞生物群というサッチャー的意味での文字通り「集積」となるであろう。個人自身で完全だとすれば、弁証法的倒置により、それらは、自身が持つ欲望と享楽--今日ではいかなる場合であれ社会的に処理されていることが多い--の満足以上の目的が無いため、大きく「脱」個人化されているのである。
個人は自分で動機付けするものであり、自由意志を持っているということを認めても、集産主義を拒否することにはならない。個人はこうした優れた潜在能力を行使できる社会条件に関する意識をも発達させることが出来るためである。自由の達成は、子供を育てたことがある人なら誰でも知っているように、一部生物学的事実に依っており、地域生活をしたことがある人なら誰でも知っているように、一部は社会的事実に依っており、そして社会構造主義者とは正反対に、思索する人なら誰でも知っているように、一部を環境と生来の私的諸性癖との相互作用に依っている。個性は「ab novo」となるように発現していなかったのだ。自由という思想同様、それは長い社会的心理学的歴史を持っているのである。
自身の自己に留まることで、その人は不可欠な社会的よりどころを失ってしまう。その社会的よりどころは、アナキストが個性の中で賛美すると思われているであろうこと--その大部分が対話から生じる熟考力、不自由に対する激情を育む感情的技量、急進的変化への希望を動機づける社会性、社会的行動を引き起こす責任感覚--に多大なる影響を与えているのである。
確かに、ブラウンのテーゼには社会行動を妨げる示唆がある。もし個人の「自律」が「集産性」に対するいかなるコミットメントをも覆しているのなら、社会的制度化・意志決定・行政的調整に対してさえも何ら基盤が無いことになる。自分の「自律」に自己充足している個々人は、自分が欲していることなら何でも行う自由があることになる--多分、昔の自由主義的公式に従えば、他者の「自律」を阻害しない限り。民主的意志決定でさえ、権威主義だとして放り出されてしまう。「民主的ルールはそれでもルールである」とブラウンは警告している。「それが独裁政治や全体主義独裁よりも多くの個人が政府に参画できるようにしているとしても、そこではなおも誰かの意志を抑圧しているのである。これは明らかに実存的個人とは調和しない。実存的個人が実存的に自由となるためには、意志の誠実さを保ち続けなければならないのだ。」(POI、53ページ)。実際、ブラウンの目に非常に超越的に神聖不可侵だと映っていることは、自律した個人の意志であり、彼女はピーター=マーシャルの、アナキスト原理に依れば『小数が大多数を支配する権利を持っていないように、「たった一人の小数派であっても」、大多数は小数を支配する権利を持っていない』(POI,140ページ、強調は筆者)という要求を賛同的に引用しているのだ。
集産的意志決定の理性的で多岐にわたった直接民主的手続きを、「独裁的」で「支配的」だと汚すことは、一人の主権者エゴの少数派に、大多数の決定を放棄する権利を与えることである。だが、自由社会は民主的なものであるか、それとも全く確立されないかのどちらかである、これが依然として事実である。アナキスト社会の「実存的」(お望みならばこう言ってもいいが)状況--直接リバータリアン民主主義--では、意志決定は公開討議後になされる可能性が最も高い。その後、得票数の少ない少数派は--たった一人の小数派であっても--その決定を変えようとする補足論証を提起するあらゆる機会を持つことになる。逆に、コンセンサスによる意志決定は、その場に現れる「意見の相違」--個人的創造力と同様社会的創造力に必要不可欠な継続的対話・不一致・異議申し立て・その異議に対する反論といった非常に重要なプロセス--を阻害するのである。
どちらかと言えば、コンセンサスを基に活動することは、重要な意志決定が少数派によっても操作されるか、もしくは完全に崩壊することを確実にしているのである。そして、なされる決定は、大部分の人が同意する最低限の見解を具現化し、創造性が最も低い同意を組織することになる。ここで私は、1970年代のクラムシェル同盟においてコンセンサスを使った痛々しい長期にわたる経験について触れておこう。丁度、この擬似アナキズム的反原発運動がその闘争のピークに達したときだった。この運動は少数派によるコンセンサス過程の操作によって破壊されてしまった。コンセンサス意志決定が生み出した「構造のない専制政治」は、充分組織された小数が、運動内部で扱いにくく、脱制度化し、大きく混乱した多数を支配できるようにしてしまったのだ。
また、コンセンサスに対する非難の声の中には、「意見の相違」が存在できなくなり、議論を創造的に刺激できなくなり、そのために新しく永続的に拡充する見解を生み出しうる思想の創造的な発達を促すこともできなくなる、というものもあった。いかなる地域においても、意見の相違--そして意見を異にする個人--は、地域を沈滞させないようにしているのである。独裁や支配といった軽蔑の言葉は、少数派反対意見の沈黙のことを適切に述べているのであって、民主主義の行使のことを述べているのではない。皮肉なことに、コンセンサスに基づいた「民意」こそが、ルソーの社会契約論からの記憶しておくべきフレーズ『人間を自由にせしめる』ことを充分にできるようにしているのだ。
いかなる地上的語意においても実存的であることから離れ、ブラウンの「実存的個人主義」は個人を「歴史から分離して」扱っている。彼女は個人を超越的カテゴリーとして純化し、それは丁度1970年代にロバート=K=ウォーフがその怪しげな書物「アナキズムの弁護」の中でカント主義の個の概念をひけらかしたようなものである。個人と相互作用することでその人を真に意図的で創造的な存在足らしめている社会要因は、超越的道徳抽象の下に埋もれている。そうした道徳抽象は、それ自体に純粋な知的生命があるとすれば、歴史と慣習の外に「実在」しているのであろう。
集産集団と個人との関係に対するアプローチの中で道徳的超越主義と単純化された実証主義の間を行き来しているため、ブラウンの詳説は進化論と創造論の関係と同じぐらいぎこちない。個人がどのようにその大部分を社会発展によって形成され、社会発展と相互作用をしているのかを示す豊潤な弁証法と豊かな歴史は、彼女の書物から全くと言って良いほど欠如している。原子的で偏狭なほど分析的な観点を多く取りながらも、抽象的に道徳的で超越的でさえある解釈をしながら、ブラウンは、社会的自由とは正反対の自律という概念に対する優れた背景を提示しているのである。一方では「実存的個人」を、そして他方では「個人の集積」でしかない社会を使うことで、自律と自由の亀裂は掛け橋不可能なものとなったのだ。(原注)
(原注:結局、ブラウンは、バクーニン、クロポトキン、私の著作を重大に読み誤っているのである--この読み誤り全てを正すためには詳細な議論を要するであろう。私自身について言えば、ブラウンが主張しているように、「「自然の」人間」などを信じてはいない。丁度私が、「自然法」に対する彼女の古臭いコミットメント(159ページ)を私が共有していないのと同じである。「自然法」は、二世紀前の民主革命の時代には有効な概念であったかもしれないが、それは哲学的神話なのであり、その道徳的前提は、ディープ=エコロジーの「内在価値」という直感的知識が現実のものでないのと同じぐらい非現実のものなのである。人間性の「第二自然」(社会的進化)は、「第一自然」(生物学的進化)を大幅に変形させたものである。したがって、「自然」という言葉は、ブラウンが扱っているよりももっと慎重にそのニュアンスが与えられていなければならないのである。私が「自由は自然の中に内在している」と信じているという彼女の主張は、私が行った、可能性とその実現との区別について大きく思い違いをしている(160ページ)。自然進化における自由の可能性と社会的進化における今もなお未完成なその実現との区別を明確にするためには、読者は大きく改訂した私の著書「社会生態学の哲学:弁証法的自然主義に関するエッセイ」、第二版(モントリオール:Black Rose Books, 1995)を参照していただきたい。)
カオスとしてのアナキズム
ブラウン自身の好みがいかなるものであれ、彼女の本は、社会的アナキズムを離れ、個人主義つまりライフスタイル=アナキズムへと向っている欧米アナキストの転換の前提を反映し、かつ、その前提を提示してもいる。実際、今日のライフスタイル=アナキズムはその主要表現を、スプレー落書き・ポストモダニストのニヒリズム・反理性主義・新原始人主義・反テクノロジー主義・新シチュアシオニズムの「文化的テロリズム」・神秘主義・フーコー主義の「私的暴動」を演じる「実践」に見出している。
これらのトレンディな姿勢は、全て現在のヤッピーファッションを追従しており、真面目な組織の構築・急進主義政治運動・社会運動へのコミットメント・理論的一貫性・実行プログラムの適切さに対するアンチテーゼであるという重大な意味で個人主義的なのである。根本的な社会変革を確立することよりも自分自身の「自己実現」を確立することに向かうライフスタイル=アナキストのこの傾向は、カティンカ=マトソンが「内面に向っている」と呼んだことを政治運動だと主張する場合に、特に有害なのである--R=D=レインの「経験の政治学」に似てはいるものの。ウクライナとスペインにおける叛乱闘争で革命的社会的アナキスト達が掲げた黒旗は、現在では、粋なプチブルご用達の馬鹿騒ぎ用腰布となり果てたのだ。
ライフスタイル=アナキズムの最も不愉快な例の一つは、ハキム=ベイ(別名、ピーター=ランボーン=ウィルソン)の「TAZ:一時的自律ゾーン(The Temporary Autonomous Zone)、存在論的アナキズム、詩的テロリズム」新自律シリーズの一宝石(ここでの語選びは偶然ではない)であり、ブルックリンのひどくポストモダニスト的なSemiotext(e)/Autonomediaグループから出版されている[8] 。「マルクス主義-シュチルナー主義」の賞賛は言うまでもなく、「カオス」・「狂気の愛」・「野生の子供達」・「異教信仰」・「アート=サボタージュ」・「海賊のユートピア」・「革命行為としての黒魔術」・「犯罪」・「魔法」の賛歌の中でなされる自律の要求は、余りにも馬鹿げたほどの長さを取っているため、自己没頭(self-absorbed)し、自己同化(self-absorbing)しているイデオロギーをパロディーにしているように思えるほどである。
TAZは、それ自体を心の状態、激しい反理性的・反文明的ムードであるとしており、そこでは、混乱は一つの芸術形態と見なされ、落書きが行動プログラムに取って替わるのである。ベイ(このペンネームは、トルコ語の「首領」や「王子」を意味する:訳注参照)は、社会革命に対する軽蔑について率直に次のように述べている。『なぜ、既にすべての意義を失い、全くの「シミュレーション」と化している「権力」に立ち向かうのに思い悩むのか?このような対峙は、すべての武器貯蔵庫と監獄の鍵を受け継いでいる空っぽ頭に糞が詰まった者たちによる、危険で醜い暴力の衝動へと帰するだけであろう。』(TAZ、邦訳書、246ページ)「権力」に疑問符?単なる「シミュレーション」?銃火器を使ってボスニアに起こっていることが単なる「シミュレーション」ならば、我々は非常に安全で居心地の良い世界に住んでいるわけだ、全く!近代生活で一貫して倍増している社会病理について不安になっている読者はベイ様の『要するにリアリズムは、我々が「あの革命」を待ち望むことをあきらめるだけではなく、我々がそれを欲することを断念することも求める。 』(TAZ、邦訳書、197ページ)というオリンポスの神々のような思考に安堵するかもしれない。この一節は、涅槃の平穏を享受するよう我々に合図しているのだろうか?それとも、新たなボードリヤール的「シミュレーション」なのだろうか?それとも、多分新たなカストリアディス的「想念」なのだろうか?
(訳注:これ以降の「ベイ」は、原文では「the Bey」と表記されている。このことについて原著者に尋ねたところ、以下のような回答であった。「私は、彼の余りにもひどいペンネームを馬鹿にしているのです。アナキストが自身をベイだと名乗ることは、マルクス主義者が自分をブルジョアだと名乗っているようなものです。これは、彼が明言しているリバータリアニズムへの傾倒と全く矛盾しているのです。」この後、the Beyはベイ様と訳出してある。)
社会を変えるという革命の伝統的目的を無視しながら、ベイ様は一度はその目的のために全ての危険を犯した人々を恩着せがましくあざけっている。『民主主義者、社会主義者、理性的なイデオローグたちは(中略)音楽を聞く耳を持たず、リズムのセンスをまったく欠いている』(TAZ、邦訳書、134ページ)。本当だろうか?ベイ様と彼の侍者達自身は、「ラ=マルセーイエーズ」の詩と音楽に熟達し、グリエールの「ロシア水夫のダンス」のリズムに恍惚として踊ったことがあるのだろうか?過去数世紀にわたり革命家達が作り上げた、実際、ロックンロール以前・ウッドストック世代以前の普通の労働者が作り上げた豊潤な文化をベイ様が忘却していることには、うんざりするほどの傲慢さがある。
真に、ベイ様の夢の世界に入った人々が、社会的コミットメントに関するナンセンス全てを放棄するようにしてあげなければなるまい。『民主主義的な夢?社会主義的な夢?あり得ないことだ。』ベイ様は横柄なほどの確信を持って詠唱している。『夢の中では、我々は愛、あるいは魔術師以外によっては統治されていない』(TAZ、邦訳書、131ページ)。このようにして、何世紀にもわたる偉大なる諸革命で理想主義者達が喚起していた新世界という夢は、ベイ様によって高圧的に、彼の熱にうかされた夢の世界の知恵へと還元されてしまっているのだ。
アナキズムについては、それは『「倫理的ヒューマニズム」や「自由思想」、「筋肉的無神論」、「生硬な根本主義者的デカルト派論理」といったものが引っかかった蜘蛛の巣だらけのものをでっちあげ』(TAZ、邦訳書、106ページ)るというのだ--ほっとけ!ベイ様は、一挙に、アナキズム・社会主義・革命運動が以前はその根幹としていた啓蒙の伝統をやっつけているだけでなく、あたかも、それらが入れ替え可能だったり、お互い必然的に前提条件となっているかのように、「根本主義者的デカルト派論理」というリンゴを「自由思想」と「筋肉的人道主義」のようなミカンと混ぜ合わせているのである。
ベイ様ご自身はオリンポスの神々宣言を行い、気難しい論証法を行うことに何の躊躇もしていないのだが、彼は『アナーキズムと自由意志論の口先だけのイデオローグたち』(TAZ、邦訳書、96ページ)には我慢できないのだ。『アナーキーはドグマを知らず』(TAZ、邦訳書、107ページ)と主張しながらも、粗野なドグマというものがあるとするなら、ベイ様は自分の読者をその一つの粗野なドグマに陥らせている。『アナーキイズムは、本源的にはアナーキーを内包している。--そして、アナーキーとはカオスである。』(TAZ、邦訳書、130ページ)。まるで、主曰く、「私は「ここにいる」だから私は存在する」だ--そして、モーゼは宣言の前に震えたのであった!
実際、病的ナルシシズムの発作の最中、ベイ様は、主権者は、全てのものを所有している自己、そびえたっている「我(I)」、巨大な「私(me)」であると定めている。『我々の一人一人は我々自身の肉体の、我々自身の産物の統治者なのだ--何物であっても、我々は掴み、保持することができるのである。』(TAZ、邦訳書、135ページ)ベイ様にとって、アナキストと王--そしてベイ様達--は皆、絶対主権者である以上、区別できないものとなっているのである。
『我々の行動は自分勝手な布告により正当化され、そして我々の利害関係は他の専制君主との条約によって形作られる。我々は自身の行動圏のために法を制定する--そしてその法の鎖は、既に断ち切られているのである。現在では、恐らく我々は単なる「王位請求者」として生き延びているに過ぎない--しかし、そうであっても我々は、我々の絶対的意志を強制するリアリティのほんの一瞬を、一握りの面積を奪い取るだろうが、それがわれわれの「王国」なのである。「朕は国家なり」。(中略)もし我々が、倫理あるいは道徳に縛られているとすれば、それらは我々自身が想像していたものでなければならない。』(TAZ、邦訳書、135-136ページ)
朕は国家なり? ベイ様達に従えば、今世紀にこれらの徹底的な特権を楽しんでいた二人の人間を少なくとも思い浮かべることが出来る。ヨセフ=スターリンとアドルフ=ヒットラーである。残りの我々死ぬべき人間の大部分は、金持ちも貧乏人も同様に皆、アナトール=フランスがかつて述べたように、セーヌ川の橋の下で寝ることを禁じられているのである。実際、フリードリッヒ=エンゲルスの「権威論」が、ヒエラルキーの弁護と共に、ブルジョア形態社会主義を示しているとすれば、TAZとその傍系はブルジョア形態のアナキズムを示しているのである。ベイ様は我々に語っている。『生成は存在せず、革命も、闘争も、指針も存在しない。であれば既に、あなたはあなた自身の生命の君主である。--あなたの侵すことのできない自由は、ただ別の君主たちの愛によって完成されるのを待ちうけている。それは夢のポリティックスであり、空の青さのように渇望されているものなのだ。』--ニューヨーク株式取引所に、エゴイズムと社会的無関心の信条表明として銘記されてもよさそうな言葉である(TAZ、邦訳書、16ページ)。
確かにこの観点が、長髪・髭・ジーンズが高級ファッションの興行的世界を撃退しているほどにも、資本主義「文化」のブティックを撃退することなどないであろう。不幸にして、この世界--「シミュレーション」でもなく、「夢」でもない--にいるはるかに多くの人々は、刑務所で一つなぎにされている囚人達が最も具体的な服役期間中に証言できるほどにも、自身の表皮さえも持ってはい「ない」のだ。特権を持ったプチブルを除き、地上的な貧困王国の外で、「夢のポリティックス」を漂っている人などこれまでいなかった。そうしたプチブルどもは、特に退屈している時に、ベイ様の宣言を受け入れるであろう。
ベイ様にとっては、実際、伝統的な革命的暴動が示していることでさえも、フーコーの「限定経験」の香り漂う私的陶酔状態と同じなのである。『この意味で反乱とは、「通常の」意識や経験の基準とは反対の「至高体験」のようなものだ。』と彼は我々に確信させている(TAZ、邦訳書、194ページ)。歴史的に、『アナーキストたちのあるものは、(中略)それが共産主義的あるいは社会主義的なものであったとしてもあらゆる反乱や革命に参加したのであるが、それは彼らが、蜂起の瞬間それ自体の中に彼らが探し求めていた種類の自由を見いだしたからだ。それゆえ、ユートピア主義がこれまで常に失敗してきた一方で、個人主義者や実存主義者のアナーキストたちは、(それが短期間であっても)戦時において彼らの力への意志の実現を達成する程度には成功をおさめてきたのである。』(TAZ、邦訳書、p.174)オーストリア労働者の1934年二月革命の叛乱と1936年のスペイン戦争は、全てが審美的顕現日などではなく、乱ちき騒ぎ的「叛乱の瞬間」以上の、死物狂いの真剣さと壮大な魂と共に行われた苦闘だった、と私は証言出来る。
それでもなお、暴動はベイ様にとってサイケデリック=「トリップ」と同じであり、ベイ様お気に入りのニーチェ主義的超人は『自由な精神』なのである。その超人は、『改革の扇動、抗議、非現実的な夢、あらゆる種類の「革命的殉教」といったものに--要するに、最も今風のアナーキストの活動に--時間を浪費することを潔しとはしない』であろう。多分、夢は、それが『非現実的』(社会的にコミットした、とも読める)でない限りオーケーなのである。むしろ、ベイ様は『酒を飲み』、『個人的な直感的知覚』を持っていることだろう(TAZ、邦訳書、176ページ)。このことは、デカルト主義論理の拘束から確実に自由になるための精神的自慰に他ならないことを示唆している。
ベイ様が、『形而上学には関わっていないが、それでもなお、「唯一者」にある種の絶対性を与えている』(TAZ、邦訳書、137ページ)マックス=シュチルナーの考えを好んでいるということを知っても何ら驚くべきことではない。確かに、ベイ様は、『シュティルナーに欠けている要素(ニーチェはより近くまで到達している)とは、「通常ではない意識」についての実行概念である。』(TAZ、邦訳書、138ページ)と見出している。明らかに、シュチルナーはベイ様にとっては余りにも理性主義過ぎるのである。『東洋の、オカルトの、そして部族の文化は、真のアナーキストのファッションにおいて「ふさわしい」ものとなり得るテクニックを備えている。(中略)酩酊しておとなしくなってしまっているシャーマニズムを民主化することなのだ。』(TAZ、邦訳書、128ページ)そこで、ベイ様は彼の使徒を「魔法使い」となるように召喚し、使徒に「黒マレー霊魔の呪い」を使うように示唆しているのである。
結局のところ、「一時的自律ゾーン」とは何なのだろう?『TAZは、国家とは直接交戦しない反乱のようなものであり、(国土の、時間の、あるいはイマジネーションの)ある領域を解放するゲリラ作戦であり、それから、「国家」がそれを押しつぶすことができる<前に>、それは、何処か他の場所で/他の時に再び立ち現れるために、自ら消滅するのである。』(TAZ、邦訳書、196ページ)。一つのTAZにおいて、我々は『自ら多くの「真実の欲望」を理解できることだろう。その欲望が、ただ一時期の、短い「海賊のユートピア」の、つまり古い「空間/時間」の連続体の中で捻じ曲げられたフリーゾーンのためだけであったとしても。』(TAZ、邦訳書、126ページ)『潜在的なTAZ』には、『60年代風の「部族集会」、エコタージュする者たちが森で開く秘密会議、ネオ多神教徒の牧歌的ベルテーン祝祭、アナーキスト会議、同性愛の人たちの夢幻郷のようなサークル』があり、『ナイトクラブ、晩餐会』、『古の自由主義者たちのピクニック』--まさか!--は言うまでもない(TAZ、邦訳書、205ページ(訳注:TAZの邦訳者はリバータリアンを自由主義者と訳している))。1960年代のリバータリアン同盟の一員だった者として、私は『古の自由主義者たちのピクニック』でベイ様とその使徒の外面を見てみたかったものだ!
恐るべき安定性を持った国家とブルジョアとは逆に、TAZは余りにも短期間で、余りにもはかなく、全く曖昧なため、『TAZが名付けられる(表現される、あるいはメディアによって媒介される)や否や、(中略)それは消滅しなければならないし、消滅する(だろう)が、それは単にどこか他の場で再び飛び上がる』(TAZ、邦訳書、197ページ)。結局、一つのTAZは、一つの叛乱ではなく、一つのシミュレーションなのであり、未熟な脳味噌の想像の中に生きている暴動なのであり、空想への安全な退却なのである。実際、ベイ様は次のように熱弁を奮っている。『我々がそれを推奨するのは、それが、暴力と殉教へ導かれる必要のない(!)反乱と一体になった高揚の質を与えてくれるからである。』(TAZ、邦訳書、196ページ)もっと正確に言えば、丁度アンディ=ウォーホールの「ハプニング」のように、TAZは束の間の出来事なのであり、一瞬の絶頂感なのであり、「力への意志」の束の間の表現なのであり、それは、実際には、個人の人格・主観性・自己形成にさえも何らかの痕跡をも残すほどの能力も全くなく、ましてや出来事と現実を形成することなどないのである。
TAZのはかない性質があれば、ベイ様の使徒は「放浪の存在」を生きるという束の間の特権を享受することが出来る。なぜなら、『「家を持たないこと」(ホームレス)は、ある意味である種の美徳、冒険ともなり得る』(TAZ、邦訳書、250ページ)からである。あぁ悲しいかな、ホームレスであることは、その人が帰る心地よい家があるからこそ「冒険」となり得るのであり、放浪生活は自分の生計の糧を得ることなく生活出来る人々の明らかな贅沢なのである。「放浪生活をしている」浮浪者の大部分について、空腹・病気・冷遇という絶望的生活と、普通に見られた未熟死とを被ってきた大恐慌時代から、私は非常に鮮明に思い出す--北米都市の街路では現在でも同じなのだ。「路上の生活」を享受しているように見えたジプシー系の人々は、良くて特異体質であり、悪くて悲劇的に神経症的であった。さらに、私は、ベイ様が注目に値するほど打ち出している別な「暴動」、『自発的な無(識)字』(TAZ、邦訳書、248ページ)を無視することも出来ない。彼はこのことを教育システムに対する叛乱として打ち出しているが、そのさらに望まんとしている効果は、彼の読者に接触不可能なベイ様の様々な権威による命令を示すことなのかもしれないのだ。
多分、「地球全土評論(Whole Earth Review)」誌に載ったものよりもTAZのメッセージをうまく記述したものはないであろう。その評論者は、ベイ様の小冊子は『急速に、1990年代のカウンターカルチャーの聖書となっている(中略)ベイの概念の多くが、アナキズムの主義と近縁関係にあるが』、「評論」誌はそのヤッピー常連読者を次のように再保証しているのである。ベイは、
『政府の転覆についてお決まりの「レトリック」を明らかに避けている。その代わり、彼は「叛乱」の機敏な性質を好んでおり、それは「人生全体に形を与え意味を与える(ことが出来る)厳しさの瞬間」を提示すると彼が信じていることなのである。これらの自由のポケット空間、つまり一時的自律ゾーンは、「個人が」大きな政府という図式的鉄格子を避け、「短期間」「完全な」自由を経験できる王国内で時折生活できるようにするのである。』(強調は筆者)[9]
このこと全てに関する翻訳不可能なイディッシュ語がある:nebbich!1960年代には、近縁グループ「壁に立ち向かう糞ども(Up Against the Wall Motherfuckers)」は、同様の混乱・組織破壊・「文化的テロリズム」を蔓延させていたが、結局その後すぐに政治シーンから消えうせた。実際、そのメンバーの中には、彼らが軽蔑すると公式に主張していた商業的・専門的・中産階級的な世界へ入ったものもいた。こうした行動は米国人に独自のものではない。1968年の5月-6月革命のフランス「老兵」が皮肉っぽく述べていた。「俺達は68年に楽しんだんだ。今はもう大人になるときさ。」サークルAと共に、同じ弱体サイクルは、1984年のチューリッヒにおける非常に個人主義的な青年の叛乱にも繰り返され、結局、悪名高いコカイン・クラック常習者のたまり場、ニードル=パークを造っただけで終わってしまった。それは市当局が麻薬中毒の青年達を合法的に自滅させるために造られたのだった。
ブルジョアがこうしたライフスタイル攻撃を怖がる理由など全くない。制度や大衆型組織の嫌悪・大規模なサブカルチャー志向・道徳的退廃・一時性の称賛と共に、この種のナルシシスティックなアナキズムは社会的に無害であり、優勢な社会秩序に対する不満の単なる安全弁となっているだけのことも多い。ベイ様と共に、ライフスタイル=アナキズムは、スリル・ポストモダンのニヒリズム・目もくらむようなニーチェ主義的意味のエリート主義優越感へと解消することで、全ての意味ある社会活動主義と永続的で創造的な計画への不動のコミットメントから逃避しているのである。
もしこのガラクタを初期のリバータリアンの理想に取って代わるものだとしてしまえば、アナキズムが払うことになる代価は莫大なものとなるであろう。ベイ様のエゴ中心主義的アナキズムは、個人主義的「自律」、フーコー主義的「限界経験」、新シチュアシオニズムの「恍惚」へのポストモダニズム的撤退とともに、アナキズムという正にその言葉を政治的にも社会的にも無害なもの--全年齢のプチブルの興味をそそる単なる流行--にしてしまう恐れがあるのだ。
神秘主義的・非理性主義的アナキズム
ベイ様のTAZは、魔法に、さらには神秘主義に対するアピールという点で独自に存在しているわけではない。多くのライフスタイル=アナキストは、人類が転落する前のメンタリティを持っているため、その最も先祖返りした形態の反理性主義へと向い易い。「第五権力(Fifth Estate)」誌の最近号(1989年夏号)の背表紙全体を占めている「アナーキーのアピール」について考えてみよう。そこでは、「アナーキーは、「完全な解放の切迫」」を認識しており(まさか!)、「君の自由の証として君の儀式の中で裸になれ」というのだ。「歌い、踊り、笑い、祝宴をし、遊ぶこと」に従事せよ、と我々は命じられている--ミイラになったやかまし屋がいない人々は、これらラブレー風の楽しみに反論することが出来るだろうか?
しかし残念ながら、差し支えが一つある。「第五権力」誌が張り合っているように見えるラブレーの「テレームの僧院」は、召使・料理人・馬丁・職人で満ち足りていたのだ(訳注)。彼らの一生懸命の働きがなければ、その明らかな上級階級ユートピアという自己耽溺の貴族主義者は、寺院の別な冷たい大広間で餓死し、裸のままで積み上げられたことであろう。確かに、「第五権力」誌の「アナーキーのアピール」はテレームの僧院を物質的にもっと単純化したバージョンを念頭に置いているのだろう。そして、その「祝宴」とは、詰め物入りのヤマウズラと美味なトリュフではなく、豆腐と米のことを差しているのであろう。しかし「それでも」--テーブルの上の豆腐と米を得るためにさえも必要な、民衆を苦労から解放してくれる主要テクノロジーの進歩抜きで、どのようにして、この種のアナーキーに基づいた社会が、「全ての権力を放棄する」ことを、「全てのものを共有する」ことを、祝宴をあげることを、踊り・歌いながら裸で走り回ることを出来るようになるのだろうか?
(訳注:ラブレーの『第一之書ガルガンチュワ物語』(制作年から言えば『第二之書パンタグリュエル物語』が先行する)の「第52章 ガルガンチュワが修道士ジャン・デ・ザントムールのためにテレームの僧院を建立させたこと」が初出である。テレームの僧院のくだりは、以下58章まで(つまり第一之書の終り)描写される。アナーキー大王のガルガンチュワが、配下の修道士に、戦争の褒賞として与えたのが、「テレームの僧院」であり、一種のユートピアが緻密な描写で語られている。第57章には、その基本コンセブトが語られている。
「彼らの生活はすべて、法令や定款或いは規則に従って送られたのではなく、皆の希望と自由意思とによって行われた。起きるのがよかろうと思われた時に、起床したし、そうしたいと思った時に、飲み、喰い、働き、眠った。誰に眼を醒まされることもなく、飲むにせよ食べるにせよ、その他何事を行うにつけても、誰かに強いられるということはなかった。そのようにガルガンチュワがきめたのである。一同の規則は、ただ、次の一項目だけだった。「欲することをなせ」」
もっともこれには、条件があり、教養も人格も兼ね備えた高貴な人々に限られるわけだ。訳者の渡辺一夫氏によると、「極めて理想主義的な性善説に立脚した貴族的な自然主義の主張」で、16世紀フランスへ、イタリアから流入してきた「ネオ・プラトニスム」の影響で、ラブレーのオリジナルとは言えないようだとのこと。)
この疑問は「第五権力」誌グループに特に関連している。その雑誌に捕まっていることは、その諸論文の中核に横たわっている原始人主義的・反テクノロジー的・反文化的なカルト宗教である。そして、「第五権力」誌の「アピール」は、アナキストが『魔法円を投げ、恍惚のトランス状態に入り、全ての権力を追い払う魔術を大いに楽しむ』ように勧誘しているのである--正確には、もう少し進歩した社会における僧侶どもは言うまでもなく、部族社会におけるシャーマンが、教主としての自分の立場を高めるために長年使い、自ら作りだした神秘から人間の精神を解き放つために理性が長く戦わなければならなかった魔術テクニックのことだ。『「全ての」権力を追い払う』?ここでもまた、フーコーの手ざわりがある。資本主義とヒエラルキーという正に現実の権力に対抗して、明確に権能を持った自己管理型制度を確立する必要性を--確かに、情欲と恍惚が真のリバータリアン共産主義で本当の達成を見出すことが出来るような社会の実現の必要性を--常に無視しているのである。
「第五権力」誌の「アナーキー」に対するごまかしの「恍惚的」賛歌は、余りにも社会的内容を欠いており--その技巧的雄弁の華やかな表現は全ておいておくとして--、粋なブティックの壁に張られたり、挨拶状の裏にプリントされるポスターとして簡単に現れうる。実際、最近ニューヨークを訪れた友人達が私に教えてくれたのだが、ローワー=イースト=サイドのセント=マークス=プレイスにある、リンネルでカバーされたテーブルがあり、メニューが結構高く、ヤッピーの常連客がいるレストラン--1960年代には闘争の場であった--はアナーキーという名前だったそうだ。この都市のプチブル飼育場は、有名なイタリア壁画「第四権力」のプリントを見せびらかしている。この壁画は、そこに描かれていないボスや多分警察署に対する暴動的な19世紀末の労働者の武装行進を示したものだ。ライフスタイル=アナキズムは優良消費者のひ弱さとなり得易いようだ。先に述べたレストランには警備員もいるという。多分、壁画に描かれている地域の最下層民を締め出しているのだろう。
安全で、私事中心主義的で、快楽主義的で、心地よくさえある、ライフスタイル=アナキズムは、臆病なラブレー主義者の陳腐なブルジョア生活様式を刺激するための巧妙な無駄口をたやすく与えてしまっているのかもしれない。MITが数年前に前衛プチブルを楽しませるために展示した「シチュアシオニストの芸術」のように、恐ろしく「邪悪な」アナキストのイメージ--多分、幻影--と同じ物を提示しているのである。丁度、アメリカの太平洋沿岸にそって繁栄している人々のように、東方を示しているのだ。一方、「恍惚産業」は、近代資本主義下で非常にうまくやっており、売り物になるお下劣イメージを大きくしようとライフスタイル=アナキストのテクニックをたやすく吸収できるだろう。その昔、長髪・髭・服装・性の自由・芸術とともにプチブルにショックを与えたカウンターカルチャーは、長い間、ブルジョア興行主に盗まれてきた。ブルジョア興行主のブティック・カフェ・クラブ・ヌーディスト=キャンプさえも、「ヴィレッジ=ヴォイス」誌などのような雑誌の新たな「恍惚」に対する多くの湯気の立つような広告を目撃して、華やかなビジネスを行っているのである。
実際、「第五権力」誌の粗暴な反理性主義的見解は、非常に問題のある示唆を含んでいる。想像力・恍惚・「原始性」に対するその感情的な称賛は、理性主義的効率性だけでなく、理性そのものをも明らかに攻撃している。1993年秋冬号の表紙は、フランシスコ=ゴヤの有名な誤解されている「カプリチョスNo.43」、「Il sueno de la razon produce monstros」(「理性の眠りは怪物を生み出す」)を使っている。ゴヤの寝ている絵は、アップル=コンピュータの前にある机の上に横倒しになって示されている。ゴヤの碑文の「第五権力」誌の英訳は「理性の夢は怪物を生み出す」であり、怪物は理性そのものの産物だということを意味している。事実はといえば、ゴヤは、彼自身のメモが示しているように、彫刻にあるモンスターは、理性の眠りによって生み出されたのであって、夢によってではない、ということをはっきりと意味していたのだった。彼自身のコメントに書いてあるように、『理性に見放された想像力は途方もない怪物を生み出す。理性と結合すれば、想像力は全ての芸術の母であり、芸術の驚異の源泉となる。』[10] 理性を軽視することで、この断続的なアナキスト雑誌は、今日の新ハイデッガー主義的反動の最も気味の悪い側面の幾つかとの共謀に参入しているのである。
反テクノロジー・反文明
さらに問題なのが、ジョージ=ブラッドフォード(別名デヴィッド=ワトソン)である。彼は、テクノロジー--明らかにテクノロジーそれ自体--の恐怖に関する、「第五権力」誌の主要理論家の一人である。社会関係がテクノロジーを決定するのではなく、テクノロジーが社会関係を決定するように思えるのだろう。社会生態学ではなく通俗的なマルクス主義に非常に近い概念である。『テクノロジーは孤立したプロジェクトでもなければ、技術的知識の集積ですらない』とブラッドフォードは「産業ヒドラの阻止」(Stopping the Industrial Hydra: SIH)の中で述べている。『「社会関係」の中の何らかの形で独立しているもっと根本的な領域が決定しているである。大規模技術は、ラングドン=ウィナーの言葉を借りれば、「その環境の」、従って大規模技術をもたらした正にその社会関係の、「再構成を、その操作条件が必要としている機構」となっている。大規模技術--初期の社会形態と古代の階級制度の産物--は現在、自己充足的生命を保ちながら、その技術を作り出していた諸条件よりも肥大化している。(中略)それらは、総論的にも各論的にも、一種の完全環境と社会システムを提供して、もしくは、そのものになってきているのである。(中略)こうした機械化されたピラミッドの中では(中略)道具の関係と社会の関係は同一なのだ。』[11]
この表層的な概念体系は、「どのように」テクノロジーが使われることになるのかを強硬に決定している資本主義の諸関係を回避し、テクノロジーがどう「ある」べきだと仮定されているのかに焦点を当てている。テクノロジーが「使われて」いる全く重要な生産プロセスを強調するのではなく、社会関係と根本ではない何かとを関連付けることでブラッドフォードは、機械と「大規模技術」に、テクノロジーに関するスターリン主義的仮説のように、最終的には反動の目的を果たすことになる神秘的自治権を与えているのである。テクノロジーがそれ自身の生命を持っているという考えは、ナチが自分たちの支離滅裂な反テクノロジー的イデオロギーをどれほど褒め称えていたにせよ、前世紀の保守的なドイツロマン主義と、国家社会主義イデオロギーに組み込まれたマルティン=ハイデッガーとフリードリッヒ=ゲオルグ=イェンガーの著作に深く根ざしているのである。
我々の時代の近代イデオロギーという観点で見れば、このイデオロギー上の手荷物は、現在ではよく見られる次のような主張に象徴されている。それは、新しく開発された自動機械が民衆に仕事を様々なやり方で課したり、民衆の搾取を強くしたりしているのだ、というものである。どちらも疑う余地のない事実だが、それはテクノロジーの進歩にではなく、「正確には資本主義の搾取という社会関係に」根を下ろしているのである。荒っぽく述べてみよう。「ダウンサイジング」は今日、機械によって行われているのではなく、労働に取って代わったり、もっと集中的に労働を搾取するために機械を「使ったり」している貪欲なブルジョアによってなされているのだ(原注)。実際、ブルジョアが「労働コスト」を削減するために使っている正にその機械こそが、理性的社会においては、もっと創造的で個人的に行う甲斐のある活動をするために必要な、情け容赦ない労苦から人間を解放してくれるであろう。
(原注:資本主義を機械と置き換えてしまうことは、つまり読者の注目をテクノロジーの使用を決定している全く重要な社会関係からテクノロジーそれ自体へと移すことは、前世紀と今世紀の反テクノロジー文献のほぼ全てに見られる。イェンガーが、『技術の進歩は一貫して仕事の総量を増加させ、これが、これまでのところ、何故失業が増大するのが、いつも機械労働の組織を危機や不安が脅かしている時なのか、の理由なのである。』と吟味している時、彼はこのジャンルのほぼ全ての著者を代弁しているのである。フリードリッヒ=ゲオルグ=イェンガー著、「テクノロジーの失敗」(シカゴ:Henry Regnery Company、1956)、7ページ参照。)
ブラッドフォードがハイデッガーやイェンガーに親しんでいるという証拠はないが、むしろ、彼のインスピレーションは、ラングドン=ウィナーとジャック=エリュールから引き出されているようだ。後者についてブラッドフォードは賛同的に引用している。『今日、社会の一貫性を作りだしているのは、テクノロジーの一貫性である(中略)テクノロジーはそれ自体で一手段であるだけでなく、諸手段の小宇宙--排他的かつ総合的という、Universumの元来の意味での--なのである。』(SIH、10ページより引用)
その最も有名な著書「テクノロジー社会」において、エリュールは、世界と世界に関する我々の思考方法とは道具と機械(「la technique」)を手本にしている、という粗雑なテーゼを打ち出していた。この「テクノロジー社会」がどのようにして出現したのかについていかなる社会的説明もなく、エリュールの本はいかなる希望も提供せずに終わっている。ましてや、「la technique」に完全に吸収されてしまうことから人間性を回復するためのいかなるアプローチも示していないのだ。実際、人間の欲求を満たすためにテクノロジーを利用しようとしている人道主義でさえも、彼の観点では、『テクノロジーの進化に影響を与える機会などを全く持たない偽善的な希望』へと還元されているのである[12] 。そして、それほど決定論的だとすれば、まさしくそうなのであり、世界観はその論理的帰結に従っていることになる。
だが、うれしいことにブラッドフォードは、我々に解決策を示している。『すぐにも機械を完全撤廃し始めるのだ』(SIH、10ページ)。そして、彼は文明との一切の妥協を許さずに、ある種のニューエイジ環境保護カルトによく見られる擬似神秘的・反文明的・反テクノロジー的決まり文句全てを基本的に繰り返している。近代文明は『諸力の母体』であり、そこには『商品関係・大規模コミュニケーション・都市化・大規模技術に加え、(中略)それらと連動し、それらに匹敵している原子力-サイバネティックスの状態』があり、これら全ては『地球規模のメガマシーン』へと一極集中しているというのである(SIH、20ページ)。彼は別なエッセイ「肥大した文明」(Civilization In Bulk: CIB)で、次のように述べている。『商品関係は』単なるこの『諸力の母体』の『一部』でしかない。文明は、『当初から労働者収容所』であり、『分厚く積み重なっているヒエラルキーの厳格なピラミッド』であり、『無機物の領域の莫大な拡大』であり、『火を盗んだプロメテウスから国際金融基金への直線的進展』であった『一機械』なのだ[13] 。したがって、ブラッドフォードは、モニカ=スジョー(Monica Sjoo)とバーバラ=モー(Barbara Mor)の馬鹿げた本「偉大なる宇宙の母:地球宗教の再発見」を批判しているのだが、それはその先祖返り主義的で回帰的な有神論のためではなく、著者らが「文明」という言葉に引用符をつけているからなのだ。つまり、『文明の条件全てに挑戦するのではなく、文明に対する代替観点や逆の観点の存在を仮定しているこの素晴らしい(!)本の傾向を反映している』(CIB、注23)実践だからなのだ。その文明との妥協にも関わらず、冥界の神々に基づく自分の領域が『素晴らしい』ということを拒否しようとしているのは、多分、これら二人の地球の母達ではなく、プロメテウスであろう。
メガマシーンの社会的効果に関するルイス=マンフォードの悲しみを引用せずに、メガマシーンについて述べることは、確実に、いかなるものであれ完全なものとはなり得ないだろう。実際、こうしたコメントが通常マンフォードの意図を誤って解釈しているということは注目に値する。マンフォードは、ブラッドフォードなどが我々に信じ込ませようとしているような反テクノロジー主義者ではなかったし、いかなる言葉の意味でも、彼の好みとして、ブラッドフォードの反文明的原始人主義に見出せるような神秘主義者ではなかった。この点について、私は、1972年頃にペンシルベニア大学で開かれた会議に参加して、一定時間、マンフォードの見解について本人と話をしたときの直接の私的知識から述べることが出来る。
しかし、マンフォードが『機械的手段』を『潜在的に理性的で人間的な目的達成の手段』[14] だと心の底から好ましく記述しているのを見るためには、「技術と文明」(Technics and Civilization: TAC)のような彼の著作をひもとくだけで良い。ブラッドフォード自身もそこから引用している。マンフォードは、読者に機械は人間から生じていることを繰り返し思い起こさせながら、機械は「人格の特定側面の投影」である、と強調している(TAC、317ページ)。実際、機械の最も重要な機能は、人身に及ぼす迷信のインパクトを払拭することなのだ。従って、
『過去、不合理で悪魔的な人生の側面が、それらが属していなかった領域をも侵食していた。ブラウニーではなくバクテリアが牛乳を腐らしめているということが発見され、空気冷却型モーターは魔女の帚よりも効果的な高速長距離移動法だと発見されたのは、一歩前進だった。(中略)科学と技術は我々の道徳心を強固にした。科学と技術は、その正なる厳しさと自制によって、(中略)子供じみた恐怖、子供っぽい推論、同様に子供っぽい主張に対する侮蔑を投げかけているのである。』(TAC、324ページ)
マンフォードの著作にあるこの主たるテーマは、我々の中の原始人主義者達によって頑なに無視されつづけている--特に、機械は、『共同思考と共同行為のテクニック』を促すという『莫大な貢献』をなしてきたという彼の信念が無視されているのだ。マンフォードは『機械の美的素晴らしさは、(中略)結局のところ、多分、この新しい社会的道具とのより繊細で理解しやすい交流を通じて、また、機械の慎重な文化的同化を通じて存在するに至るもっと客観的な人格を形成するであろう』(TAC、324ページ)とほめたたえることを躊躇してはいなかった。実際、『直接経験という生のデータとは区別して事実という中立的世界を創造するテクニックは、近代の分析科学の偉大なる総体的貢献だったのである』(TAC、361ページ)。
ブラッドフォードの明らかな原始人主義を共有することからは程遠く、マンフォードは、機械を完全に拒否している人々を鋭く批判し、彼は『絶対的な原始人への回帰』をメガマシーン自体の『神経症作用』と見なしていた(TAC、302ページ)。実際、大災害なのだ。『野蛮人による機械の単なる物理的破壊よりももっと破滅的なことは、我々の主要技術を達成せしめた共同思考プロセスと公正な研究を抑圧することで、人間の動機を無にしたり屈折させたりする野蛮人の脅威なのである』、と彼は非常に鋭い言葉で述べていた(TAC、302ページ)。そして、彼は次のように命じていた。『我々は、未開時代への逆戻りを馬鹿げているように見せることで、機械に抵抗するための無益で哀れな我々の誤魔化しを放棄しなければならない。』(TAC、319ページ)
彼の後年の著作も、彼がこの観点を緩めていたといういかなる証拠も示してはいない。皮肉なことに、彼は生活劇場のパフォーマンスと暴走族の『無法地帯』というヴィジョンを『野蛮な状態だ』と示し、『現在の俗物的で、規格化された、無個性の文化は何も恐れることはない』という観点から、ウッドストックを『大規模な学徒動員だ』と批判していたのだ(原注)。
(原注:ルイス=マンフォードは、「権力のペンタゴン」第二巻(ニューヨーク:Harcourt Brace Jovanovich、1970)で、挿絵13と26にこの説明を付けている。この二巻の書は、常に、テクノロジー・理性・科学に対する攻撃として読み誤られて来た。実際は、そのプロローグが示しているように、この書物は人間の労働力を--そう、社会関係をも--組織する一形態としてのメガマシーンを、科学とテクノロジーが達成したことと対比させているのである。マンフォードは通常科学とテクノロジーを賛美し、ブラッドフォードが見下しているまさにその社会文脈の中に科学とテクノロジーを置いていたのである。)
マンフォードは、彼自身の観点では、メガマシーンにも原始人主義(「有機的な」)にも賛成しておらず、それよりも、民主的で人間サイズの方向にそったテクノロジーの洗練を好ましいとしていた。『機械を「超える」(そして新たな統合へと向かう)我々の能力は、機械を「消化する」我々の力に依存している。』と彼は「技術と文明」の中で示していた。『我々が客観性・非人間性・中立性の教訓、つまり機械領域の教訓を「吸収する」まで、我々はもっと豊潤に有機的で、もっと深遠なる人間への発達をさらに押し進めることなど出来はしない』(TAC、363ページ、強調は筆者)。
テクノロジーと文明を、先天的に人間性の抑圧であると非難することは、実際、ある種の社会関係をベールで隠すことになる。その社会関係は、搾取される側に及ぼす特権を搾取者に与え、服従者に及ぼす特権を支配者に与えていることが多い。過去のいかなる抑圧的社会よりも、資本主義は、マルクスの「資本論」における用語を使えば「物神崇拝」の覆面の下にその搾取を覆い隠しているのである。結局、多種多様に--そして表面的に--シチュアシオニストによって「スペクタクル」へとそしてボードリヤールによって「幻影」へと編み込まれている「商品崇拝」なのである。ブルジョアが剰余価値を獲得することが、表向きにのみ平等な労働力の契約的賃金交換によって覆い隠されているように、商品崇拝とその運動は、資本主義の経済的社会的関係の優越性を覆い隠しているのである。
ここで、重要な、確かに重大な、ポイントを指摘しておかねばならない。こうした隠蔽工作は、民衆の目から、我々の時代の危機を生み出している資本主義競争の因果的役割を隠しているのだ。これらの神秘化に対して、反テクノロジー主義者と反文明主義者達は、テクノロジーと文明の神話を先天的に抑圧的だと付け加え、そこで、社会的関係を媒介し、我々の時代の技術-都市の風景を生み出している資本主義に特有の社会的関係--特に、物(商品、交換価値、モノ--お好みの言葉を使えばよかろう)の使用方法--を覆い隠しているのである。丁度、資本主義の「産業社会」というフレーズを使った言い換えが、近代社会を形作っている資本と商品の関係の特定的で一次的な役割を覆い隠しているように、社会関係の技術-都市文化という言い換えが、ブラッドフォードが明らかに従事しているところの、近代文化を形成している市場と競争の主要な役割を隠しているのである。
ライフスタイル=アナキズムは、主としてそれが社会ではなく「スタイル」に関わっているために、そのルーツを競争市場に持ち、生態破壊の源泉としての、資本主義の蓄積から目を背け、あたかも立ちすくんでいるかのようにして、「自然」と人間性の「神聖なる」もしくは「恍惚的な」統合の前提となる破壊を、そして科学・唯物論・「理性中心性(logocentricity)」による「世界の脱魔術化」を凝視しているのだ。
従って、今日の社会病理と私的病理の源泉を公開する代わりに、反テクノロジー主義は、我々が資本主義をテクノロジーともっともらしく挿げ替えることが出来るようにしているのである。それは基本的に成長と生態破壊の根底にある原因としての資本の蓄積と労働の搾取を「促している」のである。文明は、文化センターとしての都市に組み込まれているために、その理性的側面を剥奪されている。部族生活や村落生活の偏狭な制約とは全く正反対の位置に置かれることで、都市は、あたかも、人間の交際範囲を普遍化するための潜在的地域ではなく、弱まることのない癌となってしまったかのようだ。資本主義の搾取と支配という基本的社会関係は、社会的生態的危機の基本原因への民衆の洞察--権力・産業・富の大企業ブローカーを生み出している商品関係--をぼやかしながら、エゴと「la technique」に関する形而上学的な一般化によって隠されているのである。
だからといって、多くのテクノロジーが先天的に支配的で生態学的に危険であるということを否定したり、文明は純然たる天恵だと主張したりしているわけではない。核融合炉、大規模ダム、高度に中央集権化された産業複合体、工場システム、軍需産業は--官僚制度・都市の荒廃・近代メディアのように--ほぼそれらの始まりから非常に破滅的である。しかし、18世紀と19世紀には、北米の巨大エリアを氷解したり、その原住民族を実質的に滅亡させたり、全領域の土壌を破壊したりするために、スチームエンジンも、製造業も、また、このことに関して言えば、巨大都市と手の届かない官僚制度も必要なかったのだ。逆に、鉄道がその土地全体にしかれる前でさえ、この破壊の多くは単純な斧、黒色火薬のマスケット銃、馬車、すきの刃を使って既になされていたのだった。
ブルジョア事業--前世紀の文明の野蛮な側面--が、オハイオ川流域の多くを投機的な不動産へと切り開くのに使ったのは、これらの単純なテクノロジーであった。南米では、プランテーション所有者は、綿を植えたり摘んだりする機械が存在していなかったため、奴隷の「手」を数多く必要としていた。実際、アメリカの小作農業は過去二世代で消滅してしまった。それは、新しい機械が導入され、「自由にされた」黒人小作人の労働に取って代わったことに大きく依っていたのだった。19世紀には、半封建的な欧州から農夫が、川と運河を通って、アメリカの原生地帯へと流入し、抜きんでた反生態調和的方法を使って、穀物を生産し始め、結果的に北米資本主義を世界の経済的指導者へと押し進めたのだった。
乱暴に言ってしまおう。現代の爆発的な環境危機を生み出したのは資本主義--その歴史全体へと拡大した「商品」関係--だったのである。それは、エンジンではなく、風をその動力源としていた航海船に乗って全世界へと持ちこまれた初期の家内工業商品に始まったのだ。今日最も大きな不名誉に達している機械は、大規模手工業がその歴史的突破口をなしていた英国の織物村落や街から離れ、欧州と北米の多くの場所で資本主義が支配力を獲得してから長いことたった「後に」作りだされたのだ。
しかし、欧州文明の賛美からその大規模な中傷へと現在振り子が移っているにもかかわらず、我々は近代世俗主義・科学知識・普遍救済説(ユニヴァーサリズム)・理性・テクノロジーの勃興の重要性を思い起こすことがうまく出来るだろう。これらは「潜在的に」、社会の出来事の理性的で解放的な摂理という希望を提供しているのだ。実際、ラブレーのテレーム僧院で「ましな」貴族の食欲につけ込んだ多くの召使と職人達を抜きにして、情欲と恍惚とを十全に実現するためなのだ。皮肉なことに、今日の文明を侮蔑している「反」文明のアナキスト達は、それらを可能にした欧州の歴史における骨の折れる発展という感覚を持たずに、その文化的果実を享受し、リバティという拡大しやすく非常に個人主義的な専門分野を作り出している人々の仲間なのである。少なくともクロポトキンは、『近代技術の発展、それは生活必需品全ての生産を素晴らしく単純にしているのだ』[15] と明確に強調していた。歴史文脈の感覚を失った人々に対して、傲慢な後知恵はた易くやってくるのだ。
原始人の神話化
反テクノロジー主義と反文明主義の当然の帰結は、原始人主義である。有史以前のエデンの園的な賛美とその憶測の純潔に対する一種の回帰願望である(原注)。ブラッドフォードのようなライフスタイル=アナキストは、原住民族とエデンの園的な有史以前の神話からそのインスピレーションを導き出している。ブラッドフォードによれば原始民族は、『テクノロジーを拒絶していた。』原始民族は、『器械を用いる技術や実際的な技術の相対的重要性を最小限にし、(中略)恍惚的技術の重要性を拡大していた。』これは、原住民族が、物活論(アニミズム)という信仰を持ちながら、動物の生命と原生地帯の『愛』に満たされていたからだった。彼等にとっては、『動物・植物・自然の物体』は『「人間」であり、親類でさえ』あったのである(CIB、11ページ)。
(原注:我々に、我々のテクノロジーを顕著に、抜本的にさえも、減らすように忠告している人達は、同時に我々に、ありったけの論理をつくして、「石器時代」へ--少なくとも、(前期・中期・後期の)新石器時代や旧石器時代へ--戻るように忠告している。我々が「原始世界」へ戻ることなどできはしないという論法に対して、ブラッドフォードは、その論理ではなく、それを実際に述べている人々を攻撃している。『大企業の技術者と左翼やサンジカリストの資本主義批評家どもは、テクノロジー支配に関する自分達以外のいかなる見解をも(中略)「後戻り的」で、石器時代へ戻ろうとする「テクノ恐怖症的」願望だとして』簡単に片付けてしまっている、と彼は不満を述べている(CIB、脚注3)。ここでは、テクノロジーの進歩それ自体を望ましいとすることが、多分人間と人間以外の自然に対する、「支配」の拡大を望ましいとしていることを意味している、といういいかげんな噂はとりあえず脇に置いておこう。だが、「大企業の技術者ども」と「左翼やサンジカリストの資本主義批評家ども」は、確かに間違いなく、テクノロジーとその使用方法に対するその見解という点で、お互いに置換可能なのだ。「左翼やサンジカリストの資本主義批評家ども」が、資本主義に対する真面目な階級抵抗に賞賛に価するほど関与しているという事実を考えてみると、今日彼等が大きな労働運動の支持を得ることができていないことは、祝典の機会などではなく、喪に服すべき悲劇なのである。)
従って、ブラッドフォードは、有史以前の食糧探索文化の生活方法を「恐ろしく・獣のようで・放浪的な、血生臭い生存闘争」と決めつけている「公式的」見解に異論を唱えている。むしろ、彼は「原始世界」をマーシャル=サーリンが「本来の裕福な社会」と呼んだものとして崇拝している。
『裕福な、なぜならその必要物はほとんどなく、その欲望全ては簡単に達せられるからだ。その道具一式は洗練され軽く、その見解は言語学的に複雑で概念的に深遠だが単純で万人に接触可能である。その文化は発展性があり恍惚的である。所有制度がなく共有で、平等主義的で協働的である。(中略)無政府で、(中略)仕事をする必要もない。ダンスの社会であり、歌う社会であり、祝宴の社会であり、夢を見続ける社会なのである。』(CIB、10ページ)
ブラッドフォードによれば、「原始世界」の住民は、自然の世界と調和して生活しており、多くの余暇時間を含め、その裕福さの利益全てを享受していた。狩猟と採取は今日人々が一日八時間つぎ込んでいる労力よりも少なくてすむため、原始社会では『仕事をする必要がなかった』、と彼は強調している。彼は確かに、原始社会は『時折飢えを経験することができた』ことを情け深くも認めている。しかし、この「飢え」は非常に象徴的で、自ら課したものだった。なぜなら原始民族は『相互の密接な関係を促したり、遊んだり、ヴィジョンを見たりするために、時々(自らすすんで)飢えた』(CIB、10ページ)からだというのである。
この馬鹿げた戯言を論駁することはおろか、その戯言自体を整理するだけでも一本のエッセイが必要となるであろう。真理の数が少ない上に、全くの幻想とご茶混ぜになっていたり、覆われていたりするからである。ブラッドフォードの説明は、『より批判的な(中略)人類学』による『原始民族とその直系子孫の見解とのより多くの接触』に基づいているという(CIB、10ページ)。実際、彼の「批判的人類学」の多くは、1966年4月にシカゴ大学で開かれた「狩人としての人間」シンポジウムで提出された考えから導き出されているようだ[16] 。このシンポジウムに寄稿された論文の大部分は非常に価値があるものだったのだが、中には1960年代のカウンターカルチャーに浸透していた--そして現代まで長く患っている--「原始性」の素朴な神話化に従っていたものもあった。当時の多くの人類学者に影響を及ぼしていたヒッピー文化が断言していたことは、今日の狩猟採取民族は、他の世界で機能している社会・経済的諸力によって無視され続けているが、彼等は旧石器時代と新石器時代の生活方法の孤立したなごりとして、未だに太古の状態のままで生活している、ということだった。さらに、狩猟者・採取者として、彼等の生活は非常に健康で平和的であり、豊富な自然の恵みの上に今も昔も生活している、とも述べていた。
例えば、その会議の論文集を共同編集したリチャード=B=リーは、「原始」民族のカロリー摂取は非常に高く、一日数時間だけ探索するために必要だったある種の人跡未踏の「裕福さ」へと向かって進むことで、食物供給も豊富だった、と見積もっていた。『自然な状態の生活は、必ずしも、不潔で・残酷で・貧窮しているわけではない』とリーは書いている。例えば、カラハリ砂漠の!Kungブッシュマンの生息地域は、『自然に生じている食物が豊富にある。』ドーブ地域のブッシュマンは、リーによれば、現在でも新石器時代に入る寸前の状態にいる。
『ブッシュマン民族が公式に発見されていた範囲の中で最も生産性の低い地域に閉じ込められているにも関わらず、彼等は今日でさえ野生の植物と肉によって生活している。過去、彼等がアフリカ生息圏の中で最高の場所を選んでいた時代には、さらに実りある生計基盤がこうした狩猟採取生活者達の特徴となっていた見込みが高い。』[17]
そんなことはない!--以下で簡単に考察して見よう。
「原始生活」に夢中になっている人々は、誰も彼もが、あたかも原人と人類という全く異なる種族が、同種の社会組織で生活していたかのように、有史以前の数千年間を一括りにしてしまう。「有史以前」という言葉は、非常に不明確である。幾つかの異なる種を含めたヒト属に関して言えば、三万年ほど前のオーリニャック文化(南フランスオーリニャック周辺で発見された旧石器時代後期の文化)とマグダリニアン期(旧石器時代後期の最後)の食糧調達者達(「Homo sapiens sapiens」)の「見解」を、「Homo sapiens neanderthalensis」(ネアンデルタール人)や「Homo erectus」(直立原人)のそれと同等に扱うことなどできはしない。彼等の道具一式・芸術能力・会話能力は全く異なっていたのだ。
もう一つの問題は、様々な時代において有史以前の狩猟採取者や食糧探索者達は、どの程度、ヒエラルキーのない社会で生活していたのか、である。二万五千年ほど前のSungir(現在の東欧)墓地についていかなる推論をしても構わない(そして、その生活について我々に教えてくれる旧石器民族が我々の周りにいない)としても、二人の青年の墓跡から出土した膨大な宝石・槍・象牙の槍・ビーズの衣服のコレクションは、人類が食物耕作生活に定住するずっと前に身分の高い家族が存在していたことを示しているのだ。旧石器時代の大部分の文化は、多分比較的平等主義的なものだっただろうが、旧石器時代の平等主義に対するレトリックをちりばめた賛歌の下に包含されることなどできないほど著しい多種多様な程度・タイプ・範囲の支配と共に、ヒエラルキーは旧石器時代後期にすでに存在していたと思われる。
ここで生じるさらなる問題は、様々な時代におけるコミュニケーション能力の多様性--初期の場合、その欠如--である。書き言葉は有史時代になるまで見られなかったため、初期の「Homo sapiens sapiens」の言語でさえ、「概念的に深遠だった」わけではなかった。絵文字・象形文字、とどのつまりは過去の知識のために「原始」民族が頼っていた記憶手段は、明らかに文化的に制限されているのである。「概念的に深遠な」思考はともかく、世代の累積的知識を記録する文字知識なしには、歴史的記憶を保持することなど困難である。むしろ、それらは時間と共に失われ、甚だしく歪められてしまうのだ。とりわけ、口述で伝えられた歴史が厳しい批評対象となることは少なく、むしろ、エリート「予言者」やシャーマンの道具となってしまいやすいのである。こうした人々は、ブラッドフォードが呼んでいるような「詩人の原形」とは全く異なり、自分自身の社会利権を果たすためにその「知識」を使っていたように思われる。[18]
これらのことは、一貫して優れた反文明的原始人主義者ジョン=ザーザンの下へと我々を導く。「アナーキー:武装した欲望」誌(Anarchy: A Journal of Desire Armed)の一貫した寄稿者の一人であるザーザンにとって、話言葉・言語・書き言葉の欠如は積極的に評価すべき賜物なのである。「狩人としての人間」という時間の歪みのもう一人の住人であるザーザンは、その著書「未来の原始人」(Future Primitive: FP)の中で、『実際、家畜や農業以前の生活は、主として、レジャー・自然との親交・感覚的知恵・男女の平等・健康が一体となったものだった』という立場を堅持している[19] 。「狩人としての人間」との違いは、ザーザンの「原始性」のヴィジョンの方が四足動物に非常に近い、ということである。実際、ザーザン流の旧石器人類学では、「Homo sapiens」を一方とし、「Homo habilis」・「Homo erectus」・そして「ずっと有害になった」ネアンデルタール人を他方とした場合の双方の解剖学的区別は疑わしいとされる。初期の「Homo」(ヒト)諸種は全て、彼の観点では、「Homo sapiens」の精神的・肉体的能力を有しており、さらに二百万年以上にもわたって原始的喜悦の中で生活していたのだ。
これらのヒト科種族が現代人と同じ知性を有しているのなら、何故彼等はテクノロジーの革新を創造しなかったのだろう、と素朴に質問したくなってしまうことだろう。ザーザンは快活に次のように推論している。『狩猟採取者としての存在の成功と満足によって与えられた知性が、「進歩」の著しい欠如のその正なる理由なのだ。これが全くもって本当だと思われる。労働の分業・牧畜・記号文化--これらは明らかに(!)最近になるまで拒絶されていたのだった。』「ヒト」科種族は『長い間、文化よりも自然を「選んで」』おり、「文化」はザーザンにとって『基本的記号諸形式の操作』(強調は筆者)を意味している--邪魔者の締め出し(an alienating encumbrance)だ。実際、彼は次のように続けている。『知性が十全にそれらを行う能力を持っていたにも関わらず、時間・言語(この時代全体もしくはその大部分における、明らかに文字と、多分、話言葉も)・数字・芸術の具象化の余地などなかったのだ。』(FP、23ページ、24ページ)
とどのつまり、ヒト科種族は記号操作も、話すことも、ものを書くこともできたのだが、そうした能力に頼ることなく彼等はお互いに理解し合い、本能的にその環境を理解することができたため、慎重にそれらの能力を拒絶したというのである。従って、ザーザンは、とある人類学者が次のような瞑想をしているのにうんうんと肯いているわけだ。『サン・ブッシュマンの自然との霊的交渉』が到達していたのは、『神秘的と呼んでも良いほどの経験のレベルだった。例えば、彼等はゾウ・ライオン・アンテロープ(そしてバオバブの木でさえも)であるかのように実際に感じるということがどういうことなのかを知っていたように思われる。』(FP、33-34ページ)
言語・洗練された道具・俗事・労働の分業(多分彼等は一度やって見て不満の声をあげたのだろう、「ふん!」)を拒絶するという意識的「決定」をしたのは、「Homo habilis」(初めて道具を使った猿人)だったそうだ。ここで言っておかねばならないが、「Homo habilis」は、現代人のほぼ半分の大きさの脳しか持っておらず、多分明瞭な発音で話をする解剖学的能力を持っていなかったと思われる。しかし、我々はザーザンの並外れた権威によって、「habilis」(そして多分、大体「二百万年前」頃から存在しているのであろう「Australopithecus afarensis」(アウストラロピテクス)でさえも)は、これらの機能を「十全に行う知性」を持っていた--まさか!--のだがそれらを使うことを拒否していたのだ、と叱られてしまうのだ。ザーザン主義の旧石器人類学では、初期のヒト科種族や人間は、崇高な知恵を使った発話のような極めて重要な文化的特性を採用することも拒否することもできたことになっている。修道僧が沈黙の誓いを立てるようなものだ。
しかし、一度その沈黙の誓いが破られた時から、「全て」がおかしくなってしまったのだ!神とザーザンしか知らない何らかの理由で、
『記号文化の出現は、操作と支配というその「先天的な」意思と共に、すぐに自然の家畜化への扉を開けてしまった。自然の領域内で他の野生種族と調和していた二百万年の人間生活の後に、農業が我々のライフスタイルを、我々の「適応」の仕方を前例のないやり方で変えてしまったのだ。それまでこのようなラジカルな変化が、一種族の中でこれほどまでに徹底的でこれほどまでに急速に起こったことはなかった。(中略)言語・習慣・芸術を通じた自己の家畜化は、その後動植物の飼い馴らしを「刺激した」のだ。』(FP、27-28ページ、強調は筆者)
このはったりには、真に目を引くほどの一種の見事さがある。明らかに異なる時代・ヒト科種族とヒト諸種・生態学的状況とテクノロジーの状況が全て一まとめに、「自然の領域内での」共有生活へと掃き集められてしまっている。人間と非人間的自然との非常に複雑な弁証法的対立のザーザンによる単純化は、その前に畏敬の念を持って立たねばならないほど、余りにも還元主義的で余りにも単純化しすぎなメンタリティを示している。
確かに、我々は非常に多くのことを、特に「人間の本質」とよく呼ばれていることの無常性について、石器時代の文化--拙著「自由の生態学」の中で私は有機的社会と呼んでいる--から学ぶことができる。彼等の集団内の協働精神、そして最も優れている場合には、その平等主義的見解は、驚嘆に価する--彼等が生活していた不安定な世界からすれば社会的に必要なことだった--だけでなく、競争と貪欲が本質的人間特性であるという神話とは逆の、人間行動の順応性の有無を言わさぬ証拠を提示しているのである。実際、彼等の用益権の実践と平等者の不平等は、生態調和社会に大きく関連している。
だが、まさにその「原始的」もしくは有史以前の民族は、非人間的自然が良くて猫かぶり、最悪の場合完全に腹黒いものだと「崇めていた」のだ。村落・街・都市といった「不自然な」環境がなくとも、「生息地」とは区別されるようなまさにその「自然」という観念はなおも「概念化」されねばならなかったのだ--ザーザンの観点では真に締め出しの経験である。我々の遠い祖先が、歴史文化の人々がしたほどにも道具的ではなく自然の世界を見ていたという見込みもない。彼等自身の物質的関心--生存と幸福--への当然の配慮と共に、有史以前の民族は、出来るだけ多くの獲物を追いつめていたと思われ、もし彼等が擬人的属性を持って動物の世界を想像力で満たしていたなら、また確かにそうだったのだが、それは、動物の世界を単に崇拝する目的だけでなく、それを操作する目的を持ってそれとコミュニケーションをとろうとしてのことだったのだろう。
従って、この非常に道具的な目的を心に、彼等は「話をする」動物達・動物の「部族」(彼等自身の社会構造を摸していることが多かった)・返事をしてくれる動物の「魂」を出現させていたのだった。当然、その知識は限定的なものであったため、彼らは夢を現実だと信じていた。夢の中では、人間は空を飛ぶかもしれないし、動物が話をするかもしれない。不可解な、恐ろしいことも多い夢の世界を彼等は現実だと見なしていた。獲物たる動物を支配する・生息地を生存目的で使用する・天候の移り変わりに対処する・こうしたことなどを行うために、有史以前の民族は、直接的にであれ儀式的にであれ比喩的にであれ、『これらの事象を擬人化し、彼等に「話しかけ」』ねばならなかったのだ。
実際は、有史以前の民族は、出来るだけ断固たる態度でその環境に介入しようとしていたのではないだろうか。例えば、「Homo erectus」以後のヒト諸種は、火の使用を学習するやいなや、多分獲物を崖の上や食肉処理し易い自然の袋小路へと追い込むために、火を使って森を焼き払ったのではないだろうか。有史以前の民族の「生命崇拝」は、従って、動物・植物・山々(悪魔的かつ慈悲深い神々の大きな家だとして恐れていた可能性は高い)に対する愛情ではなく、食物供給を促し制御するための非常に実際的な関心事の現れだったのだ[20] 。
ブラッドフォードが「原始社会」の行為としている「自然の愛」も、今日の食糧探索民族を正確に描写しているわけではない。むしろ彼等は仕事と獲物を残忍に扱うことが多いのである。例えば、イチュリの森のピグミー族は罠にかかった獲物を非常にサディスティックに苦しめており、エスキモー族はそのハスキー犬を酷使することが普通であった[21] 。欧州人と接触する前のアメリカ原住民族について言えば、食物を栽培し、狩りの時に獲物を見つけ易くするために火を使って土地を一掃することで、欧州人が出会った『パラダイス』が『明らかに人間らしく』されていたほどにまで、大陸の多くの部分を大規模に変貌させたのであった[22] 。
多くのインディアン部族がその場にいる食用動物を激減させ、物質的生活手段を得るために新たなテリトリーへと移動しなければならなかったように思えるのは止むを得まい。実際、彼等が元々からそこにいる部族を追い出すために戦争を起こさなかったとすれば、それは驚くべきことである。彼等の遠い祖先は、氷河紀後期の北米の巨大ほ乳類数種(特に、マンモス・マストドン・長角バイソン・馬・ラクダを)を絶滅せしめたのかも知れない。厚く堆積しているバイソンの骨は、大量殺戮と北米の通常は水のない狭い水路の多くでの「流れ作業」的畜殺を示している場所で今でも発見されている[23] 。
また、農業をしていた民族では、土地の使用は必ずしも生態学的に優しいものではなかった。スペイン人の征服以前の中央メキシコ高原のパツクアロ湖周辺では、『有史以前の土地利用は実際には環境保護主義者のそれのようではなく』、高率の土壌腐蝕を引き起こしていた、とカール=W=バッツアーは書いている。実際、原住民族の農業実践は『旧世界における前産業社会的土地利用と同じぐらい害を与える類のものだった可能性がある』のだ[24] 。森林の過剰削減と持続可能な農業をできなかったことは、マヤ人社会の土台を徐々に崩し、その崩壊に寄与していた、と示している研究もある[25] 。
今日の食糧探索諸文化の生活様式が祖先のそれを正確に反映しているかどうかを知ることなど我々にはできないであろう(原注)。近代原住民俗文化は何前年もの間に発展して来ただけでなく、西洋研究者の研究以前から、他文化からの数え切れないほどの特性の流布によって、明らかに変貌していたのだった。実際、クリフォード=ジーツがどちらかといえば刺々しく述べていたのだが、近代原始人主義者が初期の人間性と関連づけている原始民族文化には原始時代的なところなど、全くとは言えないにせよ、ほとんどないのだ。『(現存原住民族の太古の原始性は)ピグミーにおいても、エスキモーにおいてもそれほどのものではないということ、こうした民族は実際には、彼等を現在の彼等にせしめ、そしてそのようにせしめ続けている大規模な社会変化過程の産物なのだということを、しぶしぶながらも、おそまきながらも実感することは、(民族学という)分野に本質的な危機を導く何らかの衝撃として生じてきている。』[26] 多くの「原始」民族は、彼等が住んでいた森林同様、「ダンス=ウィズ=ウルヴズ」で全く逆の描き方をされている北米南北戦争時にラコタ=インディアンがそうだったよりも、欧州人が接して来た時に既に「無垢」などではなかったのだ。非常に客引き的な現存原住民族の「原始的」信仰システムの多くには、明らかにキリスト教の影響が見られる。例えば、ブラック=エルクは熱心なカトリックだった[27] し、十九世紀後半のパイウート族とラコタ族の交霊ダンスは、キリスト教の福音伝導主義的至福千年説(キリストが再臨して地上を統治するという千年間)信仰に深く影響を受けていたのだ。
(原注:L=スーザン=ブラウンによって、私の『ヒエラルキーの全くない「有機的」社会の「証拠」には、議論の余地がある』(160ページ、強調は筆者)と再び述べられるのも奇妙なことだ。もし、『男女の調和と完全なる平等』は、現存の『人類学的証拠』を元に一貫して証明することが出来る、とか、『性別による労働分業』は、必ずしも『男女の平等と両立』しているわけではないと主張することが、ブラウンが引用しているマージョリー=コーエンによって『説得力のないこと』だとされるのなら、私が言いえることはただ一つ、よかろう!である。彼等は周りにいて我々に話しをしてくれてもいなければ、ましてや何かについて「説得力ある」証拠を提示してくれているわけでもないのだ。同じことが、私が「自由の生態学」で示していた男女の関係についても言うことができる。実際、「男女の調和」に関する現代「人類学の証拠」全ては、近代人類学者が原住民族を調査するずっと以前に欧州文化によって、良かれ悪しかれ、条件調節させられていたのだ。
あの本で私が示そうとしていたことは、男女の平等と不平等の「弁証法」だったのであり、有史以前に関する決定的説明--ブラウン・コーエン・私自身が永遠に絶対手に入れることができない知識--ではなかった。私は近代データを思弁的に使ったのだ。ブラウンがいかなる種類の支持データもない二つの文章で軽率にも簡単に片付けていた、私の結論が「理性的」だと示すためにである。
「どの様にして」階級制度が生じたのかに関する私の主張に「証拠」がないとしたブラウンの主張について言えば、中央アメリカに関する最近の文献は、マヤ文明の絵文字の解読に従い、ヒエラルキーの出現に関する私の再現像を立証している。最後に、私がその優位性は多分ヒエラルキーの初期形態であろうと主張している元老政治についても、人類学文献に記述されている中で最も普及したヒエラルキー発展の一つなのである。)
真面目な人類学研究では、「恍惚的で」太古の狩人という概念は、「狩人としての人間」シンポジウム以来三十年と残ってはいない。「原始的裕福さ」という神話の狂信的帰依者によって引用されている「裕福な狩人」社会の大部分は、園芸的な社会システムから--多分彼らの願望に全く反して--文字通り発展したのだった。カラハリ砂漠のサン民族は、砂漠に追いやられる前には園芸者だったと現在では知られている。エドウィン=ウィルムセンによれば、数百年前には、サン語を話す民族は集団で農業をしていたそうだ。彼らがインド洋にまで拡大したネットワークの中で近隣の農業支配権を交換し合っていたことは言うまでもない。その遺跡は、西暦千年までに、彼等の領域であるドーブは、陶器を造り・鉄を使い・牛の群れを連れていた人々であふれていたことを示している。1840年までにそれらと共に欧州へ輸出されたのは膨大な量の象牙だった。象牙の大部分は、サン民族自身が狩り立てたゾウからのものであり、彼等は疑いもなく厚皮動物という「兄弟」の大量虐殺を、ザーザンが彼等に帰属させている非常に大きな感受性を持って行ったのだった。1960年代の研究者を非常に魅了したサン民族の二次的な食糧探索的生活様式は、実際には、19世紀後半の経済変化の結果なのだ。その一方で、『外からの観察者が想像していたそっけなさは(中略)在来のものではなく、商業資本の崩壊によって作り出されたのだった。』[28] 従って、『アフリカ経済の辺境部にいる現在のサン語を話す民族の状態は』とウィルムセンは次のように記している。
『植民地時代の社会政策・経済・その余波という点だけで説明することができる。彼らが食糧探索者だと見なされているのは、現在の千年期以前に始まり今世紀初頭の数十年で頂点に達した歴史的諸過程の外で遊んでいる最下級階層へ彼らが追放されたためなのである。』[29]
アマゾンのユークィ族も、1960年代に誉めたたえられた太古の食糧探索社会の縮図にた易くなってしまい得る。1950年代まで欧州人に研究されていなかったこの民族はイノシシの鉤づめと弓矢程度の道具一式しか持っていなかった。彼等を研究したアリン=M=スティアーマンは書いている。『火を起こすこともできなかったことに加え、船舶も・家畜(犬でさえ)も・石材も・儀式の専門家も持っておらず、ただ初歩的な宇宙哲学を持っていたにすぎなかった。彼等は放浪者として生涯を暮らし、彼等の食糧探索技能が与えてくれる獲物などの食物を捜してボリヴィア低地の森をさまよっていたのである。』[30] 彼等は、作物を育てることなど全くしなかったし、魚を取るために鉤と糸を使う経験もなかったのだ。
しかし、平等主義者からは程遠く、ユークィ族は、その社会を特権的エリート階級と軽蔑対象の労働奴隷集団とに分けて、世襲的奴隷制度を維持していた。この特徴は現在では昔の園芸的生活方式の名残だと見なされている。ユークィ族は奴隷所有していた前コロンビア期社会の子孫であると思われ、『時間とともに彼らは文化剥奪を経験し、移動しやすくあり続け、土地を食い物にしていく為の必要物となっていた文化的伝統の多くを失っていった。しかし、彼らの文化の多くの要素は失われていったかもしれないが、残ったものもあった。奴隷制度は、明らかにそれらの内の一つだったのだ。』[31]
「太古の」食糧探索者たちという神話が粉々に崩れ去っただけでなく、「裕福な」食糧探索者たちのカロリー摂取に関するリチャード=リー自身のデータも、ウィルムセンとその共同研究者によって重大に問題視されている[32] 。!Kung民族の平均寿命は大体五十歳だった。乳幼児死亡率は高く、ウィルムセンによれば(ブラッドフォードには申し訳ないが!)、この民族は収穫の少ない季節には病気と飢餓に襲われていたのだった。(リー自身はこの根拠に関する観点を1960年代以来変えて来ている)
同時に、初期の我々の祖先の生活が喜びに満ちたものなどではなかったことはほぼ確実である。事実、彼等にとって人生とは、実際全く残忍で、一般に短命で、物質的に非常に厳しいものだった。彼等の寿命に関する解剖学的調査結果によれば、半数が幼児期もしくは二十歳前に死んでおり、五十年以上生きていたものはほとんどいなかったという(原注)。彼等は狩猟採取者というよりも死体漁りだった可能性が高く、多分ヒョウやハイエナの餌食となっていたことだろう[33] 。
(原注:このぞっとするような統計については、コリーン=シェア=ウッドの「人間の病気と健康:生物文化的観点」(パロ=アルト、カリフォルニア:Mayfield Publishing Co.、1979)の17ページ~23ページを参照して頂きたい。ネアンデルタール人--ザーザンが主張していたように「有害な」民族だったことからは程遠く、最近では素晴らしい民族だったとの批評を受けている--については、クリストファー=ストリンガーとクライヴ=ギャンブルの「ネアンデルタール人を求めて」(ニューヨーク:Thames and Hudson、1993)において寛大に扱われている。しかし、これらの著者達の結論は次のようなものだった。『ネアンデルタール人が送っていた酷い生活とそれによって生じた肉体の消耗について我々が知っていることを鑑みれば、彼等に変質性関節疾患が多く見られることは驚くべきことではないだろう。しかし、重大な怪我が多かったことの方がもっと驚くべきことであり、それは、ネアンデルタール人社会における「老年」に達していなかった人々にとってさえ、どれほどその生活が危険に満ちていたかを示しているのである。』(94ページ~95ページ)
有史以前の人々の中には、疑いもなく、八千年前ごろにフロリダの湿地帯にいた食糧探索者達のように、70歳代まで生きていた人達もいたが、それらは非常に希な例外なのである。しかし、最後まで頑張った原始人だけがこうした例外を手に入れ、その例外をルールにしてしまったのだろう。あぁ、その通りだ--文明下にいる大部分の人間にとってこれらの状況は酷いものである。しかし、文明には制限のない喜び・御馳走・愛が莫大に見られると主張しようとする人がはたしているだろうか?)
有史以前とその後の食糧探索民族は、自身の集団・部族・一族の成員に対しては、通常、協働的で平和的であった。しかし、他の集団・部族・一族の成員に対して、彼等は好戦的であることが多く、彼等の財産を奪い、土地を盗もうとして大量虐殺を行うことさえあった。先祖の中でも最も至福に満ちていた、例の(もし我々が原始人主義者を信じるのであれば)「Homo erectus」は、ポール=ジャンセンズがまとめたデータによれば、人間同士の虐殺という荒涼たる記録を後世に残している[34] 。中国とジャワ島の多くの人々は火山の噴火によって死んでいたとされているが、ジャワ島において、致命傷を負った頭部が切り落とされていた四十人の死体に関しては、その説明のもっともらしさはない--『火山のせいなどでは決してない』とコリーン=シェア=ウッドは冷淡に述べている[35] 。近代の食糧探索民族について言えば、アメリカ原住民部族間の闘争は余りにも多すぎて如何に膨大な長さで引用してもしきれないほどである--北米南西部におけるアナサジ族とその近隣部族、そして、モヒカン族とヒューロン族間の情け容赦ない闘争について見てみれば、前者の諸部族は最終的にイロクォイ同盟(この同盟それ自体は、作らなければお互いに撲滅しあうことになりかねなかったため、生存のためのものだった)を作らざるをえず、後者の場合、ヒューロン族をほぼ全滅させ、残ったヒューロン族諸部落も追放することになってしまったのだ。
ブラッドフォードが断言しているように有史以前の民族の「欲望が簡単に達せられる」とすれば、それは正確には、彼等の生活の物質的条件--ひいては彼等の欲望--が非常にシンプルだったからだったのだ。このことは、大規模に「革新している」のではなく「適応している」、自身の欲求に合わせてその生息地を「変えている」のではなく与えられた生息地に「順応している」いかなる生活形態についても言えるだろう。確かに、初期の人類は生息場所について優れた理解をしていた。結局、彼等は知的水準の高い、想像的な人々だったのかもしれない。だが、彼等の「恍惚的な」文化は、不可避的に、喜びと「歌い、祝宴をあげ、夢を見る」ことによってだけでなく、迷信と操作され易い恐怖とによって満たされていたのだ。
我々の遠い先祖も現存原住民族も、現代の原始人主義者達によって彼等に帰されている「魔術化された」ディズニーランド的考えを持っていたなら、生存し続けることなどできなかっただろう。確かに、欧州人は原住民族にいかなる荘厳な社会的施しをも与えてはいなかった。全く逆であった。帝国主義者は土着民族に、甚だしい搾取・徹底的な大量虐殺・彼等が免疫を持っていない病気・恥知らずの略奪をもたらしたのだった。いかなるアニミズム的呪いも、この襲撃を防げなかったし防ぐこともできなかったのだ。銃弾を防ぐとされた幽霊シャツの神話に全く痛々しく裏切られてしまった、1890年のウーンデッド=ニーの悲劇のように。
決定的に重要なことは、ライフスタイル=アナキストが持つ原始人主義への回帰は、種としての人間性が持つ最も顕著な特徴と、欧米文明が潜在的に持っている解放的な側面を無視している、ということである。人間が他の動物と大きく異なっているのは、周囲の世界の単なる「適応」以上のことをしている点である。人間は世界を「革新」し、新世界を創り出すのである。人間としての自身の諸力を発見するだけでなく、個々人としても種としても発達するために、もっと適した世界を自分達の周りに創り出すのだ。現在の不合理な社会によってこの能力が歪められてはいるが、世界を変える能力は天分であり、人間の生物学的進化の賜物--テクノロジー・理性・文明の単なる産物ではなく--なのである。自身をアナキストと呼んでいる例の人々こそ、適応性と受動性というむき出しのメッセージを持った人間動物説に近接し、革命的思想・理想・実践を持つ数世紀を汚し、教区制度・神秘主義・迷信から自身を解放して世界を変えようとなされた人間性の記憶されるべき努力を中傷している原始人主義を進歩させるべきなのだ。
ライフスタイル=アナキストにとって、特に反文明的で原始人主義的ジャンルにとって、歴史それ自体は全ての区別・和解・発展段階・社会的特性を吸収する下劣な一枚岩(モノリス)となっている。資本主義とその矛盾点は、全てをむさぼり食らう文明と、ニュアンスも区別もないテクノロジー的至上命令の付随現象へと還元されている。我々が歴史を人間性の「理性的」要素--自由・自己意識・協働へと「発展している」潜在可能性--の開花として捉えている限り、歴史は人間の感受性・制度・知性・知識の教化の複合的説明、もしくは以前ならば「人間性の教育」と呼ばれていたことなのである。ザーザン・ブラッドフォード・彼等のお仲間が程度の差こそあれマルティン=ハイデッガーのそれと非常によく似たやり方で行っているように、歴史を、人間動物説的「信憑性」からの一貫した「転落」だとして扱うことは、人間発展の時代を特徴づけている自由・個性・自己意識という発展している諸理想--これらの目的を達成するための拡大しつづける革命的闘争は言うまでもなく--を無視することなのである。
反文明的ライフスタイル=アナキズムは、二十世紀の終わり数十年間を特徴づけている社会的堕落の単なる一側面でしかない。資本主義が、自然史をより単純でそれほど細分化されていない地理学的動物学的時代へと戻してしまうことで、自然史の解明に脅威を与えているように、反文明的ライフスタイル=アナキズムは、未発達で曖昧な、人間堕落以前の世界--人間性が「神の恩寵からの転落」以前に存在していた「罪のない」前テクノロジー・前文明社会--へと人間の魂とその歴史を引き戻すという点で、資本主義と共犯関係にある。ホメーロスの「オデッセイア」に描かれているロートスの実を食べた人達のように、人間が「真正」なのは、過去も未来もない--記憶や観念形成に煩わされることもなく、伝統もなく、生成によって挑戦されることもない--永遠の現在に生きている時だというわけだ。
皮肉なことに、原始人主義者が理想化している社会は、実際には、マックス=シュチルナーの個人主義後継者達が誉めたたえているラジカルな個人主義を排除してしまうだろう。近代の「原始」部落は強力に描き出された個々人を生み出しているが、習慣の力と集団としての高い連帯性がその厳しい諸条件によって促されているため、エゴの優越性を賞賛しているシュチルナー主義アナキストが要求している類の発展性のある個人主義的行動の余地をほとんど許してはいない。今日、原始人主義に遊び半分で手を出すことは、正しくは、裕福な都会人の特権なのだ。彼等は、飢えている人々・貧乏人・都市の路上に住まざるをえない「放浪生活者」だけでなく、働き過ぎの労働者にも許されていない空想のおもちゃを買うことができるのだ。子持ちで働いている現代女性は、どれほど最小限であったにせよ、日常的な家事から解放される--家計収入の大部分を得るため仕事に行く前に--ために、洗濯機なしではやっていけないだろう。皮肉なことに、「第五権力」誌を出しているコレクティブでさえ、コンピュータなしではやって行けなくなったことが分かり、それを「無理矢理」買わざるをえなくなってしまい、不誠実な否認を述べていたのだった。『ムカつく!』[36] 。反テクノロジー的文章を作るために最新テクノロジーを使いながら、そのテクノロジーを非難することは不誠実なだけでなく、信心ぶった様相をも持っている。こうしたコンピュータへの「ムカつき」は、日曜礼拝の時に、御馳走で腹を膨らませながら、清貧の美徳を誉めそやしている特権階級のげっぷにしか見えないのだ。
ライフスタイル=アナキズムの評価
今日のライフスタイル=アナキズムにおいて最も強く目を引くことは、精神と現実との素朴な一対一関係に対する思索ではなく、「即時性」への貪欲さである。この即時性は、微妙なニュアンスを持つ媒介された思索の要求をリバータリアン思想から引きはがしているだけでなく、理性的分析と、このことに関して言えば、理性それ自体を排除しているのである。人間性を非時間的・非空間的・非歴史的なこと--「自然」の「永遠な」サイクルに基づいた一時性という「原始的」概念--に委ねながら、それによって、精神からその創造的唯一性と、自然界に介入するその自由とを剥ぎ取ってしまっているのだ。
原始人主義ライフスタイル=アナキズムの立場では、人間が最善の状態にいるのは、非人間的自然に介入するのではなく適応している時か、理性・テクノロジー・文明・話言葉さえからも解放されて、直感的で本質的に無分別な「恍惚的」条件において、多分「自然の権利」を付与されながら、既存の現実との穏やかな「調和」の中で生活しているときなのである。「TAZ」・「第五権力」・「アナーキー:武装した欲望」・マイケル=ウィリアムズのシュチルナー主義「デモリション=ダービー」のようなルンペン的「ファンジン」--これら全ては、媒介がなく、歴史を無視し、我々がそこから「転落し」てしまった反文明的な「原始性」、つまり、「自然の領域」、「自然法」、もしくは我々の激烈なエゴによって様々な形で導かれていた完全性と「確実性」の状態、に焦点を当てている。歴史と文明は、「産業社会」という不確実性への転落以外の何物でもないというわけだ。
すでに示した様に、「確実性からの転落」というこの神話は、反動的浪漫主義にその根を持っている。最近では、volkisch(民族的)な「観念論」というマルティン=ハイデッガーの哲学に見られ、その著書「存在と時間」には潜在的で、その後のファシスト的著作に顕在している。現在ではこの観点は、ディープ=エコロジストが提起しているエコロジー観念論と「自己達成」の非政治的探求の中で、「グリーン=アドルフ」による「救済」へのむき出しの欺瞞的なアピールと共に、ルドルフ=バーロの反民主主義的著作にたっぷりと描かれている寂静主義的神秘主義を育んでいるのだ。
最終的に、個人のエゴは、歴史と生成・民主主義と責任を排除することで、現実性の最高寺院となる。確かに、社会それ自体との生身の接触は、ナルシシズムによって希薄なものにされている。そのナルシシズムは、余りにも全てのものを包容しすぎて、多極共存関係(コンソシエーション)を、それ自身の満足を求めて金切り声の要求と主張でしかない幼児化されたエゴへとしなびさせているのだ。解放の究極的充足として具象化されると、文明は単にエゴの欲望の恍惚的自己実現を妨害しているだけだというのだ。あたかも、恍惚と欲望とは教養と歴史的発展の産物ではなく、社会を剥奪された世界でab novoとして現われている単なる内的衝動であるかのように 。
プチブルのシュチルナー主義エゴ同様、原始人主義ライフスタイル=アナキズムは、社会制度・政治組織・革命プログラムの余地を許していない。我々が検証してきた著者たちが皆自動的に治国策と公的領域を同一視していることも言うまでもなかろう。「ファンジン」やパンフレットを発行すること--もしくは、ゴミ箱に火をつけること--は別として、散発的・非体系的・支離滅裂・断続的・直感的なものが、一貫した・目的的・体系的・理性的なものに、実際、持続的で焦点の定まったいかなる形態の活動にも、取って代わっているのだ。想像力は、理性と理論的一貫性への願望に対立させられる。まるでお互いにラジカルな矛盾にあるかのようだ。理性のない想像力は怪物を生み出すというゴヤの警告は、想像力が、微妙なニュアンスを持たない「一体性」との媒介のない経験で、よりよく活躍するかのような印象を残すように変えられる。つまり、社会的自然が生物学的自然へ、革新的人間性が適応的動物性へ、一時性が前文明的永遠性へ、歴史が古臭い周期性へと抜本的に解消されているのである。
その経済的荒っぽさが一日毎に硬直し愚鈍になっているブルジョアの現実性は、ライフスタイル=アナキズムによって、放縦・未完成・無秩序・支離滅裂へと抜け目なく突然変異させられている。1960年代には、シチュアシオニストは、「スペクタクル理論」という名の下に、実際に、理論の具現化されたスペクタクルを生み出していたが、彼等は少なくとも、労働者評議会のような組織的調整策を提示し、自分達の審美主義に何かしらの重みを与えていた。ライフスタイル=アナキズムは、組織・実行プログラムとの関与・真面目な社会分析を攻撃することで、運動を起す計画に執着することなく、シチュアシオニズム的審美主義の最悪の側面を猿真似しているのだ。1960年代の破片として、エゴの領域(ザーザンによって「自然の領域」と名前を変えられた)の中で目的もなくうろうろし、ボヘミアン的支離滅裂さを美徳としているのである。
最も問題なのは、ライフスタイル=アナキズムの放縦で審美的な気まぐれが、以前は、社会的関連性を主張し、解放への非妥協的コミットメント--主観の領域で、歴史の「外」ではなく、客観の領域で、歴史の「中」で--に正確に重きをおいていた左翼-リバータリアン=イデオロギーの社会主義的中核を重大に蝕んでいるということだ。第一インターナショナルの偉大なる叫び--それはマルクスとその支持者がそれを放棄した後でもアナルコサンジカリズムと無政府共産主義が維持し続けていた--は次の要求だった:「義務のない権利はなく、権利のない義務もない。」数世代にわたって、このスローガンは我々が今では回顧的に「社会的」アナキズム雑誌と呼ばねばならなくなってしまったものの発行人欄を飾っていた。今日、それは、基本的にエゴ中心的な「武装された欲望」の要求・道教の瞑想・仏教の涅槃と対立関係にあるとされている。社会的アナキズムが民衆に革命を惹起し、「社会」の再構築を求めるように呼びかけていた場所で、現在では、ライフスタイル=アナキズムのサブカルチャー世界の住人である怒れるプチブルが、一時的な叛乱と、ドゥルーズとガタリの専門用語を使えば「欲望機械」の満足を要求しているのである。
社会闘争に対する古典的アナキズムの歴史的コミットメント(単に本能的なものだけではなく、全ての次元における自己実現と願望充足が達成不可能だとすることのない)から一貫して退却すれば、必ずや経験と現実の破滅的神話化が伴うことになる。ほとんど物神崇拝的に解放の所在地と同一視されたエゴは、明らかに、自由競争主義的個人主義の「主権者の個人」と同じだと判明する。その社会的拠り所から切り離されることで、エゴは自律ではなく、プチブル事業の他律的「自己性」を確立するのである。
実際、自由であることから程遠く、その主権者の自己性のエゴは、酷く拘束され、見た目では何の特徴もないような市場法則--競争と搾取の法則--に手足を拘束されているのだ。その市場法則は、個人の自由という神話をもう一つの物神崇拝にし、資本の蓄積という執念深い法則を覆い隠しているのである。その従者は株式市場の動きほども、価格変動やブルジョア貿易の世俗的事実ほどにも「自律して」はいない。誰もが自律を主張しているにも関わらず、この中流階級の「反抗」は、投石用の煉瓦を手にしていようといまいと、食物共同組合から地方の共同体まで、「近代社会生活の中で「自由だ」とされている領域全てを支配している秘密市場の力に完全にとらわれているのだ。」
資本主義は我々の周りに--物質的だけでなく文化的にもー-渦巻いている。ザーザンというテクノロジー敵対者の家にテレビがあることに困惑したインタビュアーが彼に質問したところ、彼が次のように答えたことは忘れがたい。『皆と同じ様に、私も麻痺させられなければならないのさ。』[37]
ライフスタイル=アナキズムそれ自体が「麻痺している」自己欺瞞であることを最も良く見ることができるのは、マックス=シュチルナーの「唯一者とその所有」である。そこでは、神聖犯すべからずの「自己」という神殿の中にあるエゴの「唯一性」の要求は、ジョン=スチュワート=ミルの自由主義的忠誠心よりも遥かに上位にある。実際、シュチルナーにとって、エゴイズムは認識論の問題になっている。「唯一者とその所有」を満たしている矛盾と酷く不完全な言質の迷路を切りひらくと、シュチルナーの「唯一の」エゴは神話なのだと分かる。何故ならエゴの根源はその見せかけの「他者」--社会それ自体--にあるからなのである。実際、シュチルナーはエゴイストを次のように扱っている。『君の行いと共に真実が前進することは出来ない、動くことも変化することも発達することも出来ない。真実は待ち、「君」から全てを補給し、そしてそれ自体は単に君を通り過ぎるだけなのだ。何故ならそれは単に--「君の頭の中にある」だけだからだ。』[38] シュチルナー主義エゴイストは、実際、客観的現実に、社会の事実性に、従って根本的な社会変革と、ブルジョア市場の隠れた悪魔の一つである自己満足を越えた全ての倫理基準と理想とに、別れを告げている。この媒介の欠如が、具体物のまさにその存在を破壊しているのだ。シュチルナー主義エゴそれ自体の権威--自己の社会的根源とその歴史的形成を排除するほど全てを包含している主張--を破壊していることは言うまでもない。
ニーチェは、シュチルナーとは全く別個に、真実それ自体の事実性と現実性を消滅させることで、真実に関するこの見解をその論理帰結へと導いていた。『ならば、真実とはなんぞや?』彼は問うていた。『隠喩・換喩・擬人観--とどのつまりは、それは詩的にも修辞学的にも高められ・転置され・潤色されてきた人間関係の要約なのである。』[39] シュチルナーよりも率直に、ニーチェは事実は単なる解釈なのだと論じていた。実際、彼は『諸解釈の背後にいる解釈者を断定する必要があろうか?』と問うていた。明らかにその必要はない。なぜなら『これさえも作り出されたものであり、仮説である』からだ[40] 。ニーチェの無情な論理に従えば、本質的にそれ自身の現実を創り出すだけでなく、単なる解釈以上のものとしてそれ「自身の」存在を正当化しなければならない自己と共に、我々は取り残されているのである。従って、このエゴイズムは、シュチルナー自身は述べていない諸前提の霞の中へ姿を消しているエゴそれ自体を徹底的に破壊しているのである。
同様に、自身の「メタファー」を越えた歴史・社会・事実性をはぎ取ることで、ライフスタイル=アナキズムは非社会的領域に生活している。そこではエゴはその秘密の欲望と共に論理的抽象へと蒸発する。だが、エゴを直感的即時性に還元する--単なる動物性や「自然の領域」、「自然の法則」に固定する--ことは、エゴは常に発展し続ける歴史の産物である、という事実を無視するも同然であろう。実際、歴史が単なるエピソード以上のもので構成されているのであれば、歴史は、進歩と退歩・必然と自由・善と悪・そして--そう!--文明と野蛮の基準に対する指針として理性を利用しなければならないのだ。実際、一方では薄っぺらな唯我論の落とし穴を、他方では単なる「解釈」としての「自己」の喪失を避けようとしているアナキズムは、明らかに社会主義的なものか集産主義的なものにならざるをえないのだ。つまり、アナキズムは、社会生活の前提条件を避けている空虚な放浪のエゴを通じてではなく、構造と相互責任を通じた自由を追求する「社会的」アナキズムでなければならないのだ。
乱暴に述べてみよう。アナルコサンジカリズムと無政府共産主義(これらが、自己実現の重要性と欲望の充足を否定したことは一度もなかった)の社会主義の系譜、ライフスタイル=アナキズム(これは、徹底的な社会否定ではないにせよ、社会の無用性を助長している)の基本的に自由主義的で個人主義的系譜の間には、我々が双方の全く異なる目標・方法・それらを区別している根本的哲学を完全に無視しない限り、掛け橋不可能な対立が存在するのである。シュチルナー自身の計画は、実際に、ウィルヘルム=ワイトリング(19世紀末のドイツの国家共産主義者)とモーゼス=へス(19世紀末のドイツのプルードン主義的社会主義者)の社会主義との議論の中で生じ、そこでシュチルナーは社会主義に完全対峙するためにエゴイズムを呼び出したのである。『全般的革命ではなく私的暴動が(シュチルナーの)メッセージだった』とジェームズ=J=マーチンは感嘆しながら述べている[41] 。それは、歴史主義・個性の社会基盤・理性社会へのコミットメントにその根源を持つ社会的アナキズムとは別の、今日、ライフスタイル=アナキズムとそのヤッピー的分派の厄介になって何とか生きのびている反対勢力なのである。
これらの本質的に混乱したメッセージが持つ正にその不調和は、ライフスタイル=「ファンジン」の全ページに同時に存在しており、苦しみもがいているプチブルの熱狂的声に表れている。もしアナキズムがその社会主義的中核と集産主義的目標を失えば、もしアナキズムがリバータリアン的プログラム・政治・組織の代案として、審美主義・恍惚・欲望へと、そしてつじつまのあわないことだが、道教的瞑想主義と仏教的自己謙遜へと押し流されてしまえば、アナキズムは社会の再生と革命的ヴィジョンではなく、社会の腐敗と短気でエゴイスティックな反抗を代表するものとなるであろう。さらに悪い場合、アナキズムは現在10代と20代の裕福な成員を既に席巻している神秘主義の波を肥え太らせることとなろう。恍惚に対するライフスタイル=アナキズムの賞賛は、「ラジカルな社会基盤において確かに賞賛すべき」ものなのに、ここではあつかましくも「妖術」と混ざり、理性的で弁証法的な世界の意識とではなく、魂・幽霊・ユング的元型とのおぼろげな併合を生み出しているのである。
特徴的なことだが、広く読まれている米国の野生的なアナキズム雑誌、「反体制報道評論」(Alternative Press Review)の最近号(1994年秋号)の表紙は、渦を巻いている銀河系星雲群とニューエイジ的装備という何か宇宙的なものを背景として、穏やかな涅槃の平安の中にいる三つの頭を持った仏教の神で飾られている--ニューエイジ的ブティックにある「第五権力」の「アナーキー」ポスターにた易く結び付けることができるだろう。表紙の裏では、グラフィックスが叫んでいる。「自由を開拓し始めると、人生は魔術になり得る」(魔術(Magic)のAは円で囲まれている)--ならば、次のことを問わねばなるまい。「どうやって?」「何を」使って?この雑誌それ自体にはグレン=パートンによるディープエコロジーのエッセイが載っている。そのタイトルは、デイヴ=フォアマンの雑誌「野生の地球」(Wild Earth)をもじった、「野生の自己:何故私は原始人主義者なのか」で、我々の『第一の課題』を、その『生活様式が、前もって存在する自然界に適合している』『原始的諸民族』を誉めそやし、新石器時代の革命を嘆き、『文明を「構築せずに」原生地帯を復元する』ことであると特定している。この雑誌のアートワークは野卑な状態を賞賛している--人間の頭蓋骨と破滅のイメージがそれを明らかに証明している。その最もくどくどしい寄稿論文、「デカダンス」は、「ブラック=アイ」誌からの再録なのだが、ルンペンと空想的なこととを混ぜあわせており、狂喜して次のように結論づけている。『本物のローマンホリデイだ、さぁ野蛮人どもを出せ!』
あぁ悲しいかな、野蛮人どもは既にここにいるのだ。今日の米国諸都市における「ローマンホリデイ」は、クラック・暴行・無神経・愚鈍・原始人主義・反文明主義・反理性主義・カオスとして理解されている相当量の「アナーキー」で飾りたてられているのだ。ライフスタイル=アナキズムは、堕落した黒人ゲットーと反動的な白人の郊外だけでなく、「原始性」の表面上の中心地であるインディアン保護居住地という現在の社会文脈でも、見られるはずである。インディアンの若者ギャングたちはお互いに銃で撃ち合い、ドラッグ売買が蔓延し、『神聖なるウィンドウロック記念碑でさえもギャングの落書きが観光客を出迎える』、とセス=マイダンズが「ニューヨーク=タイムズ」誌(1995年3月3日号)で報告している。
つまり、蔓延している文化的堕落は、1960年代新左翼のポストモダニズムへの退化、そしてそのカウンターカルチャー世代のニューエイジ観念論への退化の後に生じたのだ。臆病なライフスタイル=アナキストに対して、ハロウィーンのアートワークと扇動的な諸論文が、現実の理解と希望とをどんどん遠くへと押しやってくれているのである。「文化的テロリズム」と仏教修行所の魅惑によって引き裂かれながらも、ライフスタイル=アナキストは実際に、ウォールストリートとニューヨークで社会の頂点にいる野蛮人達と、欧米都市の陰鬱なゲットーの底辺にいる人々との間の激しいやりとりの只中に自身がいるということに気がついている。悲しいかな、そのルンペン的生活方法(大企業の野蛮人どもも今日では同類だ)を賛美しているが故に、彼等が陥っている葛藤は、自由社会を創り出す必要性と関連してはいないのだ。まだ、ドラッグ・人体・法外な貸付の売りつけ--そしてがらくた証文と国際通貨も忘れてはなるまい--から得た戦利品を分け合おうとしている人々間の残忍な戦争の方が関係しているぐらいだ。
単なる動物性--いや、「脱文明」と呼ぶべきだろうか?--への逆戻りは、「自由への回帰ではなく、本能への回帰なのである」。脳よりも遺伝子によって導かれている「確実さ」の領域への回帰なのである。過去の偉大なる革命によって常に発展する形で明確に示されていた自由の諸理念ほど進歩したものはない。そして、DNAなどのような生化学的至上命令への完全服従以上に残酷な物などないのだ。それは、文化と、理性的文明を求めた闘争とが扉を開けた創造力・倫理・相互依存とは全く異なるものなのだ。全くの野生ということで、我々が単なる動物性を形成する生得的行動パターンの命令を意味しているのであれば、「原生地帯」には自由などない。「自己意識した」自由--感情と同様に理性によっても、願望と同様に洞察によっても、詩と同様に散文によっても与えられる自由--の莫大な潜在可能性に対するしかるべき認識なしで文明を中傷することは、思考がぼんやりし、知性形成(intellectuation)が単なる進化の約束事であった時代の獣性という影の多い世界に退却することなのである。
民主主義的コミューン連合論(Democratic Communalism)に向けて
私のライフスタイル=アナキズム像は完全なものではない。このイデオロギーという粘土に対する個人主義的攻撃は、「想像力・神聖の・直感的・恍惚的・原始的」といった言葉がその表面を飾り立てている限り、その粘土をどの様な形にもこねることができる様にしている。
私の観点では、社会的アナキズムは根本的に異なるものからなり立っており、その伝統の限界と不完全さにしかるべき敬意を払いながらも、啓蒙運動の伝統の後継者なのだ。理性をどの様に定義するかにもよるが、社会的アナキズムは、情熱・恍惚・想像力・遊び・アートを無視せずに、思考する人間精神を賞賛しているのである。ただ、それらを曖昧なカテゴリーの中に具象化するのではなく、それらを日常生活に組み込もうとしているのである。社会的アナキズムは、経験の理屈づけに反対しながら理性に関与し、「メガマシーン」に反対しながらテクノロジーに関与し、階級支配とヒエラルキーに反対しながら社会制度に関与し、議会政治と国家に反対しながら、顔の見える直接民主主義において民衆が行う自治体や共同体の連合調整に基づく本物の政治運動に関与しているのである。
初期の諸革命が持っていた伝統的スローガンを使えば、この「共同体群からなる共同体」(Commune of communes)は、「コミューン連合論」(Communalism)として適切に呼ぶことができる。民主主義を「支配」だとする反対者とは全く逆に、コミューン連合論は、アナキズムの「民主主義的」側面を、公的領域に関する多数決行政として描いている。従って、コミューン連合論は、私がこれまで対峙させて来た意味において、自律よりも自由を追求するのだ。それは、個性は生まれた時から「自然の権利」を身にまとったab novoとして生じたのではないと主張することで、独立した主権者としての心理的-私的なシュチルナー主義的・自由主義的・ボヘミアン的エゴときっぱりたもとを分かち、個性の大部分を、歴史と社会の発展という常に変化し続ける活動として、生物学主義に硬直させられたり一時的で偏狭なドグマに捕われたりすることのない自己形成のプロセスとして見なすのである。
主権者、つまり自己充足的「個人」は、左翼リバータリアンの見解を定着させるためにはいつも不安定な基盤であった。マックス=ホルクハイマーは以前次のように述べていた。『個々人が独りでやっていくと決めると、個性は損なわれてしまう。(中略)絶対的に孤立した個人というのはいつでも単なる幻想であった。自律・自由への意思・共感・正義の感覚のような最も尊重される私的資質は、個人的美徳であると同時に社会の美徳でもあるのだ。十全に発達した個人とは十全に発達した社会の極致なのである。』[42]
もし、未来社会に関する左翼リバータリアンのヴィジョンが、ボヘミアン的でルンペン的な花柳会に消えうせてしまっていないのなら、社会問題に対する解決策を提供しなければならない。下手な詩と下品なグラフィックスで理性から自身を覆い隠してしまいながら、スローガンからスローガンへと尊大に飛びまわっていてはならないのである。民主主義は、アナキズムに対するアンチテーゼなどではない。ましてや、多数派裁定や非コンセンサス意思決定がリバータリアン社会にふさわしくないというわけでもない。
いかなる社会であれ全くの制度構造なしには存在し得ないということは、シュチルナーやその類の人々によって無感覚にされていない人には透通って見えるほど明白である。諸制度と民主主義を否定することにより、ライフスタイル=アナキズムは社会的現実から絶縁している。そのことで、無駄な激情を持ってますます激高できるようになり、結果、お人好しの青年と、黒服と恍惚的ポスターを買っている退屈した消費者にとってのサブカルチャー的悪ふざけであり続けているのだ。それが「たった一人の少数派」のものであったとしても、その意思に対するいかなる妨害も私的自律の冒涜となるため、民主主義とアナキズムは両立しないと主張することは、自由社会ではなく、ブラウンの言う「個人の集積」--つまり、群れ--を擁護することになる。「想像力」はもはや「権力」に至りはしないだろう。権力は、「いつでも存在する」が、明確に制度化された顔の見える民主主義を使っている集産集団に属すことにもなるかもしれないし、「構造のない専制政治」を生み出す可能性のある寡頭政治為政者数名のエゴに属すことになるかもしれない。
クロポトキンが「エンサイクロペディア=ブリタニカ」論文で、シュチルナー主義的エゴをエリート主義だと見なし、ヒエラルキー的だと非難していたことはもっともだった。彼はV=バッシの批判を賛同的に引用していた。バッシはシュチルナーの個人的アナキズムを、『全ての優れた文明の目的は、地域の「全」成員が普通に発達できるようにすることではなく、多くの人間の幸福とその存在を犠牲にしても、より恵まれた個々人が「十全に発達する」ことができる様にすることだ』という立場を維持しているエリート主義の一形態だとしていたのだ。アナキズムにおいて、このことは実際に逆戻りを生み出す。
『超越的少数者になろうとしている人々が皆擁護している最も俗悪な個人主義への逆戻りである。実際、人間がその歴史の中で、これら個人主義者達が戦っている正にその国家などを持つようになったのは、超越的少数者の御陰なのだ。彼等の個人主義は、自身の出発点の否定に終わることにさえなる--言うまでもなく、「美しき貴族政治」によって大衆を抑圧している状態で、個人が真に十全な発達を手に入れることなど出来はしないのだ。』[43]
その無道徳主義という点で、このエリート主義は、究極的に大衆を「唯一者達」の保護下に置いてしまうことで、「大衆」に不自由をもたらすきっかけとなり易い。これは、ファシストのイデオロギーに特徴的な指導原理を生み出す可能性のある論理なのだ[44] 。
合州国と欧州の大部分で、国家に対する民衆の幻滅が空前の規模に達している正にこの現在、アナキズムは退却状態にある。政府それ自体への不満は大西洋の両岸で高くなっている。新しい政治を、安全と倫理的意味を考慮した方向性の感覚を民衆に与えることができる新しい社会秩序さえをも求める民衆の強力な情念は近年これほどまでに見られることはなかった。アナキズムがこの状況を扱えていない理由を何らかの単一源泉に帰して構わないなら、常に縮小し続けている公的領域に潜在的左翼リバータリアン運動を参与出来なくさせているという理由で、ライフスタイルアナキズムとその個人主義的土台が持つ島国根性を抜擢せねばなるまい。
その名誉のために言っておくが、アナルコサンジカリズムはその最盛期には労働者階級の中で--ライフスタイルアナキズムとは全く異なり--生活実践に従事し、組織的運動を創り出そうとしていた。その主たる問題は、構造と参画への欲求やプログラムと社会運用への欲求にあるのではなく、革命の主体としての労働者階級の衰退、特にスペイン革命後のそれにある。しかし、元々のギリシャ語の意味における地域の自主管理--歴史的に有名な「共同体群からなる共同体」--において理解されているように、アナキズムには政治などないと言うことは、いかなる共和制にも内在している民主主義を急進化し、国家に対抗するための自治体連合の力を造りだそうとしている歴史的で「変形可能な」実践を拒絶することなのである。(原注)
(原注:拙著「都市化の勃興と市民権の没落」(今では「都市のない都市化」と題が変更されている(訳注:さらに「都市化から諸都市へ」と変わった)の嫌らしい「レビュー」の中で、ジョン=ザーザンは、古代アテネが「近代政治の復興に関するブクチンのモデルであり続けている」といういいかげんな戯言を繰り返している。実際、私はアテネの「都市国家(ポリス)」の失敗(奴隷制度・家父長制度・階級対立・戦争)を示そうと大いに骨を折っていたのだ。私のスローガン「共和国の民主化、(共和国に潜在的に存在する)民主主義の急進化」--明らかに二重の権力を創り出すことを目的としている--は、皮肉にも不完全に読まれているのである。『我々はゆっくりと、「既存制度」を拡大し、「共和国を民主化しようと」しなければならない、と(ブクチンは)忠告しているのだ。』こうした理念の表面的操作は、「アナーキー:武装した欲望」と「反体制報道評論」のレヴ=チャーニイ(別名ジェイソン=マックゥイン)によって、ザーザンの「未来の原始人」の忠告めいた前書きで賞賛されている(11ページ、164ページ、165ページを参照)。)
伝統的アナキズムの最も創造的な特徴は次の四つの基本的信条に対するコミットメントである。それは、権力分散型自治体連合・国権主義に対する確固たる反対・直接民主主義に対する信念・リバータリアン共産主義社会というヴィジョンである。左翼リバータリアニズム--アナキズムに他ならないリバータリアン社会主義--が今日直面している最も重要な問題は次のことである。これら四つの強力な信条を持って何を「行う」のか?どの様にしてそれらの信条に社会的「形態」と社会的「内容」を与えるのか?どの様な「方向」に、そしてどの様な「手段」を用いて、それらの信条を我々の時代に関連づけ、権能と自由を求める組織された民衆運動の助力となるようにそれらの信条を導くのか?
アナキズムは、十六世紀の原始人主義的な裸体主義者(アダムの子孫)が行ったような放縦な行動に消散してしまってはならない。ケネス=レクスロスが軽蔑して述べているように、裸体主義者達は「森の中を裸で歌い踊りながらさまよって」おり、ジャン=ジズカによって追い詰められ、根絶させられる--自分の土地を彼等に略奪されることに憤慨していた農夫を安堵させるためであることが多かった--まで、「自身の時間を不断の乱交パーティー」で過ごしていたのだった[45] 。アナキズムは、ジョン=ザーザンとジョージ=ブラッドフォードの原始人主義的花柳会へと退却してはならない。私は、アナキストは日常生活において--社会的にも私的にも、実際的にも美学的にも--出来る以上に自身のアナキズムを生きてはならない、と主張するつもりはない。しかし、アナキストは、運動として・実践として・プログラムとしてのアナキズムを国家社会主義とは区別している最も重要な特徴を減少させ、かき消してさえいるアナキズムを生きてはならないのだ。今日、アナキズムは「社会」運動--活動主義的であると同時に「実行プログラムを持った」社会運動--としてのその特徴を断固として保有していなければならない。それは、リバータリアン共産主義社会というその戦闘的ヴィジョンを「産業社会」のような名前によってはっきりと示されている資本主義に対する率直な批判と融合している運動なのだ。
結局、社会的アナキズムはライフスタイル=アナキズムとの違いをはっきりと断言しなければならないのだ。もし社会的アナキスト運動がその四つの信条--自治体連合論・反国権主義・直接民主主義・究極的にはリバータリアン共産主義--を新たな公的領域における生活実践に翻訳できなければ、もしこれらの信条が公式的宣言と公式的会議に関する過去の闘争の思い出のようにしなびてしまえば、さらに悪いことに、それらの信条が「リバータリアン」恍惚産業と寂静主義的なアジアの有神論によって破壊されてしまえば、その革命的社会主義の中核は新しい名前の下に復元されなければならなくなってしまうだろう。
確かに、私の観点では、ライフスタイル=アナキストと区別する修飾形容詞を付け加えなければ自身をアナキストと呼ぶことなどできはしない。最低限、社会的アナキズムは、ライフスタイル・恍惚に対する新シチュアシオニズム賛歌・常に矮小し続けているプチブルエゴの主権性に焦点を当てたアナキズムとはラジカルに反目しているのである。これら二つはそれらの規定的諸原理--社会主義か個人主義か--において完全に分離しているのである。諸理念と実践を持ってコミットした革命的組織体と、私的恍惚と自己実現への気まぐれな憧憬との間には、共通特徴などありえない。国家に対する単なる反対が、シュチルナー主義的ルンペンとファシスト的ルンペンを団結させるのは当然である。この現象には歴史的前例が幾つもあるのだ。
1995年6月1日
付記
私の研究仲間であり友人でもあるジャネット=ビールに対し、このエッセイに使う資料を捜し、編集するときに貴重な援助をしてくれたことについて感謝したい。
[1] 「The Political Philosophy of Bakunin」, G. P. Maximoff編 (Glencoe, Ill.: Free Press, 1953), p. 144.
[2] 「Political Philosophy of Bakunin」, p. 158.
[3] Peter Kropotkin著, 'Anarchism,' the Encyclopaedia Britannica article, in 「Kropotkin's Revolutionary Pamphlets」, Roger N. Baldwin編 (New York: Dover Publications, 1970), pp. 285-87.
[4] Katinka Matson著, 'Preface,' 「The Psychology Today Omnibook of Personal Development」 (New York: William Morrow & Co., 1977), n.p.
[5] ミシェル=フーコー著、「性の歴史Ⅰ 知への意志」、渡辺守章 訳(新潮社、1986年)、123ページ。素晴らしいことに、フーコーから率直な公式を得ることが出来、その観点は矛盾していることが多いという理解を得ることができる日がやってきそうだ。
[6] Paul Goodman著, 'Politics Within Limits,' in 「Crazy Hope and Finite Experience: Final Essays of Paul Goodman」, Taylor Stoehr編 (San Francisco: Jossey-Bass, 1994), p. 56.
[7] L. Susan Brown著, 「The Politics of Individualism」 (Montreal: Black Rose Books, 1993). 無政府共産主義に対するブラウンの曖昧なコミットメントは、分析からよりも直感的好みから引き出されているように思える。
[8] ハキム=ベイ著、「T.A.Z. 一時的自律ゾーン」、箕輪裕 訳(インパクト出版会、1997年)。ベイの個人主義は、TAZが『ハイテクに基づいた「心理的旧石器時代主義」』(邦訳書、90ページ) を混乱しながら主張していることを除けば、後期フレディ=パールマンとその反文明論的従者、そしてデトロイトの「第五権力」の原始人主義者達のそれとよく似ているように思える。
[9] T.A.Z.,' 「The Whole Earth Review」 (Spring 1994), p. 61.
[10] Jose Lopez-Reyに引用されている, 「Goya's Capriccios: Beauty, Reason and Caricature, vol. 1」 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1953), pp. 80-81.
[11] George Bradford著, 'Stopping the Industrial Hydra: Revolution Against the Megamachine,' 「The Fifth Estate」, vol. 24, no. 3 (Winter 1990), p. 10.
[12] Jacques Ellul著, 「The Technological Society」 (New York: Vintage Books, 1964), p. 430.
[13] Bradford著, 'Civilization in Bulk, 「Fifth Estate」 (Spring 1991), p. 12.
[14] Lewis Mumford著, 「Technics and Civilization」 (New York and Burlingame: Harcourt Brace & World, 1963), p. 301. 本エッセイにあるページナンバーは、この版による。
[15] Kropotkin著, 'Anarchism,' 「Revolutionary Pamphlets」, p. 285.
[16] 会議の諸論文は次の本として出版された。Richard B. Lee and Irven DeVore編著, 「Man the Hunter」 (Chicago: Aldine Publishing Co., 1968).
[17] 'What Hunters Do for a Living, or, How to Make Out in Scarce Resources,' in Lee and Devore編著, 「Man the Hunter」, p. 43.
[18] Paul Radin著, 「The World of Primitive Man」 (New York: Grove Press, 1953), pp. 139-150.を特に参照のこと。
[19] John Zerzan著, 「Future Primitive and Other Essays」 (Brooklyn, NY: Autonomedia, 1994), p. 16. ザーザンの研究を信頼している読者は、その参考文献に載っている"Cohen (1974)"と"Clark (1979)"(それぞれ、24ページと29ページに引用されている)のような重要な資料を捜して見てはいかがだろうか--これらやその他の論文は完全に消えうせてしまっているのだ。
[20] 有史以前の生活のこれらの側面に関する論文は非常に多い。Anthony Legge and Peter A. Rowly著、 'Gazelle Killing in Stone Age Syria,' 「Scientific American」, vol. 257 (Aug. 1987), pp. 88-95、では移動している動物を、捕獲用の柵を使って全滅させるほどの効果を持って大量に殺すことができていたことが示されている。アニミズムの実践的側面に関する古典的研究は、Bronislaw Malinowski著、「Myth, Science and Religion」 (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1954)を参照して欲しい。Kaj Arhem著、 'Dance of the Water People,' 「Natural History」 (Jan. 1992)において報告されているマクナ族の神話にあるように、擬人化操作は、シャーマンによって主張されている人間世界から非人間的世界への生まれ変わりに関する多くの説明の中に明らかである。
[21] ピグミー族に関しては、Colin M. Turnbull著、「The Forest People: A Study of the Pygmies of the Congo」 (New York: Clarion/Simon and Schuster, 1961), pp. 101-102.を参照。エスキモー族に関しては、その他多くの伝統的エスキモー文化に関する著作と同様、Gontran de Montaigne Poncins著、「Kabloona: A White Man in the Arctic Among the Eskimos」 (New York: Reynal & Hitchcock, 1941), pp. 208-9を参照。
[22] 世界中の多くの牧草地帯が、多分「Homo erectus」の時代まで遡れるだろうが、火によって作り出されたということは、人類学論文のあちこちに見られる仮説である。Stephen J. Pyne著、 「Fire in America」 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982)は優れた研究である。また、William K. Stevens著、'An Eden in Ancient America? Not Really,' 「The New York Times」 (March 30, 1993), p. C1 で引用されている、Annals of the American Association of Geographers (Sept. 1992)に載っているWilliam M. Denevanの論文も参照して欲しい。
[23] 「過剰殺傷」という激しい議論を引き起こしている問題については、「Pleistocene Extinctions: The Search for a Cause」, P. S. Martin and H. E. Wright, Jr.編著を参照。気候的要因と人的「過剰殺傷」双方が氷河紀ほ乳類の大量絶滅をもたらしたのか、どちらか一方がもたらしたのかに関する議論は、余りにも複雑すぎてここで取り扱うことはできない。Paul S. Martin著, 'Prehistoric Overkill,' in 「Pleistocene Extinctions: The Search for a Cause」, P. S. Martin and H. E. Wright, Jr.編著 (New Haven: Yale University Press, 1967)を参照。拙著「The Ecology of Freedom」 (Montreal: Black Rose Books)の1991年版のイントロダクションでこの議論の幾つかについて探求してみた。その証明は未だに議論の渦中にある。マストドンは、生息環境が制限された動物として見なされていたが、現在では、生態学的により柔軟だったと知られるようになり、氷河紀の狩人によって、多分ロマンティックな環境保護主義者達が信じたいと思っているほどには良心の呵責も感じずに、絶滅させられたのだろうとされている。私は狩りだけが、こうした巨大ほ乳類を絶滅させたと主張するものではない--大量数の畜殺で充分だったであろう。通常は水のない狭い水路におけるバイソンのかり立てについては、Brian Fagan著, 'Bison Hunters of the Northern Plains,' 「Archaeology」 (May-June 1994), p. 38.で見ることができる。
[24] Karl W. Butzer著, 'No Eden in the New World,' 「Nature」, vol. 82 (March 4, 1993), pp. 15-17.
[25] 以下の著作を参照。T. Patrick Cuthbert著, 'The Collapse of Classic Maya Civilization,' in 「The Collapse of Ancient States and Civilizations」, Norman Yoffee and George L. Cowgill編著 (Tucson, Ariz.: University of Arizona Press, 1988); and Joseph A. Tainter著, 「The Collapse of Complex Societies」 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), esp. chapter 5.
[26] Clifford Geertz著, 'Life on the Edge,' 「The New York Review of Books」, April 7, 1994, p. 3.
[27] ウィリアム=パワーズが述べているように、『「ブラック=エルク語る」は1932年に出版されたが、そこにはブラック=エルクのキリスト教徒としての生活が記録されてはいなかった。』ブラック=エルクの逸話に関する現在の熱狂ぶりの正体を徹底的に暴いているものとしては、次の本を参照。William Powers著、'When Black Elk Speaks, Everybody Listens,' 「Social Text」, vol. 8, no. 2 (1991), pp. 43-56.
[28] Edwin N. Wilmsen著, 「Land Filled With Flies」 (Chicago: University of Chicago Press, 1989), p. 127.
[29] Wilmsen著, 「Land Filled with Flies」, p. 3.
[30] Allyn Maclean Stearman著, 「Yuqui: Forest Nomads in a Changing World」 (Fort Worth and Chicago: Holt, Rinehart and Winston, 1989), p. 23.
[31] Stearman著, 「Yuqui」, pp. 80-81.
[32] Wilmsen著, 「Land Filled with Flies」, pp. 235-39 and 303-15.
[33] 例えば、Robert J. Blumenschine and John A. Cavallo著, 'Scavenging and Human Evolution,' 「Scientific American」 (October 1992), pp. 90-96.を参照。
[34] Paul A. Janssens著, 「Paleopathology: Diseases and Injuries of Prehistoric Man」 (London: Jon Baker, 1970).
[35] Wood著, 「Human Sickness」, p. 20.
[36] E. B. Maple著, 'The Fifth Estate Enters the 20th Century. We Get a Computer and Hate It!' 「The Fifth Estate」, vol. 28, no. 2 (Summer 1993), pp. 6-7.
[37] 「The New York Times」, May 7, 1995.から引用。ザーザンほど信心ぶっていない人の中には、テレビを持たないようにして、上品な音楽・ラジオ放送・本などで愉しみを得ている人達がいる。彼等は単にテレビを買わないだけなのだ!
[38] Max Stirner著, 「The Ego and His Own」, James J. Martin編, Steven T. Byington訳 (New York: Libertarian Book Club, 1963), part 2, chap. 4, sec. C, 'My Self-Engagement,' p. 352, 強調は筆者。
[39] Friedrich Nietzsche著, 'On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense' (1873; fragment), in 「The Portable Nietzsche」, Walter Kaufmann編訳 (New York: Viking Portable Library, 1959), pp. 46-47.
[40] Friedrich Nietzsche著, fragment 481 (1883-1888), 「The Will to Power」, Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale訳 (New York: Random House, 1967), p. 267.
[41] James J. Martin著, editor's introduction to Stirner, 「Ego and His Own」, p. xviii.
[42] Max Horkheimer著, 「The Eclipse of Reason」 (New York: Oxford University Press, 1947), p. 135.
[43] Kropotkin著, 'Anarchism,' 「Revolutionary Pamphlets」, pp. 287, 293.
[44] Kropotkin著, 'Anarchism,' 「Revolutionary Pamphlets」, pp. 292-93.
[45] Kenneth Rexroth著, 「Communalism」 (New York: Seabury Press, 1974), p. 89.