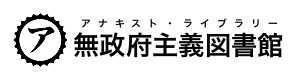秋山清
『アナキスト詩集』編集後記(断片)
アナキストの詩はマルクス主義的詩人(私はこの双方をプロレタリア詩と見る)の詩とどこが違うのか。それはアナキズムとマルキシズムの革命思想としての本質的差異とのその対立に由来するが、それを作品にみる場合、芸術革命の問題に要約される。マルクス主義詩人の第一人者中野重治が『赤と黒』等のアバンギャルドの活動に対して「私はまだ謂わば叫喚派あるいは騒音詩派とも称すべきものを屢々見せられている。それは常に街頭であり自動車であり、ドタン、バタン、クシャツ、×××などである。それはどうにも我慢ならぬ気持ちであり黒い虚無の風穴である。/そしてこれらの何れもが、それ自体には全然無産階級的ではない。/けれども私たちはここに言う騒音詩派のみは必ずしも捨てないであろう。何となれば『新しい形式への探究は実にあらゆる××の本質的なダイナミズムに対する偏愛である』からである。」(市に関する断片)といったことは、ここでは芸術革命の問題として、考えることの手がかりとする。
回想詩派、幻想詩派などと並べて叫喚と騒音の詩派(ダダとその他の前衛派を目指す)を指して「我慢のならぬ虚無の風穴」といい、「全然無産階級的ではない」と否定しながら、その騒音詩派のみは「必ずしも捨てない」といった時、マルクス主義詩人中のが、反マルキシズムの『赤と黒』などの形式革命運動の奥に潜む時代的な芸術変革の必然性とそのボリュームに心引かれたことを、この言葉は示している。芸術革命としての『赤と黒』出現の意味は、新体詩から民衆詩派までの形式(とイデオロギー)を否定したところにある。彼らの作品はまだ殆ど態をなさなかったが、表現そのものに新時代を要求したことは、あり来たる形式で「革命」を歌いあげようとした。イデオロギー偏重の社会主義的詩人とは次元の違った革新を孕んでいた。階級意識を宣伝扇動するために詩を必要と考えることと、詩人の主体において変革の情熱を謳わんとすることとの必然なる詩的落差はそこから生ずる。後者それは芸術革命によって革命芸術を進めると言う、詩人の主体を生かす道でなければならぬ。しかしそのように出発をしながら、『赤と黒』同人を含めてアナキストたちが芸術革命の歩みに外れざる詩の道を歩いた、ということにはならない。多分それは、時の勢いで協力化するマルキシズム芸術運動の政治中心の組織力に目を奪われたためであろうか。青野季吉のレーニン論を文学運動に転用した「自然成長と目的意識」論によって、アナ・ボル共同戦線が排された以降のアナキスト側の混乱は、文学と政治における主体性の動揺である。芸術革命に出発した変革の詩のプログラムは、集団の力に如何にかかわらず、唯一人によってでも進められるべきであったものを、イデオロギーの対立(これは必然)にも目を奪われて、芸術をアナキズムのイデオロギーに従わせようとした、スケールの短い活動に落ちる危険があった。その道はアナキストの詩であるよりも、アナキズムの宣伝、そのための活動、のための詩の運動ということに下落せんとするものであった。芸術が革命の奴隷となってよいという主張はどこにもなかったのに、常識的な組織を必要と考え、革命の理論にのみ芸術の意味を見出そうとして、そのための転向者も輩出した。曲がりなりにも昭和の初めにアナキスト詩人が存在し得たのは、それから後のことに属する。革命も芸術も文学も、人間のために必要である、ということを漠然と納得し得たのは文学におけるアナ・ボルの対立がはっきりしてからのことであった。
「書かれざるものは詩にあらず。我々はこの言葉の中に、在来の種々の矛盾を一掃し、視野を我々の生活と芸術の前途に展開せしめる可能性を含む意企をみることができる。生活そのものの中に詩を見、詩と生活の一致を唱動する“誠実なる”詩人の体内の血よりも、むしろこの暴言を為す者の身内に逆流する血の方が新鮮である。」(「今日の詩人」一九百三◯年『弾道』創刊号)
「詩と行動をごっちゃに取扱うことは詩の本質をアイマイにする。詩の本質を究めるためには、詩と現実を截然と区別する必要がある。しかし新しい詩論家のように、文学と現実を平行線の上においてその各々をみるのではなく、現実を文学の延長線上に考える。それは二本の平行線ではなく、あくまで一本の現実の直線なのだ。その一本の上で、僕のいう詩(プロレタリア詩)と行動は、二つに分つことが出来る。即ち文学行動は生活行動のある水準以下に於いてのみ生活行動と一致し得る。生活行動が上騰する時文学行動はそれに追い付けぬ。(「芸術に関する断片」一九三一年『弾道』第7号)
これはアナキストの最も有力な雑誌『弾道』における主宰者小野十三郎の意見の要旨である。組織あるいは指導部からの司令に服従するのみではないアナキストの文学活動に、文学の自由性あるいは芸術主義的独立性の意向が潜んでいる事は、むしろ必然である。しばしばアナキスト詩人らが落ちた生活優位の心情と、またマルキシズムの政治優位の文学観に対するやや明瞭な立場が、初めて確固と押し出された、と私は思う。
ここに至るまでには、『赤と黒』以来のアバンギャルドの活動があり、それをうらがえしにしたにした反政治-生活優先のセンチメンタルなヒューマニズムが、アナキズムと混同されすぎたこともあった。
革命のための文学の主張も人間主義のうた声も、耳に入りやすい。詩と生活の二元論は詩に甚だしく現実的に見えもしたものである。
今日ふりかえるアナキスト詩人の足跡もこれからの不安定の中に動揺しつつ、詩に自己嫌悪を持って、自己と戦い、流行するヒューマニズムや所詮左翼と対峙しつつ支えられた。各々に片よりがありながら、連帯と対立を敢えてしながら、味方に敵を、敵に敵を見ようとしてきた足跡としても、幾人かの詩人の作品を読む事はできるだろう。