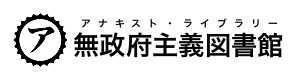James v. Hopkins
アナキストは社会革命をよびかけている
資本主義・帝国主義の定義拡張を
時代とその世界像は20世紀をつうじて、みごとに一循環したようにみえる。ブルジョワ・リベラリズムは、ソーシャリズム・ロシアの消滅を契機にヨーロッパ・アメリカを軸にその最後的勝利を宣伝したかにみえた。資本主義各メディアはしばしいたるところで「市民社会の勝利」を宣言した。しかし「市民社会」とはただ政治的な社会像としてわれわれに残されているひとつのイマージュである。それがいかなるかたちをもって実現されるかはわれわれ自身の作業・創意工夫とその構想にまったく委任されたものなのだ。だから、われわれの眼前にあるようなブルジョワ・リベラリズムに依ったヘボ市民社会だけが「市民社会」のお手本というわけではないことはあきらかである。ときにアナキストは「市民」から除外されて議論され、扱われる(要するにアナキストであるということだけで逮捕拘禁されるという歴史経験があった)場に遭遇してきたのであるが、「市民」という観念が歴史的には地位と財産に担保されたブルジョワによって詐称されてきたことがそうした判断の背景としてあるのだろう。わたしはそれに組みしない。われわれはまづ人間としてこの世にやってきたことによって、政治的にたつことを余儀なく運命づけられているとわたしは思考判断する。ただ「市民」ということばをことさらに強調する必要性も感じない。
一方、ブルジョワ社会システムは20世紀の国家的な実験をつうじてより完成された社会形態を実現したようにおもわれる。核家族をユニットにした消費および再生産と労働供給というのが資本主義近代社会の最終形態であることにわれわれはそろそろ気づかなければならないときにきている。ちなみにわれわれは日本に生まれ育ったゆえに、ひとつのきわめてユニークな政治社会を経験している。このイデオロギー社会システムをつうじた不可視の現実は、意識的な作業と反省をつうじてしか洞察することができない。個々人の意識観念の基底部にもこの政治社会の支配的なイデオロギーは浸透しているのであって、そのことがよけいわれわれ自身をお互いに鏡のようなものにしてしまうのである。こうした構図が、意識性によって眼前の現実を突破して、人間とその社会の可能性をべつの形態へとみちびこうと夢想する者(アナキストあるいはコミュニスト)以外の者らの意識観念を飼い馴らしつづけているのである。極言すればそうした者らは、資本主義のメディアが与えてくれる自画像の断片を後生大事に拝受しているか、実際の自分とはかけはなれたメディア・イメージのなかに自分を投影して、一向に輪郭が明瞭にならない自画像の断片を拾い集めて自己観念を取り繕っているのである。
われわれはどこにいるのか? いかなる者としていまここにあることを結果的に強いられているのか? これは焦げついてしまっていないか、あるいは粉々に散ってしまっていない者たちすべてにむかって発される問いである。この問いのないところでは、われわれは制圧された観念(永遠の植民地)に生きるいわば目隠しされた羊の群れである。そして、資本主義とその自由の勝利はこの「永遠の植民地」経営、すなわちわれわれ自身が「資本主義とその自由」の植民地でありつづけることなのである。大杉栄はこのことを「征服の事実」(1913)として洞察した。われわれはいまこの地上に生きるすべての者らにむかってこの事実を突きつける。この一点の気づきからこそ、われわれに委任されてある根源的な自由とその実践的な展望展開総体への夢想開眼が起きるのだ!真実、われわれの自由とはこの夢想中に去来するいっさいのなかに生の可能性を探求し、その実現可能性を模索試行することである。アナキストはこのことを大胆にしかしときにしずかにしかし決定的によびかけ、示唆宣伝しているのである。
アナキストが示唆するこの自由は、われわれを救い出す”革命”とほぼ同義である。(それはまづ自我意識上におきる革命ということができる。)「資本主義・帝国主義の定義拡張」はわれわれの態度決定と不可分であり、表裏一体の判断作業である。自由と革命はこの洞察によってこそそのヴィジョンの端緒にとりつくのである。
COMMERCIAL TV & MAGAZINES FUCK OUR HEADS!
われわれのただなかに居座っているブルジョワ・リベラリズムとその軍勢は、この国ではむかうところ敵なしといった風情である。かつての天皇制国粋主義によって自殺的な愚行に身を捧げたこの国の人民はなおそのすこやかで逞しい人間の素顔とその心魂を回復していないようにみえる。あいもかわらず、強いられた種々のくびきに馴らされつつ、なお眼前にさしだされるかにみえる生温い砂糖水にストローを差し込むことに汲々としているかのごとしである。いかに資本主義メディアがコマーシャルで「ゆたかな生活」を宣伝しようが、そういったものは残念ながらおおかた絵に画いたモチである。衆人環視のタレント芝居は現実生活の真実な情景ではない。連中はわれわれを作為捏造されたイメージ幻想のなかに飼い馴らそうと日々、手練手管を繰り出しているのである。結局、この国のなかでもっとも決定的な闘争域は、この観念形成の場である。この地点の闘争は困難をきわめる。というのも実際のところ、この域はほぼ制圧されているからである。 ほんとうにオゾマシイことだが、この国の青年らはほとんどfuckingTVheadsの状態にある。どうにかならんのか!ここいらは語るに愚というほかないのかもしれない。テレビのスイッチは切っておけ!というほかない。スイッチを入れたがただちに耳目を制圧され、意識がほぼ捕捉されてしまうアノ、テレビという奴を原則的に警戒せよ。この忠告をくりかえす以外に妥当な選択はないといっておく。テレビと資本主義という問題はおおきい。それはいづれも今どき、意識観念の問題であるからである。(テレビの映像音声によって保育されるイメージとはなにか?)
ブルジョワ・システムが宣伝流布する非現実的なイメージからは身を離せ!そこからようやく意識と身体の自由が回復されるようになるのだ。世界像の読解編集権(エディターシップ)をみずからの手に奪還せよ!
資本主義の臨界点は爆発か消滅である:進行する社会恐慌
ブルジョワ・リベラリズム・システムは、抽象的な経済合理性のなかへ人間と社会総体をまきこんでいく。そこに人間的な生の論理はない。大杉栄がアンリ・ベルクソンの哲学に共感洞察をもったという思想的な意味はここに背景理由がある。そもアナルコ・サンディカリスト理論(「暴力に関する考察」1908)をつくったジョルジュ・ソレル(1847~1922)がさきにベルクソン哲学に導きをみいだしていたということはある。ただ、いまにしても「生の哲学」が依然として抜き差しならない緊要性をおびた課題であることは厳然たることであるとわたしは考える。というのもくりかえしになるが、資本主義・自由主義の社会は「人間の生総体」を収奪横領し、つひに干上がらせてゆく強力な性質をうちにかかえもっているからだ。
日本のような開発独裁と操作管理が強力に成功してきた社会では、ブルジョワ・リベラリズムの論理的な帰結はこの社会に生きる具体個人に極限化されたかたちで表現されていると考えることもできよう。生きたコミュニティとその自治的規範から遠ざけられて生育した青少年らが一種のアノミー(規範喪失)状態に陥りはじめているこの間の情況はこのことを実証している。社会のそも底辺である未成年者の世界が深刻な混乱混迷をはらみはじめていると考えてもよいだろう。同様な事態は過去にもあったのだが、いま現在の相はいまここにおいて洞察しなければならないものである。事態が鮮やかに展開する光景に立ち会うことは実際できなこうした変化は意識的な展開を含んだ革命とはまったくべつのものだからだ。事態の深層はじわじわと進行する。
つまるところ、われわれはあらたなソーシャル・クラッシュの時機を眼前にしている。この社会的衝突の力はその実、「生の力」を証明しているのである。ブルジョワ・リベラリズム・システムの社会構成はそこに生きる個々人の生を巧妙な袋小路へと誘いこむ仕組みになっている。無形の生命力を巧みに操作し、管理することでブルジョワ・リベラリズムはみずからの命脈をはかりつづけているのである。ときに明確な意思をもって抵抗叛乱する者には(警察および軍事的な)排除あるいは弾圧が実行される。こうした抵抗と叛乱による人間的生のあらたな可能性への挑戦をこそブルジョワ・リベラリズムの制度的保証人は恐怖するのだ。アナキストはまづこの「生のかたち」をめぐる夢想とその自由をもってたつ。この自由なる夢想がわれらアナキストの革命観の根である。社会革命を政治権力の奪取によって着手することをはかる共産主義者・ボルシェヴィキの地点とはここにおいていささか性質を異とするようにおもわれる。アナキストはむしろ社会革命に要請される具体的な諸力を当座の社会とそこに生きる具体個人のなかに育むことに熱心なのかもしれない。しかし、これとてソーシャリストおよびコミュニストのいずれもが実践していることではあろう。つまるところ問題の質は、われらアナキストは社会革命を導来する実践力の自治化(より根源的には自己所有化)に密着するということである。それは、社会構成力の主体性を自身当事者として手放さないという態度にある。つまり武装解除を原則的には断乎拒否するということである。で、結局この問いはつねなるプロレタリア・デモクラシーの問題へとかえっていくことになるのだ。(これは歴史的なソーシャリスト・ソヴェート革命の根幹に関わる問題でもある。)おそらく、わたしの頭脳中においては、アナキストは革命の原器としてインディヴィデュアル(個人)の質内容に信頼することでソーシャリズムの具体内容を展望しているという理解がある(注;オスカー・ワイルドのソーシャリズム思想理解にはこうした視点がある)。片や、マルクス主義的なソーシャリスト・コミュニスト(いわゆるボルシェヴィキ)は集団的なソーシャリスト政治権力の樹立を一義的に観念しているとわたしは判断する。社会革命の訴求をめぐる作質において異なるこのふたつの傾向が互いの地点から慎重かつ大胆に協働できればソーシャリスト革命は歴史的な成功を遂げるであろう。(というのも、方法において異なっていてもその目指すところの究極はほぼ一致しているのだから。ソーシャリズム革命の兄弟粛清にわたしは反対する。)
しかし、いずれにしろ状況は悪い。条件的福祉政策を手管にしてきたブルジョワ家父長制権力は無産階級人民の意識観念を馴致してきた。ネオ・リベラリズムの政治はここにきてケインズ的な福祉政治からの撤退をはかっている。人民大衆のアトム(分解孤立)化を戦略とするネオ・リベラリズム政治はブルジョワ・リベラリズム論理の社会的な貫徹をその綱領の基本としている。
こうした事態は、ソーシャリスト労働者党の政治権力成立以前の問題を噴出させる。1990年代後半に入ってみられるようになったフランスの失業者集団の闘争は左翼連合政権下においても一定の威力を発揮した。問題はつねに党以前であり、かつ党以後なのだ。つまり、党と革命はかならずしも一致するものではなく、まさにわれわれ自身の場こそが現実的な闘争あるいは運動の根底的な立脚点であることをわれわれはいま再確認するときなのだ。望むべき現実の救済や革命はどこからともなくふいにやってくるものではない。制度的福祉の解体縮小への圧力のなかで、われわれは自身相互の諸力の協同合作によって生き延びることを模索かつ企図する時機に立ち会っている。
社会革命の準備と作業をただちに開始しよう!
1990年代をつうじて顕著になった金融市場における投機的な行動は、国際的な資本主義自由経済の攪乱要素としてはたらきはじめている。1994年1月1日のNAFTA・北米自由貿易協定の発効に叛旗をひるがえすべく決起したメキシコ・チアパスにおけるサパティスタ民族解放軍の抵抗は、残虐な軍事的鎮圧攻撃にさらされた。ここでひとつあきらかにしておきたいことは、日本の石油資本がメキシコの油田開発に参入を表明していることである。そしていみじくもメキシコ・チアパスの地下には有望な石油鉱床があるといわれている。日本の多国籍資本はメキシコとペルーを中南米地域への進出の橋頭堡として確保しようとしている。1998年、日本政府は日系移民がおおく在住する地域(ブラジルならびにボリビア)に天皇を派遣することで、歴史的にみるならば、いわば「大日本主義」のフレームを画こうとしている。すくなくとも意識的なソーシャリストを自負する者であるならば、今現在の政治経済のうごきを100年の時間軸で捕捉する程度の歴史的な感性を備えていたいものだ。ソーシャリストとしての歴史理解の基本テキストは、カール・マルクス「資本論」中のいわゆる「本源的蓄積論」である。帝国主義ブルジョワジーが歴史上、いかにふるまってきたかは、いま現在においてもその事例に事欠くことはないのだが、それらのルーツがいまも変わらぬ蛮行のくりかえしであったことを識るのは大事な学習である。帝国主義の軍事介入はいまも平然とくりかえされる。地域的な抵抗への軍事的弾圧にしろ、いたるところで展開継続されていることは(ブルジョワ・メディアによる報道では)なかなか知り得ないことである。世界のいたるところを流血の惨状に追い込んでいるのは、流血の場に立ち会っている人々の本来的な性格や性質のためでは決してなく、それらの背景を丁寧にたどれば、そうした武力衝突と流血の決定的な因子がおおくの場合、当地に関与している権益をめぐる帝国主義の圧力であることを識るであろう。人間は好き好んで殺し合うのではない。この素朴な事実がかえって判りづらくされているのは、ブルジョワ・メディアの限界でもあり、またその責任のかたちである。連中は肝心なところを避けているのだ。その限界と沈黙の行間を丁寧に読み抜くことこそ、われわれの日々の洞察でなければならない。
いずれにしろ、この世界のありさまを決定してゆくのは、根底的にはわれわれ自身の世界観と人間観ならびに社会観である。そして、その洞察批判およびあらたな造形はわれわれ自身の自由に委任されてある。たとえ眼前のいかなる権力がわれわれを操作誘導しようとも、そこから自由になる者にとって世界はあらたな横顔を垣間見せてくれるものである。隠然たる圧力と障害のなかで、闘いはつねに困難である。しかし、闘いは次第に深まってゆく態度決定をもってその根を養う。この一見したところみごとに飼い馴らされたかにみえる日本の社会においても、水面下の静かではあっても次第に根を張り拡がってゆく態度決定の連鎖のなかでこそ、自由と革命への洞察が成長してゆくのである。物事を一気に展開することはできない。しかし、いまここからはじまるすべてということがある。すべてはいまここで進行していることだ。だから(あなたをふくめた)われわれ自身もいまここから広汎な活動ならびに闘争を開始することができる。
James v. Hopkins
samedi, 31 janvier 1998
/ samedi, 7 septembre 2002