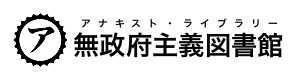大杉栄
奴隷根性論
一
斬り殺されるか、焼き殺されるか、あるいはまた食い殺されるか、いずれにしても必ずその身を失うべき筈の捕虜が、生命だけは助けられて苦役につかせられる。一言にして言えば、これが原始時代における奴隷の起源のもっとも重要なるものである。
かつては敵を捕えればすぐさまその肉を食らった赤色人種も、後にはしばらくこれを生かして置いて、部落中寄ってたかって、てんでに小さな炬火をもって火炙にしたり、あるいは手足の指を一本一本切り放ったり、あるいは灼熱した鉄の棒をもって焼き焦したり、あるいは小刀をもって切り刻んだりして、その残忍な復讐の快楽を貪った。
けれどもやがて農業の発達は、まだ多少食人の風の残っていた、蛮人のこの快楽を奪ってしまった。そして捕虜は駄獣として農業の苦役に使われた。
また等しくこの農業の発達とともに、土地私有の制度が起った。そしてこのこともまた、奴隷の起源の一大理由として数えられる。現にカフィールの部落においては、貧乏という言葉と奴隷という言葉とが、同意味に用いられている。借金を返すことのできない貧乏人は、金持の奴隷となって、毎年の土地の分配にも与からない。そして犬と一緒になって主人の意のままに働いている。
かくして従来無政府共産の原始自由部落の中に、主人と奴隷とができた。上下の階級ができた。そして各個人の属する社会的地位によって、その道徳を異にするのことが始まった。
二
勝利者が敗北者の上に有する権利は絶対無限である。主人は奴隷に対して生殺与奪の権を持っている。しかし奴隷には、あらゆる義務こそあれ、何等の権利のあろう筈がない。
奴隷は常に駄獣や家畜と同じように取扱われる。仕事のできる間は食わしても置くが、病気か不具にでもなれば、容赦もなく捨てて顧みない。少しでも主人の気に触れれば、すぐさま殺されてしまう。金の代りに交易される。祭壇の前の犠牲となる。時としてはまた、酋長が客膳を飾る、皿の中の肉となる。
けれども彼等奴隷は、この残酷な主人の行いをもあえて無理とは思わず、ただ自分はそう取扱わるべき運命のものとばかりあきらめている。そして社会がもっと違ったふうに組織されるものであるなどとは、主人も奴隷もさらに考えない。
奴隷のこの絶対的服従は、彼等をしていわゆる奴隷根性の卑劣に陥らしむるとともに、また一般の道徳の上にもはなはだしき頽敗を帰さしめた。一体人が道徳的に完成せられるのは、これを消極的に言えば、他人を害するようなそして自分を堕落さすような行為を、ほとんど本能的に避ける徳性を得ることにある。しかるに何等の非難または刑罪の恐れもなく、かつ何等の保護も抵抗もないものの上に、容赦なくその出来心のいっさいを満足さすというがごときは、これとまったく反対の効果を生ずるのは言うまでもない。飽くことを知らない暴慢と残虐とが蔓こる。
かくして社会の中間にあるものは、弱者を虐遇することに馴れると同時に、また強者に対しては自ら奴隷の役目を演ずることに馴れた。小主人は自らの奴隷の前に傲慢なるとともに、大主人の前には自らまったく奴隷の態度を学んだ。
強者に対する盲目の絶対の服従、これが奴隷制度の生んだ一大道徳律である。そして主人および酋長に対するこの奴隷根性が、その後の道徳進化の上に、いかなる影響を及ぼしたかは次に見たい。
三
先きにも言ったごとく、奴隷は駄獣である、家畜である。そして奴隷はまず、家畜の中の犬を真似た。
カフィール族はその酋長に会うたびに、「私はあなた様の犬でございます」と挨拶をするという。しかし自分の身を犬に較べるこの風習は、ただに言葉の上ばかりでなくその身振りや処作においても、人間としての躰の許せるだけ犬の真似をするということが、ほとんど例外もないほどにいたるところの野蛮人の間に行われている。
まずその一般の方法としては、着物の幾分かを脱いで、地に伏して、そして土挨を被るにある。
アフリカは奴隷制度のもっとも厳格なところであった。したがってこの犬の真似の儀式も、ほとんど極端なまでに行われている。
アルゲン島附近のアザナギス族は、酋長の前に出ると、裸になって、額を地につけて、頭と肩とに砂を被る。イシニー族もやはりまず着物を脱いで、腹這いになって、這いながら口へ砂をつめる。
クラツバートン氏によれば、氏がカトウンガの酋長に謁見した時、二十余名の大官がいずれも腰まで裸になって、腹這いになったまま顔も胸も土まみれになって酋長の傍へ這いずって行って、初めてそこに坐って酋長と言葉を交えることを許されたのを見たという。
ところがこの貴族等はまた、自分が酋長に対してやることを、同じようにその臣下のものに強いる。バロンダ族の平民は、道で貴族の前に出ると、四這いになって、体や手足に土をぬりつける。キアマ族もまた貴族の前に出ると、急に地べたに横になる。
ダホメーの酋長の家では、臣下は玉座の二十歩以内に近よることを禁ぜられて、ダクロと称する老婆によって、酋長へのいっさいの取次ぎをして貰う。まずその取次ぎを請うものは、ダクロの前へ四這いになって行く。そしてダクロはまた四足になって、酋長の前へ這って行く。
四
野蛮人のこの四這い的奴隷根性を生んだのは、もとより主人に対する奴隷の恐怖であった。けれどもやがてこの恐怖心に、さらに他の道徳的要素が加わって来た。すなわち馴れるに従ってだんだんこの四這い的行為が苦痛でなくなって、かえってそこにある愉快を見出すようになり、ついに宗教的崇拝ともいうべき尊敬の念に変ってしまった。本来人間の脳髄は、生物学的にそうなる性質のあるものである。
そして酋長は他の人間以上のあるものになってしまった。
ナチエーの酋長は太陽の兄弟であった。そしてこの資格をもって、その臣下の上に絶対権を握っていた。酋長の嗣子は生れるとすぐに、その時母の乳房にすがっているいっさいの嬰児の主人であるとせられた。
中央アフリカにおいても、大中小の酋長はいずれもみな神権を持っていて、自由に地水風火の原素を使役する。ことに雨を降らすに妙を得ている。
バッテル氏によるに、ルアゴンでは畑に雨の必要があると、酋長に願って空に弓を射て貰う。これは雲にそのつとめを命じさすのである。
そこで人民が酋長に雨乞いを願うと、酋長の方からはその代りに租税を要求するというような争いが起きる。「羊を持って来なければ雨は降らせぬ」などと威張る。また洪水の時などには、麦幾許を納めなければ永劫にあらしがあるなどと嚇す。
ブーサ族の酋長が、ヨーロッパでは一夫多妻を禁じていると聞いて、「外の人にはそれも善かろうが、しかし酋長には怪しからんことだ」と言ったという。
アシャンチ族の酋長は、いっさいの法律の上に超絶していて、酋長の子はどんな悪事をしても罰せられることがない。そして臣下は酋長のために死ぬことを至上の義務と心得されている。
五
なおこの時代の野蛮人は、一般にごくお粗末な霊魂不滅観を抱いていた。すなわち人が死んだ後、なお幾許かの間、生きているものと信じていた。死人の影が、地上の生活と同じような生活を、どこかで続けているものと信じていた。
そしてこの天上の生活は、ことに大人物にのみ限られていた。平民や奴隷はこの世限りで死んでしまうのである。そこで大小の酋長が死ぬと、食物だの、武器だの、奴隷だの、女だのと、いろいろなものをその未来の生活に伴って行く。
カライブ族の酋長が死んだ時に、その妻の一人が一緒に葬られた。彼女はこの酋長の子を幾人か生んだというので、ことにこの役目に撰ばれたのである。
かつてハワイで、ハワイナポレオンと称せられた、大虐殺王タメハメハの死んだ時などは、大勢の人間の強制的犠牲を供えたのみならず、なお無数の忠良な臣下が自殺しまたは自ら傷つけて不具になった。そしてその後数年間、国民は毎年その日に糸切歯を抜いて、タメハメハを祭った。
ベナン族の酋長の葬式には、墓の側に徳利形の大きな深い穴を掘って、その口から大勢の奴隷や召使を投おり込んで、そこに餓死さしてしまう。
アシャンチの酋長が死ぬと、その親族のものは外に走って出て、手あたり次第に道に会う人々を殺す。それから数百または数千の奴隷の首をしめる。そして時々また、何か事のあるたびに、天上の酋長に使いするために、幾多の奴隷を殺す。
六
僕はあまりに馬鹿馬鹿しい事実を列挙して来た。今時こんなことを言って、何のためになるのかと思われるような、ベラポーな事実を列挙して来た。けれどもなお僕に一言の結論を許して戴きたい。
主人に喜ばれる、主人に盲従する、主人を崇拝する。これが全社会組織の暴力と恐怖との上に築かれた、原始時代からホンの近代に至るまでの、ほとんど唯一の大道徳律であったのである。
そしてこの道徳律が人類の脳髄の中に、容易に消え去ることのできない、深い溝を穿ってしまった。服従を基礎とする今日のいっさいの道徳は、要するにこの奴隷根性のお名残りである。
政府の形式を変えたり、憲法の条文を改めたりするのは、何でもない仕事である。けれども過去数万年あるいは数十万年の間、われわれ人類の脳髄に刻み込まれたこの奴隷根性を消え去らしめることは、なかなかに容易な事業じゃない。けれども真にわれわれが自由人たらんがためには、どうしてもこの事実は完成しなければならぬ。