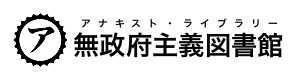1964(昭和39)年12月25日
※本作品中には、身体的・精神的資質、職業、地域、階層、民族などに関する不適切な表現が見られます。しかし、作品の時代背景と価値、加えて、作者の抱えた限界を読者自身が認識することの意義を考慮し、底本のままとしました。(青空文庫)
大杉栄
自叙伝
自叙伝(一)
一
赤旗事件でやられて、東京監獄から千葉監獄へ連れて行かれた、二日目か三日目かの朝だった。はじめての運動に、一緒に行った仲間の人々が、中庭へ引き出された。半星形に立ちならんだ建物と建物との間の、かなり広いあき地に石炭殻を一面にしきつめた、草一本生えていない殺風景な庭だ。
受持の看守部長が名簿をひろげて、一列にならんでいるみんなの顔とその名簿とを、しばらくの間見くらべていた。が、やがて急に眉をしかめて、幾度も幾度も僕の顔と名簿とを引きくらべながら、何か考えているようだった。
「お前は大杉東というのの何かかね。」
部長はちょっと顎をしゃくって、少し鼻にかかった東北弁で尋ねた。
名簿には僕の名の右肩に、「東長男」とあることは知れきっている。それをわざわざこう言って聞くのは、いずれ父を知っている男に違いない。その三十幾つかの年恰好や、監獄の役人としては珍らしい快活さや、ことにその僕に親しみのある言葉の調子で、僕はすぐにどこかの連隊で下士官でもやっていたのかなと思った。
「先生、親爺の名と僕の前科何犯とをくらべて見て、驚いてるんだな。」
僕はそう思いながら、返事のかわりにただにやにや笑っていた。それに、こんなところで父を知っている人間に会うのは、少々きまりも悪かったのだ。
「東という人を知らんのかね。あの軍人の大杉東だ。」
部長は不審そうに重ねてまた尋ねた。
「知らないどこの話じゃない。それや大杉君の親父さんですよ。」
それでもまだ僕がただにやにやして黙っているので、とうとう堺君が横あいから答えてくれた。
「ふうん、やっぱりそうか……あの人が大隊長で、僕はその部下にいたことがあるんだが……あの精神家の息子かね……」
部長はちょっとの間感慨無量といったような風で、ひとり言のように言っていたが、やがて自分に帰ったようになって、
「その東という人は第二師団で有名な精神家だったんだ。その人の息子がどうしてまたこんなところへはいるようになったんだか……」
と繰りかえすように附け加えた。
この精神家というのは、軍隊での一種の通り言葉で、忠君とか愛国とかのいわゆる軍人精神のおかたまりを指すのであった。十分尊敬の意味は含まれているんだが、しかしまた、戦術がへただとか融通がきかないとかいうそしりの意味もないことはなかった。
僕が陸軍の幼年学校から退学させられて家に帰った時にも、
「お父さんはあんなにおとなしい方だのに……」
と、よくいろんな人に不思議がられた。そしてそのたびに、僕の家のことをもっとよく知っているらしい誰かが、
「それやあなたはお母さんをよく知らないからですよ。」
と僕のために弁解してくれた。
実際僕は父に似ているのか、母に似ているのか、よく知らない。もっとも顔は母によく似ていたらしい。
「そんなによく似ているんですかね。でも私、こんないやな鼻じゃないわ」
母はよく僕の鼻をつねっては、人にこう言っていた。
母は綺麗だった。鼻も、僕のように曲った低いのではなく、まっすぐに筋の通った、高い、いい鼻だった。
父が近衛の少尉になった時、大隊長の山田というのが、自分の細君の妹のために婿選びをした。そして二人候補者ができたのだが、ついに父の手にそれが落ちたのだそうだ。
その当時母は山田の家にいた。なかなかのお転婆娘で、よく山田の出勤を待っている馬に乗っては、門内を走らして遊んでいたものだそうだ。
「この母方のお祖父さんというのが面白い人だったんだそうですね。大阪で米はんにいろいろ聞いたんだが、あんまり面白いんですっかり忘れちゃった。が、兄さんなんかはこのお祖父さんの血を受けているのかも知れないね。」
いつか次弟の伸といろいろ近親のものの話をした時、弟がこう言って、しきりに折があったら米はん(従兄)にその話を聞いて見るように勧めた。
それまで僕は、母方の親戚では、山田の伯母と、そのすぐ次の妹の米はんのお母さんと、それからお祖母さんとだけしか知らなかった。そしてこのお祖父さんについては、何にも聞いたこともなく、また考えて見たこともなかった。お祖母さんが妙に下品な人だったので、母の家というのも、ろくな家じゃなかったろうくらいにしか考えていなかった。
それにこの米はんが大阪のある同志と知っていて、その同志との間によく僕の話をするということも聞いていたので、多少なつかしくも思っていた折だった。で、その翌年であったか、もう二、三年前になるが、大阪へ行ったついでにしばらく目で米はんを訪ねて見た。米はんはお祖母さんの家を継いで、淀屋橋の近くで靴屋をしていた。僕はちょうど二十年目で米はんと会った。
「僕誰だか分る?」
僕は店にいた米はんにいきなり声をかけた。尾行をまいて行ったので、店のものに僕が誰だかが分っても面白くないと思ったからでもあった。
「分らんでどうするものか。そんな目はうちの一族のほかにはどこにもないよ。」
米はんは僕よりももっと大きな目を見はりながら、大げさにこう言って、奥へ導いて行った。
お祖父さんは楠井力松と言った。和歌山の湊七曲りというところにあった、かなり大きな造り酒屋だったそうだ。子供の時から腕力人にすぐれて、悪戯がはげしく、十二の時に藩の指南番伊達何とかいう人に見出されて、その弟子となって、十八で免許皆伝を貰った。剣道、柔道、槍術、馬術、行くとして可ならざるはなく、ことに柔道はそのもっとも得意とするところであったそうだ。後、その指南番の後見のもとに、町道場を開いて、門弟五百人、内弟子百人あまりも養っていた。身の丈六尺四寸、目方四十貫という大男で、三十三で死んだのだが、その時でも三十五貫あまりあったそうだ。
「ある時、たぶんお祭の時だったろうと思うが、何でもないことにまで侍と町人との待遇があんまり違うというので怒り出して、とうとう大勢の侍を相手に大喧嘩をやって、それ以来いつも侍を敵にしては町人のために気を吐いていたんだそうだ。そしてそんなことで、とうとう家をつぶしてしまったんだね。」
お祖父さんについての米はんの話は、ずいぶん長くもあり、また雄弁でもあった。が、僕もやはり弟と同じように、それがあんまり面白いんで大がいは忘れてしまった。
父の家は、名古屋を距る西に四里、津島という町の近くの、越治村大字宇治というのにあった。今では、その越治村が隣り村と合併して、神守村となっている、父の家は代々その宇治の庄屋を勤めていたらしい。
大杉という姓も、邸内に大きな杉の木があって、何とかいう殿様が鷹狩りか何かの折に立ちよられて、「大きな杉じゃなあ」と御感遊ばされたとかいうところから、それを苗字にしたのだそうだ。あんまり当てにはならない話だが。そして今でもまだ、街道から目印になるような、大きな杉の木がそこに立っている。
父が日清戦争で留守の間に、宇治のお祖父さんが死んだというので、一日無理に学校を休ませられたことがあった。が、このお祖父さんについては、権九郎とか権七郎とかいう名のほかには、何にも聞いた覚えがない。
清洲の近くにいた丹羽何とかいう老人が、このお祖父さんの弟で、少しは名のある国学者だったように聞いている。その形見の硯や水入れが家にあった。そして僕が十五の時、幼年学校にはいるんで名古屋へ行った時、第一にこの老人に会うようにと父から言いつけられて行った。
父には二人兄があった。長兄は猪といって、宇治の家を継いで、村長などをやっていた。次のは一昌といって、名古屋にいたが、そして僕が幼年学校にいた間はずいぶん世話にもなったが、何をしていたのか僕には分らなかった。折々裁判所へ出かけて行くらしいので、僕は高利貸かなとも思っていた。
お祖父さんにはどのくらい財産があったのか知らないが、その死ぬ時に、この二人の伯父と父との間にそれが分配されたらしい。そして父の分は猪伯父が管理していたのだが、伯父がいろんな事業に手を出して失敗して、自分のは勿論父の分までも無くしてしまった。
「あれがあれば、お前達二人や三人の学費くらいは楽に出るんだったがね。」
母はよくこう言っては愚痴っていた。
たぶんそんなことからだろうと思うが、父は猪伯父のことをあまり面白く思っていなかったらしい。一昌伯父についてもやはり同じようだった。
そして父や母がほんとうに親戚らしくつきあっていたのは、山田の伯母一家だけらしかった。そしてまた、僕が多少の影響を受けているのも、この山田一家からだけらしい。僕の名の栄というのも、この伯母の名のよみを取ったものだ。
しかし肉親というものはさすがに争われない。猪伯父も一昌伯父も吃った。丹羽の老人も吃ったようだ。父も少し吃った。そして僕がまた吃りだ。
二
父には学歴はまるでなかった。
ただ子供の時から本を読むのが好きで、丹羽の老人のところから本を借りて来ては読んでいた。そしてその土地の習慣で、三男の父は一時お寺にはいって坊主になっていた。が、西南戦争が始まって、初めて青雲の志を抱いて、お寺を逃げ出して上京した。
そしてまず教導団にはいって、いったん下士官になって、さらにまた勉強して士官学校にはいった。
父は少尉になると間もなく母と結婚して、丸亀の連隊へやられた。そしてそこで僕が生れた。町の名も番地も知らない。戸籍には明治十八年五月十七日生とあるが、実際は一月十七日だそうだ。当時尉官はほとんど結婚を禁ぜられていたようなもので、結婚すると三百円の保証金を納めなければならなかった。父はそれができないで、母の姙娠が確定するまで結婚届が出せなかったのだそうだ。そしてそれと順送りに僕の出生届も遅れたのだそうだ。
が、父はまたすぐに近衛に帰った。
そして僕が五つの時に、父と母とは三人の子供をかかえて、越後の新発田に転任させられた。父はこの新発田にその後十四、五年もくすぶってしまった。僕も十五までそこで育った。したがって僕の故郷というのはほとんどこの新発田であり、そして僕の思い出もほとんどこの新発田に始まるのだ。
もっともその以前東京にいた時のことも少しは記憶している。
家は番町のどこかにあった。門の両側に二軒家があって、父の家はその奥にあった。そして門のそばのどちらかの家に、たしかお米さんという名の、僕より一つ年上の女の子があった。僕はそのお米さんと大仲好しだった。
お米さんはもう幼稚園へ行っていた。僕はまだだった。お米さんは学校で唱歌を教わって来ては、家へ帰って大きな声でそれをおさらえした。歌を何にも知らない僕はそれが癪にさわって堪らなかった。そして向うで何か歌い出すたびに、僕はせい一ぱいの声で、ただ
雨こんこん
雪こんこん
とだけ、幾度も繰りかえしては怒鳴りつづけていた。
が、五つの春から、僕も幼稚園に行くようになった。そして毎日お米さんと手をひいて、富士見小学校へ通った。
しかし、その幼稚園がはたして富士見小学校附属のであったかどうかは、実は断言することができないんだ。ただ、いつかふいとその前を通ったら、どうも見覚えがあるので、中にはいって見た。するとそれが長い間僕の頭の中にあった幼稚園そのままなんだ。で、僕はそれがこの富士見小学校附属のだと、ひとりで決めてしまったのだ。
この幼稚園でのことはほとんど何にも覚えていない。ただ、一度女の先生に叱られて、その顔に唾をひっかけてやったことがあるように思うが、これはその後母が話したのを覚えているのかも知れない。
唾では、その後も一度、小学校の女の先生にひっかけて泣かしたことがあった。
父が勤めていた連隊は青山練兵場の奥の方にあった。父は折々週番で帰って来なかった。ある日、たぶんその週番が三日目四日目と進んで大ぶさびしくなった頃だろう、例のお米さんを連れ出してそっと青山に出かけて行った。練兵場にはいった頃に、お米さんはもう歩けないと言って泣き出す。そこへ犬が吠えついて来て僕も泣き出す。しまいには二人で抱き合って声を限りに泣いていた。そして通りかかった兵隊になだめられて、ようやく父のところへ連れて行かれた。
新発田の連隊へ送られるのは、多くは何かのしくじりがあって、島ながしにされるのだと聞いたことがあった。新発田ばかりではない。遠い地方の田舎へやられるのは、多くはそうであったのかも知れない。
もうよほど後のことであるが、家に大勢士官が集まった。父はその士官等に、山田の伯父から送って来た葉巻をご馳走した。しかしそのお客の中で、この葉巻を満足に吸ったものはほとんど一人もなかった。みんな太い方を口へ持って行って、とがった先きにマッチの火をつけようとした。新発田というのはそんな田舎だったのだ。
しかし僕は父が何の失態で新発田へ逐いやられたのか知らない。週番で宮城につめていた時、何かの際に馬から跳ね飛ばされて、お濠の中に落っこちて、泥まみれになって上って来た。それを陛下がご覧になって、「猿じゃ猿じゃ」と笑い興ぜられたことがあったそうだ。しかしこれは父の光栄であって、決して失態ではなかろう。実際父はちょっと猿のような顔をしていた。
が、とにかく父は新発田に逐いやられたのだ。
父は、やはり同じ近衛から新発田へやられるもう一人の下士官と一緒に、東京を出た。僕はその旅の中で、碓氷峠を通る時のことだけを覚えている。碓氷峠にはまだアプト式の鉄道も布かれてなかった。そしてその海抜幾千尺か幾里かの峠を、僕等は二台のガタ馬車で走った。一台には父の同僚の家族が乗っていた。親子三人のようだった。もう一台には僕等が乗っていた。父と母とは各々一人ずつの妹を抱きかかえていた。僕は一人でしっかりと何かにしがみついていた。折々馬車が倒れそうに揺れる。下を見ると、幾十丈だか知れない深い谷底に、濃い霧が立ちこめている。僕は幾度胆を冷やしたか知れない。
僕はこの自叙伝を書く準備をしに、最近に、二十年目で新発田へ行って見た。その間には、もう十幾年か前に鉄道がかかって、そこに停車場もできている。ほとんど面目一新というほどに変っているだろうと期待して行った。そしてほとんどどこもかも、まるで二十年前そのままなのに驚かされた。
停車場の附近が変っていることは論はない。そして僕はそこを出るとすぐ、また新しい華奢な監獄のような製糸場が聳えているのを見て、ここにもやはり産業革命の波が押しよせたなとすぐ感じた。しかしそれは嘘だった。その後町のどこを歩いて見ても、その製糸場以外には、工場らしい工場一つ見つけ出すことはできなかった。新発田の町はやはり依然たる兵隊町だった。兵隊のお蔭でようやく食っている町だった。
製糸場は大倉喜八郎個人のもので、大倉製糸場の看板をさげていた。そしてこれは喜八郎の営利心を満足させるよりも、むしろその虚栄心のためのものであるようだ。喜八郎は新発田に生れた。何かで失敗して、近所じゅうに借金を残して、天秤棒一本持って夜逃げしたんだそうだ。が、あの通りの大富豪になり、ことには男爵になるに及んで、その郷里にこの製糸場と、そのすぐそばの諏訪神社の境内に自分の銅像を立てたのであった。
けれども、ここにもやはり、道徳的にはもう資本家主義が漲れて来ていた。喜八郎が自分の銅像を自分で建てることは喜八郎一人の勝手だ。しかしこの喜八郎の肖像が、麗々しく小学校の講堂にまで飾ってあるのだ。
父の家は十幾軒か引越して歩いた。そしてその中で三、四軒火事で焼けたほかには、ほとんどみな昔のままで残っていた。僕はその家の前を、ほとんどその引越し順に、一々廻って見た。
最初の家は焼けて無かった。しかしこの家については何の記憶もなかった。
その次の家も焼けて無かった。小学校へはこの家から通い出したのだから、七つか八つまでの頃だと思う。隣りに大川津という大工がいて、そこに僕よりも一つ二つ年上の男の子と、やはりそのくらい年下の女の子といた。僕はその二人と友達だった。
が、僕がそこで思い出したのは、この二人の友達のことではなかった。それは、もう一人の、そこから四、五丁離れたところにいた女の友達のことだった。この友達のことは、こんごもたぶん幾度も出て来るだろうと思うが、かりに光子さんと名づけて置く。
光子さんとは学校で同じ級だった。僕は何となく光子さんが好きで仕方がなかった。しかしお互いの家に交際があるのではなし、近所でもなし、ちょっと近づきになる方法がなかった。そして学校では、ぶつかりさえすれば、何かの仕方で意地悪をしていた。
ある日僕は、家にいて、急に光子さんの顔が見たくて堪らなくなった。そしてそとにいた大川津の妹の顔をいきなり殴りつけて、その頭にさしていた朱塗りの櫛をぬき取って、それをしっかと握ったまま、光子さんの家の方へ駈けていった。光子さんはうまく家の前で遊んでいた。僕は握っていた櫛をそこへほうりつけて、一目散にまた逃げて帰った。
三番目の家は、三の丸という町のつき当りの、小学校のすぐそばであった。学校は改築されてすっかり変っていたが、その家はもう大ぶ打ち傾きながらも三十年前そのままの面影を保っていた。
僕はしばらく門前にたたずんで、玄関のすぐ左の一室の窓を見つめていた。それが僕の室だったのだ。
窓の障子はとり払われていて、その奥の茶の間までも見えた。その茶の間と僕の室との間にも障子があった筈なのだ。そして僕の思い出はこの障子一つに集まった。
何をしたのかは忘れた。が、たぶんマッチで何か悪戯をしていたのだろう。母にうんと叱られて、その口惜しまぎれに、障子に火をつけた。障子は一度にパァと燃えあがった。母は大声をあげて女中を呼んだ。そして二人であわてて障子を押し倒して消してしまった。
この家から道を距てたすぐ前は、尋常四年の時の教室だった。僕はその教室のあったあたりを慄えるようにして眺めた。
受持の先生は島といった。まだ二十歳前後だったのだろう。ちんちくりんの癖に、いつも妙に口もとを引きしめて、意地悪そうに目を光らして、竹の根の鞭で机の上をぱちぱち鳴らしていた。何かというとすぐにそれで打つのだった。僕はほとんど毎日のようにこの鞭の下に立ちすくんだ。そして僕は、その事情はよく覚えていないが、この先生のお蔭で算術が嫌いになったような気がする。
その後五、六年して僕が幼年学校にいた頃、暑中休暇に、ふと道で東京でこの先生と出っくわしたことがあった。昔と同じように口もとを引きしめて意地悪そうな目つきはしていたが、僕よりもずっと背の低い、みすぼらしい風をした、小僧のような書生だった。
この学校の先生で覚えているのは、もう一人、斎藤というもういい加減な年の先生だった。二年か三年の時の先生だ。いつも大きな口をあけてげらげら笑いながら、いやに目尻をさげて女の生徒とばかり遊んでいる先生だった。よくいやがる光子さんなどを抱きかかえては、キャッキャッと言わしていた。
そして何か悪戯をすると、きっとその罰に、女の生徒の教室に立たした。教壇の上にあがらして、一杯に水を盛った茶碗を両手に持たして、みんなの方に向かして立たした。僕は先生の方から見えないのを幸いに、いつも舌を出したり目をむいたりしてみんなをからかっていた。
この教室の向うに教員室があって、そのまた向うに物置の土蔵があった。僕はその教員室に幾度とめ置きを食ったか知れない。そして時々はその真暗な土蔵の中にも押しこまれた。そこには古い机や椅子が積み重ねられてあった。だんだん目が馴れて来ると、鼡がその間をちょろちょろするのがよく見えた。あんまり長く置かれると、退屈して、よくそこに糞をたれてやった。
が、生徒の面倒をよく見てくれたのは、それらの先生ではなくって小使だった。背の低い、いつもにこにこしたのと、背の高い、でこぼこの恐い顔のと、二人いた。二人とも、ひまがあると、小使室で、大きな炉の中の大きな鉄瓶の前で、網をすいていた。僕はよく先生に叱られてはこの小使室へあまえに行った。そして小使の言うことは僕もよく聞いた。
三
こうして僕は毎日学校で先生に叱られたり罰せられたりしていた間に、家ででもまた始終母に折檻されていた。母の一日の仕事の主な一つは、僕を怒鳴りつけたり打ったりすることであるようだった。
母の声は大きかった。そしてその大きな声で始終何か言っていた。母を訪ねて来る客は、大がい門前まで来るまでに、母がいるかいないか分るというほどだった。その大きな声を一そう大きくして怒鳴りつけるのだ。そしてその叱りかたも実に無茶だった。
「また吃る。」
生来の吃りの僕をつかまえて、吃るたびにこう言って叱りつけるのだ。せっかちの母は、僕がぱちぱち瞬きしながら口をもぐもぐさせているのを、黙って見ていることができなかったのだ。そして「たたたた……」とでも吃り出そうものなら、もうどうしても辛抱ができなかったのだ。そしてこの「また吃った」ばかりで、横っ面をぴしゃんとやられたことが幾度あったか知れない。
「栄。」
と大きな声で呼ばれると、僕はきっとまた何かの悪戯が知れたんだろうと思って、おずおずしながら出て行った。
「箒を持っておいで。」
母は重ねてまた怒鳴った。僕は仕方なしに台所から長い竹の柄のついた箒を持って行った。
「ほんとにこの子は馬鹿なんですよ。箒を持って来いと言うと、いつも打たれる[#「打たれる」は底本では「打れたる」と誤記]ことが分っていながら、ちゃんと持って来るんですもの。そして早く逃げればいいのに、その箒をふりあげてもぼんやりして突っ立っているんでしょう。なお癪にさわって打たない訳には行かないじゃありませんか。」
母は僕の頭をなでながら、やはり軍人の細君の、仲好しの谷さんに言った。
「でも、箒はあんまりひどいわ。」
谷のお母さんもやはり家の母と同じように大勢の子持だった。そしてやはりよくその子供を打った。しかし母にこの抗議をする資格は十分にあったのだ。
「それや、ひどいとは思いますがね。もうこう大きくなっちゃ、手で打つんではこっちの手が痛いばかしですからね。」
谷のお母さんは、優しい目で「でも、ひどいわね」という意味を僕に見せながら、それでもやはりこれには同感しているようだった。そして話はお互いの子供の腕白さに移って行った。
が、僕は母の言うこの「馬鹿なんですよ。」に少々得意でいた。そして腹の中でひそかにこう思っていた。
「箒だってそんなに痛かないや。それに打たれるからって逃げる奴があるかい。」
父はちっとも叱らなかった。
「あなたがそんなだから、子供がちっとも言うことを聞かないんですよ。」
母はよく父を歯がゆがって責めた。そして日曜で父が家にいる時には、今日こそは是非叱って下さいと迫った。
「今日は日曜だからな、あしたうんと叱ってやろう……うん、そうか、また喧嘩をしおったのか……何、勝った?……うん、それやえらい、でかした、でかした……」
父は母が迫れば迫るほど呑気だった。
母はたべ物にずいぶん気むずかしかった。ことに飯にはやかましかった。
「僕のもめっかちだよ。」
母が飯の小言を言うと、僕もすぐそれについて雷同した。
「心が曲っていると、めっかちのご飯が行くんだ。お父さんのなんか、それやおいしい、いいご飯だ。」
僕は父がこう言うんで、ほんとうかしらと思って、無理に父の茶碗の飯を食って見た。しかしそれは、勿論、やはりめっかちだった。
父はこんなふうで、女中達にも小言一つ言ったことがなかった。
父は家のことも子供のこともすっかり母に任しきりにしていたのだ。それで、小言も言わない代りに、家のことや子供等とはまるで没交渉でいたのだ。朝早く隊へ出て、夕方帰って来て、夜は大がい自分の室で何か読むか書くかしていた。で、子供等は朝飯と夕飯の時のほかは、めったに父と一緒のことはなかった。
それでも父は僕を軍人に仕込むことだけは忘れなかったようだ。父が日清戦争に行く前のことだから、僕がまだ九つか十の時だ。父は毎日他の士官等と一緒に、家のすぐ前の練兵場の射的場で、ピストルの稽古をした。それにはきっと僕を連れて行った。そして僕にもピストルの撃ちかたを教えて撃たして見た。
僕が父の馬に乗るのを覚えたのも、やはりその頃のことだった。
また、その日清戦争から帰って来てからは、一里ばかりある大宝寺という、ほんとうの実弾射撃をやる射的場へ連れて行った。そしてそこでは、ビュウビュウ頭の上へ弾丸が飛んで来る、的の下の穴の中へ連れて行かれた。
十四か五の時には刀剣の見かたを教わった。刀屋が刀を持って来ると、僕もきっとその席に出しゃばっていた。そして無銘の新刀を一本貰って、藁の中に竹を入れて束ねたのを試し斬りをやらされた。スパリスパリと気持よく斬れた。
幼年学校にはいってからは、暑中休暇に是非一度、佐渡へ地図をとりに連れて行くと言っていたが、これは父の方にひまがなくって果されなかった。そして一、二度、一、二泊の近村への演習に連れて行かれた。
それと、幼年学校にはいる前に父からドイツ語を少し教わったほかには、僕は子供の時の父との親しい交渉をあまり覚えていない。
日清戦争前には、僕の家は、今言った練兵場に沿うた、片田町というのにあった。四番目の家だ。これも焼けて無かった。
その頃の僕の遊び場は練兵場だった。
射的場と兵営のお濠との間には障害物があった。これは、二、三百メートルばかりの間に、灌木の藪や、石垣や、濠や、独木橋や、木柵などをならべ立てたもので、それを兵隊が競走するのだった。僕はそこで毎日猿のように、藪を飛び、濠を越え、橋を渡って遊んでいた。兵隊が競争しているそばへ行って、それと一緒に走り出しても、大がいは僕が先登だった。それが飽きると、というよりもむしろ、もう夕方近くなって兵隊がみな隊に帰ると、僕はよく射的場の弾丸をほりに行った。
大宝寺の方の弾丸は鉛の細長いのだったが、ここのは丸かった。昔の単発銃のだからずいぶん大きかった。僕はそれを四十も五十も拾って来ては、それを溶かして、いろんな形をこしらえて喜んでいた。
この弾丸をほることは一つの冒険だった。時々衛兵が見廻りに来た。衛兵でない兵隊もよくそこを通った。で、普通は、夜暗くなってからでなければ取りに行かなかったのだ。
が、僕のこの例を見て、仲間が大ぶ増えた。そしてその仲間等は、僕が一緒にいれば見つかって捕まっても大事はないと思ったのか、いつも僕を誘っては取りに行った。僕はこの仲間の中にはいって妙なことを発見した。それは、みんなの弾丸を一つにまとめて、ジャン拳で番をきめて、どこかへそれを売りに行くのだった。そして帰りには何かの菓子を買って来た。僕も一度その仲間入りをした。もっともジャン拳だけは遁れた。それがどうした訳だったか、その一度きりで僕はまた仲間はずれになってしまった。この仲間というのは、町はずれの、ちょっと貧民窟といったようなところの子供等だった。
この家の裏に広い竹藪があった。栗だの、柿だの、梨だの、梅だのの、いろんな果物の木もあった。
そしてその竹藪には、孟宗のほかに、細い、その竹の子をおもちゃにしてポンポン吹いて鳴らす竹があった。やはりどうかした拍子に急に会いたくなって、僕は一度、その竹の子を持って光子さんのところへ行ったことがあった。
しかしこの竹藪はそんな優しいことばかりには使われなかった。
新発田は新発田町というのと、新発田本村というのと二つに分れていた。町というのは昔の町人町で、本村というのは侍屋敷のあったところだ。今でもやはりそうだが、その当時もやはり大体そうなっていた。小学校も尋常小学校は別々にあった。そしてこの町と本村では、風俗にも気風にも大ぶ違うところがあった。
町の子が練兵場に遊びに来ると、彼等は障害物も何もできないので僕等はよく彼等をからかったり苛めたりした。そんなことがいろいろと重なって、とうとう町の子と僕等との長い間解けなかった大喧嘩となった。
僕等の方は十二、三の子が十人ほどいた。士官の子は僕一人で、あとはみな土地の子だった。そして僕は十で一番年下だった。町の方は二十人くらいから三十人くらいまでいた。年はやはり十二、三が多いのだが、十四、五のも三、四人まじっていた。
戦争は大がい片田町から町の方の仲町というのに通ずる竹町で行われた。いつも向うから押しよせて来るので、僕等はそれを竹町の入口で防いだのだった。竹町というのは、わりに道はばも広く、それに両側に家がごくまばらだったので、暗黙の間にそこを戦場ときめてしまったのだ。
僕は家の竹藪から手頃の竹を切ってみんなに渡した。手ぶらで来た敵は、それでもう第一戦で負けてしまった。
次には彼等もやはり竹竿を持って来た。しかしそれは、多くは、長い間物ほしに使ったのや、あるいはどこかの古い垣根から引っこぬいて来たのだった。接戦がはじまって、両方でパチパチ叩き合っているうちに、彼等の竹竿はみなめちゃくちゃに折れてしまった。
二度とも僕は一番先登にいたんだが、向うでもやはり二度とも同じ奴が先登にいた。そいつは仲町の隣りの下町の、ある豆腐屋の小僧で、頭に大きな禿があるので、それを隠すためにちょん髷を結っていた。もう十五、六になっていたんだろうが、喧嘩がばかに好きで、一銭か二銭かで喧嘩を買って歩くという男だった。この時にもやはり幾らか出して敵の仲間に入れて貰ったのだ。僕はそいつが気味が悪いのと同時に、憎らしくって堪らなかった。で、どうかしてそいつを取っちめてやろうと思っていた。
三度目の時は石合戦だった。両方で懐ろにうんと小石をつめこんで、遠くからそれを投げ合っては進んで行った。どうしたのか、敵の方が早く弾丸がなくなって、そろそろ尻ごみしはじめた。僕はどしどし詰めよせて行った。敵は総敗北になった。が、ちょん髷先生ただ一人、ふみ止まっていて動かない。とうとうみんなでそいつをおっ捕えて、さんざんに蹴ったり打ったりして、そばのお濠の中へほうりなげて、凱歌をあげて引きあげた。
四
僕はこんな喧嘩に夢中になっている間に、ますます殺伐なそして残忍な気性を養って行ったらしい。何にもしない犬や猫を、見つけ次第になぐり殺した。そしてある日、例の障害物のところで、その時にはことさらに残忍な殺しかたをしたように思うが、とにかく一疋の猫をなぶり殺しのようにして家に帰った。自分でも何だか気持が悪くって、夕飯もろくに食わずに寝てしまった。
母は何のこととも知らずに、心配して僕の枕もとにいた。大ぶ熱もあったんだそうだ。夜なかに、ふいと僕が起きあがった。母はびっくりして見守っていた。すると僕が妙な手つきをして、「にゃあ」と一と声鳴いたんだそうだ。母はすぐにすべてのことが分った。
「ほんとうに気味が悪いの何のって、私あんなことは生れて初めてでしたわ。でも私、猫の精なんかに負けちゃ大変だと思って、一生懸命になって力んで、『馬鹿ッ』と怒鳴ると一緒に平っ手でうんと頬ぺたを殴ってやったんです。すると、それでもまだ妙な手つきをしたまま、目をまんまるく光らしているんでしょう。私もう堪らなくなって、もう一度、『意気地なし、そんな弱いことで猫などを殺す奴があるか、馬鹿ッ』と怒鳴って、また頬ぺたを一つ、ほんとうに力一杯殴ってやったんです。それで、そのまま横になって、ぐうぐう寝てしまいましたがね。ほんとうに私、あんなに心配したことはありませんでしたよ。」
母はよくこう言って、その時のことを人に話した。そして僕は、その時以来、犬や猫を殺さないようになった。
やはり片田町のその家にいた時のことだ。
正月に下士官が大勢遊びに来た。父はしばらくそのお相手をしていたが、やがて奥の自分の室にはいって寝てしまった。父は酒が飲めないんで、ほんの少しでも飲むとすぐに寝てしまうんだった。
下士官等はまだ長い間座敷で飲んでいた。が、そのうちに、誰か一人が「副官がいないぞ」と怒鳴り出した。
「怪しからん、どこへ逃げた。」
「引きずって来い。」
「来なけれやこれで打ち殺してやる。」
へべれけに酔った四、五人の曹長どもが、長い剣を抜いて立ちあがった。僕はその次の室で、母や女中と一緒に、どうなることかと思ってはらはらして聞いていた。
「奥さん、副官をどこへ隠した?」
曹長どもはその間の襖を開けて母に迫って来た。僕は母にぴったりと寄り添っていた。女中は青くなって慄えていた。
「どこへも隠しやしません。宿もまたどこへも逃げかくれはしません。さあ、私がご案内しますからこちらへいらっしゃい。宿は自分の室でちゃんと寝ているんです。」
母はこう言いながら突っ立って、
「栄、お前も一緒においで。」
と僕の手をとって、さっさと父の室の方へ行った。そしてそこの襖を開けて、
「さあ、みなさん、この通りここに寝ているんです。突くなり斬るなり、どうなりともお勝手になさい。」
と、きめつけた。僕も母のこの元気に勢いを得て、どいつでも真っさきにこの室へはいって来る奴に飛びついてやろうと、小さな握拳をかためて身構えていた。
が、曹長どもは母のけん幕に飲まれて、うしろの方から一人逃げ二人逃げだして、とうとうみんな逃げ出してしまった。そして※々にして帰ってしまった。
翌日、その下士官どもが一人ずつあやまりに来た。僕は母と一緒に玄関に出て、そのしょげかえった様子を見て、痛快でもあり、また可笑しくて堪らなかった。
父が日清戦争で出征するとすぐ、竹町とは反対の方の片田町の隣りの、西ヶ輪[#底本では「西ケ輪」]という町に引越した。斎藤という洋服屋の裏の小さな家だった。そして父がまだ宇品で御用船の出帆を待っている間に、母に男の子が生れた。父から「イサムトナヲツケヨ」と電報が来た。三の丸では次弟が生れた。片田町では三番目の妹が生れた。そして、これで僕は三人の妹と二人の弟との五人の兄きとなった。母はこの六人の子と一人の女中と都合八人で、二階一間下三間の、庭も何にもない小さな家にひっこんだのだ。片田町の家は七間か八間あった。そしてできるだけの倹約をして貯金を始めた。
母は仮名のほかは書けないので、手紙の上封はみな僕が書かされた。中味も、父と山田の伯母へやるののほかは、大がい僕が書かされた。母が口で言うのを候文になおして書くんだが、まだ学校で教わらないような用事ばかりなので閉口した。母はずいぶんもどかしがりながらも、そのできあがるのを喜んで、自慢で人に見せていた。しかし僕は、それよりも、よそから来る手紙を母に読んで聞かせる方が、よほど得意だった。
ある日僕は学校から帰って来た。そしていつもの通り「ただ今」と言って家にはいった。が、それと同時に僕はすぐハッと思った。母と馬丁のおかみさんと女中と、それにもう一人誰だったか男と、長い手紙を前にひろげて、みんなでおろおろ泣いていた。僕はきっと父に何かの異状があったのだと思った。僕は泣きそうになって母の膝のところへ飛んで行った。
「今お父さんからお手紙が来たの。大変な激戦でね、お父さんのお馬が四つも大砲の弾丸に当って死んだんですって。」
母は僕をしっかりと抱きしめて、赤く脹れあがった大きな目からぽろぽろ涙を流して、その手紙の内容をざっと話してくれた。
場所は威海衛だ。父の大隊は海上に二艘日本の軍艦が浮かんでいるので、安心して海岸の方へ廻って行った。するとその軍艦が急に日章旗をおろして砲撃を始めた。それが鎮遠、定遠だとかいうことだった。父の大隊は驚いて逃げだした。するとこんどはその逃げ出すさきの丘の方から、味方の軍隊が盛んに鉄砲を打ち出した。たぶん、日本の軍艦から砲撃されるんだから敵の軍隊だろうと思ったんだろう、ということだった。父の大隊は敵と味方とに挾みうちされて進退きわまった。
大隊の副官であった父は、すぐに大隊長と相談して、その味方の軍隊まで伝令に行った。敵の砲弾はますます花火のように散る。味方からの弾丸もますます霰のように飛んで来る。父はその間を二人の騎兵を連れて駈けて行った。が、その一人はすぐに倒れてしまった。そして父の馬もまた続いて倒れてしまった。父は仕方なしにもう一人の騎兵をそこに残して、その馬を借りてまた駈け出して行った。
「それで首尾よく任務は果したんだそうだがね、可哀そうにお馬は、お腹と足と四つも弾丸を受けて、その場で死んでしまったんですとさ。お父さんのお身代りをしたんだわね。」
母はこう言ってまた大きな涙をぽろぽろと流した。馬丁のかみさんも女中もまた一緒になって泣いた。しかし僕は、あの馬が父の身代りをしてくれたのかと思うと、何だかこう非常に勇ましいような気がして、どうしても泣けなかった。
父が凱旋して来てから、ある日家で、その当時の同じ大隊の士官連が集まって酒を飲んだことがあった。
「奥さん、この男がその時に即死の電報のあった男ですがね。その筈ですよ。今でもまだこんな大きな創が残っているんですからね。」
もう大ぶ酒がまわった頃に、一人の士官がもう一人の士官の肩を叩いて言った。そして、
「おい、貴様はだかになれ、何、構うもんか、名誉の負傷だ。ね、奥さん。」
と言いながら、無理にその士官をはだかにさせてしまった。酒に酔って真赤になっている背中の、左の肩から右の腋の下にかけて、大きな創あとの溝がほれていた。
「この通り、腕が半分うまってしまうんですからな。」
最初の士官が腕を延ばして、それをその溝の中へ当てがって見せた。実際その腕は半分創あとの中にうまっていた。
さすがの母も「まあ」と言ったきり顔をそむけていた。僕も少し気味が悪かった。
父の馬もこの士官と同じように、いったん即死を伝えられた後に生き返って、ちんばになって帰って来た。父は母と相談して、生涯飼い殺しにしたいと言っていたが、そうもできないものと見えてその後払下げになってしまった。
父はこの功で金鵄勲章を貰った。
僕は今まであちこちの父の家が焼けて無くなっていたと書いて来た。それは、やはりこの日清戦争で留守の間に、与茂七火事という大きな火事があったのだ。
幾月頃か忘れたが、もう薄ら寒くなってからのことのように思う。ある夜、十一時頃に、火事が起きた。僕のいた西ヶ輪[#底本では「西ケ輪」]は新発田のほとんど西の端で、その火もとはほとんど東の端だった。で、一時間ばかりは、家でその火の手のあがるのを見ていた。が、火は容易に消えそうもなかった。ますます火の手が大きくなって近所へ燃え移って行くようだった。
僕はすぐ走って見に行った。そして一時間か二時間あちこちで見物していた。ある時には火のすぐそばまで行って見た。というよりもむしろ、火にすぐそばまで追っかけられて来た。火事場から四町も五町も遠くで見ていたつもりなのに、うっかりしているうちにもう火がすぐそばまで来ていた。火焔の舌が屋根を舐[#底本では「舐」が「甜」]めるようにして走って来るのだ。そして、僕は、そうこうしているうちに、火事場へ走って行く人はほとんどなくなって、火事場の方から逃げて来る人ばかりなのに気がついた。
長い間天気が続いて、薄い板の木っ葉屋根がそり返るほどに乾ききっていた。火はこの屋根の上を伝って、あちこちの道に分れて、しかもそれがみな飛ぶようにして走り廻るのだ。ついには消防夫すらも逃げて帰った。
僕もあわてて家の方へ走った。そして二、三町行った頃に、今までそのそばで見ていた鬼子母神という寺に火のついたのを見た。茅ぶきの大きな屋根だ。それがその屋根一ぱいの大きな火の柱になって燃え出した。
火はまだ僕の家からは七、八町のところにあった。しかし僕はもう当然それが僕の家まで燃えて来るものと思った。僕は家に帰ってすぐ母に荷物を出すようにと言った。近所でももうみな荷ごしらえにかかっていたのだ。
「見っともないからそんなにあわてるんじゃない。」
母はこう言ってなかなか応じない。しかし火の手はだんだん近づいて来る。僕はもう一時間としないうちにきっと火がここまで来ると思った。そして母にせめては荷ごしらえでもするように迫った。
「荷物は近所でみな出してしまってからでも間に合います。あんまり急いで、あとで笑われるようなことがあってはいけません。まあ、もう少しそこで見ていらっしゃい。」
母はこう言いながら、しかし女中には何か言いつけているようだった。そしてしばらくして僕を呼んだ。
「もういよいよあぶないから、お前は子供をみんなつれて立ちのいておくれ。練兵場の真ん中の、あの銀杏の木のところね。あそこにじっとしているんだよ。いいかい、決してほかへは行かないようにね。」
母はふろしき包みを一つ僕に持たしてこう言った。そしてすぐの妹に一番下の弟をおんぶさした。
西ヶ輪[#底本では「西ケ輪」]を真っすぐに行けば、三、四町でもう練兵場の入口なのだ。練兵場にはもうぼつぼつ荷物が持ちこまれてあった。僕等は母の言いつけ通り銀杏の木の下を占領した。
この銀杏の木は前に言った射的場ともとの僕の家の間にあった。そしてその家にはやはり軍人の秋山というのが住んでいた。母はその「秋山さんの伯母さんにみんなが銀杏の木の下にいることを知らしてお置き」と注意してあった。
秋山家ではのん気でいた。裏は広し、近所は離れているし、どんなことがあっても大丈夫だと安心していた。が、僕がその家を出て銀杏の木の下に帰るか帰らないうちに、僕は大きな火の玉のようなものがそこの屋根へ落ちたのを見た。そしてアッと思っているうちに、それがパッと燃えあがった。
母と女中が少しばかりの荷物を持ってやって来た。僕は布団にくるまって寝てしまった。
火は昼頃まで続いて、新発田のいわゆる町のほとんど全部と本村の一部分の、二千五百戸ばかりを焼いてしまった。
与茂七火事というのは、その幾十年か前にも一度あったんだそうだ。与茂七というのが無実の罪でひどい拷問にあって殺されてしまった。そのたたりなんだそうだ。そして現に、今言った秋山家の家は、当時その拷問をした役人の一人の家だったそうだ。それで近所はみな焼け残ったのに、特にその家だけが焼けたのだそうだ。僕の見た火の玉というのもほかに見たと言う人が大勢あった。ほかにもまだ、大ぶあちこちにそういった家があった。そしてそれは、秋山家をはじめほとんどみな、大きな茅ぶきの古い家だった。僕のいたその家のあとは、いまだに、まだ家もできずに広いあき地になっている。
大倉喜八郎の銅像が立っている諏訪神社の境内に、与茂七神社という小さな社がある。これはその後与茂七を祀ったものだ。
自叙伝(二)
一
焼け出されの僕等は、翌日の夕方、やはり軍人仲間の大立目という家に同居することになった。練兵場に沿うた、小学校の裏の家だった。
そこにも子供が六、七人いた。その一番上のが明といって、学校も年も僕より二年上だった。僕はその明の少しぼんやりなのをふだんから軽蔑していた。そして引越し早々喧嘩を始めて、その翌日、家の前の溝の中に叩きこんでしまった。
明は泥だらけになって泣いて帰った。そしてそのお母さんから、「年上のくせに負けて泣く奴があるか」と叱られて、着物を着かえさせられる前に二つ三つ頬をなぐられた。
母は珍らしく大して僕を叱りもせずに、すぐどこかへ出かけて行った。そして、その翌日の朝早く、八軒町裏という町の、小学校のある女の先生の家に引越した。玄関とも入れて三間ばかりの家の六畳の座敷を借りたのだ。先生は一人でその次の室にいた。
「お前が喧嘩なんぞするものだから……」
母はこう言ってちょっと僕をにらみながら、こんどは何か荷物を片づけている女中の方に向いて、
「ほんとうにこの子が少し負けてくれればいいんだがね……」
と眉をしかめて見せながら、それでも
「こんどは相手が先生なんだから……」
と笑っていた。
半月ほどその家にいるうちに、四、五軒先きの小さな家があいて、そこへ引越した。
大きな一廓の中に、三つ建物があって、その一つが二軒長屋になっていた。その一軒に横井というたぶん軍属がいて、もう一軒の方に僕等が住んだのだ。一番大きな建物には石川という少佐の家があった。その家は、ほかの二つの建物とは裏合せになって、特に塀で区劃されて、八軒町という町の方に向いていた。もう一つの僕等の方と隣りの建物には、山形というやはり少佐か大尉かの家があった。僕の父もその頃は戦地で大尉になっていた。
山形の家には僕より二つ三つ上のを頭に四、五人男の子がいた。その一番上の太郎というのは、会津の中学校にはいっていて、滅多に家には帰らなかった。その次の次郎がちょうどいい僕の友達だった。石川の家にも男の子が二人いた。その上の四郎というのは山形の一番上のと同じ年恰好だった。横井の家にも僕と同じ年頃の男の子が一人いた。それともう一人、石川の家の筋向いの、大久保という大尉の家の子供と、それだけがすぐに友達になってしまった。もっとも横井の「黄疸」だけは僕のほかの誰も相手にしなかった。そしてその僕もいじめることのほかにはあまり相手にしなかった。
しかしみんなはあまり仲のいい友達ではなかった。喧嘩はしなかったが、お互いに軽蔑し合っていた。石川と大久保とは古くから向い合って住んでいて仲が善かった。僕はこの二人のレファインされたお坊ちゃんらしさが気にくわなかった。二人は僕の野生的なのを馬鹿に[#底本では「に」が欠如]していたようだった。山形の次郎もお坊ちゃんだった。が、彼は長い間町の方に住んでいて、町の小学校に通っていたところから、石川や大久保とは違ったレファインメントを持っていた。したがってその二人とほんとうに親しむことはできなかった。僕はその山形の中にも多分の野獣性が潜んでいるのを見ていた。しかしその町人らしいレファインさは堪らなくいやだった。彼は多くはその弟を相手に遊んでいた。僕は大がい横井の「黄疸」をいじめて暮していた。栄養不良らしいその黄色な顔から、僕等は彼をそう呼んでいたのだ。横井はその妹の、やはり痩せた黄色い顔をしたのと、さびしそうに遊んでいた。
お互いの母同士の間にも親しい交際はまるでなかった。
その山形の家からお化が出た。
夜なかに、台所で、マッチを磨る音がする。竈の火の燃える音がする。まな板の上で何かを切る音がする。足音がする。戸棚を開ける音がする。茶碗の音がする。話し声がする。そうした騒ぎが一時間も続くのだ。
ある晩、山形の「伯母さん」というのが、便所へ行った帰りに、手を洗おうと思って雨戸を開けた。まんまるい大きい月が庭の松の木の間に引っ懸っているように見えた。庭はその月あかりで昼のように明るかった。伯母さんは手洗鉢の方へ手をやった。鉢の中の水にもまんまるい月が映っていた。が、その水を汲もうとすると、急にバラバラと大粒の雨が降って来た。可笑しいなと思って顔をあげると、雨も何にも降っていないで松の木の間にはやはりまんまるい月があかあかと光っていた。伯母さんは再び手洗鉢の方へ手をやった。すると、急にまた、バラバラと降って来た。伯母さんは恐ろしくなって、そのまま、寝床へ逃げて帰った。
翌晩、伯母さんはまた夜遅く目がさめた。そしてまた便所へ行きかけた。障子をあけた拍子に伯母さんの足もとに、何だか重そうなものがバタンと落ちた音がして、それが向うの方へころころと転がって行った。伯母さんは気味悪がりながら、暗をすかしてその転がって行くのを見ていると、それが真暗な中にはっきりと大きな人の首に見えた。伯母さんはそのままキャッと叫んでそこに倒れてしまった。
それから二日目か三日目の晩に、伯母さんは、こんどは大入道が突っ立っているのを廊下で見た。
山形家は大騒ぎになった。もといた家の近所の、町の若衆が四、五人泊りに来た。みんなは樫の棒を一本ずつ横において夜じゅう飲みあかした。それで二晩三晩はお化が出なかった。が、その若衆連が帰ると、すぐまたお化が出た。
そんなことが幾度も繰返されているうちに、最後に、山形のお母さんがふだんから信心しているある坊さんが祈祷に来た。そして坊さんは幾晩か泊って行ったようだった。
その祈祷のおかげでお化が消えてなくなったかどうかは今よく覚えていない。しかしこの坊さんというのがどうもくせものだったように思われる。
石川や大久保の家ではこのお化の話をてんで相手にしなかった。そしてそれを、要するにその坊さんを泊りこませたい、何等かの策略のようにうわさしていた。山形のお母さんというのはちょっと意気なところのある人だった。
それから、やはりその頃のことだが、戦勝の祈祷と各自の夫の無事を希う祈祷との、夫人連の会があった。その祈祷にはやはり今ここに問題になっている坊さんが出たのだった。そしてその席上で、どことかの奥さんが、その坊さんの肩にしがみついたとかどうとかという話もあった。また、その坊さんのお寺というのは、新発田から三里ばかりある菅谷という山の中にあるのだが、そこまでわざわざお参りに行った奥さんもあった、というような話もあった。
が、このお化は僕の家にもたった一度出た。母は何かの病気で一週間ほどどこかの温泉へ行っていた。その留守のある晩に、僕のすぐの妹と女中とが夜なかにふと目がさめてどうしても眠られずにいる間に、台所の方で例のカタカタコトコトが始まった。二人はものも言わずに慄えていた。が、それと同時に、横井の家の小さな飼犬が盛んに吠え出した。そしてわずか二、三分の間にお化は逃げ出してしまった。
しかし妹等と隣りの室に寝ていた僕は何にも知らずに眠っていた。そして翌日その話をされた時にも僕は「馬鹿な」と言って笑っていた。が、女中は恐いのと心配なのとで、母に電報を打ってすぐ帰って貰った。母は「お母さんとお兄さんとがいれば大丈夫だ」と言ってみんなを慰めていた。そして実際母は何にも心配しているように見えなかった。
その後四、五年して、名古屋の幼年学校で山形の太郎と会った時、自分はこの耳でその音を聞いたんだからどうしてもあのお化を信ずると言っていた。山形は僕より二年前に幼年学校にはいっていたのだ。
お化はまた戦死した軍人の家にも出た。
ある若い細君が、夜なかにふと自分の名を呼ばれたような気がして、目をあけた。するとその枕もとに、血だらけになった夫が立っていた。
そしてその細君は、翌朝、夫の名誉の戦死の電報を受けとった。
二
二、三カ月その家にいたあとで、二軒町という隣り町の、高等小学校のすぐ前に引越した。そして、そこで初めて、十の年の暮に、僕は性の遊びを覚えた。
同じ焼け出されの軍人の家に川村というのがあった。そのお母さんと娘とがすぐ近所に間借りをしていた。母とそのお母さんとは兄弟のように親しくしていた。僕もそのお母さんは大好きだった。が、それよりも僕は、その娘のお花さんというのがもっと大好きだった。
お花さんは僕とおない年か、あるいは一つくらい年下だった。ほとんど毎日僕の家に遊びに来た。そして大抵は、妹等と遊ばずに、僕とばかり遊んでいた。
みんなで一緒に遊ぶ時には、よくみんなが炬燵にあたって、花がるたかトランプをして遊んだ。そんな時にはお花さんはきっと僕のそばに座を占めた。お花さんの手と僕の手とは、折さえあれば、炬燵の中でしっかりと握られていた。あるいはそっとお互いの指先きでふざけ合っていた。そして二人で、お互いにいい気持になって、知らん間にそれをほんとうの(三字削除)びに使っていた。
が、お花さんも僕も、それだけのことでは満足ができなかった。二人は、二階の僕の室で、よく二時間も三時間も暮した。そしてそこでは、誰に憚ることもなく、大人のようなことをして遊んでいた。
その頃僕にはもう一人の女の友達があった。それは、やはり近所に住んでいた、千田という軍人の娘だった。
ある日僕は、どんないたずらをしたのか忘れたが、母に「あやまれ」と言って迫られた。が、迫られれば迫られるほど、ますますあやまることができなくなった。
夕飯が済んでから、母は「もうこんな強情な子の世話はできないから、東京の山田の伯母さんのところへ行ってしまう」と言って、女中や子供等にみんなに着物を着かえさして、小さな行李を一つ持って、みんなでどこかへ出かけて行った。僕は東京へ行くというのは嘘だろうと思ったが、そのやりかたが大げさなので、実際どこかへ行ってしまうのじゃあるまいかと心細くなった。しかし、何だってあやまるものかと思いながら、仕方なしに床を敷いて寝ていた。
二、三時間して、玄関へどやどやと大勢はいって来る声がした。母を始め出て行ったみんなと、千田のお母さんと娘の礼ちゃんとが来たのだ。
「伯母さんがあやまってあげるから、もう決してしないっておっしゃいね。」
千田のお母さんは僕の枕もとに来てしきりに僕を説いた。が、それが母と相談の上だと思うと、なお僕はあやまりたくなくなった。
「ざまあ見ろ。とうとうみんな帰って来たじゃないか。」
僕はひそかにそう思いながら、黙って布団を頭からかぶっていた。
「あの通り強情なんですからね……」
母はそう言いながら、また何か嚇かす方法を相談しているようだった。
「あなたもまたいい加減に馬鹿はお止しなさいよ。」
千田のお母さんは母をたしなめて、このまま黙って寝かして置くようにと勧めていた。
その間に礼ちゃんが僕のそばへやって来た。そしてそっとその手を布団の中に入れて僕の手を握った。
「ね、栄さん、わたしがあやまってあげるわね。いいでしょう、もう決してしないから勘弁して下さいってね。わたしが代りにあやまってあげるわ。ね、いいでしょう。もうあやまるわね。」
礼ちゃんは布団をまくって、じっと僕の顔を見ながら、「ね、ね」と幾度も繰返して言った。僕の堅くなっていた胸が、それでだんだん和らいで行った。そしてとうとう僕は黙ってうなずいてしまった。
お花さんは町の方の小学校に通っていた。礼ちゃんは僕よりも一年下の級だった。そして光子さんは僕と同じ級だった。
礼ちゃんの級では、礼ちゃんが一番評判の美人だった。学科の方でもやはり一番だった。光子さんの級では、光子さんが一番出来がよかった。しかし綺麗という点の評判では、有力な一人の競争者を持っていた。それは絹川玉子さんといった。
玉子さんは休職軍人の娘だった。まる顔の、頬の豊かな、目の小さくまるい、可愛らしい子だった。しかし僕は、そのどこかしら高慢ちきなのが、気に食わなかった。着物もいつも綺麗なのを着ていた。そして妙にそり返って、ゆったりと足を運んで歩いていた。今考えても、ちょっとこう、小さな公爵夫人というような気がする。
光子さんは衛戍病院のごく下級な薬剤師か何かの娘だった。彼女の着物はいつも垢じみていた。細面で、頬はこけていた。そして、玉子さんのように色つやのいい赤味ではなく、何だかこう下品な赤味を帯びていた。目は細く切れていた。
ある日僕は玉子さんを道に要して通せんぼをした。彼女は何にも言わずに、ただ頬を脹らして、じっと僕をにらめていた。僕はそうした彼女の態度が大嫌いだったのだ。それがもし光子さんであれば、彼女はきっと「いやよ」とか何とか叫んで、僕の手を押しのけて行こうとするのだ。そしてそれを望みで僕はよく彼女を通せんぼした。
美少年の石川や大久保は玉子さんびいきだった。それで僕はなおさら玉子さんを嫌って光子さんびいきになった。
二軒町のその家の隣りに、吉田という、近村のちょっとした金持が住んでいた。
僕はそこのちょうど僕と同じ年頃の男の子と友達になった。が、すぐに僕は、その男の子と遊ぶのをよして、そのお母さんと遊ぶようになった。
この伯母さんは、火事で火の子をかぶったのだと言って、髪を短かく切っていた。どちらかの眉の上に大きな疣のようなほくろのある、あまり綺麗な人ではなかった。
伯母さんはその子と僕とにちょいちょい英語や数学を教えてくれた。そしていつも僕が覚えがいいと言っては、その御ほうびに、僕をしっかりと抱きかかえて頬ずりをしてくれた。僕はその御ほうびが嬉しくて堪らなかった。
「私はね、こんな家へお嫁に来るんじゃなかったけど、だまされて来たの、でも、今にまたこんな家は出て行くわ。」
伯母さんはその子供のいない時に、いつもの御ほうびで僕を喜ばせながら、そんな話までして聞かした。そして実際、その後しばらくして出て行ったらしかった。
この家の裏は広い田圃だった。そして雨のしょぼしょぼと降る晩には、遠くの向うの方に、狐の嫁入りというのが見えた。
提灯のようなあかりが、一つ二つ、三つ四つずつ、あちこちに見えかくれする。始まったな、と思っていると、それが一列に幾町もの間にパッと一時に燃えたり、また消えたりする。そうかと思うと、こんどはそれが散り散りばらばらになって、遠くの田圃一面にちらちらきらきらする。
吉田の伯母さんは、「これはきっと硫黄のせいよ」と言って、ある晩僕等がまだ見たことのない蝋マッチを持ち出して、雨にぬれた板塀に人の顔を描いて見せた。青白い、ぼやけた輪郭の、ぼっぼと燃えているようなお化がそこに現れた。僕は面白半分、恐さ半分で、伯母さんの言いなり次第に、指先きでお化の顔をいじって見た。するとこんどは僕の指先きから青白い光が出た。それを僕はお化の顔のまわりのあちこちに塗りつけた。そしてその塗りつけたあとがみんな青白い光になってしまった。
「よく恐がらずにやったわね。またいろんな面白いことを教えてあげましょうね。」
伯母さんは僕を抱きあげて、頬の熱くなるほど頬ずりをしてくれた。
この狐の嫁入りについては、あとで、次のような伝説をきいた。
昔何とかいう大名と何とかいう大名とがそこで戦争をした。何とかの方は攻め手でかんとかの方は防ぎ手だった。防ぎ手はとても真ともではかなわないことを知って、ある謀りごとをめぐらした。それはこの辺が一面の沼地で、ちょっと見れば何でもない水溜りのように見えるのだが、過まってそこへ落ちこめばすぐからだが見えなくなってしまうほどの深い泥の海のようなものだった。この沼の中へ案内知らない敵を陥しこもうというのだ。味方はみな雪の上を歩く「かんじき」というのをはいた。そしてわざと逃げてこの沼地の上を走った。敵はそれを追っかけて来た。そしてみんな泥の中にはまって姿が見えなくなってしまった。その亡霊がああした人玉になってまだ迷っているのだと。
実際その辺の田からは、その頃でもまだ、よく人の骨や槍や刀や甲などが出てきた。
三
父が戦争から帰って来る少し前に、家はまた片田町の、前のとは四、五軒離れたところに引越した。そしてそこから僕は二年間高等小学校に通った。
学校の出来はいつも善かった。尋常小学校の一年から高等小学校の二年まで、三番から下に落ちたことはなかった。高等小学校では、町の方の尋常小学校から来た大沢というのをどうしても抜くことができずに、二年とも大沢が級長で僕と大久保とが副級長だった。大久保は僕よりも一つ年が多く、大沢は二つくらい多いようだった。
高等小学校にはいってからは、学校のほかにも、英語や数学や漢文を教わりに私塾に通った。英語は前にいた片田町の家の隣りの速見という先生に就いた。どんな学歴の人か知らないがハイカラで道楽者のように見えた。生徒は朝から晩までほとんど詰めきりで、いつも三、四十人は欠かさなかったようだ。数学と漢文とは、その英語の先生がいなくなってから教わり出したように思うが、最初の先生は名も顔もまったく忘れてしまった。が、ただその家が外ヶ輪[#底本では「外ケ輪」]という兵営の後ろの町にあったことだけを覚えている。
二度目の漢文の先生は監獄の看守だった。背の低い、青い顔をした、ずいぶんみすぼらしい先生だった。それにその家もずいぶんみすぼらしい家だった。先生は朝早く役所へ出かけるので、僕はいつもまだ暗いうちに先生の家へ行った。生徒[#「生徒」は底本では「先徒」と誤記]は僕ともで二、三人だった。
僕は冬、三尺も四尺も雪が積って、まだ踏みかためられた道も何にもないところを、凍えるようになって通った。行くと、先生のお母さんが寒そうな風をして、小さな火鉢に粉炭を少し入れて来て、それをふうふう吹いて火をおこしてくれた。僕は先生のこのお母さんが可哀そうな気がして、母にその話をした。母はすぐに馬丁に炭を一俵持たしてやった。先生のお母さんは涙を流してお礼を言った。そしてその翌日からは大きな炭でカッカと火をおこしてくれた。
僕はこの先生に就いて、いわゆる四書の論語と孟子と中庸と大学との素読を終えた。
先生はまだ二十四、五か、せいぜい七、八の年頃で、その風采は少しもあがらなかった。しかしそのお母さんは、風は汚なかったが、どこかしらに品のある顔をしていた。が、そうした士族の落ちぶれたようなのは僕にはちっとも珍らしいことではなかった。
僕はその後幾度も囚人として監獄にはいって、そのたびにいつもこの先生のことを思い出した。生徒の僕等に何かものを言うんでさえ少々はにかんでいたようなおとなしい先生だ。きっと先生は囚人などとは直接に交渉のない、内勤の方の何かの事務を執っていたのに違いない。とても囚人を叱ることのできるような先生ではなかった。
それからまた、やはりその頃に、夜五、六人の友人を家に集めて、輪講だの演説だの作文だのの会を開いた。すぐ一軒おいて隣りの西村の虎公だの、町の方の杉浦だの、前にそのお母さんのことを話した谷だのが、その常連だった。虎公と杉浦とは僕よりも一年上の級だったが、近所の柴山という老先生の私塾に通っていたので、虎公が杉浦を連れて来たのだった。谷は僕よりも一年下だった。
本読みの僕はいつもみんなの牛耳をとっていた。僕は友人のほとんど誰よりも早くから『少年世界』を読んでいた。そしてある妙な本屋と知合いになって、そこからいろんな本を買って来て読んでいた。修身の逸話を集めた翻訳物のようなのも持っていた。また誰も知らない、四、五冊続きの大きな作文の本も持っていた。そうした雑誌や書物からそっと持って来た僕の演説や作文はみんなの喝采を呼ばずにはおかなかった。
新発田から三、四里西南の水原という町に、中村万松堂という本屋があった。そこの小僧だか番頭だかが、新発田に来て、ある裏長屋のようなところに住んでいた。それをどうして知ったのか、僕がたぶんほとんど最初のお客となって、何かの本を買いに行った。店も何にもなくて、ただ座敷の隅に数十冊の本を並べてあっただけだった。しかし、それまで本屋というもののまるでなかった、ただある一軒の雑貨屋が教科書と文房具との店を兼ねていただけの新発田では、それでも十分豊富な本屋だったのだ。僕はひまがあるとその本屋へ遊びに行って、寝ころんでいろんな本を読んで、何か気に入ったものがあると買って来た。小使銭というものを一文も貰わなかった僕は、文房具でも本でも、要るだけのものは母に黙っててもどこかの店から月末払いで持って来ることができた。その払いが少し嵩むと、母はこれからはあらかじめそう言うようにと注意はしたが、決して叱ることはなかった。その後すぐこの本屋は上町に店を持って、やはり万松堂と言っていた。そして僕は、それから三、四年経って新発田を去るまで、そこの店の一番いいお客の一人だった。
この夏新発田へ行った時、僕は第一番にもっともこれが宿のすぐ近くであったからでもあるが、この店を訪ねた。主人はやはり昔の主人だった。
「僕誰だか分るかい?」
僕は黙って僕の顔を見つめている主人に尋ねた。
「ええ、確かに見覚えはあるんですけれど、どなたでしたかな。」
「もうちょうど二十になるんだからね。分らんのも無理はあるまいが……」
「いや、そのお声で思い出しました。これやほんとうにしばらくめですよ。」
主人はそれで小僧にお茶を入れさした。そして僕は昔の友人の行方をいろいろとこの主人から聞いた。新発田の中学校を出たものなら、主人はほとんどみなよく知っていた。
友人等との会の話が本屋のことにそれてしまった。もう一度話をもとに戻そう。
この会での一番大きな問題は、遼東半島の還附だった。僕は『少年世界』の投書欄にあった臥薪嘗胆論というのをそのまま演説した。みんなはほんとうに涙を流して臥薪嘗胆を誓った。
僕はみんなに遼東半島還附の勅諭を暗誦するようにと提議した。そして僕は毎朝起きるとそれを声高く朗読することにきめていた。
虎公は高等小学校を終えるとすぐ北海道へ小僧にやられた。そしてその数年後にまったく消息が絶えてしまった。谷は僕よりも一年遅れて幼年学校にはいった。今はたぶん少佐くらいになっているだろう。杉浦は、その家が何をしていたのか当時は知らなかったが、そしてその家の相応な構えなのにもかかわらず馬鹿にけちだったところから後では高利貸かとも想像していたが、こんど行って聞いて見ると新発田第一の大地主だった。今は当主でぶらぶら遊んでいる。
「ほかではどうか知らないが、少なくともこの越後では農民運動は決して起りませんよ。地主と小作人とがまったく主従関係で、というよりもむしろ親子の関係で、地主は十分小作人の面倒を見ていますからね。」
杉浦君は先日会った時、室のあちこちにある神棚のあかりを手際よく静かに団扇で消して、その農民との関係を詳しく話してくれた。
四
そんなふうで、その頃はずいぶんよく勉めもしたようだが、しかしまたずいぶんよく遊びもしたようだ。
遊び場は、前の片田町にいた時とは違って、もうすぐ前の練兵場ではなくなっていた。前にも言った大宝寺の射的場のバッタ狩り。その後ろの丘の茸狩り。昔殿様の遊び場であった五十公野山の沢蟹狩り。また、昔々、何とかという大名が城を囲まれて、水路を断たれて、うんと貯えてあった米を馬の背中にざあざあ流して、敵に虚勢をはって見せたという城あとの加治山。そこではまだ、頂上の狭い平地の赤土をちょっと掘ると、黒く焦げた焼米が出て来た。綺麗な冷たい水の加治川。それらはみな、子供の足にはちょうどいい遠足の一里前後のところにあった。
あの夏の日、僕は虎公と一緒に加治山へ遊びに行った。山百合が真盛りだった。
虎公は百合の根を掘りはじめた。虎公はその家の裏に広い畑があって、よくその年とったお婆さんの手伝いをしていろんなものを作っていたところから、そんなことについての知識を持っていたのだ。僕も一緒になって掘りはじめた。収穫は大ぶ多かった。が、僕はそれをすっかり虎公にやってしまった。
「虎公のうちは貧乏なんだから……」
僕はそうきめていたのだ。虎公はまた釣が好きで、よく朝の三時頃から連れ出されたが、そんな時にもいつも僕は全収穫を虎公にやっていたのだ。
が、帰りがけに僕は、母が何かちょっとした病気で寝ていることを思い出した。そして百合の花をおみやげに持って帰ることに気がついた。僕はあちこち駈け廻って、なるべく大きそうなそして幾つもの花のついている、十幾本かを蒐めた。
二人とも大喜びで帰った。そして僕はすぐに離れの母が寝ている室へ行った。
「根の方を持ってくればいいのにね。ほんとにお前は馬鹿だよ。そしていつも虎公にそんな目に遭っているんだろう。」
母はもう大ぶしおれた花には目もくれずに、僕が虎公に百合の根をやってしまったことを批難した。
僕はこれほど悲しかったことはなかった。涙も出ずに、ただ胸がそくそくと迫って来るような悲しさだ。そして僕はそのわけを母に話すこともできずに、というよりはむしろ、そんな気は少しも起らずに、しおしおとして自分の室に帰った。
これが僕の、もっともそのわけさえ話せば母は自分の過言をあやまって僕をほめてくれたに違いないとは思うものの、母に対するただ一つのしかし大きな悲しみの思い出だ。
けれども僕はやはり母は好きだった。
その夏のある晩に、みんなで座敷で涼んでいた。ふと、次の妹が庭先を見つめながら、
「あれえ」と叫び出した。みんなはびっくりして庭の方を見た。暗い隅の方に何だかぴかぴかと光る大きな目玉のようなものが一つ見えた。子供等はみな「あら」と言ったままおびえてしまった。
母はすぐに立って庭下駄をはいて下りて行った。僕等は黙ってそれを見送っていた。
「さあ、みんなここへお出で。何にも恐いことはありません。お化の正体はこんなものです。」
母は一人ずつそこへ呼んで、そのいわゆるお化の正体を見せた。それは罐詰か何かのブリキの鑵が二つ転がっていたのだった。
けれどもまた、たぶん僕のいたずらが年とともにますますはげしくなったせいであろうが、母の折檻もますますひどくなった。僕は母と女中と二人に、荒縄でぐるぐるからだを巻きつけられて、さんざんに打たれたことを覚えている。母の留守に女中の言うことを聞かなかったというのがそのもとだったようだ。母は大勢の子供をほったらかして、半日も一日も、近所のやはり軍人仲間の島さんのところへ行ってよく遊んでいた。そして子供等の上には、女中に絶対の権力を持たしていた。
喧嘩もよくした。
「自分のことではまだ人にあやまったようなことはないんだが、この子のためにだけはしょっちゅうあやまり通しですからね。」
母はよくこう言って、喧嘩の尻を持って来られる愚痴をこぼしていた。そして僕は父や母がただあやまるだけでは済まないようなことまでも幾度も仕出かした。
高等二年の時だ。同じ級の、しかしたぶん違う組の、西川というのと何かの衝突をした。僕が甲組第一のあばれもので、彼は乙組第一のあばれものであったのだ。僕はその日の帰り路があぶないと思った。そしてひそかに、習字の紙の圧えにする鉄の細長い「けさん」というのを懐ろに入れて、何食わん顔をして学校を出た。はたして西川は僕のあとについて来た。彼の家は僕の家とあべこべの方向にあったのだ。そして彼のあとにはその仲間の七、八名がついていた。
僕はいつものように、衛戍病院の横から練兵場にはいった。そしてそこへはいるとすぐ右の手を懐ろに入れて用心していた。今まで大ぶ離れていたみんなが、がやがや言いながらだんだん接近して来た。悪口の挑戦がはじまった。なぐっちゃえ、なぐっちゃえ、などという声も、すぐ後ろに聞えた。僕は誰かが駈け寄って来るのを感じた。僕はけさんを握って、止まって、後ろをふり返った。西川が拳をあげて今にもなぐりかかろうとしていたのだ。僕はいきなりけさんを振りあげた。西川はちょっと後ろを向いた。その拍子に彼の頭から血がほとばしり出るように出た。みんなはびっくりして西川を取りまいた。僕は多少の心配はしながら、それでも意気揚々と引きあげて帰った。
西川の頭にはその後二寸ばかりの大きな禿ができていた。
それからよほど経ってからのことであるが、ある日、父が連隊から帰るとすぐその室に呼ばれた。父と母とが心配そうな顔つきをして向い合っていた。
「この頃お前学校で誰かの肩をなぐるか蹴るかしやしないか。」
父が厳かに、しかし不安そうに、尋ね出した。父の顔には太い筋が見えていた。
父がこんな裁判をするのは初めてのことだった。で、僕も何か非常な大事件のような気がしたが、そんな覚えは少しもなかった。僕は黙って考えていた。
「それでは何とかいう子を知らないか。」
と、こんどは母が尋ねた。
僕はその子は知っていた。同じ級のたしか同じ組だった。親しい友達でも何でもないが、とにかく学校で知っていた。けれどもそれがこの妙な事件と何の関係があるのか、僕にはますます分らなくなった。しかし知っているということだけは答えた。
「その子の肩をなぐるか蹴るかしやしないかい。」
母は僕の返事を待ってさらにこう尋ねた。
「いいえ。」
僕にはそれはますます覚えのない変なことだった。
母はそれでようやく安心したようになって、事の顛末を詳しく話して聞かした。
八軒町に岡田という少佐がいた。父が前に副官をしていた連隊長だ。そこの馬丁か従卒かが門前を掃除していると、学校の子供が一人通りかかって、それがフラフラ右左によろめきながら幾度も門の溝の中に落ちかけた。妙だな、と思って肩をつかまえて聞くと、
「それが君んとこの子供の仕業だと言うんだそうだ。それでとにかくその家まで送り届けさして置いたそうだがね。医者は頸の根のところは急所で、ちょっと針でさしても死ぬくらいだが、これは治ってもたぶん馬鹿になってしまうだろう、と言っていたそうだ。」
という岡田少佐の話だったんだそうだ。
そう言われると僕は思い出した。その頃学校では毎日「隅取り」という遊びをしていた。それは雨天体操場の二つの隅に各々一隊ずつ陣取って、その陣屋を守っているものを押しのけくぐり抜けて、それを占領する遊びだった。が、普通尋常に押しのけくぐり抜けているんでは、いつ勝負がつくか知れない。それでまず第一攻撃隊にそれをやらして置いて、敵の陣容の大ぶくずれかかった時に、一人か二人の勇者をそこへ飛びこませるのだった。この勇者等は、組打ちをしている敵味方の肩の上から陣屋のなるべく奥へ飛びこんで、一挙にしてその一番奥の隅を占領するのだ。僕はいつもこの勇者の役目がお得意でいた。その飛びこむ時に、何とかいう子の肩の急所を蹴ったのじゃあるまいかと。
僕は父と母とにその話をした。そして三人できっとその時のことだろうときめてしまった。
父と母とはすぐ見舞いに行った。が、向うでは、それをひどく恐縮して、何でもよいことにしてしまった。
その後その子がどうなったかよく覚えていないが、目つきがちょっと藪にらみのようになって、いつも何にも言わずに黙っているのを見たようにも思う。
自叙伝(三)
一
高等小学校の二年を終る少し前のことだった。ある日先生から、大沢と大久保と僕と三人に、その晩先生の下宿を訪ねるようにと言われた。
「何の用だろう。」
三人は心配しだした。先生に自分の家へ来いなぞと言われたのは初めてだった。が、いくら三人が首をあつめて見ても、それが何の用だかは、どうしても見当がつかなかった。それだけ三人はなお心配した。
三人はどこかで待合せて、びくびくしながら、地蔵堂町の先生の下宿へ一緒に行った。
先生はにこにこしていた。そして自分でお茶を出してくれて、かしこまっている僕等に無理無理にあぐらをかかした。
「こんどこの土地に中学校ができるんだがね、どうだ、みんなはいって見ないか。」
先生は真黒な顔の中に白い歯を見せながら切りだした。中学校ができるといううわさは僕等もうすうす聞いていた。しかし、それがまだはっきりした話でなかったようなのと、高等二年を終えればすぐはいれるなぞとは知らなかったのとで、僕等は大してそれを問題にしていなかった。三人はどう返事をしていいのか分らんので、しばらくの間黙ってただ顔を見あわしていた。
「高等二年を終えればすぐはいれるんだがね、ほかのものはとにかく、君等三人だけは僕が保証するから是非はいって見ないか。家へ帰って先生がこう言ったからと言って、お父さんやお母さんと相談してごらん。」
僕等は急にうれしくなった。そして、もう中学校へはいったような気になって、「しかしこのことはほかのものには話ししないようにね」という先生の注意もうわの空で、大喜びで家へ帰った。
先生は、僕等には初めての師範出の若い先生だった。それまでの先生は、尋常四年の時の島先生を除けば、みないいかげん年とった先生ばかりだった。そして先生は、僕等とほんとうに友達になって遊んでくれた、初めての先生だった。「僕」なぞと言ったのも先生だけだった。
先生は来るとすぐ高等一年の僕等の組を受持った。先生の真黒な顔は最初僕等にあまり受けがよくなかった。ちょっとこわそうに見えたのだ。が、この先入見は、唱歌の時間にすぐ毀されてしまった。今までは女の先生ばかりがやっていた唱歌までも先生が受持ったのだ。それだけですらすでに先生の上に、ある人望と好奇心とが加わった。そしてその最初の時間は実に奇観なものだった。
兵隊のようにからだのいい、腕を前につき出して、真黒な顔の先生が、オルガンの前に腰かけた。僕等はそのオルガンからどんな音が出るだろうと待ち構えていた。オルガンの音は優しい顔の女の先生のと別に変りはなかった。が、そのやはり真黒な、毛もしゃくしゃの、大きな指が、少しもぎこちなくはなく器用にそして活発にキイの上を走るのが、まずみんなを愉快がらした。
やがて先生が歌い出した。真黒な顔一ぱいに広がった大きな口から、教室じゅうに響き渡る、太いバスが出て来た。おちょぼ口をして聞えるか聞えないような声を出している、女の先生の声ばかり聞いていた僕等は、それですっかり先生に参ってしまった。そしてみんなは非常に愉快になって、できるだけ大きな口を開けて、できるだけ大きな声で歌った。
そして、これは特筆大書しなければならんことだが、僕はこの先生にだけはただの一度も叱られたことがなかった。
それだのに、どうだろう、僕はこうして二年間もずいぶん可愛がってもらったこの先生の名さえも忘れてしまっているのだ。
先生から中学校行きを勧められたことは、堅く口どめされていたのにもかかわらず、すぐにみんなの間に拡がった。そしてそれと同時に、中学校ができるということも確実になり、高等二年を終えたものはすぐにはいれるということも知れ渡った。僕等と同じ級からの入学希望者も大ぶできた。そしてそれらのものから僕等三人は一種の憎しみの的となった。
四月のはじめに、僕は中学校の仮校舎になっていた何とか寺へ入学願書を持って行った。受付の事務員が、しばらくの間それを読んでいたが、やがて「あんたは年が足りないから駄目です」と言ってそれを突っ返した。僕は泣きそうになって家へ帰った。
学校の入学規則には満十二年以上とあった。そして僕の願書には満十一年十一月とあった。一カ月足りないのだ。僕はくやしくて堪らなかった。父も母も「そんなに急ぐには及ばんから来年のことにするさ」と言って慰めてくれるんだが、僕はどうしても思いきることができなかった。みんなが「ざまあ見ろ」と言ってあざ笑っているのが、すぐ目の前に見えたのだ。
僕は満十一年十一カ月というのを十二月となおして、もう一度中学校の事務所へ行って見た。
「よく勘定して見ると十一カ月じゃないんです。十二カ月です。十二カ月なら都合十二年になる訳なんだから、それでいいでしょう。」
僕は一生懸命になって、自分の生れた月の五月から始めて六七八九……一二三四月と十二まで指を折って見せてその確かに十二カ月になることを力説した。
事務員は笑っていたが、「とにかく相談して見ましょう」と言って願書を受けつけてくれた。僕はその翌日また行って見た。そして要するに、一学期間はみんな仮入学を許して、九月からほんとうの生徒になるんだからというので、僕は入学を許されることとなった。
中学校には僕等三人のほかに同じ級から二十名近くはいった。が、その半分は本入学の時に篩い落され、あとの半分も大部分は二年へ行く時に落されてしまった。そしてその残りの一人か二人も三年に登る時に落されてしまった。
二
この十三の春は、からだの上にも心の上にも大きな変化を僕にもたらした。
ある日、偶然僕は僕のからだのある一部分に、うぶ毛ではない黒い毛の密生して来ていることを発見した。僕はそれが非常に恥かしかった。これは僕と同じ年の友達には勿論、一つ二つ年上の友達にもまだ見ないことだったのだ。僕は幾度も、あるいは便所で、あるいは自分の室で、そっとそれを(十二字削除)した。が、いつの間にかまたそれが前よりも、もっと(五字削除)して来るのだった。
それとほとんど同時頃に、僕はほんとうの自慰を覚えた。前にお花さんとやったほんの遊びが、こんどは(十三字削除)なったのだ。
それ以来僕は机の前に長い間坐って本を読むことができなくなった。一時間も坐っていると、(五字削除)して来て、どうしてもじっとしていることができなかった。そして一日に二度も三度も自慰に走った。
勉強家だった僕はすっかり怠けものになってしまった。
僕は父や母が少しでも猥りがましいことをしたり、そんな話をしているのを見たことも聞いたこともなかった。
従卒や馬丁が女中とふざけているのはよく見た。馬丁はほかから通って来るのでそれほどでもなかったが、従卒は書生か下男同様に泊りこんでいるので、始終女中とふざけ合っていた。従卒の室へはいって行って、従卒と女中とが今相撲を取っているのだというところを見たこともあった。また、女中が真赤な顔をして、息をきらしながら着物の前を合せ合せ従卒の室から飛び出て来るのにぶつかったこともあった。やがてこの女中はその従卒の子を孕んで宿にさがった。
僕等がいた片田町の裏の
一度、馬丁に連れられて、西ヶ輪[#底本では「西ケ輪」]の何とか温泉といったお湯屋へ行った。真白な頸の女が大勢はいっていた。男も二、三人まじっていた。馬丁は僕に待っていろと言って、自分一人その中へはいって行った。男と女とが湯船の中に入りまじって、キャッキャッと言って騒いでいた。僕はいやになって、馬丁がとめるのも聞かずに、一人で家へ帰った。
が、僕自身は女の友達とはだんだんに遠ざかって行った。
学校が別になってめったに会う機会のなくなった光子さんは、折々その小さい弟を連れて、夕方近くに練兵場へ散歩に来た。彼女はたしかに僕に会いに来るのに違いなかった。その弟を連れて来たのもそとに出る口実に違いなかった。僕は彼女の姿を見るとすぐに練兵場へ走って行った。二人は一、二間そばまで近よってかすかな微笑を交せば、それでもう事は十分に足りるのだった。彼女はそれで満足して帰った。
光子さんと僕との間は要するにただこれだけのことに過ぎなかった。僕は光子さんと交したただの一と言も覚えていない。というよりもむしろ、お互いに言葉を交したというほどのこともかつてなかった。それでも二人は、少なくとも僕の心の中では、立派な恋人同士だったのだ。
その後僕は彼女がどうなったか知らない。彼女の姉さんは、やはり彼女と同じように美しかったが、貧乏人の子の秀才が勉強するにはそのほかに方法はなかった、新潟の師範学校にはいっていた。彼女もやはりその姉さんと同じ運命に従ったことと思う。
光子さんの姿が見えなくなったあとで、あるいはやはりその頃であったかも知れないが、その小さな妹を連れて、やはりたしかに僕との単なる微笑を交すために、練兵場へ散歩に来た女の子があった。警察署長の娘だった。
やはり僕はただの一度も言葉を交したことはなかった。そして彼女と向い合って立ったのはただ次の場合の一度だけだった。
僕は父の使いで署長の官舎へ手紙を持って行った。玄関で取次ぎを乞うと、ふいと彼女が出て来た。彼女も僕も真赤になって何にも言うことができなかった。僕は黙って手紙をさし出し、彼女も黙ってそれを受取って奥へ走って行った。
彼女は唇の厚くて赤い子だった。
僕は彼女といつ、どこでどうして知ったのか覚えていない。そしてただこれだけの間柄に過ぎなかったのに、不思議にもまだその名は覚えている。
お花さんもお礼さんもいつの間にか僕の頭の中から消えてしまった。
お花さんはどうしたのか覚えていないが、お礼さんは柏崎へ行ってしまった。そのお父さんが、金鵄勲章の叙勲にもれたのに不平を言って、柏崎の連隊区に左遷されたのだった。
このお礼さんについてだけはまだ後日談がある。
中学校にはいろんな種類の人間がはいった。僕等を一番の年少者として、もう三、四年も前に高等小学校を終えて自分の家の店で坐っていた二十近いものまでもいた。もうすっかり農村の若い衆になりきっているものもはいって来た。新潟や長岡の中学校の食いつめものもいた。
それらの年長者がいろんなことを僕等の間に輸入した。学校が始まってから間もなく、寄宿舎にいる二、三の年長者達が十三、四の七、八人の生徒を連れて、女郎屋へ遊びに行った。これはすぐ学校に知れてその年長者等は退校になった。それ以来、そうした方面のことはまったくなくなった。
そして生徒の間にすぐに一番の勢力を占めたのは、他の中学校を流れ歩いて来たごろつき連中だった。この連中はみな一人ずつごく年少のそして顔の綺麗なのをその親しい友人に持った。彼等はお互いに指を切って、その血をすすり合って、義兄弟の誓いをした。
一年の間は僕もまだそんなことは知らなかった。が、二年の末頃になって、やはりそれを覚えて、指を切ったり血をすすったりはしなかったが、一人の弟を持った。
この風習はその後二年も三年も僕につきまとった。
煙草を吸うこともやはりその頃に覚えた。
父がいつも吸っている中天狗というのをちょいちょい盗んでは吸い覚えた。そしてしまいには父が大事にしてしまっている葉巻までも盗みだして吸うようになった。
三
中学校にはいったのと同時頃に、高等小学校の坂本先生というのが、主として軍人の間から寄附金を募って、講武館という柔道の道場を建てた。
軍人の子は大がいそこにはいった。石川もはいった。大久保もはいった。また、前に言った威海衛の戦争の時に一週間山の中にかくれて出て来なかったという評判の、そして凱旋するとすぐ非職になった脇田という大尉の子もはいった。脇田は僕なぞと同じ級で年は二つほど多く、からだも大きかったが、僕等はその親爺のせいで馬鹿にしていた。が、ある時彼自身の口から、彼のほんとうの父は何とかという人で、金沢で大久保利通を暗殺した一人で、しかもその最初の太刀を見舞ったのだと聞いて、少し彼を尊敬したい気になった。勿論僕もはいった。
この柔道はずいぶんよく勉強した。午後と夜と代る代るあったのだが、僕はほとんど一日も欠かしたことがなかった。ことに寒稽古には三尺も積った雪の中で乱どりをやった。成績も非常によかった。そして一年半か二年もしてからはそこでの餓鬼大将になってしまった。毎年秋の諏訪神社のお祭には、各々の町から山車が出た。そしてその山車と山車とがよく喧嘩した。鍛冶町の鍛冶屋連がこの喧嘩に負けて、翌年の復讐を期して、十人ばかりが入門した。みんな僕なぞの足くらいもある太さの、恐ろしいほど瘤や筋の出ばった腕を持った、二十前後の若い衆ばかりだった。先生は僕をその相手に選んだ。ちょっと彼等に握られると、腕の骨がくだけるかと思うほどに痛かった。が、彼等の腰と足とは子供のように弱かった。僕はそれにつけこんで彼等をころころ転がしてやった。みんなは喜んで僕を先生の代理にしていた。そして折々小刀なぞを作って持って来てくれた。
そこではまた棒も教わった。縄も教わった。棒はことにお得意だった。今でもまだ棒が一本あれば二人や三人の巡査が抜剣して来たところで、あえて恐れないくらいの自信がある。
幼年学校にはいってからの第一の暑中休暇に、坂本先生のそのまた先生の森川というお爺さんから、ある伝授をするから一週間ばかり泊りがけで来いという迎いが来た。
お爺さんは新発田から二里半ばかり距たった次弟浜という海浜にいた。で、僕は海水浴がてら行って見た。お爺さんはもと通りちょん髷を結って、もう腰がすっかり曲っていた。それでも行くとすぐ、前にも道場でよくやったように、棒の相手をさせられた。お爺さんが木太刀を持って、僕が棒を持ってそれに向うのだ。お爺さんのかけ声はこっちの腹にまで響くように気合がこもっていた。そしてその太刀で棒を圧えるようにして、じりじり進んで来られると、僕はちょっと自分の棒を動かすことができなかった。
お爺さんは目がわるくて自分で書けないからと言って巻物になっている「目録」を持って来て、僕に写さした。東方の摩利支天、西方の何とか、南方の何とか、北方の何とか、というようなことがあって、呪文めいた片仮名の何だか訳のわからんことの書きつづけられた妙なものだった。そしてその最後には、この「目録」を伝えられたことの系図のようなもので、源の何とかから藤原の何とかに、という十幾つか二十幾つかの名が連らねられてあって、最後に源の何とか森田何兵衛殿へとあった。これがお爺さんの名なのだ。そしてお爺さんは、この系図のおしまいに自分の名をいれて、そのあとへ大杉栄殿へと書くように言った。
片仮名の呪文は何の意味だかちっとも教えてくれなかった。が、人が見てはいけないと言って、裸で土蔵の中にはいって、あて身や何かを教えてくれた。
その後このお爺さんは、父のところへ来て、兵隊に玉除けのまじないをしたいからと言って、大ぶ手こずらしたということであった。
この柔道は荒木新流という、実はもう古い流儀のものだった。
その後坂本先生は、僕が最初の入獄を終えて初めて家を持った時、こんど上京したからと言って訪ねて来た。これは後で間接に聞いたことであるが、実は父と相談して僕を説得しに来たのだったそうだ。が、そんなことは少しもなしに、今でもまた折々訪ねて来ては昔ばなしをして行く。
「どうしたって、そんな病気になる筈はないんだがね……」
僕が肺の悪いことを聞いて先生は不思議がっていた。そして先生発明の曲伸法という運動方法を勧めてくれた。最近に僕はこの曲伸法で獄中で大たすかりをした。
先生はもう五十をよほど越しているのだろうが、昔僕が知っている三十幾つかの頃の、小造りであるがまんまると太った、色つやのいい顔の先生そのままでいる。そして今でも、小石川のその修養塾のそばに道場を造って柔道の先生をし、また夏は子安辺で水泳の先生をして、毎年の冬隅田川で寒中水泳を催している。
この柔道から少し遅れて、撃剣も教わりに行った。昼の柔道の時間をその方へ廻したのだ。流儀の名は忘れたが、先生は今井先生と言った。
先生は大兵肥満の荒武者で、大きな竹刀の中に電線ほどの筋がねを三、四本入れていた。一種の国士といったような人で、昔星享が遊説に来た時、車ごと川の中へほうりこんだとかいう話もあった。最近にも大倉喜八郎の銅像の除幕式の時、そこへ飛びこんで行って大倉をなぐるのだと言って意気ごんでいたそうだが、みんなにとめられて果さなかったそうだ。
僕はそこで荒っぽい、竹刀の使いかたの大きな撃剣を教わったので、その後幼年学校にはいって、おもちゃのような細い竹刀でほんのこて先きだけでチャンチャンやるのが実にいやだった。
学校では器械体操とベースボールとに夢中になっていた。そしてこうして一日とび廻っては、大飯を食っていた。
十三の正月から十四の正月までに、背が五寸延びた。そうして十四から十五までに四寸延びて五尺二寸何分かになった。
四
中学校の校長は、先年皇子傅育官長になって死んだ、三好愛吉先生だった。
僕等は先生を孔子様とあだ名していた。それは先生が孔子様のような髯をはやしていたばかりでなく、何かというとすぐに孔子様孔子様と先生が言っていたからでもあった。先生は真面目な謹厳そのもののような顔をしていた。そして主として論語によって倫理の講義をしていた。
たしか二年の初め頃だった。ある日先生が、倫理の時間に、みんなの理想し崇拝する人の名を尋ねた。秀吉も出た。家康も出た。正成も出た。清麿も出た。そしてだんだん順番が廻って僕の番になった。
僕にはまだ、実は、理想し崇拝するというほどの人はなかった。それにいいかげんに誰かの名を言うにしても人の言った名をまた言うのはいやだった。誰にしようか、と考えて見てもちょっと新しい名が浮んで来なかった。そこへ僕の番が来たのだ。僕はすっかり困ってしまった。
が、とにかく立ちあがった。するとふいに、最近に買って読んだ、誰だかの西郷南洲論を思いだした。僕はいい見つけものをしたつもりで、「西郷南洲です」と答えた。
先生は一と廻りしてしまったあとで、みんなの答えたそれぞれの人についての批評をした。
「なるほど西郷隆盛は近代の偉人だ。あるいは、日本の近代では一番の偉人であるかも知れない。が、彼は謀叛人だ。陛下に弓をひいた謀叛人だ。そしてこの謀叛人であるということに、よしそれがどんな事情からであったにしろ、またほかにどんな功労があったにしろ、とうてい許されることはできない。いわんやその謀叛人を理想し崇拝するなぞとは、もってのほかだ。」
先生の僕の答に対する批評は大たいこんな意味だった。そして最後に先生は、みんなの理想し崇拝しなければならぬ人物として例の孔子様をあげて大いにその徳を頌した。
僕はこの批評が非常に不平だった。僕が読んだ本では彼の謀叛は陛下に弓をひいたのではない、いわゆるその何とかの下にかくれている姦臣どもを逐い払うための謀叛だとあった。僕もそう信じていた。しかし先生にこう言われてからは、そんなことはもうどうでもよくなった。許されようが許されまいがそんなことはもう問題ではなくなった。とにかく彼は偉かったんだの一点ばりになった。そして家へ帰ってまた西郷南洲伝を読み返して彼をすっかり好きになってしまった。
この西郷南洲伝はさらに僕を吉田松陰伝や平野国臣伝に導いた。そしてそのどんなところが気に入ったのか忘れたが、とにかく平野国臣は何だか非常に好きだったように覚えている。
三好先生は深田先生というのを教頭に連れて来た。小柄の綺麗な顔に頬髯を一ぱいにはやした先生だった。
先生は一年の時の倫理と英語を受持った。倫理には、長い間続けて郡司大尉の千島行の話を聞かされた。先生の英語は、声が綺麗で、今までの小学校や私塾の英語の先生のとはまるで違った、いい発音だった。
博物や理化の先生もやはり学士であったが、意地わるなので、僕等はその学科に興味を持つことができなかった。
お爺さんだった習字の先生は、いつも僕に、よく手本を見て書けばうまく書けるのだから、ぞんざいに書いてはいけないと言って注意してくれた。が、僕には、どうしてもお手本の一点一劃をその通りに見て書くということができなかった。そしてこのぞんざいのお蔭で、今でもまだろくに字の恰好をとることができない。
図画は最初鉛筆画で、あとで毛筆画になったが、一年から二年までの間に数えるくらいしか描いたことがなかった。まるで描けないし、それに大嫌いだったのだ。
学校の勉強はまるでしなかったが、成績は英語が一ついつでもいいくらいなもので、あとはみな乙ぞろいだった。そして三分の一ほどの席順にいた。
僕が一年から二年へ越える時に、虎公が高等小学を終えた。
虎公の家は、虎公とお婆さんと二人きりで、どうして食っていたのか知れないが、相変らず貧乏だった。虎公はしきりに中学校へはいりたがっていたが、どうしても駄目らしかった。僕は虎公が可哀そうで堪らなかった。そしてとうとう一策を案出してそれを虎公に謀った。それは僕が使った本はみな虎公にやるから、虎公はその伯父さんから月謝だけ出してもらって、学校へ行くがいいというのだった。
虎公は非常に喜んで、すぐそれをお婆さんに話して、伯父さんに相談に行った。伯父さんというのは典獄を勤めていた。
が、虎公の運命はもう、そのよほど以前にきまっていたのだった。彼は伯父さんの家から泣いて帰って来た。中学校へはいりたいなぞという非望を叱られて、近々に函館のある商店へ小僧に行くようにと命ぜられて来たのだ。
僕は虎公のこの運命をどうともすることができなかった。二人は相抱えて泣いた。そして僕は大将になるから、君は大商人になり給えと言って、永久の友情を誓った。
虎公と僕とは記念の写真を撮った。そして僕は母にねだって、暖かそうなフランネルのシャツとズボン下とを作ってもらって、それを餞別に送った。
僕は大将になり損ねたが、虎公ははたしてどうしているか。彼の本名は西村虎次郎と言った。
虎公が行ってしまってからすぐ僕は幼年学校の入学試験を受けた。そして虎公にも誓ったように、自分の写真の裏には未来の陸軍元帥なぞと書いていたが、試験のための勉強はちっともしなかった。そして見事に落第した。
五
その夏初めて一人で旅行に出た。
最初は東京までのつもりで、十円もらって出かけたのだったが、それが名古屋までとなり、大阪までとなって、大旅行になってしまった。
越後はまだ直江津までしか鉄道がなかったので、新潟から船でそこまで行った。汽船や汽車に乗ったのは勿論、そんなものを見たのも、それが覚えてから初めてのことだった。
山田の伯父が四谷にいた。威海衛で戦死した大寺少将の邸を買って、そのあとを普請したばかりのところだった。伯父は大佐で近衛の何連隊かの連隊長をしていた。
「よく一人で来た。」
伯父は僕の頭を撫でて、父でもめったにしてくれないほどの可愛がりかたをしてくれた。伯母も「栄、栄」と言って自分のそばを離さなかった。
従兄が二人いた。弟の哲つぁんは病気で学習院の高等科を中途でよして、信州の方へ養蚕の実習に行っていた。女中どもはこの哲つぁんのことを若様と呼んでいた。兄の良さんは中尉になったばかりで、綺麗な花嫁のお繁さんと一緒に奥の方の離れにいた。士官学校の教官をして、陸軍大学校の入学準備をしていたのだ。
女中どもは僕を越後の若様と言った。そして僕が何かするたびに何か言うたびに袂で口を蔽うては笑いこけていた。お繁さんは(僕はお姉さまと呼んでいたが)そのたびに美しい目で女中どもをにらみつけるようにしていたが、やはりその可笑しさを隠しきることはできなかった。
洋食の御馳走が出た。越後の若様はどうしてそれをたべていいか分らなかった。新発田にはまだ洋食屋もなく、家ででも洋食なぞをたべることがなかった。で、みんなのする通りにビフテキか何かをようやくのことでナイフで切って、それを口に入れたが、切りかたが大きすぎたので口の中で一ぱいになって、どうともすることができなかった。みんなは笑った。そしてお繁さんだけは、いつまでもいつまでも、僕の顔を見ては思い出すように笑っていた。
僕はお繁さんを日本で一番の美人だと思った。お繁さんの姉さんも綺麗だった。そしてこの姉さんは、田中という騎兵大尉の、陸軍大学校の学生のところに嫁いていた。
僕は来年は必ず幼年学校の試験に及第してうんと勉強して陸軍大学にはいるんだときめた。
お繁さんの里の、飯倉の末川という家へも行った。山田の家の心地よさに酔うていた僕は、末川家のさらに幾倍もの贅沢に少々驚かされた。
家は上と下とに二軒あった。下は妾宅で上は本宅だった。長男が一人本妻の子でしかもそれは馬鹿で、あとはみな男も女も綺麗な、もと烏森とかにいたという妾の子だった。お繁さんもその姉さんも勿論この妾の子だった。お繁さんの下にもまだ女の子が二人いた。そして下の家には妾とそれらの女の子とだけがいた。みんなはその妾を自分のほんとうのお母さんを、栄ちゃんと呼んでいた。
食事時には、ふだんは男ばかりいる上の家へみんなが集まった。僕も行けばきっとこの上の家の、西洋室の応接間にはいってソファの上に横になっていた。
僕はこの家で初めて電話というものを知った。また、お繁さんの姉さんの手で初めてピアノというものの音を聞いた。僕はこの家のみんなが、その綺麗でそしてお上品な中に、どこかしら冷たいものを持っていることに気がついた。が、それでもやはり、その贅沢な生活を味いに、時々遊びに行かない訳には行かなかった。
末川家は鹿児島の家老の家柄で、その主人はもと海軍の主計監とかをしていたと聞いた。そして、その頃は実業に関係していたようだった。山田家では最初この家との縁談があった時、妾の子ではと一時躊躇したのだそうだが、川村大将とか高島中将とかが中にはいって、無理にもらわしてしまったのだのとかと聞いた。その後、今の皇太子や皇子達が川村大将の家にいた頃、良さんの子供等はよくそこへ遊びに行って、熊だの象だののおもちゃをもらって来た。
良さんは今少将でどこかの旅団長を勤めている。そしてお繁さんの姉さんの方の田中は、中将になって今ワシントンの太平洋会議に陸軍代表の主席として出ている。ついでに言うが、山田の伯父は、とうに中将で予備になって、今は和歌山に隠居している。
名古屋と大阪とでは、名古屋では父方の親戚を、大阪では母方の親戚を歩き廻った。
が、そのどちらでも、商家や農家ばかりなので、そしてつましい家ばかりなので、一向面白くなかった。そしてすぐまた東京に帰って、一カ月あまり遊んでいた。
六
この旅行は僕に金を使うことを覚えさした。それまで僕は、小遣銭というものは一文ももらったことがなく、いるものは何でも通いで持って来たのであった。しかしもうそれでは済まなくなった。
中学校は新発田から五十公野へ行く途中の、長い杉並木の間に新しい校舎ができた。そしてその並木路の入口にある小料理屋風の蛇塚屋というのが、僕等不良連の間にスネエクと呼ばれて、みんなの遊び場でもありまたいろんな悪事の本拠地でもあった。みんなはよく学校をエスケエプしてはそこへ行った。
僕は母の財布から金を盗むことを覚えた。母はいつも財布をどこかへ置きっぱなしにしていた。そしていり用のたびにあちこちとそれを探していた。そんなふうで、自分の財布にいくらはいっているのかもよくは知らなかったようだった。僕はそれをいいことにして、二、三十銭から五十銭くらいまでをちょいちょいと盗んだ。
が、だんだん、そんなことではとても追っつかなくなった。そしてとうとう僕は父からもらった時計を売ってしまった。それは銀側の大きな時計で、鍵を真ん中の穴に入れてギイギイと廻す、ごく古い型のものだった。
それがどうしてか母に知れた。
「時計を持ってお父さんのお室へおいで。」
僕は持って行く時計はないのだから、仕方なしにただうんと叱られる決心だけを持って、父の室へ行った。
父の裁判がはじまった。僕は売ったと答えた。が、その金の行方については、どうしてもはっきり言うことができなかった。それは、もしスネエクのことを言えば、そこでいろんな悪事、ことに例の義兄弟のことなどが知れる恐れがあったからだ。
僕は父と母とにうんと責められた。うんと叱られた。しかし、言えないことはやはりどうしても言えなかった。
その冬、この不良連の親分の、その頃の最上級の四年と三年とのものから一大事を聞いた。それは三好校長が組合会議から排斥されて、不信任案の決議をされるということだった。
僕等の中学校は、新発田町外四十何カ村の組合立で、その組合の会議というのがあったのだった。この組合会議が、往々その職分の経営のことを超えて、教育方針にまで差出口をするということは聞いていた。そしてそのたびに校長がそれを峻拒したということも聞いていた。
僕等は組合会議がどんな差出口をしたのかも少しも知らなかった。また、その不信任案というものの内容も少しも知らなかった。そしてまた、その間にわだかまるいろんな事情というようなことも少しも知らなかった。が、とにかく組合が不埓だときめてしまった。そして校長擁護の一大運動を起すことにきめた。
翌日すぐ、長徳寺というのに学生大会が開かれて、二年三年四年の全生徒は校長と運命をともにするという満場一致の決議をした。
この騒ぎは学年試験を前に控えて一カ月ばかり続いた。そして最初の同盟休校というのが同盟退校の決議にまで進んだ。
もうこんな学校に用はないというので、ガラス戸は滅茶苦茶にこわされた。そして生徒控室にあった机や椅子は、ほとんど全部火鉢の中のたき木になってしまった。
ある先生は、組合と内通しているというので、夜車で練兵場を通るところを袋だたきにされた。
ある日父と母とは茶の間の火鉢のそばへ僕を呼んだ。
「この頃お前はちっとも学校へ行かんで騒いでいるそうだが……」
父の話は、組合から生徒の父兄に送って来たものによって、多少校長を批難して、明日からでも学校へ出ろというようなことであった。
「いやです。」
僕はただ一言そう言ったきりで、席を蹴って起ちあがった。
「あの子はいったん何か言いだしたら、何があっても聞かんのですから、どうぞそのままにほおって置いて下さい。」
母はしきりに父をなだめて、懇願しているようだった。
しかしこの騒ぎは、組合で不信任案を取消すということと、校長が辞職するということとで治まって、生徒は校長の懇請でようやく学年試験を受けることになった。
三好校長は深田教頭と一緒に、長野の中学校へ行くこととなった。その送別会が仲町の何とかという料理屋の広間で開かれた。校長は大酒家だった。みんなに一合ばかりの酒がついた。校長は初めから終りまでその四角な顔をにこにこさせていた。教頭はお得意のいい声で、その郷里の白虎隊の詩を吟じた。
そして校長がいよいよ出発する時には、全校三百余の生徒が、校長の橇を真ん中にして降り積る雪の中を七里の間、新潟まで送って行った。
そのあとへ、広田一乗という、名前から坊主臭いしかしハイカラな新しい文学士が来た。が、この新校長は、来る早々校友会の席上で記憶術の実験か何かをやって、すっかり生徒の評判を悪くしてしまった。そして、生徒がみな素足ではいる習慣になっていた、御真影を安置してある講堂へ、校長が靴ばきのままはいったとかいうので、危く排斥運動が起りかけさえした。
その春、僕は二度目の幼年学校の入学試験を受けた。
そしてその最初の日に、もう少しで身体検査ではねられるところだった。去年はよく見えた検査の符号のようなものが、下の二、三段のほかはみなぼんやりして、上があいているのか下があいているのかよく分らなかった。
若い軍医は首をかしげて奥の方の室へはいって行った。そして、僕が子供の時から何かの病気の際にはいつも世話になっていた、平賀という一等軍医を呼んで来た。
「これはことしはどんなことがあっても入れなけやならないんだ。」
平賀軍医はそう言いながら、僕の目の検査をし直した。そして暗室へ連れて行ったり、いろんな眼鏡をかけさして見たりして、要するに合格にしてしまった。
学科の方は、別に何の勉強もしなかったのだが、高等小学校卒業程度の試験なんだから、やすやすとできた。
そして官報で及落が発表される少し前に、山田の伯父から、「サカエゴウカクシユクス」という電報を受取った。
自叙伝(四)
一
幼年学校は、東京に中央幼年学校というのがあって、そして当時の六個師団の各師団司令部所在地に地方幼年学校というのがあった。中央は本科で地方は予科だ。ある師団、たとえば第一師団の管轄に本籍を持っているものは、その師団司令部所在地の、すなわち東京の地方にはいった。そしてそこで三年間いわゆる軍人精神を吹っこまれて、各地方のものがみんな東京の中央に集まるのだった。
僕は僕の本籍地の名古屋の幼年学校にはいった。
父は、後に僕が社会主義者になったのを、僕のフランス語のせいにしていた。フランスは革命の国だというごくぼんやりした理由からだ。僕もそれは、もっと細かなそしてもっと込みいった理由から、部分的に承認する。が、僕のそのフランス語というのは、この幼年学校で、しかも命令的にはじまったのだった。
東京の地方にはフランス語とドイツ語とロシア語とがあった。が、その他の地方には、フランス語とドイツ語としかなかった。そして入学志願者は、その願書の中に、その中のどれか一つを希望語学として書き入れて置くのだった。
僕は、フランスはもう旧い、これからは何でもドイツだというので、ドイツ語を選んだ。そして父を覚束ない先生にして、一カ月ばかりかかって、たしかヘステルの第一読本をあげていた。
名古屋へ行く途中、東京で、一、二年前から上京していた大久保を訪ねた。彼も去年は落第して今年は東京の地方に及第したのだった。彼もやはりドイツ語を希望していた。そこへ、熊本の地方の先輩である石川が、休暇で東京に遊びに来ていて、一緒に落ち合った。彼はやはりドイツ語で、しかもそれが非常にお得意らしかった。彼はフランス語をさんざんにけなした。大久保と僕とは、何が書いてあるんだかちっとも分らない亀の子文字の彼の本をいじくり廻しながら、大いに彼をうらやんだ。
が、学校にはいったその日の、第一番目の出来事は五十名の新入生が撃剣場でせいの順に並ばされたことで、そしてその次がそれに続いてすぐみんなの語学を決定されたことであった。希望者はフランス語よりもドイツ語の方が遙かに多かった。そして学校の方針はそれを公平に二分することであった。すなわち五十名の新入生を二十五名ずつそれぞれドイツ語とフランス語とに分けることであった。
「もっとも、今までドイツ語をやっていたものは、希望通りドイツ語をやらせる。しかしそれは、単にアベチェを知っているとか、エス・イスト何とかを知っているとかいうんでは駄目だ。試験をする。」
せいの高い、胸とお尻のうんと張り出た、ドイツ士官のような大尉が、左の手をそのお尻の上に乗せ、右の手でねじ上った髯をさらにねじ上げながら、そのエス・イスト何とかというのを非常に流暢にやった。このエス・イスト組は僕の外にも五、六人あったようだった。が、みんな「試験をする」というのにおどかされて黙ってしまった。そしてその大尉は、恐らくは気まぐれに、すぐその場でドイツ語とフランス語の二組をつくってしまった。
僕の名はそのフランス語の方にあった。僕はがっかりした。しかし、命令でそうきめられてしまった以上は、もうどうともすることができなかった。それに、元来語学の好きな僕はフランス語もすぐに好きになった。そして、その他の科目はすべて中学校でやったことの復習のようなものなので、僕はこのフランス語に全力を注いだ。
本はアメリカでできたフレンチ・ブックとかいうので、英語でフウト・ノートがついていた。僕はまだ碌に発音もできないうちから、そのノートと大きな仏和辞書と首っ引きで、一人で進んで行った。そして二学期か三学期かの初めに、原書の辞書を渡されてからは、先生の言う通りに分っても分らんでもその原書の辞書ばかりを引いていた。先生はまた、この辞書と同時に、向うの子供雑誌の古いのを折々分けてくれた。「分っても分らんでもいい、とにかく読んで行け」というのが先生のモットーだった。僕は忠実に貰った雑誌の初めから終りまでを読み通した。ちっとも分らんのを二度も三度も読み通した。そして、そうこうしている間に、原書の辞書の方もいい加減分るようになり、子供雑誌も当てずっぽうに判読するようになった。
学校にはいった幾日目かの最初の土曜日に、それまでいろんな世話をしてくれた三年のある生徒から、あしたは「国」の下宿に集まるようにと言われた。
元来僕にはこの「国」という観念が少しもなかった。讃岐の丸亀に生れてそこを少しも知らず、尾張に本籍があってそこも碌に知らず、そして「国」というような言葉もあまり聞いたことがなかった。今までいた新発田では、ほとんどみんなが新発田かあるいはその附近の人であった。僕はそれらの人と一緒に自分を北越男子などと言っていた。しかしその越後に対しても「国」というような感じはまるでなかったのだ。
で、この「国」の下宿というのも、よくはその意味が分らなかった。しかし、上官の言うこと、古参生の言うことはよく聞かなければならないとは、何よりも先きに教えられたことであった。そしてこの古参生には、敬礼は勿論のこと、ちょっともの言うのでも不動の姿勢をとらなければならなかったのだ。僕は気をつけの姿勢のまま「ハア」と答えた。
「国の殿様がつくってくれたんで、みんなが日曜日にはそこへ行って遊ぶんだ。」
その古参生は僕が堅くなっているのを慰め顔に言った。が、僕にはまた、この「殿様」というのが妙に響いた。これも感情の字引の中にはない言葉だった。なるほど新発田には殿様があった。殿様という言葉もよく聞いた。が、その言葉の中に盛られている感謝や崇拝の感じは、少しも僕に移って来なかった。そして一、二年前に、何とか三十年祭とかいうんで、その殿様夫婦が東京からやって来た時、僕は彼等の通ったあとの麝香か何かの馬鹿に強い香に鼻をつまんだ、そのいやな感じがあるだけだった。しかしその殿様のお蔭で、日曜日の遊び場があるというのは、うれしかった。
その下宿というのは学校から近いあるお寺だった。その本堂の広間に古参生と新入生と四、五十名集まった。
「君等はまず国の者同士の堅い団結を形づくらなければならない。そしてその団結の下に将校生徒としての本分を発揮して行かなければならない。断じて他国のものの辱かしめを受けてはならない。」
山田という、小作りのしかし巌丈なからだの、左肩を右肩よりも一尺も上にあげた男が「訓戒」し出した。僕はそれを聞きながら、新発田で僕が一番えらいと思っていた不良連の首領の、井上というのを思い出した。そして「ここにも仲間がいるな」と僕はすぐ感じた。
山田の「訓戒」も、それに続いたまだ四、五人の「訓戒」も、要するにみなこの「断じて他国のものの辱かしめを受けてはならない」ということに帰着した。第一期生すなわち当時の三年生は、愛知県人と石川県人とがいずれも十名ばかりずつで互いに覇を争って来た。第二期生では愛知県人の方が少し数が増えた。そして僕等の第三期生では、愛知県人すなわち国のものが二十六名という絶対多数を占めたのであった。が、頭数が増えたからといって、油断はできない。また、こんなに多い頭数をかかえていて、それで負けてはなおさら見っともない。そこで団結を堅くしなければならない、と言うんだ。
僕は何で石川県人と愛知県人とがそうして争わなければならないのかは分らなかった。しかし、誰一人知っているもののない中にはいって、こうして「国のもの」という特別な友人がすぐできたのは、何よりもうれしかった。そしてこの友人等の敵になる石川県人が訳もなく憎らしくなった。
「訓戒」が済むと菓子が出た。菓子屋の箱に山のように盛った餅菓子が出た。それを食ってしまうと、こんどはちょっとした肴に酒が出た。本当の牛飲馬食だ。もともとあまり酒は飲めない僕も、みんなの勢いに駆られて、多少の盃を重ねた。そして山田等の詩吟につれて、みんなの驚きのうちに「宗次妙齢僅成童」などと吟じ出した。それで僕はすっかり山田等の「仲間」になってしまった。
二
第一期生は、最初の後輩である第二期生に対しては、ずいぶんひどく威張った。またずいぶんひどくいじめた。が、第三期生の僕等に対しては、ずいぶんあまくしてくれた。そして僕は、たぶんそんなのは僕一人だったろうと思うが、すぐにこの先輩から「仲間」として可愛がられるようになった。
最古参生たる第一期生の「仲間」には、学校の中では、どんな悪いことでも無事にやれた。たとえば煙草は、もし見つかれば営倉ものだった。しかしそれも、彼等だけには、安全な場所があった。国の先輩は僕をそこへ連れて行くことは最初遠慮していた。が、他国の先輩、ことに東京から来た先輩がすぐに僕をそこへ連れて行った。
また、これは見つかれば軽くて営倉、重くて退校の処分に遇うのだが、夜みんなが寝静まってから左翼の方の寝台へ遊びに行くこともやはり東京から来た先輩に教わった。「仲間」の仕事というのは、これが一番主なことであったのだ。
この東京から来た先輩の中には、もっとも「仲間」ではなかったが乃木将軍の息子もいた。からだは第一期生じゅうで一番大きかったが、学科は一番できなかった。そしていつも大きな口をにやにやと微笑ましていた。
が、そんな「武士道の迷行」へばかりでなく、僕はまた本当の武士道へもまじめに進んで行った。
何とかいう文学士の教頭が、倫理の時間に、武士道の話をした。それは、死処を選ぶということが武士道の神髄だ、というのだった。
僕はその話にすっかり感服した。そして僕の武士道を全うするためには、僕自身の死処をあらかじめ選んで置かなければならないと決心した。それ以来僕は古来の武士の死にかたをいろいろと研究し出した。何かの本を読んでは、これはと思う武士の死にざまを、原文のまま写し取った。そしてその写しは、たしかに一巻の書物くらいにはなっていた。
そのいろんな死にざまの中で、僕の心を一番動かしたのは、戦国時代の鳥井強右衛門のはりつけだった。というよりもむしろ、そのはりつけの図に題した、誰だかの「慷慨赴死易、従容就死難」という文字だった。
「よし、俺も従容として死に就いて見せる。」
僕は腕を扼して自分で自分にそう誓った。
やはりこの教頭の話で、もう一つ覚えていることがある。それは、遼東半島還附の勅語の中の、「報復」という言葉の解釈についてであった。その言葉の前後は今は何にも覚えてない。たぶん「臥薪甞胆して報復を謀れ」というような文句だったろうと想像する。この「報復」というのは、表むきは何とかの意味だが実は復讐のことだ、と言うんだった。そして僕はその表むきの意味が何であったかは今でも思い出すことができないほど、そのいわゆる本当の意味をありがたがった。
何月か忘れたが、たぶん初夏の頃だったろうと思う。平壌占領記念日[#底本では「紀念日」]というのがあった。
僕はその日の朝飯に初めて粟飯というものを食わされた。ちょっと甘い味がしてうまいと思った。おかずは枝豆と罐詰の牛肉が少々とだった。名古屋の第三師団全部が、その朝はこの御馳走だったのだ。
当直の、前にも言った北川という大尉が、食堂でこの御馳走のいわれを話した。平壌を占領した晩だか朝だかの、これが咄嗟のお祝いの御馳走だったのだそうだ。
食事が済むとみんなは講堂に集まった。そこには、正面に大きなアジア地図が掛かっていて、支那の遼東半島が日本と同じ赤い色で色どられていた。学校じゅうの武官と文官とが左右にならんだ。そこで今言った教頭の「報復」の話が始まったのだった。
教頭の講演が済むと、こんどは名古屋の東の町はずれにあたる、陸軍墓地へ連れて行かれた。北川大尉を始め学校の他の士官等は、その多くの戦友の墓をここに持っていた。そして彼等はその墓の一つ一つについて、その当時の思い出を話して聞かした。
「これらの忠勇な軍人の霊魂を慰めるためにも、われわれは是非とも報復のいくさを起さなければならない。」
士官等の結論はみな、いわゆる三国干渉の張本であるロシアに対する、この弔い合戦の要求であった。僕等はたぎるように血を沸かした。
間もなく、僕は初めての暑中休暇で新発田へ帰った。
ある日ふと父の机のひき出しを開けて見たら、「極秘」という字の印を押した、状袋が出て来た。封が切ってあるので僕はすぐ披いて見た。それは、当時の参謀本部の総長か次長かの何とかの(四字削除)ら各師団長および各旅団長に宛てたもので、(十七字削除)、そのつもりで将校や兵の教育をしろ、という命令風のものであった。
僕はすぐに指を折って数えて見た。三十七年と言えば、僕がちょうど少尉になった頃のことだ。僕は躍りあがって喜んだ。
父の机の上には、ロシア語の本だの、黒竜会の何とかいう雑誌だのが幅をきかしていた。
(が、ここまで書いて来て、この記憶があるいは幼年学校入学以前のことでなかったかという疑いが出て来た。それは、これが片田町の家の、父の室での出来事であったように思われるからである。その頃から父は旅団副官をやっていた。幼年学校にはいるその年か前年かに、僕の家は尾上町に引越した。どうもこの尾上町でのことではなかったようだ。すると、ロシアに対する報復ということを教えられた時にそれを思い出して、そしてその思い出がかえって後の事実のように記憶されて来たのかも知れない。しかし、僕がその(四字削除)を見て、少尉になってからのことだと喜んだのは、確かに事実である。そして僕は、この「極秘」ということについてすでに何か知っていたものと見えて、その喜びを自分一人の胸の中にたたみ込んでかつて誰にも話したことがなかった。)
三
十幾番かではいった僕は、学年試験の結果七、八番かに席順があがった。
が、この学科の上で席順を争うということは、中学校以来僕にはまるでないことだった。一番とか二番とかいう奴は、気のきかない、糞勉強の馬鹿だときめていた。「なあに、実力では遙かに俺の方が上だ」とひそかに威張っていた。そしてただいい加減上の方の席にいることで、十分満足していた。で、学科は、前にも言ったように好きな語学に耽るほかは、ことさらに勉強する必要もなくまた碌に勉強もしなかった。
しかし腕力とか暴力とか、またはそれにもとづく勢力とかの上では最初から決して人後に落ちなかった。もっとも単なる腕力では、せいの順で右翼から十四、五人目の僕は、とても一番とは行かなかったろう。が、暴力とか勢力とかいうことになれば、それには大ぶ趣きが違って来る。それに僕には愛知県という絶対多数の背景があった。
古参生等の「仲間」にはいった僕には、まず同級生等の間で傍若無人の振舞いをした。僕と同じ寝室のものや左翼の寝室のものは黙っていた。が、中の寝室のものの中に、中村という男がいた。東京のもので、口先きばかりでなく、真から元気のいい男だった。そいつが、僕がそいつの隣りの何とかいう男のところへ夜遊びに行くのを、愚図愚図言い出した。まだ外にも二、三人それに同ずるものがあったようだった。ある晩僕は、何かのことからその中村を、そいつの寝室のみんなの見ている前でなぐりつけた。奴は腕まくりしながら黙って、なぐられて笑っていた。それでそいつは友達になってしまった。この中村はその後肺を悪くして死んだ。そしてその弟の彝[#読みは「つね」]というのが第五期にはいって来た。西洋画のあの中村彝君がそれだ。
また、同じ寝室で、僕よりも右翼に佐藤というのと河野というのとがいた。どちらも、武揚学校という名古屋での陸軍予備校から来たもので、その友達が多かった。国の名古屋のものは、大がいその友達だった。中にも、僕よりも右翼にいた浜村というのと坂田というのとがよほど親しかった。その佐藤と河野とがちょいちょい僕に敵意を見せだした。そして浜村や坂田は、そんな時には、僕の敵だか味方だか分らん変な態度を取った。その中のどの一人でも僕には強敵なのに、こう大勢で組んで来られてはとても堪らなかった。さっそく僕は浜村と坂田とを呼んで、「佐藤と河野との二人と決闘するが、君等の態度をはっきりきめろ」と言った。二人は中立を誓った。で、僕はすぐに、まず大きな方の佐藤を呼び出した。同期生じゅうで一番大きな男で、撃剣も一番うまかった。器械体操場の金棒の下へ連れて行って、そこでいきなり殴りつけた。げんこは眼にあたった。彼はほろほろ涙を流して、黙ってその眼を押えていた。そこへ浜村と坂田とが心配して見に来た。そして二人の中へはいった。河野はすぐに好意を見せて来た。そして五人は、五人組をつくって、何でもの悪いことの協同者となった。
四、五年前に、ふとこの佐藤が訪れて来た。子供の時の友達だというので、誰かと思って玄関へ出て見たら、昔のままのせいの高い顔一ぱい濃い髯の彼だった。連隊長とかと喧嘩して予備になったんだそうだが、今になって止されるくらいなら、あの時分一緒に退校されるんだったなあなどと、職業の世話を頼みながら今の僕をうらやんでいた。その後南米行き移民の監督か何かにありついたとか言っていたが、どうしたか。そしてついうっかりして、昔僕が殴った眼の中の赤い疵[#「疵」は底本では「やまいだれ+比」]のあとが、まだ残っているかどうかも見落してしまった。
撃剣は佐藤の次が僕だった。器械体操は佐藤と河野と僕とが相伯仲していた。が、駈足は僕が一人図抜けて早かった。僕等の班長をしていた河合という曹長が、これも駈足をお得意としていたが、いつも口惜しがりながら僕のあとについて来た。
学科の済んだあとで、毎日そんな遊戯をやらされていたが、そのほかにもよくフットボールや綱引をやった。そしてこの二つの遊びでは、班長が組を分けるのに困ってしまった。最初前列と後列とに分けた。すると幾度やっても僕のいる前列が勝った。で、こんどは、僕一人だけを後列の方の組に廻して見た。後列が勝った。フランス語の組とドイツ語の組とに分けても見た。が、それでもやはり僕のいるフランス語の方が勝った。仕方なしに班長は「君はそばで見ていろ」と言って、僕を列の中から出してしまったこともあった。
が、困ったのは遊泳だった。
最初の夏は、伊勢のからすという海岸へ遊泳演習に行った。
先生は観海流の何とかいう有名なお爺さんで、若い時には伊勢から向う岸の尾張の知多半島まで、よく泳いでは味噌を買いに行ったという話のある人だった。学校にはこの伊勢出身で、観海流の三里や五里という遠泳に及第したものもいた。ことに佐藤などは一番の名人だった。その他にも、名古屋出身のものは大ていみなこの観海流を泳いだ。
子供の時からよく川遊びや海遊びはやったが、ぱちゃぱちゃ騒ぎ廻るほかにまるで泳げなかった僕は、実に閉口した。そして第一日目の試験に力一ぱいでようやく二、三間泳いで、一番下の丙組へ編入された。
古参生や同期生の助手連が、僕等の足首を握って、その観海流というのを教えた。が、僕はそれを教えられるのが癪なのと、足首を握られるのがいやなのとで、いつも逃げ廻っては我流の犬泳ぎで泳いでいた。
それでも一週間目の第二回の試験には、僕はその犬泳ぎで千メートル泳いで、甲組にはいった。そして二週間目の最後の試験には、やはりその犬泳ぎで最大限の四千メートル泳いで、来年は助手ということになった。
その来年には知多半島の大野へ行った。僕は名は助手でも、観海流も何にも教えることはできなかった。そして自分の受持った丙組の幾人かをただ勝手に遊ばして置いた。が、二週間目の最後の試験の時には、その中から一人、やはり我流の犬泳ぎで四千メートル泳ぎ通したのが出た。それは僕が可愛がっていた第四期生のまだほんの子供で、途中で泣きそうになるのを絶えずそばから激励して、無理やり引っぱって行ったのだった。そしてその子は、本当のゼロから出立してそこに到達した、その年のたった一人として好成績を歌われた。
最近、汽車の中でこの男に会ったが、参謀肩章なぞをさげて立派な士官になっていた。はじめ僕はすぐ前にいるのにそれと気がつかなかったが、向うで名刺を出して見せて、「御存じでしょうな」と言われたのでやっと分った。やはり昔のように、「ハア、ハア……何とかであります」と上官にもの言うように話していた。その時にはまだ大尉だったが、この頃ではもう少佐になったろう。
四
僕の腕白は二年になってますますひどくなったが、それと同時にまた僕の頭を圧える奴が出て来た。それは、第一期生が出て行ったあとで初めてその頭をあげた、第二期生だった。
僕は第一期生の「仲間」と一緒に、外套を頭からかぶって、第二期生の左翼の寝室を襲うたこともあった。また第二期生の「少年」をちょいちょいからかったこともあった。そんなことは古参生たる第二期生どもには非常な憤慨であったに違いない。そしてその少年の一人のいた石川県人どもが、まず僕を目のかたきにしだした。
彼等は僕の「生意気」な事実をいろいろと挙げて、国の第二期生等に僕の処分を迫った。国の第二期生には浅野という「仲間」の首領がいた。が、彼にもそれをどうともすることもできなかった。また、国の第二期生の中にもひそかに僕を憎んでいる奴等があった。その結果僕はしばしば殴られた。大勢で取り囲んで、気をつけの姿勢をとらして置いて、ぽかぽか殴るんだ。石川県の奴等もよくこうして殴った。
この制裁にはいっさい手を出すことができなかった。古参生には反抗することができないのだ。僕はただ倒れないだけの用心をして黙って打たれていた。倒れると、蹴られる恐れがある。が、げんこで殴られるだけなら高が知れている。そして僕は、できるだけ落ちついて、そのげんこの飛んで来るたびに一つ二つと腹の中で勘定していた。
その勘定のできる間は、どんなにひどく打たれても我まんができた。が、どやどやと大勢が一ぺんにのしかかって来て、どいつがどう殴るんだか分らなくなると、我まんができなくなった。ことに、後ろや横からそっと蹴る奴があったりすると、そしてこれは実によくあったのだが、もうどうしても我まんができなかった。が、気をつけの姿勢のまま手出しをすることのできない僕は、ただ黙ってそいつを睨みつけることのほかに仕方がなかった。
前に班長という言葉を使ったが、これは下士官で、生徒監の士官を助けて、生徒の監督をしていた。それが一級に曹長一人と軍曹一人といた。
河合軍曹は僕を可愛がって、大がいのことは大目に見てくれた。よくいろんな犯行を見つけたが、いつも大きな声で怒鳴るだけで、めったにそれを生徒監に報告することはなかった。
が、間もなくこの河合軍曹が転任になって、何とかいうばかに長っ細い曹長が来た。この曹長はよく妙な手帳をひろげては、自習室を廻ってみんなの顔とそれを見くらべていた。ある時僕はそっとその手帳をのぞきこんで見た。そこには、勇敢とか粗暴とか寛仁とか卑劣とかいうような言葉がならんでいて、その下に二、三行ずつその説明らしい文句がついていた。曹長はきっと、この手帳の中にある二字ずつのどれかの言葉によって、みんなの性格をきめていたのだ。
曹長は来るとすぐ僕を変な目で見だした。またこの曹長が来ると同時に、それまで僕等が坊ちゃん軍曹だとかガルソン軍曹だとかあだ名していたほどおとなしかった、もう一人の班長の稲熊軍曹が、急に意地悪くなり出した。そして二人で僕のあとを嗅ぎ廻っては、何やかやと生徒監に報告した。
その結果はほとんどのべつ幕なしの外出止めとなった。一週間にたった一日の日曜の外出を止められるんだ。それも、汚れた靴下を戸棚の奥に突っこんであったとか、昼、寝台に腰かけていたとか。その他、今ちょっと思い出せないような馬鹿馬鹿しいことばかりでだ。
二階の僕等の寝台の向いに下士官等の室があった。僕等はよくそこへ、煙草がなくなると、夜盗みに行った。夜は週番の下士が一人その下の室に寝ていた。
ある時もみんなの煙草が切れてしまった。河野が一番に盗みに行った。その次に僕が行った。が、僕はその室へはいって行って机の引き出しに手をかけた時、「コラ」と言って捕まってしまった。それは週番の稲熊軍曹だった。
僕は当直の生徒監の室へ引っぱって行かれた。
「実は数日前から、もっともその以前にもちょいちょいあったのですが、下士室でみんなの煙草がよくなくなりましてことにきのうは私の金が少々なくなったのです。で、きょうは是非その犯人を取りおさえようと待ち構えていましたが、はたしてこの大杉が室へ忍びこむのを見まして、今取りおさえて来ました。」
軍曹は勝ち誇ったようにして吉田中尉に報告した。中尉は僕等第三期生の受持で、国の出身で、そして僕を可愛がっていた唯一の士官だった。中尉は青くなった。そして軍曹には詳しい報告書を書いて来るようにと言ってその出て行ったあとで僕を訊問し出した。
「煙草なぞ盗ったことはありません。金も勿論のことです。きょうはズボンのボタンが一つなくなったので、今晩じゅうにつけて置こうと思ってそれを取りに行ったのです。」
僕はあくまで泥棒の事実は否認した。
「そのズボンというのはどのズボンか。」
「今はいているこのズボンです。」
僕はそう言って、軍曹に引っぱられて来る途中にあらかじめ引きちぎって置いた、ボタンのあとを見せた。
「うん……」
中尉はこううなずいたまましばらく黙って何か考えていた。金でも煙草でも、とにかく盗んだとあれば、勿論すぐさま退校だ。また、単にボタンを取りにはいったとしても、夜無断ではいるべからざる室へはいったのだから、重営倉は免れない。それに、ただそうとして処分して置いても、下士からの報告の嫌疑は免れない。それでは本人の将来にもかかわる。また自分の責任にもなる。
中尉は軍曹を呼んだ。そしてこういったその考えを、僕にも聞かせるようにして話して、本人の将来のためにその報告書を破ってくれないかと頼むように言った。
軍曹は不承不承に承知した。が、それ以来軍曹や曹長の目はますます僕の上に鋭くなった。
五
第二期生付の何とかという中尉は、自分の受持でない僕に対しては、ほとんど無関心だった。が、第四期生付の北川大尉は、そのまだ第一期生付であった頃から、妙に僕を憎みだした。
学校の前庭で彼に会う。僕はその頃の停止敬礼というのをやる。一間ばかり前で止まって、挙手の礼をするのだ。すると彼はきまってしばらく僕を睨みつけて、帽子のひさしに当てた指先の位置がどうの、掌の向けかたがどうのと、何かの小言を言った。そしてうまく上衣かズボンのボタンでもはずれているのを見つければ、すぐその次の日曜日は外出止めと来た。また、めずらしく今日は外出ができると思って喜んでいると、銃器の検査だとか清潔検査だとか触れて寝室にはいって来て、銃の手入が足りないとか靴に埃がかかっているとか言って、せっかく服まで着換えているのを外出止めにした。
ある日大尉は、夕飯の時に、きょうの月は上弦か下弦かという質問を出した。
「大杉!」
僕は自分の名を呼ばれて立った。それが下弦だということは勿論僕は知っていた。けれども僕には、そのかという音が、どうしても出て来なかった。吃りにはか行とた行、ことにか行が一番禁物なのだ。いわんや、さらにその下にもう一つか行のげが続くのだ。
「上弦でありません。」
仕方なしに僕はそう答えた。
「それでは何だ?」
「上弦でありません。」
「だから何だと言うんだ?」
「上弦でありません。」
「だから何だ?」
「上弦でありません。」
「何?」
「上弦でありません。」
問い返されればますます言葉の出て来ない僕は、軍人らしく即答するためには、どうしてもそう答えるよりほかに仕方がなかった。それを知っているみんなはくすくす笑った。
「よろしい。あしたは外出止めだ。」
大尉はそう言い棄てて、「直れ!」の号令でみんなが直立不動の姿勢をとっている間を、さっさと出て行ってしまった。
吃りのことのついでに、僕の吃りをもう少しここに書いて見よう。
母はそれを小さい時にわずらった気管支のせいにしていた。が、父方の親戚に大勢吃りのあることは前にも言った。生れつきの吃りであったらしい。そして小学校の頃には半分唖のようだったことを記憶している。その吃るたんびに母に叱られて殴られたこともやはり前に言った。
父はそれを非常に心配して、「吃音矯正」というような薬を本の広告で見ると、きっとそれを買って僕にためして見た。が、いつもその効は少しもなかった。
こう言うとよく人は笑うが、僕には一種ごく内気な恥かしやのところがある。ちょっとしたことですぐ顔を赤くする。人前でもじもじする。これも生れつきではあろうと思うが、吃りの影響も決して少なくはあるまい。また、言いたいことがなかなか言えないので、じりじりする。いら立つ。気も短かくなる。また、人が何か笑っていると、自分の吃るのを笑っているのじゃあるまいかと、すぐ気を廻す。邪推深くなる。というような精神上の影響がかなりあるように思う。
が、もう一度北川大尉の話にもどる。
ある晩、学校のすぐ裏の裁判所から火事が出た。僕等は不時呼集の訴えるようなラッパの声で目がさめた。学校の教室と塀一つで隔てて隣り合った登記所が燃えていた。
三年生はすぐポンプを出して消防に当った。
二年生はあちこちの警衛に当った。
北川大尉は、それぞれの命令を終ると、「大杉!」と僕を呼んで、さらに五、六人組の他の四人とほかに一、二名呼んで、すぐ御真影を前庭へ持ち出して、その警護をするようにと命じた。僕等はそれを非常な光栄と心得て、喜んで飛んで行った。
そこへ、しばらくして不時呼集で駈けつけた何とかいう連隊長が来て、僕等の立っている植込のそばで小便をしようとした。
「連隊長殿、ここに御真影があります。」
僕は大きな声で怒鳴りつけた。連隊長は恐縮して、敬礼して、立ち去った。僕等は非常に緊張した心持で、朝までその御真影のそばに立ち尽した。そして僕は、その間、北川大尉に対するふだんの反感をまるで忘れていた。
また、その後、と言っても僕が幼年学校を退校した後のことであるが、僕よりも一年上だった田中という男が、喧嘩で中央幼年学校を退校させられて、僕の下宿にたよって来た。田中は北川大尉と同国の伊勢だった。で、田中のおやじさんは心配して北川大尉を訪ねた。
「大杉と一緒にいるんですか。それならちっとも心配は要りません。」
田中のおやじさんは、それで安心して、息子のところへ学費を送って来た。
僕は田中のおやじさんのこの手紙を見た時、どういうつもりなのか、北川大尉の気持がちっとも分らなかった。
下士どもの僕に対する追窮はますます残酷になった。そしてついに、もう一度、あぶないところで退学されかかった。
四月の半ば頃に、全校の生徒が、修学旅行で大和巡りに出かけた。奈良から橿原神宮に詣でて、雨の中を吉野山に登って、何とかというお寺に泊った。第二期生だけがほかの宿で、第四期生と僕等とが一緒だった。
修学旅行や遊泳演習の時には、それがほとんど毎晩の仕事であったように、「仲間」のものは左翼や下級生の少年を襲うた。その晩も僕等は、坂田と一緒に、第四期生の寝室に押しかけた。
その途で僕は、稲熊軍曹がその室のふすまの隙間から、僕等を窺っているようなのを察した。が、そうした場合によくなるようになれという気になる僕は構わず目ざす方へ進んでいった。
しばらくすると、広い室の向うの障子が少し開いて、そこから軍曹らしい顔が見えた。僕はある少年の(十一字削除)いたところであった。軍曹の顔が引っこんだ。まだその辺をうろついていたらしい坂田は、急いで反対の方の側の障子から逃げた。僕は黙って軍曹の引っこんだあとを見ていた。
軍曹は曹長を連れて来た。そしていきなり僕を引っぱって行った。
その晩はそれっきりで何のこともなく過ぎた。翌日は多武峯を裏から登って、向うの麓の桜井に降りた。僕等は同期生の右翼だけでそこの小さな宿屋に泊った。おはちを三度ばかり代えさせたりして大いに騒いだ。が、まだ何のこともなかった。僕等は処分なしかなとか、学校へ帰ってからだろうとか話していた。
その翌日は長谷の観音から三輪神社に出た。そしてこの三輪神社の裏の森の中で、とうとう来なければならないことが来た。校長の山本少佐が、全生徒に半円を画かせて、厳かに僕に対する懲罰の宣告を下した。罰は、重営倉十日のところ、特に禁足三十日に処すというのだ。
六
僕はこの懲罰がどうしてあんなに僕を打撃したのかよく分らない。僕は生れて初めて、そして恐らくは絶後であろうと思うが、本当に後悔した。三十日間の禁足をほとんど黙想に暮した。そして従来の生活を一変することに決心した。
まず煙草をよした。そして今までは暴れ廻ることに費していた休憩時間を、多くは前庭の植物園に暮した。
学校の前庭は、半分が器械体操場で他の半分が立派な植物園だった。温室も大きいのが一つと小さいのが一つとあった。そしてその間に、僕等が「天文台」と呼んでいたものが立っていた。実際そこには気温、気圧、風力、雨量などを計るかなり精巧な器械や、地震計などが備えつけられてあった。
中学校の三、四年程度までしかやらない初等学校で、こんな設備のあるのは、恐らくは今でも他にはあるまいと思う。だが、この設備は、生徒のためではなくって先生のためのものだったようだ。博物と理化の先生が校長とよく知っていて、最初学校を建築する時に、その先生が設計したのだといううわさがあった。先生は一人の若い助手と一緒に、いつも、やはりこの学校の分には過ぎた立派な設備の理化学実験室や、この天文台や植物園で暮していた。が、生徒にそれを十分利用することは少しも教えなかった。そして僕等が学校を出てから、どこかからその批難が起って、この天文台は師範学校かどこかへ売ってしまった。
僕はこの植物園の中を、小さな白い板のラテン語の学名や和名などを読みながら、歩き暮した。そして絶えず今までの生活を顧みながら考えていた。
この反省はさらに、僕を改心というよりもほかの、他の方向へ導いて行った。
それは僕がはたして軍人生活に堪え得るかどうかということであった。吉野の事件では、将校会議で僕の退校処分を主張した士官もあったそうだが、そして北川大尉の代りに来た国の津田大尉と受持の吉田中尉とのお蔭でようやく助かったのだそうだが、実際僕は退校する方がいいのじゃあるまいかと考えだしたことだ。
下士どもの僕に対する犬のような嗅ぎまわりは、僕の改心に何の頓着もなく続いた。そして時々やはり、何かの落度を見つけた。僕はまず、はたしてこの下士どもの下に辛抱ができるかと思った。彼等を上官として、その下に服従して行くことができるかと思った。尊敬も親愛も何にも感じていない彼等に、その命令に従うのは、服従ではなくして盲従だと思った。
そしてこの盲従ということに気がつくと、他の将校や古参に対する今までの不平不満が続々と出て来た。
僕は初めて新発田の自由な空を思った。まだほんの子供の時、学校の先生からも遁れ、父や母の目からも遁れて、終日練兵場で遊び暮したことを思った。
僕は自由を欲しだしたのだ。
こうした気持はまた読書によってもよほど誘い出されたことと思う。
学校では、学校で渡す教科書や参考書のほかは、いっさい読書を厳禁してあった。しかしいろんな書物がひそかに持ちこまれた。
もう人の名も本の名もよくは覚えていないが、たとえば大町桂月とか塩井雨江とかいうような当時の国文科出身の新進文学士や、久保天随とか国府犀東とかいう漢文科出身の新進文学士が、しきりに古文もどきや漢文もどきの文章を発表した時代だ。僕はそんなものをしきりに耽読した。
僕が今ここに塩井雨江という名を挙げたのは、その人の何かの文章の中に「人の花散る景色面白や」とあったのが、当時の僕の読んだものの中で覚えているたった一つのことだからである。誰の何が僕にどんな影響を与えたかは何にも記憶しない。
しかしたぶん、それらの本の中には、恐らくは幼稚なしかし自由で奔放な、ロマンティズムが流れていたのではなかったかと思う。
そんな読書の影響であろうが、僕もその頃から擬古文めいたものを書いていた。これは三年になってからのことであるが、「離宮拝観記」というものを書いて、四宮憲章という漢文の先生から、「才多からざるに非ず、文巧みならざるに非ず、ただ柔弱、以て軍人の文とす可らず」という批評を貰ったことを覚えている。その前半がきっとよほどのお得意で、そして後半がよほどの不平だったのだろうと思う。
が、二年の時の何とかいう国語の先生は、僕のこの「才」を大いに愛してくれた。そしてある雪の日の作文の時間に、こんな日の練兵は「豪快」でもあろうが、しかしまた何とかでもあろうと言って、その何とかという熟字を教えてくれた。僕はさっそく僕の文章の中にその熟字を使った。
それから数日して、僕は生徒監に呼ばれて、本当にそう思ったのかと尋ねられて、よし本当でもそんなことは書くものでないと叱られた。あとで聞くと、先生もそんな字を教えるんじゃないと叱られたそうだ。
僕は先生の家へ一、二度遊びに行った。先生は、そうした(七字削除)しさや、先生が判任官なので軍曹とともに一緒に食事しなければならないことなどを、しきりにこぼして聞かした。
「君はいい時に出た。僕もとうとう出されちゃったよ。何か仕事はないかね。」
その後五、六年たって、ふと道で先生と会った時、先生はさびしそうに笑いながら言っていた。
その夏僕は、訓育(実科)では未曽有の十九点何分(二十点満点)で一番、学科では十八点何分で二番、操行ではこれまた未曽有の十四点何分で下から一番、平均して三十五番か六番かという成績表を持って、今までの僕にはなかった陰欝な少年となって新発田へ帰った。
七
僕を佐渡へ旅行にやったりしてひそかに慰めてくれたらしい父は、僕がまた名古屋へ帰る前の晩に、初めて一晩ゆっくりと僕の将来を戒めた。母は何にも言わずに、大きな目に涙を一ぱい浮べて、そばで聞いていた。僕はそれで多少気をとり直して新発田を出た。
が、東京に着くとフランス語のある中学校の、学習院と暁星中学校と成城学校との規則書を貰うことは忘れなかった。そして別に『東京遊学案内』という本をも買った。
幼年学校を退校する決心ではもとよりなかった。もう自由を欲するなどというはっきりした気持ではなく、ただ何となく憂欝に襲われて仕方がなかったのだ。そしてぼんやりとそんなものを手に入れて、それを読むことによって軽い満足を感じていたのだ。
学校に帰ってからも、しばらく、そんな憂欝な気が続いた。そして一人で、夜前庭のベンチに腰をかけて、しくしく泣いているようなこともしばしばあった。
が、すぐにこんどは、兇暴な気持が襲うて来た。鞭のようなものを持っては、第四期生や新入の第五期生をおどして歩いた。下士官どもに反抗しだした。士官にも敬礼しなくなった。そして学科を休んでは、一日学校のあちこちをうろついていた。
軍医は脳神経衰弱と診察した。そして二週間の休暇をくれた。
学校の門を出た僕は、以前の僕と変らない、ただ少し何か物思いのありそうな、快活な少年だった。そしてその足ですぐ大阪へ行った。
大阪には山田の伯父が旅団長をしていた。僕は毎日、弁当と地図とを持って、摂津、河内、和泉と、ところ定めず歩き廻った。どうかすると、剣を抜いて道に立てて、その倒れる方へ行ったりもした。
そして、すっかりいい気持になって学校へ帰った。
が、帰るとまた、すぐ病気が出た。兇暴の病気だ。気ちがいだ。
その間に、何がもとだったのか、愛知県人と石川県人との間にごたごたが持ちあがった。石川県人は東京やその他の県の有力者に助けを求めた。
その頃僕はいつも大きなナイフを持っていた。ある時はそれでそばへ寄って来ようとする軍曹をおどしつけた。みんなはそれを知っているので、敵の四、五名もそのナイフを研ぎだした。
夕方僕は味方の四、五人と謀って、敵に結びついた東京の一番有力な何とかという男を、撃剣場の前へ呼び出した。彼は来るとすぐナイフを出した。味方の四、五名は後しざりした。僕がナイフを出そうかと思って、いったんポケットに手を入れたが、思い返して素手のまま向って行った。僕の研いだばかりのナイフを出せば、きっと彼を殺してしまうだろうと思ったのだ。
僕はナイフを振り上げて来る彼の腕をつかまえて、彼を前に倒した。彼は倒れながら、下からめった打ちに僕を刺した。
僕は全身が急に冷たくなったのと、左の手が動かなくなったのとで、格闘をやめて起ちあがった。彼も起きて来て、びっくりした顔をして目を見はった。そこへ八、九人の敵味方が来た。そしてみんな、びっくりした目を見はって僕を見つめた。僕はからだじゅう真赤に血に染って立っていたのだ。
「これから医務室へ行こう。」
僕はそう言って先きに立って行った。医務室には年とった看護人が一人いた。みんなで僕を裸にして傷をあらためた。頭に一つ、左の肩に一つ、左の腕に一つ、都合三つだが、どれもこれも浅くはないようだった。
「どうだ君が内しょで療治はできないか。」
僕は看護人に聞いた。
「とても駄目です。大変な傷です。」
看護人はとんでもないことをというように顔をあげて答えた。
「それじゃ仕方がない。すぐ軍医を呼んでくれ。」
僕はそこへ横になりながら言った。そして彼の名を呼んだ。
「仕方がない。二人でいっさいを負おう。」
僕は彼のうなずくのを見て、そのまま眠ってしまった。
二週間ばかりして、僕がようやく立ちあがるようになった時、父が来た。
父は最近の僕の行状を聞いて、「そんなに不埓な奴は私の方で学校に置けません」と言って、即座に退校届を出して僕を連れて帰った。
が、帰ってしばらくすると、「願の趣さし許さず、退校を命ず」という電報が来た。
彼も同時に退校を命ぜられた。
新発田にはもう雪が降り出した十一月の末だった。
自叙伝(五)
一
父に連れて帰られた僕は、病気で面会謝絶ということにして、毎日つい近所の衛戍病院に通うほかは、もと僕の室にしていた離れの一室に引籠っていた。
この面会謝絶ということは僕自身から言いだしたのだが、父と母とはそれをごく広い意味に採用してしまった。離れには八畳と六畳とあって、奥の方の八畳は父の室になっていたのに、父はまるでその室にはいって来なかった。母も僕の室に来ることはめったになかった。そして、女中どもは勿論妹どもや弟どもにまで堅く言いつけて、決して離れへはよこさなかった。
「兄さんは少し気が変なんだからね。決して離れへは行くんじゃないよ。」
これはあとで聞いた話なんだが、母はみんなにそう言っていた。そして小さな妹どもや弟どもは、その恐いもの見たさに、よくそっと離れに通う縁側まで来ては、何かにあわててばたばたと逃げだして行った。
ていのいい座敷牢にあったのだ。
が、飯だけは母家の方へ行ってみんなと一緒に食った。みんなは黙ってじろじろ僕の顔を見ているし、僕も黙って食うだけ食って自分の室へ帰った。
僕の頭の中にはもう、学校の士官のことも下士官のことも、学友の敵味方のことも何にもなかった。したがってまた、それに附随して起って来る兇暴な気持もちっとも残っていなかった。幼年学校の過去二年半ばかりの生活は、またその最近の気ちがいじみた半年ばかりの生活は、ただぼんやりと夢のように僕のうしろに立っているだけであった。そしてその夢がまだ幾分か僕を陰鬱にしていた。が、僕の前には、新しい自由な、広い世界がひらけて来たものだ。そして僕の頭は今後の方針ということについて充ち満ちていた。
学校での僕のお得意は語学と国漢文と作文とだった。そして最近では、学課は大がいそっち除けにして、前にも言ったように当時流行のロマンティクな文学に耽っていた。そして僕はその作物や作者の自由と奔放とにひそかに憧れていたのだ。
「君等は軍人になって戦争に出たまえ。その時には僕は従軍記者になって行こう。そして戦地でまた会おう。」
僕は軍人生活がいやになった時、よく学友等とそんな話をした。が、あながち新聞記者になろうというのではなく、ただぼんやりと文学をやろうと思っていたのだ。そして戦争でもあれば、従軍記者になって出かけて行って、「人の花散る景色面白や」というような筆をふるって見たいと思っていたのだ。
僕はまず高等学校にはいって、それから大学を出ようと思った。そしてその前に、どこかの中学校の上級にはいって、その資格を得なければならないと思った。が、それには、もう英語をほとんど忘れてしまった僕は、どこかフランス語をやる中学校を選ばなければならなかった。そしてその中学校は学習院と暁星中学校と成城学校との三つしかないことを知っていた。
僕はその夏東京で買った『遊学案内』をひろげて見た。そしてそれの中学校の上級にはいるためのいろんな予備学校のあることが分った。中学校の五年の試験を受けるには僕の学力はまだ少し足りなかった。で、僕はまずすぐに上京して、どこかの予備学校にはいって、そして四月の新学年にどこか都合のいい中学校の試験を受けようと思った。
うちへ帰って二、三日の間に、これだけのことはすっかりきまった。あとはもう、時機を見て、それを父に話すだけのことだ。
僕はその時機がただちに来るだろうことも、また父がきっとそれを承知するだろうことも、楽観して、黙ってその時の来るのを待っていた。そして終日、離れの一室に籠って、近い将来の東京での自由な生活を夢みながら、自分の好ききらいには構わずに、一人で一生懸命いろんな学課の勉強をしていた。
が、その間にも、このごく平静な気持を乱すたった一つのことがあった。それは、母家の方がいつもよりはよほど客の出はいりが多くて、そして妙ににぎやかにざわついていることだった。母は、できるだけ僕の気にさわらないように自分にもまたみんなにも勤めさせて、僕にはごくやさしくしてくれながらもできるだけ口数は少なくしているくらいだのに、その顔には憂いの暗い色よりもむしろ喜びの明るい色の方が勝っていた。そしてそのお客とはしゃぎ騒ぐ声がよく離れにまで聞えた。僕はうちに何かあるんだなと思った。そして、ふと、ある日、母とお客との話の間に「礼ちゃん」という言葉を聞きとめた。
「礼ちゃんがうちからどこかへお嫁へ行くんじゃあるまいか。」
僕はすぐそう直覚した。そういえば、いろいろ思いあたることもある。汽車で柏崎を通過した時、見覚えのある丈の高い頬から顎に長い鬚をのばした礼ちゃんのお父さんが軍服姿で立っていた。
「どうした。一緒に連れて来なかったのか。」
「うん。ちょっと都合があるんで、少しのばして、親子一緒にやることにした。」
父と礼ちゃんのお父さんとの間にそんな会話が交わされた。僕は何のこととも分らない、この親子一緒というのにちょっと心を動かされながら、父の大きな黒いマントで白い病衣のからだを包んで、黙って礼ちゃんのお父さんを盗み見していた。名古屋からどこへも寄らずに、こうして汽車の中を父と二人で黙って通して来た僕には、この会話が多少気になりながらも、発車したあとでそれを父に問いただすことはできなかった。
それから、いよいようちに着いた時にも、やはりそれと関係のあるらしいあることがあった。
「おや、一緒に連れて来なかったんですか。」
僕等の俥が玄関に着いた時、あわてて出て来た母が、父と僕とを見てがっかりしたような風で言った。僕のほかに父が誰を連れて来る筈だったのか、その時には、僕はこれと柏崎でのことを結びつけて考えることができなかった。
しかし、もう事は明白になった。きっと近いうちに礼ちゃんがうちに来るのに違いない。そしてうちからどこかへお嫁に行くのに違いない。僕はそう思うと急に胸がどきどきして来るのを感じた。もう長い間まるで忘れてしまったように思いだしもしなかった、礼ちゃんのことが、わくわくと胸に浮んで来た。そして、どうしてもこれを確かめなければならないような気持になって、飯の時のほかめったに行くこともない母家の母の室へ行った。
母はどこかの女のお客と話しながら、親子で女中していた二人の客に手伝わして、何だか知らないが綺麗な模様のある布団に綿を入れていた。そして「ほんとに綺麗な模様ですわね」とか、「こんないい布団で寝たらどんなにいい気持でしょう」とかいうようなことをその女中達が言っていた。
「誰の布団?」
僕がはいって行ったことにはまるで無関心のような顔つきをしているみんなの中へ、僕は誰にともなくこう問いかけた。みんなが異常な親しみをもってその話題にしているこの布団が、誰のために、何のために造られているのか、実際僕にはちっとも見当がつかなかった。
「お前、千田さんの礼ちゃんを知っているね。こんどあの子がお嫁に行くの。そしてこのお布団はね、その時礼ちゃんが持って行くの。あしたはきっと礼ちゃんがお母さんと一緒にうちへ来るでしょう。」
母のこの返事は一ぺんに僕の顔を真赤にしてしまった。僕はその赤い顔を人に見られないうちにと思って、急いで自分の室へ逃げて帰った。そして室へはいるとすぐ、机の上に両肱を立ててしっかりと頭を押えて、今見て来た布団のはでな色を遠のけようと思って目を閉じていたが、その目からはいつの間にかあつい涙がぽたりぽたりと落ちていた。
「人の恋人をうちで世話してよそへやるのもひどいが、人の目の前でその結婚の時の布団を縫って見せるなんて実にひどい。」
ついさっきまではもう二、三年も思いだしもしなかった、ほんの幼な友達のことを、こうして僕はまるで自分の恋人のように考えだしたのだ。そして、それを今よそへ取られるのだというような気持にまでもなったのだ。
しかしその翌日、はたして礼ちゃん親子がやって来てからは、この失恋に似た妙な気持よりも、現に彼女と一つ家に生活しているという喜びの方が、よほど強かった。
彼女等は、僕の室の窓から二間ほどの庭を隔てた向うの座敷をその室にあてがわれた。その窓からでも、彼女等の顔は、向うの障子のガラス越しに見えるのだ。彼女は来るとすぐ、いずれ母から何とか注意があっただろうのにも構わずに、僕の室を訪ねてくれた。そしてひまさえあれば、というよりもむしろ彼女の母さんの隙を窺っては、僕の室へ遊びに来た。
彼女は今すぐ嫁に行くのだというような顔はちっともして見せなかった。僕がそんな方へ話を持って行っても、すぐ僕の口をおさえるようにして、話をほかへ移してしまった。彼女はただもうほとんど治った僕の傷だけを、始終気にした。そして学校を退学されたことについては、「いいわ、軍人よりももっとえらい人になりさえすればね」と言っただけで、かえって僕の将来を祝福しているようにすら見えた。僕も彼女には僕の将来の方針を打ちあけた。
「わたしなんか、学校の先生も師範学校へはいれって勧めて下さるし、わたしもそうしてもっと勉強する気でいたんだけれど、もう駄目だわ。あなたなぞは、これからが本当の勉強なんですもの。」
彼女はこう言って僕を励ましては、僕の少年時代の才能を賞めたてその頃の無邪気ないろんな追憶に移って行った。僕も彼女がすぐ結婚するんだということもほとんど忘れて、恋人とでも話しするような甘い気持になって、彼女と一緒にその追憶に耽っていた。
ある日僕は、彼女の室で、彼女親子と母とが何事かしきりにささやき合っているのにきき耳を立てた。
「どうして、おばさん、気が変などころじゃあるもんですか。わたし、しょっちゅう遊びに行ってお話ししているんですけれど、そんなところはこれっぱかしでも見えませんわ。そして、これからが本当の勉強だと言って、一生懸命になって勉強していらっしゃるんですもの。」
「そうかね。わたしはまた、夜いつ目をさまして見ても、きっと離れの方で本の紙をめくる音がして、はばかりへ行って見ても離れでかんかんあかりが点っているので、何だか気味がわるかったくらいよ。」
「ええそうして毎晩遅くまで勉強していらっしゃるんだわ。そして近いうちに東京へいらっしゃりたいですって。これからの方針も何もかも、もう自分一人でちゃんときめていらっしゃるんだわ。ね、おばさん、本当にしっかりしていらっしゃるんだから、わたし栄さんに代っておばさんやおじさんにお願いしますわ、早く栄さんのお望み通りに東京へ出しておやんなさるといいわ。」
「まあ、そんなに勉強しているんですかね。わたしはまた、うちで少し気が変だなんて言うから、どんなに心配していたか知れないの。そして黙って見ているんだけれど、べつにこれといって変なところもなしね。かえって変に思っていたくらいですわ。礼ちゃん、本当にありがとうよ。わたし、それですっかり安心したわ。」
僕はこの話し声を聞いて、本を閉じて、一人でしくしく泣きながら、どんなことがあってもうんと勉強して、彼女のためにだけでもえらい人間になって見せると一人で誓った。
その晩は珍らしく礼ちゃんが夜遊びに来た。が、その日の話については、彼女も何にも言わなければ、僕もまた何にも言うことができなかった。僕はただ黙って、心の中でだけ彼女に感謝しているほかはなかった。そして彼女はいつもと同じように、僕を慰さめ励まして、幼な物語に夜を更かして自分の室へ帰って行った。
その翌日は、朝早くから、うちじゅうが総がかりでごたごた騒いでいた。そして夕方に、女中どもや子供達を残して、みんなが出てしまった。僕はいよいよ礼ちゃんがお嫁に行ったのだなと思った。礼ちゃんが何にも言わずに行ってしまったことはずいぶんさびしかったが、もう恋人を人にとられたような妙な気持はちっともしなかった。そして、ただ彼女の上に幸あれと思うほかに、きのう一人で彼女に誓った言葉をまた一人で繰返していた。
二
それから四、五日経って、ある晩僕は父と母との前に呼ばれた。父の顔にはもう僕を名古屋へ迎いに来て以来の、むずかしそうな筋が一つも出ていなかった。母も僕がはいって行った時にいつもちょっとやる、そのはいって行ったのを知らないような顔つきはよして、にこにこして迎い入れてくれた。
「これからどうするつもりだ。」
父はできるだけ優しく、しかし簡単にただこれだけのことを言った。僕は一人できめていただけのことをはっきりと、しかしやはり簡単に答えた。
「文学はちょっと困るな。」
父は僕の言葉を聞き終ると、ちょっと顔をしかめて首を傾けた。
「文学って何ですの。」
母は心配そうに父の顔をのぞいた。
「それ、あの桑野の息子がやったようなものさ。」
「あの、大学を卒業して、何にもしないで遊んでいる、あの方?」
「うん、あれだ。あんなんじゃ困るからな。」
「そうね。」
僕はその桑野の息子というのがどんな男か知らなかったが、母もそう言われれば、父に賛成するほかはないらしかった。
「とにかく東京へ出して勉強はさせてやるつもりだが、文学というのだけはもう一度考え直して見てくれ。お前も七、八人の兄弟の総領なんだからな、医科とか工科とかの将来の確実なものなら、大学へでもやってやるがね。どうも文学じゃ困るな。」
父はまた顔をしかめて首を傾けた。
「でも、せっかくそうときめたことを今すぐ考え直すというわけにも行きますまいし、もう一日二日考えさして見たらどうでしょう。」
母は父にそう言ってなお僕にも附けたして言った。
「お父さんも東京へ出してやるとおっしゃるんだから、今晩はもうこれで室へ帰って、もっとよく考えて見てごらん。」
僕はそれでもう僕の目的の七、八分は達したものと思って喜んで室に帰った。
その翌日は、たぶん父に頼まれたのだろうと思うが、医学士で軍医の平賀というのが来て、しきりに医者になれと勧めて行った。これは子供の時から僕が始終世話になっている医者で、幼年学校の入学試験の時にも僕の目の悪いのを強いて合格にしてくれた人だった。が、僕にはどうしても医者になる気はなかった。その後外国語学校を出た時にも、今の平民病院長の加治ドクトルが、その息子の時雄君の連れとなってフランスへ行って医学をやったらどうかと勧めてくれたのだが、やはりどうしても医者になる気はなくって断ってしまった。そしてさらにその後、自然科学に興味を持つようになってから、いっそのことあの時に医者になっていればよかったと、時々にそして今でもまだそう思うことがある。
が、そこへ、もう一人、ちょうどいい妥協論者が出てくれた。それは父が大ぶ目をかけていた森岡という若い中尉だった。父はこの中尉にきっと僕のことを相談したに違いなかった。中尉は僕のところに来て、友達のようにして相談に乗ってくれた。
「お父さんはどうしても文学は困ると言うんだが、ほかに何か方法はないものかね。」
中尉はうちの財政上のことからいろんな話をして、僕に再考を求めた。
「そんなら語学校へ行ってもいいんです。」
僕は大学が駄目ならこうという、僕の第二案を打ちあけた。
「それやいい、それならきっとお父さんも賛成する。よし不賛成でも、きっと僕が賛成さして見せる。」
中尉は、僕が語学校と言いだしたので、急に元気づいて賛成した。
当時陸軍では、ことに田舎の軍隊では、再帰熱のように時々起る語学熱が流行っていた。陸軍大学へはいれなくっても、多少語学ができさえすれば、洋行を命ぜられたり要路に就かせられたりして、出世の見込が十分についた。森岡中尉も、やはり幼年学校出身で、フランス語をやっていた。そしてそのフランス語を大成さすべく、しきりに東京へ出て語学校へはいりたがっていたのだ。礼ちゃんの花婿の隅田中尉というのも、これは中学校出身で英語がお得意なので、やはり何とかして東京へ出て語学校へはいりたいと言っていた。父も、以前にはフランス語をやったりドイツ語もやったりしていたが、その頃は新しくまたロシア語をやりだしていた。
そんな時なので、語学校を出れば何になれるのかということなどはごくぼんやりと考えただけで、中尉も[#「中尉も」は底本では「中尉のも」と誤記]父もすぐ僕の第二案に賛成してくれた。が、僕は語学校を出ればすぐ大学の選科にはいれ、その選科からはさらに普通学の試験を受けて本科に移れることをよく承知していたのだった。
とにかく僕はすぐにも上京することを許された。そして自分で元日の朝早く出発することにきめた。
が、この元日には俥屋が行こうと言わないので、仕方なしに翌二日に延ばした。
元日の朝は暖かいいい天気だった。それが昼頃から曇り出して、夕方にはもう霏々として降る大雪の模様になった。その晩の十二時少し過ぎだ。もう三、四尺積もっている雪の中を、僕は橇に乗って二人の俥夫に引かれてうちを出た。
「まあ、あんなに喜んで行く。」
母は一人で玄関のそとまで僕を送りだして、自分もやはり嬉し泣きに泣いていた。
町はずれまではまだよかった。が、町を出るともう橇は一歩も進むことができなかった。俥屋のお神はあらかじめそうと知って、ゆうべの間に一度とめに来たのだ。しかし僕がどうしても聞かないので仕方なしに一番屈強な男を二人選んで寄越したのだが町を出ると、雪ですっかり埋もっている道は、その俥夫の一歩一歩の足を腿まで食いこんだ。そんなことで橇が引けて行けるものではない。それに、橇の上に乗って、僕がその中に坐っている籠は、時々横合いから強い風を受けてひっくり返りそうになる。とうとう俥夫等は立ちどまって、「もうとても駄目です」と言う。
「それじゃ歩いて行こうじゃないか。」と僕は言いだした。「君等の中の一人が真先きに歩くんだ。その足あとを伝って僕が真ん中になって行く。そのあとへまた、君等の中のもう一人が僕の荷物をかついで行く。そして先頭のものとしんがりのものとは時々交代するんだ。僕だって、時には先頭に立ったり、しんがりになって荷物を持ったりしたっていいよ。」
俥夫等はこの提案を喜んだ。
「わしらだって、うちのお神さんや奥様とお約束して、なあに大丈夫でさあって引受けて来たんですからね。今さらとても駄目でしたっておめおめ帰れもしませんよ。」
そして彼等は急いでその橇を近所のどこかへ預けて、僕の言う通りにして歩きだした。
が、道は遠いのだ。北越線の一番近い停車場の新津へ出るのに、新発田からは七、八里あるのだ。そしてその間には、半里も一里もの間家一軒もない、広い野原を幾つも通り抜けなければならんのだ。雪は降る。眼前数歩の先きは何にも見えないほどに、細かい雪がおやみなく降る。降るばかりならまだいい。時々強い風が来ては、足もとの雪を顔に吹きあげる。そんな時には、ただしっかりと踏みとどまって、その風の行ってしまうのを待っているほかはない。そしてまた、ただほかよりは少し小高くなっている道をあてに、一歩一歩腿まで埋まりながら重い雪靴の足を運んで行くのだ。
ちょうど新発田と新津との中間の、水原という町の向うの、一里ばかりの原に通りかかった時には、三人とも疲れと餓えとでへとへとになってしまって、幾度その原の中で倒れかかったか知れなかった。そして五歩歩いては休み十歩歩いては休みして、ようやくその原の真ん中の一軒家に着いた時には、みんなもうまるで死んだもののようだった。
しかし、その一軒家で大きな囲爐裡に火をうんともやして、一時間ほどそのまわりに転がって寝て、そしてあつい粥を七、八はい掻っこんだあとでは、すっかりもとの気分になっていた。
そして夕方近い頃に、一番の汽車に間に合う筈であった新津に、ようやく着くことができた。
東京に着くとすぐ、僕は牛込矢来町の、当時から予備か後備かになっていた退役大尉の、大久保のお父さんを訪ねた。上京のたんびに僕はこの大久保のうちへ遊びに行って、そのすぐ向いに下宿屋のあることを知っていたので、大尉の監督の下にそこへ下宿するように父に申し出てあったのだった。
若松屋というその下宿には、幸いに奥の方に、四畳半の一室があいていた。そして僕は、正月の休みの間に探し歩いた、猿楽町の東京学院へ(今はもうないようだが)、中学校五年級受験科というのにはいって、毎日そこから通うこととなった。そこでは僕は自分の学力の足りないと思った数学や物理化学に特に力を入れて勉強した。そして同時にまた、あるいは四月頃になってからだとも思うが、夜は、その頃四谷の箪笥町に開かれたフランス語学校というのに通った。これは、庄司(先年労働中尉と呼ばれたあの庄司何とか君の親爺さんだ)という陸軍教授が主となって、やはり陸軍教授の安藤(今は早稲田の教授)だの、何とかという高等学校の先生のフランス人だのが始めた学校だった。
こうして僕は、東京に着く早々、何もかも忘れて夜昼ただ夢中になって勉強していた。
が、何よりも僕は、僕にとってのこの最初の自由な生活を楽しんだ。すぐ向いには監督であり保証人である大尉がいるのだが、これはごくお人好の老人で、一度でも僕の室をのぞきに来るでもなし、訓戒らしいことを言うのでもなし、また僕の生活について何一つ聞いて見るというのでもなかった。僕はまったく自由に、ただ僕の考えだけで思うままに行動すればよかったのだ。
東京学院にはいったのも、またフランス語学校にはいったのも、僕は自分の存分一つできめた。そして大尉や父にはただ報告をしただけであった。僕が自分の生活や行動を自分一人だけで勝手にきめたのは、これが初めてであり、そしてその後もずっとこの習慣に従って行った。というよりもむしろだんだんそれを増長させて行った。
僕は幼年学校で、まだほんの子供の時の、学校の先生からも遁れ父や母の目からも遁れて、終日練兵場で遊び暮した新発田の自由な空を思った、その自由が今完全に得られたのだ。東京学院の先生は、生徒が覚えようと覚えまいとそんなことにはちっとも構わずに、ただその教えることだけを教えて行けばいいという風だった。出席しようとしまいと教授時間中にはいって行こうと出て行こうと、居眠りしていようと話していようとそんなことは先生には何の関係もないようだった。そしてフランス語学校の方では、生徒が僕のほかはみな大人だったので、先生と生徒とはまるで友達づき合いだった。一時間の間膝にちゃんと手を置いて、不動の姿勢のまま瞬き一つせずに、先生の顔をにらめている幼年学校と較べればまるで違った世界だった。
僕はただ僕自身にだけ責任を持てばよかったのだ。そして僕はこの自由を楽しみながら、僕自身への責任である勉強にだけただ夢中になっていた。
三
けれどもやがて、この自由を憧れ楽しむ気持がただ自分一人のぼんやりした本能的にだけではなく、さらにそれが理論づけられて社会的に拡張される機会が来た。ごく偶然にその機会が来た。
僕はその頃の僕の記憶の一断片について、かつて『乞食の名誉』の中の一篇「死灰の中から」の中に書いた。
――僕が十八の年の正月頃だった。(あるいはもう二、三カ月かもっとあとのことかも知れない。)まだ田舎から出たてのしかも学校の入学試験準備に夢中になって、世間のことなぞはまるで知りもせず、また考えても見ない時代だった。僕は牛込の矢来に下宿していた。ある寒い日の夕方、その下宿にいた五、六人のW(早稲田)大学の学生が、どやどやと出て行く。そとにも大勢待っているらしいがやがやする音がする。障子をあけて見ると、例の房のついた四角な帽子をかぶった二十人ばかりの学生が、てんでに大きなのぼりみたいな旗だの高張提灯だのを引っかついで、わいわい騒いでいる。
――「もう遅いぞ。駈足でもしなくっちゃ間に合うまい。」
――「ああ、しかしその方がかえっていいや。寒くはあるしそれにこの人数でお一二、お一二で走って行けば、ずいぶん人目にもつくだろう。」
――「そうだ。駈足だ! 駈足だ!」
――みんなは大きな声で掛声をかけて、元気よく飛んで行った。その時の「Y(谷中)村鉱毒問題大演説会」と筆太に書いたのぼり[#「のぼり」に傍点]の間に、やはり何か書きつけた高張りの赤い火影がゆらめいて行く光景と、みんなの姿が見えなくなってからもまだしばらく聞えて来るお一二、お一二の掛声とは、今でもまだはっきりと僕の記憶に浮んで来る。これがY村という名を初めて僕の頭に刻みつけた出来事であった。そしてそれ以来僕はその頃僕がとっていた唯一の新聞のY新聞(万朝報)に折々報道され評論されるY村事件の記事を多少注意して読むようになった。
――Y村問題はすぐに下火になった。今考えて見ると、ちょうどその頃がこの問題について世間が大騒ぎした最後の時であったのだ。したがってY村についての僕の注意も一時立消えになった。しかしこの問題のお蔭で、僕はY新聞のD(幸徳)やS(堺)、M(東京毎日)新聞のK(木下尚江)W大学のA(安部磯雄)などの名も知り、同時にまた新聞紙上のいろんな社会問題に興味を持つようになり、ことにDやSなどの文章に大ぶ心を引かれるようになった。そしてその翌年の春頃には、学校で「貧富の懸隔を論ず」などという論文を書いて、自分だけは一ぱしの社会改革家らしい気持になっていた。
――僕ばかりじゃない。さらにその翌年、DとSとがその非戦論のために新聞を出て一週刊新聞(平民新聞)を創めて、新しい社会主義運動を起した時、それに馳せ加わった有為の青年の大部分は、この鉱毒問題から転じて来たものか、あるいはこの問題に刺激されて社会問題に誘いこまれたものであった。
これは谷中村の鉱毒問題について書いたものの中の一断片だ。したがって、勿論その中には嘘はないのだが、多少いっさいを鉱毒問題の方へ傾けすぎた嫌いはある。それを今後は、この行を書いている最中の自由という気持の記憶の方へ、もう少し傾け直さなければならない。その方が、少なくとも今は、本当だと思うのだ。
僕はただ一番安いということだけで万朝報をとった。田舎者でしかも最近数年間は新聞を見るのを厳禁されて、世の中はただ軍隊の生活ばかりのように考えこまされていた僕は、そのほかにどんな名のどんな新聞があるのかも碌には知らなかった。その数年間の世間の出来事についても、僕が今覚えているのは、皇太子(今の天皇)[#「今の天皇」は「大正天皇」]の結婚と星亨の暗殺との二つくらいのものだ。皇太子の結婚は僕が幼年学校にはいるとすぐだった。僕等は二人が伊勢へお参りするのを停車場の構内で迎えて、二人のごく丁寧な答礼にすっかり恐縮しかつありがたがったものだ。それを思うと、これはまったくの余談ではあるが、山川均君なぞは恐ろしいほどの先輩だ。彼はすでにその頃キリスト教主義の小さな雑誌を出していて、この結婚についての何かを批評して、そして不敬罪で三年九カ月とか食っているのだ。星亨の暗殺は僕が幼年学校を出る年のことだったが、僕はそれを学校の庭で、しばらく星の家に書生をしていたという一学友から聞いただけだった。そしてそれに対してはただ、剣客伊庭某の腕の冴えに感心したくらいのものだった。星がどんな人間でどんな悪いことをしたかというようなことはまるで知らなかった。
この盲の手をほんの偶然に手引してくれたのが万朝報なのだ。僕はこの万朝報によって初めて、軍隊以外の活きたいろんな社会の生活を見せつけられた。ことにその不正不義の方面を目の前に見せつけられた。
しかしその不正不義は僕の目には、ただ世間の単なる事物として映り、単なる理論としてはいったくらいのことで、それが僕の心の奥底を沸きたたせるというほどのことはなかった。それより僕はその新聞全体の調子の自由と奔放とにむしろ驚かされた。そしてことに秋水と署名された論文のそれに驚かされた。
彼の前には、彼を妨げる、また彼の恐れる、何ものもないのだ。彼はただ彼の思うままに、本当にその名の通りの秋水のような白刃の筆を、その腕の揮うに任せてどこへでも斬りこんで行くのだ。ことにその軍国主義や軍隊に対する容赦のない攻撃は、僕にとってはまったくの驚異だった。軍人の家に生れ、軍人の間に育ち、軍人教育を受け、そして軍人生活の束縛と盲従とを呪っていた僕は、ただそれだけのことですっかり秋水の非軍国主義に魅せられてしまった。
僕は秋水の中に、僕の新しい、そしてこんどは本当の「仲間」を見出したのだ。が、たった一つ癪にさわったのは、僕が水のしたたるような刀剣を好きなところからひそかに自ら秋水と号していたのを、こんど別に秋水という有名な男のあることを知って、自分のその号を葬ってしまわなければならないことだった。
それと、もっと近くにいて僕の目をあけてくれたのは、同じ下宿のすぐそばの室にいた佐々木という男だった。彼はもう二、三年前に早稲田を出て、それ以来毎年高等文官の試験を受けては落第している、三十くらいの老学生だった。いつも薄ぎたない着物を着て、頭を坊主にして、秋田あたりのズウズウ弁で愛嬌のある大きな声をだして女中を怒鳴っていた。その顔も厳めしそうな八字髯は生やしていたが、両頬に笑くぼのある、丸々とした愛嬌面だった。友達のない僕はすぐこの老書生と話し合うようになった。彼は議論好きだった。そして僕のような子供をつかまえても議論ばかりしていた。僕も負けない気で、秋水の受売りか何かで、盛んに泡を飛ばした。
それから、この佐々木の友人で、フランス語学校で同じ高等科にいた小野寺というのと知った。これもやはり、二、三年前に早稲田を出て、その頃は研究科でたった一人で建部博士の下に社会学をやっていた、少し出歯ではあったが、からだの小さい、貴公子然とした好男子だった。
ある晩、学校からの帰りに、同じ生徒の高橋という輜重兵大尉が、彼に社会学というのはどんな学問かと尋ねた。
「たとえば国家というものが、またその下にあるいろんな制度がですね。どんなふうにして生れて、そしてどんなふうに発達して来たかというようなことを調べるんです。」
小野寺は得意になって、やはり佐々木と同じように少々ズウズウ弁ながら、多少演説口調で言った。
「それや面白そうですな。」
士官学校の馬術の教官で、縫糸を一本手綱にしただけで自由に馬を走らせるという馬術の名手の高橋大尉は、本当にうらやましそうに言った。
社会学というのは、またそれがどんなものかということは、これが僕には初耳だった。そして僕も、高橋大尉と一緒にこんな学問をしている小野寺をうらやましがった。そして小野寺や佐々木に頼んで、社会学の本だの、その基礎科学になる心理学の本だのを借りて、まるで分りもしないものを一生懸命になって読んだ。たぶん早稲田から出た遠藤隆吉の社会学であったか、それとも博文館から出た十時何とかいう人の社会学であったか、それともその両方であったかを読んだ。また、金子馬治の『最近心理学』という心理学史のようなものも読んだ、そしてついでに、同じ早稲田から出ている哲学の講義のようないろんなものも読んだ。
小野寺はまた僕に仏文のルボン著『民衆心理』というのは面白い本だから読めと言って勧めた。それも僕は、字引を引き引きしかもとうとう碌に分らないながらも読んでしまった。
学習院は欠員なしでだめ、暁星中学校もだめとあって、その四月に、僕はあとたった一つ残っている成城中学校へ試験を受けに行った。が、願書を出す時には外国語をフランス語として出して受けつけたのが、いよいよ試験の日になって「こんどの五年にはほかにフランス語の生徒がないから」というので無駄に帰されてしまった。
そして僕は九月まで待って、どこか英語の中学校の試験を受けなければならないはめになった。それで僕は急に英語の勉強を始めた。そしてユニオン読本の四が読めさえすればどこへでもはいれると聞いて、ほかの学科の方はよして、そのユニオンの四を近所の何とかいう英語の先生のところへ教わりに行った。もう幾年かまるで英語の本をのぞいて見なかったので、初めからユニオンの四にぶつかるのは実に無茶なことだった。しかし僕は先生のところでその講義を聞いて来ては、さらにうちへ帰って字引と独案内とを首っ引きにして、それこそ本当に一生懸命になって勉強した。そして一、二月するうちにはそのユニオンの四も大した苦にはならなくなった。
すると七月か八月の幾日かに、突然僕は「母危篤すぐ帰れ」という父の電報を受取った。
自叙伝(六)
一
父の家は尾上町のすぐ近所の西ヶ輪[#底本では「西ケ輪」]という町の、練兵場の入口の家に引越していた。もと谷岡という少佐が住んでいて、僕はその息子と中学校で同級だったので、前からよく知っている家だった。谷岡は幼年学校や士官学校の試験にいつも失敗して、とうとう軍人になりそこねて、後慶応にはいって、今はどこかの新聞の経済記者になっていると聞いた。そしてその家の裏には、先年社会主義思想を抱いているというので退職された、松下芳男中尉が住んでいた。勿論まだ当時はほんの子供で僕の弟の友達だった。
玄関にはいると、僕は知っている人達や知らない人達の大勢がみんな泣きながら、あっちへ行ったりこっちへ行ったりしてうろうろしているのを見た。僕は母はもう死んだのだと思った。しかもまだ今死んだばかりのところだと思った。そしてそのうろうろしている人達の一人をつかまえて、「お母さんはどこにいます」と聞いた。が、その女の人はちょっと大きく目を見はって見て、何にも答えないで、わあと声を出して泣いて、逃げるようにして行ってしまった。僕はまたもう一人の女の人をつかまえた。が、やはりまた、前と同じ目に遭った。
仕方がないので、どこか奥の方の室だろうと思いながら、まず先きの人達の逃げこんだ玄関のすぐ次の室にはいった。その室とその奥の座敷との間の襖は取りはずされて、その二つの室一ぱいに大勢の人達が坐っていた。僕がはいって行くと、みんなは泣きはらした目をやはり先きの人達と同じように大きく見はって僕の顔を見つめていたが、僕がまた「お母さんはどこにいます」と聞くと、その中の女の人達はまたわあと声をあげて泣きだした。そして誰一人僕の問いに答えてくれる人はなかった。僕は変な気持になりながら、仕方なしに、また襖をあけて玄関の奥の一室にはいった。そこは母の居室になっていたものと見えて、箪笥だの鏡台だのがならんでいるだけで、誰もいなかった。僕はそこに突ったったまま、一体どうしたことなんだろうと思いながら、ぼんやりしていた。
そこへ、それが誰だったかはもう忘れてしまったが、とにかく母と親しくしていたそして僕も好きだったある軍人の細君がはいって来た。
「あなたはまあどうしたんです。お先きにいらっしたんですか。」
彼女もやはり目を泣きはらしながら、しかししっかりとした口調で叱るように言った。僕はその「お先きに」という言葉が何のことだか分らなかった。しかし、とにかく、
「いや、僕は今東京から来たんです。」
とだけ答えた。
「それじゃあなたは新潟へはいらっしゃらなかったんですか。」
「え、行きません、母は新潟にいるんですか。」
「ああ、それじゃあなたは何にも知らないんですね。まあ……」
と言いながら彼女はほろほろと涙を流した。
「母はもう死んだんですか。」
「ええ、きのう新潟病院でおなくなりになりました。そして、きょう、もうすぐみなさんでこちらへお帰りの筈です。」
僕はそう聞くと、なるほどうちのものは誰もいないなと気がついた。そして同時にまた、初めて自分で電報というものを受取った僕が、その差出人のところはちっとも見ずにただ中の「母危篤すぐ帰れ」というのだけを見て、驚いて向いの大久保から旅費をかりて上野の停車場へ駈けつけたことを思いついた。
「お着きです。」
という声がして、みんなが玄関へ出て行くのが聞えた。
「ああ、お着きだそうです」
彼女はぼんやりと考えている僕を促すように言って、玄関へ出て行った。僕もそのあとに随いて行った。
棺の前後に父や弟妹等やその他四、五人の人達が随いて、今車から降りたばかりのところだった。
あとで聞くと、さっき僕が車から降りた時にも、やはり「お着き」だと思って大勢出て来たのだが、僕がたった一人でしかもうろうろしながら「お母さんはどこにいます」なぞと聞くもんだから、これやきっと気でも変になったんじゃあるまいかと、みんながそう思ったんだそうだ。
母は卵巣膿腫、すなわち俗にいう脹満で死んだのだ。
その少し前に、九人目の子供を流産してからだを悪くしたので、しばらくどこかの温泉へ行っていたのだが、帰ってすぐ手術をすると言って新潟へ出かけたのだそうだ。しかも、「なあに、二週間もすればぴんぴんしたからだになって帰って来ますよ」と言って、大元気で出かけたのだそうだ。
「そんなふうでしたし、それにお母さまは栄は今試験前で勉強で忙しいんだから心配さしちゃいけないとおっしゃって、どうしてもあなたのところへお知らせするお許しが出なかったんですよ。」
母の死骸が着いた晩、三の町のお嬶といって、昔僕の家が新発田へ行ったその日から母の髪結いさんとして出はいりして、そしてその後髪結いをよしてからもずっと母の一番親しいお相手として出はいりしていた女が、お通夜をしながら僕に話しだした。僕が去年の夏、この自叙伝を書く準備に二十年目でそっと新発田へ行った時にも、僕が最初に訪ねたのはもういい婆さんになっていたこのお嬶だった。
「すると、三、四日もしないうちに、危篤という電報なんでしょう。で、私、お子さん方をみなさんお連れ申して参ったんですけれど、それやもう大変なお苦しみでしてね。注射でやっと幾時間幾時間と命をお止め申していたんです。時々、栄はまだかまだかとおっしゃりましてね、そしてあの気丈な方がもう苦しくて堪らないから早く死なしてくれ死なしてくれとおっしゃるんです。それでも、私がもうすぐお兄さまがいらっしゃいますからと言うと、うんうんとお頷き遊ばして黙っておしまいなさるんですもの。それや、どんなにかあなたをお待ち遊ばしたんですか。幾度も早く死なして死なしてとおっしゃるんですけれど、そのたびに私があなたのことを申しあげると、頷いては黙っておしまいなさるんですもの。」
お嬶は一晩じゅう、ほとんどこの話ばかり繰返して言って聞かしては、自分も泣きまた僕をも泣かした。
「それに、お母さまは、お嬶丈夫になってすぐ帰って来るからねと大きな声でおっしゃってお出かけなすったんだけれど、実はご自分でも覚悟をしていらっしたんですよ。私、お子さん方をお連れして行く時に、お召物を出しに箪笥をあけて見ますと、お母さまのお召物に何だか妙な札がついているんです。よく見ますと、それがみんな春とか菊とか松枝とかとお嬢さん方のお名前が書いてあるんでしょう。私、腹が立ちましてね。何もそんな覚悟までして、わざわざ新潟くんだりへ手術なぞしにいらっしゃらなくてもよさそうなものだと思いましてね。私、そのことはお母さまに存分お怨みを申上げましたわ。」
お嬶はまたこんな話もした。そして、母の死は実は医者の過失なので、手術後腹が痛み出してまた切開して見たら中から糸が出て来て、大変な膿を持っていたなぞとも話した。これは、そこに立ち会った人達がみんな非常に憤慨して話して、病院へなんとか掛合わなければならんなぞと言っていたが、父は悲痛な顔をしながら「いや、済んだことはもう仕方がない」と一人あきらめていた。
そんなお通夜が二晩か三晩続いて、大阪にいたお祖母さん(母の母)と僕のすぐ妹の春とが到着するとすぐ、葬式が出た。
ちょうど新発田の町のほとんど端から端までの一番賑やかな大通りを通って、僕が位牌を持たせられて、宝光寺という旧藩主の菩提寺まで練って行った。新発田にもう十幾年もいて、それに母はそとへ出ると新発田言葉で大きな声で会う人ごとに挨拶して歩くというほどだったので、見送りの人もずいぶん多かった。そしてほとんど通りの町じゅうの人がそとへ出て見送ってくれた。
「あんなご立派なお葬式はまだ見たことがありません。」
と言って、三の町のお嬶なぞは今でもまだ、その人並すぐれた小さなからだを揺すりながら、おかめのような顔を皺くちゃにして自慢にしている。
葬式が済んでから、母の棺を六人ばかりの人足にかつがして、僕と弟の伸とが引っついて、五十公野山という僕等がよく遊びに行った小さな山の奥の方へ火葬に行った。人足どもはその場所まで行くと、まず藁を敷いて、その上へあたりの松の枝を折って来ては積み重ねて、そしてその上へ棺を載せてまた松の枝を積み重ねた。そして自分等はそこから二、三間離れたところに蓆を敷いて、車座になって、持って来た大きな徳利だの重箱だのを幾つか並べたてた。こうして朝まで飲みあかしながら、死骸がすっかり骨になってしまうまで待つんだという。
僕はその人足どもの言うままに、一束の藁に火をつけて、その火を棺の一番下に敷いてある藁の屑に移した。藁はすぐに燃えあがった。その火はさらに、その上の松の枝や葉に燃え移った。そして僕はその焔々として燃えあがる炎の中に、ふだんのようにやはり肉づきのいい、ただ夏のさ中に幾日もそのまま置いたせいかもう大ぶ紫色がかりながらも、眠ったようにして棺の中に横たわっている母の顔を見た。僕はその棺箱が焼けて、母の顔か手か足かが現れて出たら、堪らないと思った。それでも僕はじっとしてその炎を見つめていた。
人足どもの一人は急いで僕等兄弟をわきへ連れて行って、すぐ帰るようにと勧めた。もう日も大ぶ暮れていたのだ。そして僕はその場所へ行ったらすぐ帰るようにとあらかじめ言いつけられて来たのだ。僕等はその人足に送られて山の麓まで出て、そこから車に乗って帰った。
二
母の死体がうちへ着いた時に、僕はその棺のそばに、礼ちゃんが立っているのを見た。礼ちゃんも二、三日前から新潟の母のところへ行っていたのだ。たしかその晩だったと思うが、夜遅くなってから、お通夜をするというのを無理やりにみんなに帰れ帰れと勧められてうちへ帰った。そして、高級副官の父のもとにやはり旅団副官をしていた何とかいう中尉の細君が、これはまだ若いそうして連隊じゅうで一番綺麗な細君で、僕は前からずいぶん親しくしていたのだったが、そっと僕の肩を突っついて、しかし高い声で、僕に礼ちゃんを送って行くようにと勧めた。ほかの人達も、それと一緒になって、同じように僕に勧めた。僕は急に胸をどきどきさせながら、ちょっとためらった。礼ちゃんはもじもじしながら、にこにこして、僕が座を立つのを待っているようだった。綺麗な細君もやはりにこにこして、僕の顔を見ているようだった。僕はこの二人の若い細君の微笑みに妙に心をそそられた。
僕はすぐ提灯を持って、礼ちゃんと一緒にうちを出た。そとは真暗だった。礼ちゃんと僕とはほとんどからだを接せんばかりに引っついて行った。二人がこんなにして歩くのはこれが初めてだったのだ。僕はもう母が死んだことも何もかも忘れてしまった。そして提灯のぼんやりした明りを二人の真ん中の前にさし出して、ますます引っついて歩いて行った。二人は何か声高に話しながら笑い興じていたようだった。
「あら、斎藤さんじゃありませんか。」
二人は向うから軍服を着て勢いよく歩いて来る男にぶつかりそうになって、礼ちゃんはその男の顔を見あげながら叫ぶようにして言った。それは礼ちゃんのうちと同僚の斎藤中尉だったのだ。この中尉は、僕がまだ幼年学校にはいる前、彼がまだ見習士官だった頃から、僕もよく知っていた。が、中尉の方ではちょっと僕等が分らないらしかった。
「君は何だ。」
中尉は礼ちゃんの方へ食ってかかるように怒鳴った。
「いや、僕ですよ。」
僕は礼ちゃんをかばうようにして一足前へ出て言った。中尉はじっと僕の顔を見つめていたが、
「やあ、君でしたか。これはどうも失礼。僕はまた……いや、これからお宅へ行くところなんです。どうも失礼。」
と、多少言葉は和らげながらも、まだぷりぷりしたような様子で行ってしまった。
「まあ、ほんとにいやな斎藤さん。お酒の臭いなぞぷんぷんさして。」
礼ちゃんはもう大ぶ行ってしまった後ろをふり返りながら呟いた。
「でもきっと、僕等があんまりふざけて来たもんだから、この辺の何かと間違えたかも知れないね。」
僕は少々気がさして言った。僕等が歩いていた西ヶ輪[#底本では「西ケ輪」]の通りというのは、その裏のお小人町と一緒に、主として軍人をお得意とする魔窟だったのだ。
「そうね。けれど、それじゃあんまり失礼だわ。」
礼ちゃんはまだ多少憤慨しながらも、しかし自分を省みない訳には行かなかった。
二人はしばらく黙って、しかし相変らずほとんど接触せんばかりに引っついて歩いて行った。
「ねえ、栄さん、私お嫁に行ってずいぶんつらいのよ。」
礼ちゃんはしんみりした調子で口を切った。
「どうして?」
「おしゅうとさんがそれやひどいのよ。お母さんの方はまだそうでもないんですが、お父さんがそれやむずかしい方でね。本当に箸のあげ下ろしにもお小言なんだけれど、そんなことはまだ何でもないわ。私がちょっとうちを留守にすると、その間に私のお針箱から何やかまで引掻き廻して何か探すんですもの。私もうそれが何よりもつらいわ。」
「へえ、そんなことをするんかね。」
僕は驚いて彼女の顔を見た。彼女は黙ってうつむいていた。が、僕にはそれ以上何といって話していいのか分らなかった。僕も仕方なしに黙ってしまった。
道は川のそばだのあまり家のこんでいないところだのでずいぶん寂しかった。それでも二人はまたしばらく黙って、引っつき合って歩いて行った。
礼ちゃんはまた口を切って、東京での僕の学校の様子を聞いた。僕は去年の暮に、この礼ちゃんのためにだけでも偉い人間になって見せるとひそかに決心したことを思い出した。が、そんなことを話そうとも思わず、またよし思ったとしても話しすることはできずに、ただ礼ちゃんの聞くままに受け答えしていた。そしてとうとう礼ちゃんのうちのすぐ近くまで行った。
僕はもう帰ると言いだした。礼ちゃんはぜひちょっと寄って行けと引きとめた。
「僕はいやだ。さっきの斎藤さんのように、また隅田さんに変に思われるかも知れないからね。」
僕はそんなことを言うつもりでもなく、ふいと戯談のように言ってしまった。
「あら、いやな栄さん。それじゃいいわ。」
礼ちゃんは手をあげて打つまねをしながら、ちょっと僕をにらんだかと思うと、そのままばたばたと駈けだしてうちへはいってしまった。
僕はぼんやりしたようになってうちへ帰った。
翌日、礼ちゃんはまたうちへ来た。そしてその後も、毎日、日に一度はきっとやって来た。
母の死骸がうちにあった間は、二人とも顔を見合わしても先夜のことなどまるで忘れたようにしていたが、そしてまた実際いろんなほかの人達と一緒に母の死についての歎きに胸を一ぱいにしていたが、葬式が済んだ翌日からは、二人とも顔さえ合せれば、もう母の死のことなどは忘れたようになって、そしてまだほんの子供のような気になって、先夜二人で門を出た時と同じように、一緒に笑い興じたり騒いだりばかりしていた。
例の綺麗な細君もほとんど毎日のように見舞いに来た。そして二人のそんなふうなのをそばで黙ってにこにこしながら眺めていて、時々、本当にお二人は仲善さそうね、なぞとからかっていた。
お祖母さんは苦々しそうにして、いつも顔をしかめていた。
この綺麗な細君は、その後、日露戦争の留守中に何か不都合なことがあったとかで離縁になったというように聞いたが、そしてそれから間もなく一度銀座でたしかにその人らしい顔をちょっと見たのだが、どこにどうしていることか。
しかし、学校の入学試験をすぐ目の前に控えていた僕は、いつまでもそうしていることができなかった。母の葬式が済んでから一週間目くらいで、僕はまた上京した。そしてまた、母のことも礼ちゃんのことも綺麗な細君のことも、何もかも忘れたようになって、勉強しだした。
三
十月の初めになって、僕は東京中学校(今はもうないようだ)と順天中学校との五年の試験を受けた。
今はどうか知らないが、その頃の東京の私立のへぼ中学校では、ほとんど毎学年毎学期に各級の入学試験をやった。そしてその毎学期の初めに二、三度生徒募集をして、そのたびに試験を受けさしては受験料を儲けるのを例としていた。東京中学校のも順天中学校のもその最後の第三回目の生徒募集の時だった。
僕はそのどっちかにどうしてもはいらなければならないと思った。が、その試験は二つともほとんど同時に行われるのだった。僕はもう自分の学力には自信があった。しかし、万一の時にはと思って、少し早くからはじまる東京中学校のは自分で受けて、順天中学校のは換玉を使うことにきめた。それには、ちょうどいい、下宿の息子の友人で僕もそれを通じて知っていた早稲田中学卒業の何とかいう男があった。
ところが、僕自身が受けた東京中学校の方は、僕の大嫌いな用器画が三題ともちっとも分らないで、その日でもう落第となった。換玉の方はうまく行って、しまいまで通過して行って、及第となった。そして僕はそのお蔭で順天中学校の五年級にはいった。
しかし僕は、こうして話を年代通りに進めて行く前に、さっきの礼ちゃんのことが少し気にかかるので、というのは、あんな甘いしかも実も何にもない初恋の話の続きを今後まだあちこちに挾んで行くのは少し気が引けるので、少々年代を飛ばして、今ここで、話しついでにその後のいきさつをも一と思いにみんな話してしまおうと思うのだ。そしてこんどは、礼ちゃんの夫の隅田が死んだ時の二人の関係の場面になるのだから、前の話のいい対照になると思う。で、なおさらそれをまず書きたいのだ。
礼ちゃんとはその後三度会う機会を持った。最初の一度は、ほとんど一度とも言えないくらいなので、その後四年ばかりして、僕が外国語学校を出て社会主義運動にまったく身を投じようとした頃のことだった。堺君や田川大吉郎君や故山路愛山君などが一緒になって、すなわち当時の社会民主主義者や国家社会主義者なぞが一緒になって、電車の値上反対運動をやった。そして日比谷で市民大会というのを開いて、そこで集まった群集の力で電車会社や市会なぞへ押しかけた。その前日だ。僕は堺君の家からあしたの市民大会のビラを抱えて、麹町三丁目あたりからそれを撒き歩きはじめた。その時僕はふと礼ちゃんらしい姿を道の向う側に認めた。ただそれだけのことなのだ。
が、あとで聞くと、それは本当に礼ちゃんだったので、その市民大会のすぐあとで兇徒聚集という恐ろしい罪名で未決監に入れられた時に、礼ちゃんが僕の留守宅に見舞いに来てくれたそうだ。その頃僕は僕よりも二十歳ばかり上のある女と一緒に下六番町に住んでいたのだ。
その次の二度目は、それからまた二、三年してからのことと思うが、彼女とその夫とを東京衛戍病院に訪ねた。どうして彼女等がそこにいることを知ったのか、また隅田がどんな病気でそこにいたのかも忘れてしまったが、僕がその病室にはいるといきなり礼ちゃんはそとへ飛び出して行ってしばらく姿を見せなかった。そして隅田はマッサージをやらしていた。
「はあ、奴、知らないお客だと思って逃げ出したんだ。」
隅田は笑いながらそう言って、そのマッサージ師に彼女を呼びにやった。
彼女は「まあ」と言って、びっくりしたような顔をしてはいって来た。
その時隅田は、前に東京へ出て英語を勉強したいために憲兵になって、憲兵何とかいう学校にはいっていたが、その後どこかへ転任して、今病気で東京に帰っているんだというような話をしていた。そして僕が社会主義者になってもう二、三度入獄していることについても、困ったものだがしかし君の性格上仕方があるまいというようなことを言って、礼ちゃんはそれに「ええ、あんまりできすぎるからだわ」と弁解して附け加えていた。
が、その時には僕は三十分ばかりで帰って、その後また彼女夫婦がどうなったかはしばらくちっとも知らなかった。
すると、それからまた四、五年して、僕が例の神近や伊藤との複雑な恋愛関係にはいり始めた頃のこと、最後の三度目に、また突然と礼ちゃんが現れて来た。
ある日僕は、僕がフランス語の講習会をやっていた牛込の芸術倶楽部へ行った。そして僕が借りていた一室のドアを開けると、そこの長椅子に礼ちゃんが一人しょんぼりと腰をかけているので、実にびっくりした。
「隅田は大変肺を悪くしましてね、熊本の憲兵隊長をしていたのをよして、今はこちらに来ているんです。そして寝たっきりでいるんですが、あなたが前に肺が大変悪かったのに今はお丈夫だということを聞きましてね、ぜひあなたにお会いして、あなたの肺のお話を聞きたいって言うんですの。お医者もいろんなことを言ってちっとも分りませんし、隅田ももう長い間の病気ですっかり弱りこんでいるんです。」
礼ちゃんが、いろいろと詳しく話しているうちに、もうフランス語の時間が来て、生徒も二、三人やって来た。
「え、それじゃ明日お宅へ参ります。」
と言って、僕は礼ちゃんを入口まで送り出した。
翌日行って見ると、隅田の病気は話で聞いたよりもよほど悪いように見えた。今まで僕が見た、肺で死んだ幾人かの人の、もう末期に幾ばくもない時のような、いろんな徴候を持っていた。僕はこれやもう一月とは持つまいと思った。それでも、僕が悪かった時の容体やそれに対する手当などをいろいろと聞かれるので、僕も詳しくいろんな話をして、何大丈夫ですよなぞと慰めた。が、話しているうちにだんだん咳がひどくなるので、僕はあんまり長く話ししていてはいけまいと思って、みんながしきりにとめるのも聞かずに、礼ちゃんにだけそっと僕の思った通りのことを話して、いい加減に切りあげて帰った。
その後も折々見舞おうとは思ったのだが、僕は伊藤の行っている九十九里の御宿へ行ったり来たりしていて、そのひまがちっともなかった。そして、そうこうしているうちに、礼ちゃんから隅田死亡という知らせを受けとった。
さっそく行って見ると、隅田の死骸のそばでは、大勢の男女が集まって、大きな珠数のような綱のようなものをみんなでぐるぐる廻しては、ナムアミダー、ナムアミダーと夢中になって怒鳴っていた。下のほかの室にも僕の知らない大勢の人がいた。礼ちゃんはすぐ僕を二階へ案内して行った。
僕は今でもまだそうだが、死んだ人の家へ行ってどうお悔みを言っていいか知らなかった。で、黙ってただお辞儀をした。
「やっぱりあなたのおっしゃった通りでしたわ。」
礼ちゃんはすっかりやつれて泣顔をしながらも、それでもいつもの生々としたはっきりした声で話しだした。
「私こんなことを言っちゃいけないんでしょうけれど、隅田のなくなることはもうとうから覚悟していましたし、今じゃ隅田のなくなった悲しみよりも私のこれからのからだの方がよっぽど心配なんですの。」
僕は来る早々意外なことを聞くものだと思った。
「経済上の心配じゃないんです。それはどうとかしてやって行けます。けれど、隅田がなくなって方々から親戚のものが集まって来てから、私今までまるでいじめられ通しでいるんです。そしてこれからもたぶん一生いじめられ通しで行くんだと思うんです。」
僕はますます意外なことを聞くものだと思った。そしてやはり黙ったまま聞いていた。
「隅田の国の方の人が来るとすぐ、私をつかまえて、おやお前はまだ髪を切らずにいるんかい、と言うんでしょう。私、今時まだこんなことを言う人があるのかと思って、何とも返事ができなかったくらいですわ。するとこんどは、壁にかけてあるヴァイオリンを見つけて、ああこれは何とかさんにすぐあげておしまい、後家さんにはもう鳴物などいっさい要らないんだから、と言うんですもの。私、髪なんか切ることは何とも思いませんわ。また、ヴァイオリンなどもちっとも欲しかありませんわ。けれども今そんなにして、みんなの言うように本当の尼さんのようになったところで、それがいつまで辛棒できるかと思うと、自分でも恐ろしくなりますの。私今まで軍人の奥さんで、ことに日露戦争の間に、旦那が戦死してすぐ髪を切った方をたくさん知っていますわ。そしてそれが二、三年か四、五年かしてどうなったかもよく知っていますわ。そのまま立派な未亡人で通した方はまるでないんですもの。そして本当の尼さんのような生活にはいった人ほど、それがひどいんですもの。」
僕はただの平凡な軍人の細君と思っていた彼女が、これほどはっきりと、いわゆる未亡人生活を見透しているのに驚いた。
「それであなたはどうしてもその辛棒ができないというんですか。」
僕は彼女がそれについてどこまで決心しているのかを問いただそうと思った。
「いいえ、どこまでも辛棒して見るつもりです。今私は隅田の郷里に帰って、世間とのいっさいの交渉を断って、ただ一人の子供を育てあげることと、隅田の位牌を守って行くこととの、本当の尼さんのような生活をするように、毎日みなさんから責められています。しかしそれも辛棒して見るつもりです。どこまでそれで辛棒できるか知りませんが、とにかくできるだけどこまでも辛棒して行きます。」
「けれどもその辛棒ができなくなる恐れがあるんでしょう。その時にはどうするつもりなんです。」
「え、それが心配なんですの、恐ろしいんですの。けれど、やっぱり、どこまででも辛棒しますわ。」
「で、あなたの方のお父さんやお母さんはどう言っているんです。」
「私には可哀相だ可哀相だと言っていますが、やはりいったん隅田家へやった以上は、隅田家の言う通りにしなければならんと言っています。」
「あなたがそうまで決心しているんなら、それでもいいでしょう。しかし、できるだけやはり辛棒はしない方がいいです。辛棒はしても、もうとてもできないと思う以上のことは決して辛棒しちゃいけません。それが堕落の一番悪い原因なんです。」
「でも、それでも辛棒しなきゃならん時にはどうしましょう。」
「いや、辛棒しなきゃならん理窟はちっともないんです。そんな場合には、もういっさいをなげうって、飛び出すんです。すぐ東京へ逃げていらっしゃい。僕がいる以上は、どんなことがあっても、あなたを勝たして見せます。」
「ええ、ありがとうございます。私本当にあなたをたった一人の兄さんと思っていますわ。けれど私、どうしても辛棒します。どこまでも辛棒します。ただね、本当に栄さん、私あなたをたった一人の兄さんと思っていますから、どうぞそれだけ忘れないで下さいね。」
僕は彼女とほとんど手を握らんばかりにして、また近いうちに会う約束で別れた。
その翌日、隅田の葬式があったのだが、僕は着て行く着物も袴も何にもなし、また借りるところもないので、わざと遠慮して、そこから余り遠くない麻布の神近の家で一日遊んで暮した。
それから幾日目だったか、ある日、礼ちゃんが麹町の僕の下宿に訪ねて来た。
いよいよあすとかあさってとか、隅田の郷里に帰るので、牛込のある親戚へ用のあったのを幸いに、内緒で立ち寄ったとのことだった。話はやはり、いつかの彼女の家での話を、もう少し詳しくして繰返したに過ぎなかった。が、そうして彼女と話している間に、僕は幾度彼女の手を握ろうとする衝動に駆られたか知れなかった。
しかし、彼女もいつまでそうしていられる訳でもなく、また僕ももう芸術倶楽部へ行く時間が迫っていたので、下宿を出て、一緒に倶楽部のすぐ近くまで行った。そして無事に、お互いに「ご機嫌よう」と言って別れてしまった。
四
順天中学校というのは、もっともほかにもそんなのが幾つもあったのだろうが、ちょっと妙な学校だった。
僕のはいった五年は三組で二百人か二百五十人かいた。四年は二組で百五十人、三年は百人、二年一年は四、五十人というように、級がさがるに従って生徒の数が減っていた。わざわざこんな学校に一年や二年かではいるものはないんだ。そしてたいがいのはすぐと四年か五年かへはいるんだ。
僕等の組には、哲学院(東洋大学の前身)を出たものだの、早稲田を出たものだの、その他いろんな専門学校を出たものがいた。そんなのは何かの必要からただ中学校卒業の免状だけを貰いに来たのだ。また、顔を見ただけでも秀才らしいまだ年少の、あるいはぼんやりとした年かさの、独学の人もかなりいた。それからまた、僕達と同じように、どこかの学校で退学させられた不良連もずいぶんいた。そして僕と同じように、換玉ではいったのもこの不良連の中に多かった。
僕と一緒にこの順天中学校へはいった友人に登坂というのがいた。やはり僕とほとんど同時頃に、男色で、仙台の幼年学校から逐われて来たのだった。
この登坂とは、その年の一月、すなわち僕が東京へ出て来るとすぐ、市ヶ谷[#底本では「市ケ谷」]の幼年学校の面会室で出遭った。そして彼から、新発田での旧友で同時に幼年学校へはいった谷という男ともう一人とが、やはり彼と一緒に退学させられたことを知った。四人はすぐ友達になった。ほかにもまだ、やはり同時頃に同じような理由で大阪の幼年学校を退学させられた、島田というのともう一人と、どこかで落ち合って、これもすぐ友達になった。みんな、名古屋、仙台、大阪と所は違うが、同じ幼年学校の同期生だったのだ。
みんなはその名誉恢復のためというので、互いに戒めて勉強を誓った。そしてその年の九月十月にはみんなどこかの中学校の五年にはいった。
その中でも登坂と僕とは、最初に出遭った関係からか、またお互いに文学好きで露伴と紅葉との優劣を論じ合ったりしていたせいか、一番近しくなった。ことに一緒に順天中学へはいるとすぐ、本郷の壱岐坂下に一室をかりてそこに一緒に住んだ。
二人とも、学校の方もよく勉強したが、小説もずいぶんよく読んだ。坂上にちょっとした、貸本屋があった。そこから借りて来るのだが、しばらくの間にその、貸本屋の本をほとんどみな読んでしまった。
後には島田もこの下宿に仲間入りした。島田は撃剣が御自慢で、真黒な顔をして巌丈なからだの男で、いつも僕等が小説なぞを読むのを苦々しそうにしていた。そこで、登坂と僕とが一策を案じて、そのいやがるのを無理押しつけに、『不如帰』を借りて来て読ました。先生、最初の間はむずかしそうな顔をしてページをめくっていたが、だんだん眉の間の皺をのばして来た、とうとうしまいにはそのさざえ[#「さざえ」に傍点]のような握拳でほろほろと落ちる涙をぬぐいはじめた。「それ見ろ」というので、その後二人は島田の喜びそうなものを選んでは読ましていたが、島田は浪六の『五人男』がすっかりお気に召して、「俺は黒田だ、大杉貴様は倉なんとかだ」というようなことを言って一人で喜んでいた。
浪六物や弦斎物はとうの昔に卒業して、紅葉、露伴のものまでももう物足りなくなっていた僕等は、島田のそんな話には相手にならなかった。しかし僕は、その「倉なんとかだ」と言われたのが、内心はよほどの不平だった。
「なるほど、僕は倉なんとかのように、一面にはごく謹厳着実に済ましている。しかし、それだけ他のもう一面には、黒田のような豪放がひそかに燃えているんだ。貴様なんかのえせ[#「えせ」に傍点]豪放が何のあてになるもんか。」
僕は自分で自分にそう叫んで、「今に見ろ」と腹の中で一人で力んでいた。
その頃、僕よりも一期上でやはり名古屋出身の田中というのが、中央幼年学校から逐い出されて、これも僕等の下宿にころがりこんだ。その他にも、登坂の仲間の何とかいうのと、島田の仲間の何とかいうのと、これも一時僕等の下宿に来たが、この二人は僕等の「謹厳着実」な生活に堪えきれないですぐほかへ出て行ってしまった。
また、僕等よりもやはり一期上で、そして僕等よりも一年ほど前に仙台を出た箱田というのが、その年に高等学校へはいって、ちょいちょい僕等の下宿に遊びに来た。僕等よりも一期二期あとの、その後に退校させられた[#底本では「退校せられた」]二、三のものも、学校やその他のいろんなことについて、僕等のところに相談に来た。
こうして、幼年学校の落武者どもが、ほとんどみな僕等の下宿を中心として集まった。そしてその次の年には、みんな無事に中学校を終えて、僕と島田とは外国語学校に、登坂と田中とは水産講習所に、谷は商船学校に、みなかなりの好成績ではいった。
谷は今郵船の船長をしている筈だ。田中はどこかの県の技師になっていると聞いた。島田は、もう大ぶ古い頃に、どこかの田舎の連隊の将校集会所でドイツ語を教えているという話だった。登坂は一時水産で大ぶ儲けて、山陰道のどこかで土地の芸者を二人ばかりかこっていたというほどの勢いだったそうだが、十年ばかり前に失敗してアメリカへ行った。そして今でもまだ失意の境遇にいるらしい。箱田は朝鮮で検事か判事かをやっている。
僕はまた、壱岐坂上の貸本屋のほかに、神保町あたりのある貸本屋のお得意にもなっていた。そこには、小説本のほかに、いろんな種類のむずかしい本があった。僕は矢来町の下宿にいた時から引続いて、そこから哲学だの宗教だの社会問題だのの本を借りて来ては読んでいた。矢野竜溪の『新社会』は矢来町時代に、丘博士の『進化論講話』は壱岐坂時代かあるいはその少し後かに、幾度も繰返しては愛読した。
『新社会』は少し早く読みすぎたせいか、その読後の感興というほどのものは今何にも残っていない。しかし『進化論講話』は実に愉快だった。読んでいる間に、自分のせいがだんだん高くなって、四方の眼界がぐんぐん広くなって行くような気がした。今まで知らなかった世界が、一ページごとに目の前に開けて行くのだ。僕はこの愉快を一人で楽しむことはできなかった。そして友人にはみな、強いるようにして、その一読をすすめた。自然科学に対する僕の興味は、この本で初めて目覚めさせられた。そして同時にまた、すべてのものは変化するというこの進化論は、まだ僕の心の中に大きな権威として残っていたいろんな社会制度の改変を叫ぶ、社会主義の主張の中へ非常にはいりやすくさせた。
「何でも変らないものはないのだ。旧いものは倒れて新しいものが起るのだ。今威張っているものが何だ。すぐにそれは墓場の中へ葬られてしまうものじゃないか。」
しかし、僕にはまだ、何かの物足りなさがあった。母が死んだ、というようなこともほとんど忘れたようにはしていたが、次意識の中ではよほどさびしかったに違いない。また、礼ちゃんのことはやはり同じように忘れたようにはしていたが、幾年も続けて来た同性のいわゆる恋をまったく棄てた僕は、その方面でもよほどさびしかったに違いない。友人といえば、さっき言った幼年学校の落武者連だけだったが、それもただ同じ境遇から互いに励み合ったというほどのことで、本当に打解け合った親しい間柄ではなかった。
たぶんそんな餓えを充たすのだったろう。僕はよく飯倉の親戚の家へ出かけた。従兄の山田良之助(今陸軍の少将で憲兵司令官をやっている)の細君の家だ。山田は当時陸軍大学校の学生で、この飯倉の邸内の小さな家に住んでいた。僕はそれらの人のしんみ[#「しんみ」に傍点]な親しみの中にもひたりたかった。その邸のかなり贅沢な適位な生活の中にもひたりたかった。そしてまた、そこのいろんな綺麗な女の人達の笑い顔も見たかった。しかし、その人達はみな、男も女も綺麗ではあったが、その顔も心も冷たかった。ことに、僕が幼年学校を逐いだされてからは、なおさらそうのような気がした。僕よりも二つ三つ年下の何とかさんという娘なぞは、僕の幼年学校時代にはずいぶんよく一緒に遊びもしふざけもして、僕は心中ひそかに「僕が任官したら」という望みをすら持っていたんだったが、もう大ぶ娘らしくなってツンと済ましていた。
そんな寂しさがきっと主になって、そしてそのほかにもまだ、新しい進歩思想を求める要求なぞが手伝って、順天中学校を終る少し前から僕はあちこちの教会へ行き始めた。そして下宿から一番近い、またそのお説教の一番気にいった、海老名弾正の本郷会堂で踏みとどまった。
海老名弾正の国家主義には気がついたのかつかなかったのか、それともまだ僕の心の中にたぶん残っていたいわゆる軍人精神とそれとが合ったのか、それは分らない。とにかく僕は先生の雄弁にすっかり魅せられてしまった。まだ半白だった髪の毛を後ろへかきあげて、長い髯をしごいては、その手を高くさしあげて「神は……」と一段声をはりあげるそのいい声に魅せられてしまった。僕は他の信者等と一緒に、先生が声をしぼって泣くと、やはり一緒になって泣いた。
先生はよく「洗礼を受けろ」と勧めた。「いや、まだキリスト教のことがよく分らんでもいい。洗礼を受けさえすれば、ただちに分るようになる」と勧めた。僕はかなり長い間それを躊躇していたが、ついに洗礼を受けた。その注がれる水のよく浸みこむようにと思って、わざわざ頭を一厘がりにして行って、コップの水を受けた。
このキリスト教は、僕を「謹厳着実」な一面に進めるのに、大ぶ力があったようだ。しかしそれも長くは続かなかった。
五
僕は外国語学校の入学試験に及第するとすぐ、父のいた福島へ行った。父はその少し前に、部下の副官の何かの不しだらの責を負って、旅団副官から福島連隊区の副官に左遷されたのだった。
その後父の兄から聞いた話ではあるが、その頃父は師団長と喧嘩していたのだそうだ。旅団長の比志島義輝が師団長の誰とかと仲が悪くて、というよりもむしろその師団長に憎まれていて、副官たる父はいつも旅団長を擁護する地位に立たなければならなかった。比志島は以前にも借金のために休職になったのだが、日清戦争で復活して、また以前のように盛んに借金していた。そして父は、表向きの副官であるよりも、より以上に比志島家の財産整理のために忙がしかった。旅団長はまた幾度も休職になりかかった。父はそのたびに仙台へ行って、旅団長のために弁解して、師団長と激論した。そんなことから、旅団長の出す進級名簿の中からは、いつも師団長の手で父の名が削られた。そしてついに比志島は休職となって、そのあとへ師団長のそばにいた何とかいう参謀長がやって来た。その結果が父の左遷となったのだそうだ。
さらにその後、これは父が誰かに話しているのを聞いたのだが、比志島は日露戦争でまた復活して、戦地から一万円二万円というような金を幾度もその債権者のもとに送って、帰る頃には借金を全部済ました上にかなりの財産までもつくっていたそうだ。
父は連隊区司令部のすぐそばの、僕等がまだ住んだこともないほどの、小さな汚ない家にいた。そして女中も置かずに、僕のすぐ妹に学校をよさして、大勢の弟妹等の世話やその他のいっさいをやらしていた。
が、僕の驚いたのは、それよりも父のはなはだしい変り方であった。年はまだ四十三、四だったのだろうが、急にふけて、もうたしかに五十を幾つもこえた老人のようになっていた。そして以前には、うちのことはいっさいを母に任して金のことなぞはつい一ことも言ったのを聞いたことがなかったのに、妙にけちんぼな拝金宗になっていた。
もっとも、以前からごく質素で、自分で自分の小使銭を持っていたこともなく、また恐らく金の使い道も知らなかったほどなので、その本来のけちんぼうが少しもそとに現れなかったのかも知れない。が、母が死んで、自分でうちの細かい会計までやって見るとなると、これが急に目立って来たのかも知れない。
とにかく父は、月給や、勲章の年金だけではとてもやって行けない、と言っていた。そして、どうして母が今よりもずっとはでな生活をしていて、それで毎月幾らかずつ残して行ったのかと不思議がっていた。父はそんな心配や、母のない大勢の子供等のための心配なぞで、急に年がふけたのだ。急に金のありがた味を感じだしたのだ。
それに、父の兄の話を本当だとすると、父はもう軍人生活に見切りをつけて、実業界へでも鞍がえするつもりでいるらしかった。毎朝新聞を見るのにでも、きっと相場欄に目を通していた。そして僕にもそれを読むように勧めて、その読みかたなどをいろいろと講釈までしてくれた。僕はいつの間に父がそんなことを知ったのだろうと怪しんだ。が、この実業熱も新聞の相場欄に対する熱心も、実はその先生があったのだった。ある日連隊区司令官の何とかいう中佐か大佐のうちへ遊びに行ったが、僕はその司令官から父の講釈そのままの講釈をまた聞かされた。
僕は父が急にふけて見すぼらしくなったのは傷ましかったが、しかしその心の変化には少しも同情ができなかった。むしろ父を賤しみさえした。そして父の先生がその司令官であったのを見て、軍人がみなそんなさもしい心になったのじゃないかと憤慨しかつさげすんだ。
したがって、しばらく目の僕の帰省も大して愉快ではなかった。そして一カ月ばかりしてまた東京に帰った。
外国語学校にはいって見てすぐがっかりした。幼年学校で二年半やって、さらにその後もつい数カ月前までフランス語学校の夜学で勉強しつづけて、もう自分で分らんなりにも何かの本を読んでいたフランス語も、またアベセの最初から始めるのだ。
もっとも一カ月ばかりしてから、仏人教師のジャクレエの心配で、卒業の時には本科卒業として出すという約束で全科目選集の選科生として、二年へ進級したが、その二年ももとより大したことではなかった。そしてこの二年へ行って気がついたのだが、先生のまるきり無茶なのに驚かされた。フランスに十年とか十五年とかいたという先生が、二年生のできのいいものよりももっとできないんだ。そして本いっぱいに鉛筆で何か書きつけて来て、それを拾いよみしながら講義して、それ以外のことにはほとんど何一つ生徒の質問に答えることができないんだ。そしてできる二人ばかりの先生は、怠けものでずいぶんよく休みもし、また出て来てもほんのお義理にいい加減に教えていた。そしてその大勢の先生の教えるものの間に、ほとんど何の連絡もないんだ。
ただ一人、ジャクレエ先生だけが、実に熱心に、一人で何もかも毎日二時間ずつ教えた。僕はこの先生の時間だけ出ればそれで十分であった。そしてそれ以外の先生の時間はできるだけ休むことにきめた。
ちょうどその頃だ。日露の間の戦雲がだんだんに急を告げて来た。愛国の狂熱が全国に漲った。そしてただ一人冷静な非戦的態度をとっていた万朝報までが急にその態度を変え出した。幸徳と堺と内村鑑三との三人が、悲痛な「退社の辞」をかかげて万朝報を去った。
そして幸徳と堺とは別に週刊『平民新聞』を創刊して、社会主義と非戦論とを標榜して起った。
これまで僕は、それらの人とは、ただ新聞上の議論と、時に本郷の中央会堂で開かれた演説会での雄弁とに接しただけで、直接にはまだ会ったことがなかった。しかしこの旗上げには、どうしても一兵卒として参加したいと思った。幸徳の『社会主義神髄』はもう十分に僕の頭を熱しさせていたのだ。
雪のふるある寒い晩、僕は初めて数寄屋橋の平民社を訪れた。毎週社で開かれていた社会主義研究会の例会日だった。
玄関をはいったすぐ左の六畳か八畳の室には、まだ三、四人の、しかも内輪の人らしい人しかいなかった。そしてその中の年とった一人と若い一人とがしきりに何か議論していた。僕は黙って、そこから少し離れて、壁を背にして坐った。議論は宗教問題らしかった。年とった方はあぐらをかいて、片肱を膝に立てて顎をなでながら、しきりに相手の青年をひやかしながら無神論らしい口吻をもらしていた。青年の方はきちんと坐って、両手を膝に置いて肩を怒らしながら、真赤になって途方もないようなオーソドクスの議論に、文字通りに泡を飛ばしていた。そしてその間に、ちょいちょいと、もう一人の年とったのが、それが堺であることは初めから知っていた、先きの男ほど突っこんでではないがやはりその青年を相手に口を入れていた。
僕はその青年の口をついて出る雄弁には驚いたが、しかしまたその議論のあまりなオーソドクスさにも驚いた。僕も彼とは同じクリスチャンだった。が、僕は全然奇蹟を信じないのに反して、彼はほとんどそれをバイブルの文句通りに信じていた。僕は自分の中にあるものと信じていたのに反して、彼は万物の上にあってそれを支配するものと信じていた。僕はこんな男がどうして社会主義に来たんだろうとさえ思った。そして無神論者らしい年とった男の冷笑の方にむしろ同感した。
この年とった男というのは久津見蕨村で、青年というのは山口孤剣だった。
やがて二十名ばかりの人が集まった。そしてたぶん堺だったろうと思うが、「きょうは雪も降るし、大ぶ新顔が多いようだから、講演はよして、一つしんみりとみんなの身上話やどうして社会主義にはいったかというようなことをお互いに話ししよう」と言い出した。みんなが順々に立って何か話した。ある男は、「私は資本家の子で、日清戦争の時大倉が罐詰の中へ石を入れたということが評判になっているがあれは実は私のところの罐詰なんです、もっともそれは私のところでやったんではなくて、大倉の方である策略からやったらしいんではあるが」と言った。
「それじゃ、やはり大倉の罐詰じゃないか。どうもそれや、君のところでやったというよりは大倉がやったという方が面白いから、やはり大倉の方にして置こうじゃないか。」
こう言ったのもやはり堺だったろうと思うが、みんなも「そうだ、そうだ大倉の方がいい」と賛成して大笑いになった。その資本家の子というのは、今の金鵄ミルクの主人辺見なんとかいうのだった。
もうほとんど最後近い頃に僕の番が来て、僕も、「軍人の家に生れ、軍人の間に育ち、軍人の学校に教えられて、軍人生活の虚偽と愚劣とをもっとも深く感じているところから、この社会主義のために一生を捧げたい」というようなことを言った。
そして最後に堺が立って、「ここには資本家の子があり、軍人の子があり、何とかがあり、何とかがあり、実にわれわれの思想は今や天下のあらゆる方面にまで拡がっている。われわれの運動は天下の大運動になろうとしている。われわれの理想する社会の来るのも決して遠いことではない」という激励の演説があった。
僕はそう言われて見ると、本当にそんなような気がして、非常にいい気持になって下宿へ帰った。その日幸徳がそこにいたかどうかはよく覚えていない。
それ以来僕は毎週の研究会には必ず欠かさずに出た。そしてそれ以外の日にもよく遊びに行ったが、ことに下宿を登坂や田中のいた月島に移してからは、ほとんど毎日学校の往復に寄って、雑誌の帯封を書く手伝いなどして一日遊んでいた。
六
平民社は幸徳と堺と西川光二郎と石川三四郎との四人で、石川を除く外はみな大の宗教嫌いだった。でもそとから社を後援していた安部磯雄や木下尚江は石川とともに熱心なクリスチャンだった。そしてそこに集まって来た青年の大半がやはりクリスチャンだった。当時の思想界では、キリスト教が一番進歩思想だったのだ。少なくとも忠君愛国の支配的思想に背くもっとも多くの分子を含んでいたのだ。
幸徳や堺等はかなり辛辣に宗教家を攻撃もしまた冷笑もした。そして研究会ではよく宗教の問題が持ちあがった。しかし幸徳や堺等は、宗教は個人の私事だというドイツ社会民主党の何かの決議を守って、同志の宗教にはあえて干渉しなかった。
石川は本郷会堂での僕の先輩だった。が、その頃にはもう教会というものにあいそをつかして、ほとんど教会に行くこともなかったらしい。
僕も平民社へ出入りするようになってからは、みんなの感化で、まず宗教家というものに、次には宗教そのものに、だんだん疑いを付け始めた。そして日露の開戦が僕と宗教とを綺麗に縁を切ってくれた。
僕は、海老名弾正が僕等に教えたように、宗教が国境を超越するコスモポリタニズムであり、地上のいっさいの権威を無視するリベルタリアニズムだと信じていた。そして当時思想界で流行しだしたトルストイの宗教論は、ますます僕等にこの信念を抱かせた。そしてまた僕は、海老名弾正の『基督伝』や何とかいう仏教の博士の『釈迦牟尼』の、キリスト教および仏教の起源のところを読んで、やはりトルストイの言うように、原始宗教すなわち本当の宗教は貧富の懸隔から来る社会的不安から脱け出ようとする一統の共産主義運動だと思っていた。
しかるに、戦争に対する宗教家の態度、ことに僕が信じていた海老名弾正の態度は、ことごとく僕のこの信仰を裏切った。海老名弾正の国家主義的、大和魂的キリスト教が、僕の目にはっきりと映って来た。戦勝祈祷会をやる。軍歌のような讃美歌を歌わせる[#底本では「歌わせる」が「歌われる」]。忠君愛国のお説教をする。「我れは平和をもたらさんがために来たれるに非ず」というようなキリストの言葉を飛んでもないところへ引合いに出す。
僕はあきれ返ってしまった。そうして海老名弾正だの、当時よくトルストイものを翻訳していた加藤直士だのと数回議論をしたあとで、すっかり教会を見限ってしまった。そして同時にまたうっかりはいりかけた「右の頬を打たれたら左の頬を出せ」という宗教の本質の無抵抗主義にも疑いを持って、階級闘争の純然たる社会主義にはいることができた。
戦争が始まるとすぐ、父は後備混成第何旅団の大隊長となって、旅順へ行った。
僕は父の軍隊を上野停車場で迎えた。そして一晩駅前の父の宿に泊った。
僕は父が馬上でその一軍を指揮する、こんなに壮烈な姿は初めて見た。ちょっと[#「ちょっと」は底本では「ちょうど」と誤記]涙ぐましいような気持にもなった。しかし何だか僕には、父のその姿が馬鹿らしくもあった。「何のために、戦争に勇んで行くのか」と思うと、父のために悲しむというよりもむしろ馬鹿馬鹿しかったのだ。
宿にはいってからも、父やその部下の老将校等はみな会う人ごとに「これが最後のお勤めだ」と言って、ただもう喜び勇んでいた。僕はまたそれがますます馬鹿馬鹿しかった。
父は僕にただ「勉強しろ」と言っただけで、別に話ししたい様子もなく、ただそばに置いて顔を見ていればいいというような風だった。
お化を見た話
自叙伝の一節
一
僕が九つか十の時、ある日猫を殺して、夜中にふいと起ちあがって、ニャアと猫の泣くような声を出して母を驚かしたことは、前に話した。また、十一か十二の時、隣りの家に毎晩お化が出て、それが一と晩僕の家にも出たそうだということも、前に話した。
が、こんどは僕自身が、しかも最近になって、お化を見た話だ。現にまだ生きてはいるが、しかし確かに怨霊であるだろう女の姿を、真夜中に、半年も続けて見た話だ。
種子を割ってしまえば何でもないことであるだろうが、それはほかでもない、神近の怨霊だ。葉山の日蔭の茶屋の一番奥の二階で、夜の三時頃、眠っている僕の咽喉を刺して、今にもその室を出て行こうとする彼女が、僕に呼びとめられて、ちょっと立ちどまって振り返って見た、その瞬間の彼女の姿だ。その姿が、その後ほぼ半年もの間、伊藤と一緒に寝ている僕の足もとの壁に、ちょうどその時刻にはっきりと現れて来るのだ。毎晩ではない、が時々、夜ふと目がさめる。すると、その目は同時にもう前の壁の方に釘づけにされていて、そこには彼女のその姿が立っているのだ。一と晩の間にこんなにもやつれたかと思われる、その死人のように蒼ざめた顔色の上に、ふだんでも際だって見える顔の筋が、ことさらにひどく際だって見えた。そして、びっくりしたように見ひらいたその目には、恐怖と、憐れみを乞う心とが、一ぱいに充ちていた。
「許して下さい。」
彼女は振り返って、僕が半分からだを起しているのを見て、泣き出しそうに叫びながら逃げ出した。
「待て。」
と、その前に僕は彼女を呼んだのだ。そして立ちあがって彼女を押えようとしたのだ。
が、そんな前後のことはいっさい断ち切られて、ただ彼女が振り返って見たその瞬間の彼女の姿だけが現れて来るのだ。
僕は、それが夢か現なのかよく分らないことが、よくあった。が、確かにそれが夢でないと思われたことも幾度もあった。そして、そのいずれの場合にも、僕が自分に気のついた時には、おびえたように慄えあがって、一緒に寝ている伊藤にしっかりとしがみついているのだった。が、それもまたほんの一時のことで、僕はまたさらに本当の自分に帰って、手を伸して枕もとの時計を見た。時計はいつもきまって三時だった。
「また出たの?」
「うん。」
と、伊藤はそれを知っていることもあった。が、ぶるぶる慄えたからだにしがみつかれながら、何にも知らずに眠っていることもあった。そして、よしそれを知っていても、僕のおびえが彼女にまでも移ることは決してなかった。彼女はいつも、
「ほんとにあなたは馬鹿ね。」
と、笑って、大きなからだの僕の頭を子供のように撫でていた。
実際僕は、このお化の時ばかりではない、何か恐い夢を見ると、きっと同じようにおびえるのだった。そしてその慄えが、どうかすると、目をさましてからもまだしばらくの間続くことがあった。
「ほんとにあなたは馬鹿ね。」
と、そんな時にもよく、僕は彼女に笑われた。僕はきっと心(しん)は非常に臆病者なのだ。それとも、僕の心の中には、無知な野蛮人の恐怖が、まだ多分に残っているのだ。
が、そんなにして、話を野蛮人のところまで引きもどす必要はない。僕は今ここで、僕が女の怨霊を見るに至った僕の心理の、科学的説明を試みようとしているのではないのだから。しかし、単にこの怨霊を見たという事実の話をするだけにしても、話は大ぶその以前に遡らなければならない。少なくとも、どうしてその女が僕を刺すに至ったかの、彼女と僕との関係の過去に遡らなければならない。
(僕は今、先きに数回本誌[#「本誌」は「改造」])に連載した自叙伝の続きとして、そのあとを数回飛ばしてこの一節を書きつつあるのであるが、その飛ばした数回ことにこの一節の前回については、何をどう書こうかという腹案がまだちっともできていないのだ。ただ、しばらく怠けていたあとの筆ならしに、すぐ書けそうに思われたこの題目を選んで書き出して見ただけのことなのだ。したがって、ここまで書いて来て、さてどこまで遡って話したらよかろうかとなると、まるで見当がつかない。仕方がない、やむを得ずんばそもそもの始めからでも書こうかということにまあきめたのだが、それにしても話の順序としては大ぶ困ることが多いようだ。が、とにかくまあ書いて行こう。)
二
そのよほど以前から、僕は日蔭のその室を僕の仕事部屋にしていた。文債がたまると、というよりもむしろそれをいい口実にして、よく一週間か二週間そこへ出かけて行っては遊んでいた。実は、今はもうその名も忘れてしまったが、よく僕の面倒を見てくれた女中も一人いたのだ。
その女中は、もう一年ほど前に、嫁に行っていなかった。が、お寺か田舎の旧家の座敷のような、広い十畳に、幅一間ほどの古風な大きな障子の立っている、山のすぐ下のその室一つだけでも、まだ僕を引きつけるには十分だった。
長い間いろいろと苦心していた雑誌の保証金が、ようやく手にはいった。その金がどうして手にはいり、またそれまでそれを得るためにどんなに苦しんだかについても、またあとで話しする機会があろうと思うが、とにかく当時の僕には、新しい小さな雑誌を一つ創めるということが、ほとんど唯一の当面の問題だった。二カ年間続いて来た『近代思想』を自ら廃刊して、新たに月刊『平民新聞』を起し、それがほとんど半カ年間発売禁止を重ねて、さらにまたもとの『近代思想』に帰り、そしてそれがまた発売禁止の連続を喰って倒れてから、僕等はもう半年あまり僕等の運動の機関を持たなかった。当時では、この機関がないということは、同時にまたほとんど運動がないというのと同じことだったのだ。僕は僕の恋愛問題がこのことに少なからざる責任のあることを感じていた。
しかし、いよいよ雑誌を始めるのには、もう少し金がいる。それに、その前に、古い文債も一とまず始末して置かなければならない。となって、単行本の翻訳を一つと雑誌の原稿を二つ抱えて、一カ月ばかりの計画でいつもの通り葉山へ出かけることになった。
一時はずいぶんこの雑誌の創刊に熱中していた神近も、その頃では、もう大ぶその熱がさめていた。僕が彼女にばかりではなく、なお伊藤にもいろいろと雑誌の相談をしかけて、伊藤がその保証金の奔走をしたりするようになってからは、彼女はむしろ僕等の計画に対して多少の反感をすら持っているようだった。そして、自分は別に宮島(資夫)の細君の麗子君と一緒に、何かやろうなどとも言っていた。しかし、それも麗子君にはあまりよく賛成されず、またひそかに頼みにしていた青山菊栄君(今の山川夫人)からは態よく拒られて、彼女は半ばそれを断念するとともに、その口惜しさのあまりを僕等の計画の上に反感として向けもしたようだ。そしてその上に彼女は、僕等の計画の上に、また僕や伊藤の上に、どうしてそんな金ができるものかという侮蔑や冷笑も持っていた。
実際僕等はずいぶん困っていた。そして僕や伊藤が困りきっている時には、いつも神近が助けに来てくれていた。そんな場合の十円か二十円の金すらも工夫のできない僕や伊藤に、数百円というまとまった金のできる筈のないことを思うのも、彼女としては当然のことであった。そして、今から思えばこうも邪推されるのであるが、彼女はそれを知りぬいていて、郷里まで金策に行くという伊藤に二度までも旅費をかしたのであった。
僕は神近に、雑誌の保証金が、それがどうしてできたかということは言わずに、ただできたというだけのことを話した。そして当分葉山へ行くということを話した。
「葉山へは一人で?」
保証金の方のことは彼女には大して興味がないようだった。が、彼女には、この「一人で」かどうかがよほど気になるらしかった。
「勿論一人だ。みんなから逃げて、たった一人になって仕事をするんだ。」
彼女はこの「たった一人に」ということにしきりに賛成した。そして、ゆっくりと、うんと仕事をして来るようにとしきりに勧めた。
当時僕は、女房の保子を四谷の家に一人置いて、最初は番町のある下宿屋の二階に、そしてそこを下宿料の不払で逐い出されてからは、本郷菊坂の菊富士ホテルというやはり下宿屋に、伊藤と二人でいた。二人とも、二人一緒にいることは、決して本意ではなかったのだ。二人とも、同じように家を棄てて出て、一人っきりになることを渇望していた。だが僕は、女房とまだ縁が切れずにいる上に、神近や伊藤との関係があった。伊藤は、家とともにその亭主とも縁は切れているが、新たに僕との関係があった。そして、こうした厄介な関係の上からのみでも、二人は一緒にいるうるさい生活に堪えられなかったのだ。
伊藤は最初からそのつもりで、家を出るとすぐ、赤ん坊を抱えて下総の御宿へ行った。そこは、かつて彼女の友人の平塚らいちょうが行っていて、彼女には話しなじみのところだったのだ。彼女は当分そこで、ほんとうの一人きりになって、勉強する覚悟だった。
僕は伊藤のこの覚悟さえ続いたら、すなわちいろんな事情がそれを続けることを許しさえしたら、僕等の三角関係というか四角関係というか、とにかくあの複雑な関係がもっと永続して、そしてあんなみじめな醜い結果には終らなかったろうと、今でもまだ思っている。が、その覚悟を毀したのは何よりもまず経済問題だった。そして、どんなことがどこへどう祟って[#「祟って」は底本では「崇って」と誤記]行くか分らない一例証として、ちょいとその話をして見よう。
伊藤はその以前と同じように、やはり原稿生活をして行くつもりだった。そして第一にまず、その家出のことを書いて、それを当時彼女が続きものを書いていた大阪毎日に売る予定だった。彼女はそれを大毎の菊池幽芳氏に交渉した。幽芳氏は彼女のそのものにかなり大きな期待を持って、激励と同時に承諾の返事を寄越した。それで、伊藤は落ちついて、御宿のある宿屋に腰を据えることになった。
ところが、その原稿が、幽芳氏の非常な称讃の辞がついて、送り返されて来たのだ。その時、ちょうど僕は御宿へ遊びに行っていた。というよりも、彼女や僕が持って行ったわずかの金も費い果して、彼女は宿料の支払を迫られる僕は帰る旅費もなしというような始末になって、二人でもう三日も四日も大毎からの送金を待っていたのだった。二人は、それが駄目と分ると、あちこち、金をかしてくれそうなところへ手紙や電報を出した。が、それはまるで返事がなかったり、来てもいい返事は一つもなかった。
その間に僕は、神近もその生徒の一人だった、フランス語の講義の日を欠かした。そして宮島が、その子供の誕生日の祝いとして、その三人の先輩の宮田修氏と生田長江氏と僕とを招いた、その御馳走をも欠かした。この御馳走には神近も連なる筈だった。神近や宮島には、僕等二人が御宿でどんなに困っているかは分らなかった。神近はそれをいろんな意味で怨んだ。そして、ことに酒でも飲めば、非常に人と同感しやすい宮島は、僕がその招待を欠いたことによってその人一倍強い自尊心を傷つけられた上に、ますます神近に同情した。僕は神近への宮島の同情がこれによって始まったなぞとは決して言わない。しかし、神近と宮島とが、同じ一つのことについて、僕等二人に対する怨みというか憎しみというかを合致させたのは、ほぼこの辺からじゃなかろうかと思う。
そして、もう百方策尽きているところへ、神近から金を送ろうかと言って来た。
「あなたが困るのは私が困るも同じことだ。野枝さんが困って、そのためにあなたが困れば、私もまたやはりそのために困るのだ。だから、誰のため彼のためということはいっさい言わずに、お送りしましょう。」
神近がこう言って来る腹の中には、僕に早く帰って欲しいという一念があることは明らかなのであるが、しかし彼女には、こういった寛大な姉さんらしい気持が多分にあったことも同じように明らかだった。そして僕は今はこの寛大にたよるほかに道はなかった。
神近からは何でも二十円ばかり送って来た。そして僕は、宿屋の方の多少の払いをして、僕一人急いで東京に帰った。神近から少しでもまとまった金をかりたのはこれが初めてなのだ。
伊藤はとうとう困りぬいて、子供を近村のものに預けて、僕の下宿にころがりこんで来た。そして二人は、もう四、五カ月の間、ますます困窮しつつ、一緒に愚図愚図していた。が、いよいよこんどの僕の葉山行きを期として、二人の別居を実行することにきめたのだった。
神近は僕等のこの別居の計画を非常に喜んだ。しかし彼女にはまだ、その葉山では、僕と伊藤とが一緒にいるのではあるまいかと疑われたのだ。
「いつ立つ? 二、三日中! それじゃ、たった一つ、こういうことを約束してくれない? あなたが出かける時、私を誘うこと。そして一日、葉山で遊ぶこと。」
ようやく疑いの晴れた彼女の願いは何でもないことだった。が、その頃の僕の気持では、彼女が事ごとにひつこく追求したり要求したりすることが、大ぶうるさくなっていた。そして、こんな何でもない願いでも、そのあとに、「ね、あなた、いいでしょう、いいでしょう」という、その「いいでしょう、いいでしょう」がうるさくて堪らなかった。が、それを拒絶すれば事がますますうるさくなるのだし、仕方がないから、ただ「うん、うん」とばかりいい加減な返事をして置いた。
三
「私、平塚さんのところまで行きたいわ。」
いよいよ出かける日の前日になって、ふいと伊藤が言いだした。らいちょうは、その頃、奥村君と一緒に茅ヶ崎[#底本では「茅ケ崎」]にいた。
伊藤はその家を出る時すでにあらゆる友人から棄てられる覚悟でいた。しかし、長年の友情を自分から棄てることもできなかったものと見えて、その家を出た日に野上弥生子君を訪い、そしてらいちょうにはハガキを出した。が、その後この二人の友人が悪罵に等しい批評を彼女の行為の上に加えているのを見て、彼女もまったくその友情を棄てていたようだった。けれどもまた、長い間の親しい友人に背くということはさびしい。彼女はよく彼女等との古い友情をなつかしんでいた。
「よかろう。それじゃ茅ヶ崎[#底本では「茅ケ崎」]まで一緒に行って、葉山に一晩泊って帰るか。」
僕は彼女の心の中を推しはかって言った。しかし、らいちょうの家では、僕等はひる飯を御馳走になって二、三時間話していたが、お互いに腹の中で思っている問題にはちっとも触れずに終った。
「いいわ、もうまったく他人だわ。私もう、友達にだって理解して貰おうなどと思わないから。」
彼女はその家を出て松原にさしかかると、僕の手をしっかりと握りながら言った。彼女はその友人に求めていたものをついに見出すことができなかったのだ。
葉山に泊った翌朝は、もう秋も大ぶ進んでいるのに、ぽかぽかと暖かい、小春日和となったようないい日だった。
「きょう一日遊んで行かない?」
僕は朝飯が済むと彼女に言った。
「ええ、だけど、お仕事の邪魔になるでしょう。」
もう帰る仕度までしていた彼女はちょっと意外らしく言った。
「なあに、こんないい天気じゃ、とても仕事なぞできないね。それより、大崩れの方へでも遊びに行って見ようよ。」
「ほんとにそうなさいましな。せっかくいらっしたんですもの。そんなにすぐお帰りじゃつまりませんわ。」
年増の女中のおげんさんまでもそばからしきりと彼女に勧めた。
大崩れまで、自動車で行って、そこから秋谷辺まで、半里ほどの海岸通をぶらぶらと歩いた。その辺は遠く海中にまで岩が突き出て、その向うには鎌倉から片瀬までの海岸や江の島などを控えて、葉山から三崎へ行く街道の中でも一番景色のいいところだった。それに、もう遅すぎるセルでもちょっと汗ばむほどの、気持のいいぽかぽかする暖かさだった。僕等二人は実際、溶けるような気持になって、その間をぶらぶらと行った。正午にはいったん宿に帰って、こんどはおげんさんを誘って、すぐ前の大きな池のような静かな海の中で舟遊びをした。そしていい加減疲れて、帰って湯にはいって、夕飯を待っていた。
そこへおげんさんがあわててはいって来て、女のお客様だと知らせた。そして僕が立って行こうとすると、おげんさんの後にはもう、神近がさびしそうな微笑をたたえて立っていた。
伊藤はまだ両肌脱いだまま鏡台の前に坐って、髪を結いなおすかどうかしていた。神近の鋭い目がまずその方をさした。
「二、三日中っておっしゃったものだから、私毎日待っていたんだけれど、ちっともいらっしゃらないものだから、きょうホテルまで行って見たの。すると、お留守で、こちらだと言うんでしょう。で、私、その足ですぐこちらへ来たの。野枝さんが御一緒だとはちっとも思わなかったものですから……」
神近は愚痴のようにしかしまた言いわけのように言った。
「寄ろうと思ったんだけれど、ちょっと都合がわるかったものだから……」
と僕も苦しい弁解をするほかはなかった。
あしたは帰るんだからというので、伊藤と僕とは、いろいろ甘そうな好きな御馳走を註文してあった。僕はおげんさんにそれをもう一人前ふやすように言った。それから食事の出るまでの三十分間がほどは、ほとんど三人とも無言の行でいた。僕には何となくいよいよもうおしまいだなという予感がした。
その年の春、二度目の『近代思想』を止すと同時に、僕は一種の自暴自棄に陥っていた。先きに僕は知識階級の間に宣伝することのほとんど無駄なことを悟って、哲学や科学や文学の仮面の下に自由思想を論じた最初の『近代思想』は、要するに知識的手淫に過ぎないものと断じた。そして二年間もいつくしんで来てようやく世間から認められだしたそれを止して、僕等の本来に帰るんだと言って、別に労働者相手の『平民新聞』を創めた。それが前にも言ったように、半年間発売禁止を続けてついに倒れ、さらに半年間の準備によって再び起された『近代思想』も同じ運命の下に倒されてしまった。僕等はもうちょっと手の出しようがなかった。それでも、もし僕等同志の結束でも堅いのであったら、また何とか方法もあったのだったろう。が、ごく少数しかいない同志の間にもこれがうまく行かなかった。同志の間にはまだ運動に対する本当の熱がなかったのだ。
「僕等はまるで暖簾と腕押しをしているのだな。」
当時ほとんど一人のようになっていた荒畑寒村と僕とが、よく慨き合った言葉だった。
かくして、もう何もかも失ったような僕が、その時に恋を見出したのだ。恋と同時に、その熱情に燃えた同志を見出したのだ。そして僕はこの新しい熱情を得ようとして、ほとんどいっさいを棄ててこの恋の中に突入して行った。
その恋の対象がこの神近と伊藤とだったのだ。が、その恋ももう堕落した。僕等三人の間には、友人または同志としての関係よりも、異性または同性としての関係の方が勝って来た。そしてその関係がへたな習俗的なものになりかかっていた。
例のおげんさんによって夕飯が運ばれた。そしてこのおげんさんの寂しい顔が、みんなの気まずい引きたたない顔の中にまじった。好きなそして甘そうな料理ばかり註文したのだが、僕も伊藤もあまり進まなかった。神近もちょっと箸をつけただけで止した。
伊藤は箸を置くとすぐ、室の隅っこへ行って何かしていたがいきなり立ち上って来て、
「私帰りますわ。」
と、二人の前に挨拶をした。
「うん、そうか。」
と、僕はそれを止めることができなかった。神近もただ一言、
「そう。」
と言ったきりだった。
そして伊藤はたった一人で、おげんさんに送られて出て行った。
二人きりになると、神近はまた、前よりももっと、愚痴らしくそしてまた言いわけらしく、来た時に言った言葉を繰返した。僕も不機嫌にやはり前に言った言葉をただ繰返した。そして僕は引返して来たおげんさんにすぐ寝床を敷くようにと命じた。
朝秋谷で汗をかいたり風にふかれたりしたせいか、そしてその上に湯にはいったせいか、少し風邪気味で熱を感じたのだ。肺をわずらっていた僕には、感冒はほとんど年じゅうのつきものであり、そしてまた大禁物だった。が、ちょっとでも風邪をひくと、僕はすぐ寝床につくのを習慣としていた。
が、その時には、それよりむしろ、神近と相対して坐っていて、何か話ししなければならないのが、何よりも苦痛だった。彼女がこの室にはいって来て、伊藤の湯上り姿に鋭い一瞥を加えて以来、僕は彼女の顔を見るのもいやになっていたのだ。
彼女は疲れたからと言ってすぐ寝床にはいった。僕は少し眠ったようだった。
夜十時頃になって、もうとうに東京へ帰ったろうと思っていた伊藤から、電話がかかって来た。ホテルの室の鍵を忘れたから、逗子の停車場までそれを持って来てくれというのだ。僕は着物の上にどてらを着て、十幾町かある停車場まで行った。彼女は一人ぽつねんと待合室に立っていた。
「いったん汽車に乗ったんですけれど、鍵のことを思いだして、鎌倉から引返して来ましたの。だけどもう今日は上りはないわ。」
彼女はそう言って、一人でどこかの宿屋に泊って明日帰るからと言いだした。
僕は彼女を強いて、もう一度日蔭に帰らした。いっそ、三人でめいめいの気まずい思いを打明け合って、それでどうにでもなるようになれと思ったのだ。が、こうして彼女が帰ると、室の空気は前よりももっといけなかった。そして三人とも、またほとんど口をきかずに、床をならべて寝た。
神近も伊藤もほとんど眠らなかったようだ。が、僕は風邪をひいた上に夜ふけてそとでをしたので、熱が大ぶ高くなって、うつらうつらと眠った。そして時々目をさましては彼女等の方を見た。神近はすぐ僕のそばに、伊藤はその向うにいた。伊藤は顔まで蒲団をかぶって、向うを向いてじっとして寝ていた。僕がふと目をあけた時、僕は神近が恐ろしい顔をして、それを睨んでいるのをちらと見た。
「もしや……」
とある疑念が僕の心の中に湧いた。僕は眠らずにそっと彼女等を窺っていなければならないときめた。が、いつの間にか熱は僕を深い眠りの中に誘ってしまった。
四
目をさました時にはもうかなり日が高かった。神近も伊藤も無事でまだ寝ていた。僕はほっとした。
朝飯を済ますと、伊藤はすぐ出て行った。勿論東京へ帰ったのだ。が、神近はそれを疑っているようだった。もともと僕と一緒にずうといるつもりで来たので、今は自分が来たからちょっと近所のどこかで避けて、また自身が帰ればすぐここへ来るのだろう、というような口ぶりだった。彼女は割合に人が好くて、ごく人を信じやすいかわりには、疑い出すとずいぶん邪推深かった。僕はもう彼女の邪推と闘うには、あまりに彼女に疲れていた。そうでなくても、きのう彼女が「侵入」して来て以来の僕の気持は、とうてい静かに彼女と話しすることを許さなかった。しかしまた、彼女をすっぽぬかして伊藤と一緒にここへ来ているという弱点は、彼女に対してあまり強く出ることも許さなかった。で、彼女のそんな疑いに対しては、ただ一言「馬鹿な」と軽く受け流して、相手にせずにいた。
そして昼飯が済むとすぐ、僕は苦りきった顔をして、机に向って原稿紙をとり出した。彼女は仕方なしにおげんさんの案内で海岸へ遊びに行った。
その時はちょうど寺内内閣ができた時で、僕は『新小説』の編集者から、寺内内閣の標榜するいわゆる善政についての批評を書くことを頼まれていた。憲政会は三菱党だ。政友会は三井党だ。したがってこの二大政党には、今日の意味での善政、すなわち社会政策を行うことはとうていできない。彼等は資本家党なのだ。官僚派は資本家の援助がなければ何事もできないことはよく知っている。しかし彼にはこの資本家の上に立つ政治家だという、ともかくもの自尊がある。そしてなお、この資本家の横暴と対抗するには、労働者の援助をかりなければならない。そこでその政治は、善政は、すなわち社会政策をとるほかはない。僕はざっとそんなふうに考えていた。そして、なおそれを歴史の事実の上から論ずるつもりで、桂がその晩年熱心な社会政策論者であったことや、またドイツのビスマルクの例を詳しく書いて見ようと思っていた。
僕は誰だかの『ビスマルクと国家社会主義』をその参考に持って来ていた。で、まずざっとその本を読んで見ようと思った。
が、こうして落ちついて机の前に坐ると、急にまた風邪の熱で頭の重いことが思い出されて来た。熱でばかりではない、いろいろな雑念で重いのだ。
僕は神近とはもうどうしてもお終いだと思った。彼女とできて半年あまりの間に、このもうお終いだという言葉が、彼女の口から三、四度も出た。が、こんどは、それを初めて僕の方から言い出そうと思った。
最初は、彼女との関係後二カ月ばかりして、さらに伊藤との関係ができかかった時、彼女からずいぶん手厳しくそれを申渡された。
「きょうはきっとあなた、どこかでいいことがあったのね。顔じゅうがほんとうに喜びで光っているわ。野枝さんとでも会って?」
ある晩遅く彼女を訪ねた時、顔を見るとすぐ彼女は言った。僕はそれまではそんなに嬉しそうにしていたとも思わなかったが、そう言われて初めて、彼女の言葉通りに顔じゅうが喜びで光っているような気がした。そして実際また、彼女の言った通り、今伊藤と会って来たばかりだったのだ。しかも、いつも亭主が一緒なのが、その日は初めて二人きりで会って、初めて二人で手を握り合って歩いて、初めて甘いキスに酔うて来たのだった。僕は正直にその通りを彼女に話した。
「そう、それやよかったわね、私も一緒になってお喜びしてあげるわ。」
彼女はもうよほど以前から僕等二人がよく好き合っていることを知っていた。そして、ただ好き合っているばかりで、それ以上にちっとも進まないことをむしろ不思議がっていた。で、自分が僕等の姉さんででもあるかのようにして、ほんとうに喜んでくれたようだった。
彼女には、この姉さんというような気持が、ずいぶんにあった。そしてこの気持の上から、僕や伊藤のわがままをいつも許してくれ、また自分からも進んでいろいろなわがままをさせていた。彼女はもう三十だった。そして伊藤は彼女より七、八つ下だった。
僕が彼女と初めて手を握った時にも、彼女は伊藤に対する僕の愛を許していた。まだどうにもなっていない、今からもどうなるか見こみはちっともない、しかし僕は非常に伊藤を愛している、今こうして相抱き合っている彼女よりも以上に愛している、僕はこの事実を偽ることはできないと言った。彼女はそれを承認した。しかも、ちっともいやな顔は見せないで、笑いながら承認した。
「たとえば、僕にはいろんな男の友人がいる。そしてその甲の友人に対するのと乙の友人に対するのと、その人物の評価は違う。また尊敬や親愛の度も違う。しかし、それが僕の友人たるにおいては同一だ。そしてみんなは、各々自分に与えられた尊敬と親愛との度で満足していなければならない。俺は乙よりも尊敬されないから、あいつの友人になるのはいやだ、などという馬鹿な甲はいない。」
というのが僕の友人観兼恋愛観だった。僕は友人と恋人との間に大した区別を設けたくなかった。
が、理窟はまあどうでもいいとして、とにかく彼女は、僕の心の中での彼女と伊藤との優劣を認めたのだ。と同時にまた、その尊敬や親愛の対象となるものの、質の違っていることも認めたのだ。そして彼女は、この優越を蔽うために、年齢の上からの自分の優越を考え出したのだ。しかし反対にまた、彼女より年の多い保子に対しては、彼女は自分の知力の優越を考えていた。そしてやはりこの優越感の上から、保子に対してまでも姉さんぶった心の態度を持っていた。この姉さんぶるという態度には、彼女の性格の一種の仁侠もあるのであるが、しかし彼女がその競争者に対してどうしても持ちたい優越感がそれを非常に助けていたのだ。
実際彼女はこの優越ということをよく口にしていた。そして彼女があらゆる点において優越を感じていた保子に対しては、ただ憐憫があるばかりで、ほとんど何の嫉妬もなかった。それからもう一人、これは今ちょっとその人の名を言えないが、やはり女文士でかりにFというのがあった。そのFと僕とのごく淡い関係についても、彼女はやはり自分の優越感から何の嫉妬をも感じていなかった。むしろ一種の興味をもってすら見ていた。
その晩は僕は麻布の彼女の家に泊った。そして翌日、保子のいる逗子の家に帰った。するとたぶんその翌日の朝だ、僕は彼女から本当に三行半と言ってもいい短かい絶縁状を受取った。それは「もし本当に私を思っていてくれるのなら、今後もうお互いに顔を合せないようにしてくれ。では、永遠にさよなら」というような意味の、あまりに突然のものだった。僕はすぐ東京へ出た。そして彼女をその家に訪うた。が、彼女は僕の顔を見るや、泣いてただ、「帰れ帰れ」と叫ぶのみで、話のしようもなかった。そして僕は何かをほうりつけられて、その家を逐い出された。
僕はすぐ宮島の家へ行った。宮島の細君は彼女にとってのほとんど唯一の同性の友達だった。
「ゆうべはひどい目に会ったよ。神近君が酔っぱらって気違いのようにあばれ出してね。そして君のことを『だました! だました!』と言って罵るんだ。ようやくそれを落ちつけさして、家まで連れて行って、寝かしつけて来たがね。実際弱っちゃったよ。」
宮島は、僕が彼女の話をすると、本当に弱ったような顔をして話した。
そこへ、しばらくして、彼女がやって来た。顔色も態度も、さっきとはまるで別人のように、落ちついていた。
「私、あなたを殺すことに決心しましたから。」
彼女は僕の前に立って勝利者のような態度で言った。
「うん、それもよかろう。が、殺すんなら、今までのお馴染甲斐に、せめては一息で死ぬように殺してくれ。」
僕はその「殺す」という言葉を聞くと同時に、急に彼女に対する敵意の湧いて来るのを感じたのであったが、戯談半分にそれを受け流した。
「その時になって卑怯なまねはしないようにね。」
「ええ、ええ、一息にさえ殺していただければね。」
二人はそんな言葉を言いかわしながら、しかしもう、お互いの顔には隠しきれない微笑みがもれていた。
彼女はまたもとの姉さんに帰ったのだが、僕と伊藤とはこの姉さんにあまりに甘えすぎたようだ。あまりに無遠慮すぎたようだ。それをあまりに利用しすぎたとまでは思わないが。そしてそのたびに彼女はヒステリーを起しはじめた。
ヒステリーとまでは行かんでも、その後彼女は、その生来の執拗さがますますひつっこくなった。いろんな要求がますます激しくなった。そして、それが満足されなければされないほど、それだけまたますますひつっこくなり、ますますうるさくなるのであった。が、ここに白状して置かなければならないのは、僕はだんだんこの執拗さにいや気がさして行ったのであるが、しかしまた、その執拗さが僕にとっての一つの強い魅力ででもあったことだ。
彼女は折々その執拗さを遠慮した。が、それはいつも、さらに数倍の執拗さをもって来る前ぶれのようなものだった。そしてその執拗さが満足されないと、彼女はきまってそのヒステリーを起した。そしてそのたびに、彼女の口から、例の「殺す」という言葉が出た。その言葉を聞くと、僕は奮然として、その席を起って出た。
かくして僕は彼女から三度ばかり絶交を申渡された。が、その翌日には、彼女はきっと謝まって帰って来るのだった。そしてその最後に謝まって来た時には、僕は彼女に、もう一週間熟考して見るがいいと言って、いったんそれを斥けた。彼女はその一週間が待てないで、その翌日また謝まって来た。
「しかし、こんどはもう、断然その絶交をこっちから申渡すんだ。」
僕は原稿紙を前に置いたまま、それにはただ「善政とは何ぞや」という題を書いただけで、独り言のように言った。
「こんどもし、君が殺すと言ったり、またそんな態度を見せた場合には、即刻僕は本当に君と絶交する。」
最後の仲直りの時に僕は彼女にそう言ったのだ。そして今、ゆうべ僕は、彼女の顔の中に確かに殺意を見たのだ。
五
彼女は散歩から帰って来た。僕は机に片肱をもたせかけて、熱でぽっぽとほてる頭を押えていた。彼女は僕が一行も書けないでいる原稿紙の上を冷やかにあざ笑うようにして見ていた。
夕飯を食うと、僕はまたすぐに寝床をしかして、横になった。彼女はしばらく無言で坐っていたが、やはりまたそばの寝床に寝た。僕はもうできるだけ何にも考えないようにして、ただ静かに眠ることだけを考えていた。が、長年の病気の経験から、熱のある時に興奮をさける、習慣のようになっているこの方法も成功しなかった。ふと僕はゆうべの彼女の恐ろしい顔を思い出した。
「ゆうべは無事だった。が、いよいよ今晩は僕の番だ。」
僕はそう思いながら、彼女がどんな兇器を持って来ているだろうかと想像して見た。彼女はよく一と思いに心臓を刺すと言っていた。刺すとなれば短刀だろう。が、彼女はそれをどこに持っているのだろう。彼女はごく小さな手提げを持っていた。しかし、あんな小さな手提げの中では、七、八寸ものでも隠せまい。すると彼女はそれを懐ろの中にでも持っているのかな。とにかく、刄物なら、何の恐れることもない。彼女がそれを振りあげた時にすぐもぎ取ってしまえばいいのだ。だが、もしピストルだと、ちょっと困る。どうせ、ろくに打ちようも知らないのだろうが、それにしてもあんまり間が近すぎる。最初の一発さえはずせば、もう何のこともないのだが、その一発がどうかすれば急所に当るかもしれない。しかし、それも滅多にはないことだろう。一発どこか打たして置いて、すぐ飛びかかって行けばいいのだ。女の一人や二人、何を持って来たって、何の恐れることがあるものか。すぐにとっちめて、ほうり出してしまえばいいのだ。
「ね、何か話ししない?」
一、二時間してからだろう。彼女は僕の方に向き直って、泣きそうにして話しかけた。彼女にはこの黙っているということが何よりもつらいのだ。寂しくて堪らないのだ。どなり合ってでも、何か話していたいのだ。そして今は、もう堪らなくなって、何もかもいっさい忘れたようになって、数日前の彼女と僕とに帰って話したかったのだ。
「してもいい。が、愚痴はごめんだ。」
「愚痴なんか言いやしないわ、だけど……」
「そのだけどが僕はいやなんだ。」
「そう、それじゃそれも止すわ。」
「それよりも、この一、二日以来のお互いの気持でも話そうじゃないか。僕はもう、こんな醜い、こんないやなことは飽き飽きだ。ね、お互いにもう、いい加減打ちきり時だぜ。」
「ええ、私ももう幾度もそう思っているの、だけど……」
「まただけどだね。そのだけどでいつも駄目になるんだ。こんどこそはもうそれを止しにしようじゃないか。」
「だけど、もっと話したいわ。」
「話はいくらでもするがいいさ。しかし、もう、お互いにこんないやな思いばかり続けていたって、仕方がないからね。本当にもう止しにしようよ。」
「ええ……」
彼女はまだ何か話したそうに見えた。が、その話のさきを一々僕に折られてしまうので、こんどは黙って何か考えているようだった。彼女がこうして折れて来ると、僕は彼女の持っている殺意にまで話を進めることができなくなった。そして僕はただ彼女のこの上折れて来ようとするのを防ごうとだけ考えた。
が、彼女はそれっきり黙ってしまった。僕も黙ってしまった。そして僕は、これだけのことでも言ったので多少胸がすいたものと見えて、何も考えないで静かに眠ったようにしていることに、こんどは成功した。
「ね、ね。」
それからまた一、二時間してのことだろう。彼女は僕を呼び起すように呼んだ。
「ね、本当にもう駄目?」
「駄目と言ったら駄目だ。」
「そう、私今何を考えているのか、あなた分る?」
「そんなことは分らんね。」
「そう、私今ね、あなたがお金のない時のことと、ある時のこととを考えているの。」
「というと、どういう意味だい?」
「野枝さんが綺麗な着物を着ていたわね。」
「そうか、そういう意味か。金のことなら、君にかりた分はあした全部お返しします。」
僕は彼女に金のことを言いだされてすっかり憤慨してしまった。
「いいえ、私そんな意味で……」
彼女は何か言いわけらしいことを言っていた。
「いや、金の話まで出れば、僕はもう君と一言もかわす必要はない。」
僕は断じてもう彼女の言いわけを斥けた。そして彼女がまだ二言三言何か言っているのも受けつけずに黙ってしまった。
いつでもあのくらい気持よく、しかも多くは彼女から進んで、出していた金のことを、今になって彼女が言いだそうとは、まったく僕には意外だった。そしてこの場合、金ができたから彼女を棄てるのだ、というような意味のことを言われるのも、まったく意外だった。そしてそれが意外なほど、僕は実に心外に堪えなかった。
金の出道は彼女には話してなかった。それも彼女には不平の一つらしかった。が、その頃にはもう、僕は彼女に同志としてのそれだけの信用がなかったのだ。僕はその金を時の内務大臣後藤新平君から貰って来たのだ。
その少し前に、伊藤がその遠縁の頭山満翁のところへ金策に行ったことがあった。翁は今金がないからと言って杉山茂丸君のところへ紹介状を書いた。伊藤はすぐ茂丸君を訪ねた。茂丸君は僕に会いたいと言いだした。で、僕は築地のその台華社へ行った。彼は僕に「白柳秀湖だの、山口孤剣だののように、」軟化をするようにと勧めた。国家社会主義くらいのところになれと勧めた。そうすれば、金もいるだけ出してやる、と言うのだ。僕はすぐその家を辞した。
茂丸君は無条件では僕に一文も金をくれなかった。が、その話の間に時々出た「後藤が」「後藤が」という言葉が、僕にある一案を暗示してくれた。ある晩僕は内務大臣官邸に電話して、後藤がいるかいないかを聞き合わした。後藤はいた。が、今晩は地方長官どもを招待して御馳走をしているので、何か用があるなら明日にしてくれとのことだった。
「なあに、いさえすればいいのだ。」
僕はそう思いながらすぐ永田町へ出かけた。
「御覧の通り、今晩はこんな宴会中ですから……」
たぶん菊池とかいう秘書官らしい男が僕の名刺を持って挨拶に出て来た。
「いや、それは知って来ているんです。とにかく後藤にその名刺を取り次いで、ほんのちょっとの時間でいいから会いたい、と言って貰えばいいんです。」
秘書官は引っこんで行った。そしてすぐにまた出て来て、「どうぞ、こちらへ」と案内した。
宴会は下のようだったが、僕は二階のとっつきのごく小さな室へ案内された。テーブルが一つに椅子が三つばかり置いてあるだけで、飾りというほどの飾りもない室だった。
すぐに給仕がお茶を持って来た。が、その給仕はお茶をテーブルの上に置くと、ドアの右手と正面とにある三つばかりの窓を、一々開けては鎧戸をおろしてまた閉めて行った。変なことをするなと思っていると、こんどは左手の壁の中にあるドアを開けて、さっきの秘書官がはいって来た。
「今すぐ大臣がお出でですから。」
彼はそう言って、出はいり口のドアをいったん開けて見てまた閉めて、それにピチンと鍵をおろした。
「ははあ、何か間違いでもあった時に、僕が逃げられない用心をしているんだな。」
僕は笑いたいのをこらえて、黙って彼の処作を見ていた。彼はさっき給仕が閉めた窓のところへ行って、一々それに窓掛けをおろして、そして丁寧にお辞儀をしてまた隣りの室との間のドアの向うに消えた。
「すると、後藤はあのドアからはいって来るんだな。」
僕はそう思って、そのドアの方に向って、煙草をくゆらして待っていた。
が、待っているというほどもなく、すぐ後藤がはいって来た。新聞の写真でよく見ていた、鼻眼鏡とポワンテュの鬚との、まぎれもない彼だ。
「よくお出ででした。いや、お名前はよく存じています。私の方からも是非一度お目にかかりたいと思っていたのでした。きょうはこんな場合ではなはだ失礼ですが、しかし今ちょうど食事もすんで、ちょっとの間なら席をはずしてもおれます。私があなたに会って、一番さきに聞きたいと思っていたことは、どうしてあなたが今のような思想を持つようになったかです。どうです、ざっくばらんに一つ、その話をしてくれませんか。」
少々赤く酔を出している後藤は、馬鹿にお世辞がよかった。
「え、その話もしましょう。が、今日は僕の方で別に話を持って来ているのです。そしてその方が僕には急なのだから、今日はまずその話だけにしましょう。」
「そうですか。するとそのお話というのは?」
「実は金が少々欲しいんです。で、それを、もし戴ければ戴きたいと思って来たのです。」
「ああ金のことですか。そんなことならどうにでもなりますよ。それよりも一つ、さっきのお話を聞こうじゃありませんか。」
「いや、僕の方は今日はこの金の方が重大問題なんです。どうでしょう。僕今非常に生活に困っているんです。少々の無心を聞いて貰えるでしょうか。」
「あなたは実にいい頭を持ってそしていい腕を持っているという話ですがね。どうしてそんなに困るんです。」
「政府が僕等の職業を邪魔するからです。」
「が、特に私のところへ無心に来た訳は。」
「政府が僕等を困らせるんだから、政府へ無心に来るのは当然だと思ったのです。そしてあなたならそんな話は分ろうと思って来たんです。」
「そうですか、分りました。で、いくら欲しいんです。」
「今急のところ三、四百円あればいいんです。」
「ようごわす、差しあげましょう。が、これはお互いのことなんだが、ごく内々にして戴きたいですな。同志の方にもですな。」
「承知しました。」
金の出道というのは要するにこうなのだ。そして僕は三百円懐ろにして家に帰った。
その金は、しばらく金をちっとも持って行っていない保子のところへ五十円行き、なおもうぼろぼろになった寝衣一枚でいる伊藤に三十円ばかりでお召の着物と羽織との古い質を受けださせて、まだ二百円は残っていた。それにもう五十円足せば、市外に発行所を置くとすれば、月刊雑誌の保証金には間に合うのだ。
「が、もう雑誌なぞはどうでもいい。あしたはその金を伊藤に持って来て貰って、こいつに投げつけてやるんだ。」
僕は一人でそう決心した。
また、彼女が伊藤の着物のことを言いだしたのから思いだすと、ふだん人の着物なぞにちっとも注意しない彼女が、そういえば伊藤の風ていをじろじろと見ていた。彼女はもう大ぶ垢じみたメリンスの袷(それとも単衣だったか)に木綿の羽織を着ていた。
「そうそう、彼女はいつか僕にいくらかの金をつくるために、その着物を質に入れていたのだっけ。せめてはあれだけでも出して置いてやるのだった。」
と僕も気がついた。が、今になってそんな気がついたところで仕方がない。
「とにかくあしたは、あいつに金を投げつけてやるんだ。」
六
少しうとうとしていると、誰かが僕の布団にさわるような気がした。
「何をするんだ?」
僕はからだを半分僕の布団の中に入れようとしている彼女を見てどなった。
「(十二字削除)。」
彼女は、その晩初めて口をききだした時と同じように、泣きそうにして言った。
「いけません、僕はもうあなたとは他人です。」
「でも、私悪かったのだから、あやまるわ、ね、話して下さいね。ね、いいでしょう。」
「いけません。僕はそういうのが大きらいなんです。さっきはあんなに言い合って置いて、その話がつきもしない間に、そのざまは何ていうことです。」
僕は彼女の訴えるような、しかしまた情熱に燃えるような目を手で斥けるようにしてさえぎった。彼女のからだからはその情熱から出る一種の臭いが発散していた。
ああ彼女の肉の力よ。僕は彼女との最初の夜から、彼女の中にそれをもっとも恐れかつ同時にそれにもっとも引かれていたのだ。そして彼女は、そのヒステリカルな憤怒の後に、その肉の力をもっとも発揮するのだった。
しかし今晩はもう、僕は彼女のこの力の中に巻きこまれなかった。僕は彼女のこの力を感ずると同時に、なおさらに奮然としてそれに抵抗して起った。今晩の彼女の態度は、初めからそのふだんの執拗さや強情の少しもない、むしろ実にしおらしいおとなしい態度だった。が、このしおらしさが、彼女の手といってもいいくらいに、こうした場合にはきっと出て来るのだった。が、僕は最初からそれを峻拒していた。
彼女は決然として自分の寝床に帰った。そしてじっとしたまま寝ているようだった。
僕はいよいよだなと思った。こんどこそは本当にやるのだろうと思った。僕は仰向きになったまま両腕を胸の上に並べて置いて、いつでも彼女が動いたらすぐに起ちあがる準備をして、目をつぶったまま息をこらしていた。一時間ばかりの間に彼女は二、三度ちょっとからだを動かした。そのたびに僕は拳をかためた。
が、やがて彼女は起き出して来た。そして僕の枕もとの火鉢のそばに坐りこんだ。
僕はこれは具合が悪いなと思った。横からなら、どうにでもして防げるのだが、頭の方からではどうしても防ぎようがないと思った。しかし、今さら、こっちも起きるのも強ばらだと思った。ピストルで頭をやられてはちょっと困ると思ったが、しかし刃物なら何とか防ぎようがあると思った。ピストルはそう急に彼女の手にはいるまい。だから、兇器はきっと刃物だろうと思った。
「しかし、どんなことがあっても、こんどは決して眠ってはならない。眠れば、僕はもうお終いなのだ。」
僕はそう決心して、やはり前のように目をつぶったまま両腕を胸の上に並べて、息をすまして、頭の向うでの呼吸を計っていた。その時、どこかで時計が三時を打つのを聞いた。僕はやはり息をすまして向うの動静を計っていた。
ふと僕は、咽喉のあたりに、熱い玉のようなものを感じた。
「やられたな。」
と思って僕は目をさました。いつの間にか、自分で自分の催眠術にかかって、眠ってしまっていたのだ。
「熱いところを見ると、ピストルだな。」
と続いて僕は思った。そして前の方を見ると、彼女は障子をあけて、室のそとへ出て行こうとしていた。
「待て!」
と僕は叫んだ。
彼女はふり返った。
(これで僕は最初に話したお化のところまで戻った訳だ。そのお化の因縁話をすました訳だ。が、事件はまだ続く。僕はそれもすっかり話してしまわなければ、僕の責めは済まないだろう。で、もっと話を続けて行こう。)
彼女はふり返った。
僕はその前夜彼女が寝ている伊藤をにらみつけた、その恐ろしい殺気立った顔を見ると思いのほか、彼女がゆうべ僕に泣きついて来た時のその顔よりももっと憐れな顔を見た。
「許して下さい。」
彼女がふり向くと同時に発したこの言葉が僕には意外だった。
しかし、もうこうなった以上、僕は彼女を許すことができなかった。少なくともその瞬間の僕は、何という理窟はなしに、ただ彼女を捕まえてそこへ叩きつけなければやまなかった。
僕は起きあがった。そして逃げようとする彼女を追うて縁がわまで出た。彼女はそこの梯子を走り下りた。僕も続いて走り下りた。そして中途で僕は彼女の背中へ飛び降りるつもりで飛んだ。が、彼女の方がほんの一瞬間だけ早かった。彼女は下の縁がわを右の方へ駆けて、七、八間向うの玄関のところからさらに二階の梯子段を登った。僕は梯子段を飛び下りた時から、急に足の裏の痛みと呼吸のひどく困難になって来たのを感じながら、なお彼女を追っかけて行った。
その二階は、僕の居室の方の二階とは棟が違っていて、大きな二つの室の奥の方が、その夜は宿の親戚の女どもの寝室になっていた。彼女はその手前の室の中にはいって、紫檀の茶ぶ台の向うに立ちどまった。
「許して下さい。」
彼女は恐怖で慄えながらまた叫んだ。
が、僕はその茶ぶ台の上を踏み越えて彼女を捕まえようとした。彼女はまた走り出した。その奥に寝ていた女どもは目をさまして、互いにかじりついて、僕等の方を見つめながら慄えていた。
僕は呼吸困難で咽喉がひいひい鳴るのを覚えながら、なお彼女を追っかけて行った。彼女はさっきの梯子段を降りて、廊下をもとの方へ走って、もとの二階へは昇らずに、そこから左の方へ便所の前に折れた。そしてその折れた拍子に彼女は倒れた。僕も彼女の上に重なって倒れた。
僕はそれから幾分たったか知らない。ふと気がついて見ると、血みどろになって一人でそこに倒れていた。呼吸はもう困難どころではなくほとんど窮迫していた。
「これはいけない。」
と僕は思いながら、ようやく壁につかまって起ちあがって、玄関の方へよろめいて行った。玄関のそばには女中部屋があった。僕は女中を起して医者を呼びにやろうと思ったのだ。が、その女中部屋の前で僕はまた倒れてしまった。そして倒れると同時に、その板の間が血でどろどろしているのを感じた。
女中は呼んでも返事がなかった。みんな二階の親戚の客におどかされて、一緒に奥の方へ逃げこんでいたのだ。しばらくして、その親戚の一人の年増の女がおずおずとそばへ来た。
「あのね、すぐ医者を呼んで下さい。それから東京の伊藤のところへすぐ来るように電話をかけて下さい。それからもう一つ、神近の姿が見えないんだが、どうかすると自殺でもするかも知れないから、誰か男衆に海岸の方を見さして下さい。」
僕はこれだけのことを相変らず咽喉をひいひい鳴らしながら、ようやくのことで言った。そして僕は煙草を貰って、その咽喉の苦しさをごまかしていた。傷はピストルではなく、刃物だということもその時にようやく分った。
やがて、どやどやと警官どもがはいって来た。そしてその一人はすぐと僕に何か問い尋ねようとした。
「馬鹿! そんなことよりもまず医者を呼べ。医者が来ない間は貴様等には一言も言わない。」
僕はその男をどなりつけながら、頭の上の柱時計を見た。三時と三十分だった。
「すると、眠ってからすぐなのだ。」
と僕は自分に言った。
それから十分か二十分かして、僕は自動車で、そこからいくらもない逗子の千葉病院に運ばれた。そしてすぐ手術台の上に横たわった。
「長さ……センチメートル、深さ……センチメートル。気管に達す……。」
院長が何か傷の中に入れながら、助手や警官等の前で口述するのを聞きながら、僕は、
「きょうの昼までくらいの命かな」
と、ちょっと思ったまま、そのまま深い眠りに陥ってしまった。