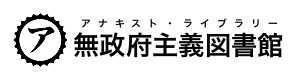この作品と「死生」の内容は、ほぼ同じです。(青空文庫より)
幸徳秋水
死刑の前
第一章 死生
第二章 運命
第三章 道徳―罪悪
第四章 半生の回顧
第五章 獄中の回顧
第一章 死生
一
わたくしは、死刑に処せらるべく、いま東京監獄の一室に拘禁されている。
ああ、死刑! 世にある人びとにとっては、これほどいまわしく、おそろしい言葉はあるまい。いくら新聞では見、ものの本では読んでいても、まさかに自分が、このいまわしい言葉と、眼前直接の交渉を生じようと予想した者は、
平生わたくしを愛してくれた人びと、わたくしに親しくしてくれた人びとは、かくあるべしと聞いたときに、どんなにその真疑をうたがい、まどったであろう。そして、その真実なるをたしかめえたときに、どんなに情けなく、あさましく、かなしく、恥ずかしくも感じたことであろう。なかでも、わたくしの老いたる母は、どんなに絶望の
されど、今のわたくし自身にとっては、死刑はなんでもないのである。
わたくしが、いかにしてかかる重罪をおかしたのであるか。その公判すら傍聴を禁止された今日にあっては、もとより、十分にこれをいうの自由はもたぬ。百年ののち、たれかあるいはわたくしに代わっていうかも知れぬ。いずれにしても、死刑そのものはなんでもない。
これは、放言でもなく、壮語でもなく、かざりのない真情である。ほんとうによくわたくしを解し、わたくしを知っていた人ならば、またこの真情を察してくれるにちがいない。堺利彦は、「非常のこととは感じないで、なんだか自然の成り行きのように思われる」といってきた。小泉三申は、「幸徳もあれでよいのだと話している」といってきた。どんなに絶望しているだろうと思った老いた母さえ、すぐに「かかる成り行きについては、かねて覚悟がないでもないからおどろかない。わたくしのことは心配するな」といってきた。
死刑! わたくしには、まことに自然の成り行きである。これでよいのである。かねての覚悟あるべきはずである。わたくしにとっては、世にある人びとの思うがごとく、いまわしいものでも、おそろしいものでも、なんでもない。
わたくしが死刑を期待して監獄にいるのは、瀕死の病人が、施療院にいるのと同じである。病苦がはなはだしくないだけ、さらに楽かも知れぬ。
これはわたくしの性の
二
万物はみなながれさる、とへラクレイトスもいった。諸行は無常、宇宙は変化の連続である。
その
これは、太陽の運命である。地球およびすべての遊星の運命である。まして地球に生息する一切の有機体をや。細は細菌より、大は大象にいたるまでの運命である。これは、天文・地質・生物の諸科学が、われらにおしえるところである。われら人間が、ひとりこの拘束をまぬがれることができようか。
いな、人間の死は、科学の理論を待つまでもなく、実に平凡なる事実、時々刻々の眼前の事実、なんびともあらそうべからざる事実ではないか。死のきたるのは、一個の例外もゆるさない。死に面しては、貴賎・貧富も、善悪・邪正も、知恵・賢不肖も、平等一如である。なにものの知恵も、のがれえぬ。なにものの威力も、抗することはできぬ。もしどうにかしてそれをのがれよう、それに抗しようと、くわだてる者があれば、それは、ひっきょう痴愚のいたりにすぎぬ。ただこれは、東海に不死の薬をもとめ、バベルに昇天の塔をきずかんとしたのと、同じ
なるほど、天下多数の人は、死を恐怖しているようである。しかし、彼らとても、死のまぬがれぬのを知らぬのではない。死をさけられるだろうとも思っていない。おそらくは、彼らのなかに一人でも、永遠の命はおろか、大隈伯のように、百二十五歳まで生きられるだろうと期待し、生きたいと希望している者すらあるまい。いな、百歳・九十歳・八十歳の寿命すらも、まずはむつかしいとあきらめているのが多かろうと思う。はたしてそうならば、彼らは単純に死を恐怖して、どこまでもこれをさけようともだえる者ではない。彼らは、明白に意識せるといなとは別として、彼らの恐怖の原因は、別にあると思う。
すなわち、死ということにともなう諸種の事情である。その二、三をあげれば、(第一)天寿をまっとうして死ぬのでなく、すなわち、自然に老衰して死ぬのでなくして、病疾その他の原因から夭折し、当然うけるであろう、味わうであろう生を、うけえず、味わいえないのをおそれるのである。(第二)来世の迷信から、その妻子・眷属にわかれて、ひとり死出の山、
いちいちにかぞえきたれば、その種類はかぎりもないが、要するに、死そのものを恐怖すべきではなくて、多くは、その個々が有している迷信・貪欲・痴愚・妄執・愛着の念をはらいがたい境遇・性質等に原因するのである。故に見よ。彼らの境遇や性質が、もしひとたび改変せられて、これらの事情から解脱するか、あるいはこれらの事情を圧倒するにいたるべき他の有力なる事情が
死は、
なるほど、人間、いな、すべての生物には、自己保存の本能がある。栄養である。生活である。これによれば、人はどこまでも死をさけ、死に抗するのが自然であるかのように見える。されど、一面にはまた
この二者は、古来氷炭相容れざるもののごとくに考えられていた。また事実において、しばしば矛盾もし、衝突もした。しかし、この矛盾・衝突は、ただ四囲の境遇のためによぎなくせられ、もしくは養成せられたので、その本来の性質ではない。いな、彼らは、完全に一致・合同しうべきもの、させねばならぬものである。動物の群集にもあれ、人間の社会にもあれ、この二者のつねに矛盾・衝突すべき事情のもとにあるものは滅亡し、一致・合同しえたるものは繁栄していくのである。
そして、この一致・合同は、つねに自己保存が種保存の基礎であり、準備であることによっておこなわれる。豊富なる生殖は、つねに健全なる生活から出るのである。かくて新陳代謝する。種保存の本能が、大いに活動しているときは、自己保存の本能は、すでにほとんどその職分をとげているはずである。果実をむすばんがためには、花はよろこんで散るのである。その児の生育のためには、母はたのしんでその心血をしぼるのである。年少の者が、かくして自己のために死に抗するのも自然である。長じて、種のために生をかろんずるにいたるのも、自然である。これは、矛盾ではなくして、正当の順序である。人間の本能は、かならずしも正当・自然の死を恐怖するものではない。彼らは、みなこの運命を甘受すべき準備をなしている。
故に、人間の死ぬのは、もはや問題ではない。問題は、実に、いつ、いかにして死ぬかにある。むしろ、その死にいたるまでに、いかなる生をうけ、かつ送ったかにあらねばならない。
三
いやしくも、狂愚にあらざる以上、なんびとも永遠・無窮に生きたいとはいわぬ。しかも、死ぬなら天寿をまっとうして死にたいというのが、万人の望みであろう。一応は無理からぬことである。
されど、天命の寿命をまっとうして、疾病もなく、負傷もせず、老衰の極、油つきて火の滅するごとく、自然に死に帰すということは、その実はなはだ困難のことである。なんとなれば、これがためには、すべての疾病をふせぎ、すべての災禍をさけるべき完全な注意と方法と設備とを要するからである。今後、幾百年かの星霜をへて、文明はますます進歩し、物質的には公衆衛生の知識がいよいよ発達し、一切の公共の設備が安固なのはもとより、各個人の衣食住もきわめて高等・完全の域に達すると同時に、精神的にもつねに平和・安楽であって、種々の憂悲・苦労のために心身をそこなうがごときことのない世の中となれば、人はたいていその天寿をまっとうすることを得るであろう。わたくしは、かような世の中が、一日も早くきたらんことをのぞむのである。が、すくなくとも、今日の社会、東洋第一の花の都には、地上にも空中にも、おそるべき病菌が充満している。汽車・電車は毎日のように衝突したり、人をひいたりしている。米と株券と商品の相場は、刻々に乱高下している。警察・裁判所・監獄は、多忙をきわめている。今日の社会においては、もし疾病なく、傷害なく、真に自然の死をとげうる人があるとすれば、それは、希代の偶然・僥倖といわねばならぬ。
実際、いかに絶大の権力を有し、百万の富を
いな、わたくしは、はじめよりそれをのぞまないのである。わたくしは、長寿かならずしも幸福ではなく、幸福はただ自己の満足をもって生死するにありと信じていた。もしまた人生に、社会的
天寿はとてもまっとうすることができぬ。ひとり自分のみでなく、天下の多数もまたそうである。そして、単に天寿をまっとうすることが、かならずしも幸福でなく、かならずしも価値あるものでないとすれば、われらは、病死その他の不自然の死を甘受するのほかはなく、また甘受するのがよいではないか。ただわれらは、いかなるとき、いかなる死でもあれ、自己が満足を感じ、幸福を感じて死にたいものと思う。そして、その生においても、死においても、自己の分相応の善良な感化・影響を社会にあたえておきたいものだと思う。これは、大小の差こそあれ、その人びとの心がけ次第で、けっしてなしがたいことではないのである。
不幸、短命にして病死しても、正岡子規君や清沢満之君のごとく、餓しても伯夷や杜少陵のごとく、凍死しても深草少将のごとく、溺死しても佐久間艇長のごとく、焚死しても快川国師のごとく、震死しても藤田東湖のごとくであれば、不自然の死も、かえって感嘆すべきではないか。あるいは道のために、あるいは職のために、あるいは意気のために、あるいは恋愛のために、あるいは忠孝のために、彼らは、生死を超脱した。彼らは、おのおの生死もまたかえりみるにたりぬ大きなあるものを有していた。こうして、彼らのある者は、満足にかつ幸福に感じて死んだ。そして、彼らのあるものは、その生死ともに、すくなからぬ社会的価値を有しえたのである。
如意輪堂の扉にあずさ弓の歌を書きのこした楠
もし赤穂浪士をゆるして死をたもうことがなかったならば、彼ら四十七人は、ことごとく光栄ある余生を送って、終りをまっとうしえたであろうか。そのうち、あるいは死よりも劣った不幸の人、もしくは醜辱の人を出すことがなかったであろうか。生死いずれが彼らのために幸福であったか。これは問題である。とにかく、彼らは、一死を
人生、死に所を得ることはむつかしい。正行でも重成でも主税でも、短命にして、かつ生理的には不自然の死であったが、それでも、よくその死に所を得たもの、とわたくしは思う。その死は、彼らのために悲しむよりも、むしろ、賀すべきものだと思う。
四
そうはいえ、わたくしは、けっして長寿をきらって、無用・無益とするのではない。命あっての
伊能
このように非凡の健康と精力とを有して、その寿命を人格の
しかも、前にいったごとくに、こうした天稟・素質をうけ、こうした境界・運命に
けだし、人が老いてますますさかんなのは、むろん例外で、ある
力士などは、そのもっともいちじるしい例である。文学・芸術などにいたっても、不朽の傑作といわれるものは、その作家が老熟ののちよりも、かえってまだ大いに名をなしていない時代に多いのである。革命運動などのような、もっとも熱烈な信念と意気と大胆と精力とを要するの事業は、ことに少壮の士に待たねばならぬ。古来の革命は、つねに青年の手によってなされたのである。維新の革命に参加してもっとも力のあった人びとは、当時みな二十代から三十代であった。フランス革命の
そして、この働きざかりのときにおいて、あるいは人道のために、あるいは事業のために、あるいは恋愛のために、あるいは意気のために、とにかく、自己の生命より重いと信ずるあるもののために、力のかぎり働いて、倒れてのちやまんとすることは、まず死に所を得たもので、その社会・人心に影響・印象するところも、けっしてあさからぬのである。これ、なんびとにとっても、満足すべきときに死ななければ、死にまさる恥があると。げんにわたくしは、その死に所をえなかったために、気の毒な生き恥をさらしている多くの人びとを見るのである。
一昨年の夏、ロシアより帰国の途中物故した長谷川二葉亭を、朝野こぞって哀悼したころであった。杉村楚人冠は、わたくしにたわむれて、「君も先年アメリカへの往きか返りかに船のなかででも死んだら、えらいもんだったがなァ」といった。彼の言は、
故に、短命なる死、不自然なる死ということは、かならずしも嫌悪し、哀弔すべきではない。もし死に、嫌悪し、哀弔すべきものがあるとすれば、それは、多くの不慮の死、覚悟なきの死、安心なき死、諸種の妄執・愛着をたちえぬことからする心中の憂悶や、病気や負傷よりする肉体の痛苦をともなう。いまやわたくしは、これらの条件以外の死をとぐべき運命をうけえたのである。
天寿をまっとうするのは、今の社会ではなんびとにとっても至難である。そして、もし満足に、幸福に、かつできうべくんば、その人の分相応――わたくしは分外のことを期待せぬ――の社会価値を有して死ぬとすれば、病死も、餓死も、凍死も、溺死も、震死も、轢死も、縊死も、負傷の死も、窒息の死も、自殺も、他殺も、なんの哀弔し、嫌忌すべき理由もないのである。
それならば、すなわち、刑死はどうか。その生理的に不自然なことにおいて、これら諸種の死となんの異なるところがあろうか。これら諸種の死よりも、さらに嫌悪し、哀弔すべき理由があるであろうか。
五
死刑は、もっともいまわしく、おそるべきものとされている。しかし、わたくしには、単に死の方法としては、病死その他の不自然と、はなはだえらぶところはない。そして、その十分な覚悟をなしうることと、肉体の苦痛をともなわぬことは、他の死にまさるともおとるところはないのではないか。
それならば、世人がそれをいまわしく、おそるべしとするのは、なに故であろぅか。いうまでもなく、死刑に処せられるのは、かならず極悪の人、重罪の人であることをしめすものだ、と信ずるが故であろう。死刑に処せられるほどの極悪・重罪の人となることは、家門のけがれ、末代の恥辱、親戚・朋友のつらよごしとして、忌みきらわれるのであろう。すなわち、その恥ずべく、忌むべく、恐るべきは、刑で死ぬということにあるのではなくて、死者その人の極悪の性質、重罪のおこないにあるのではないか。
フランス革命の
死刑が極悪・重罪の人を目的としたのは、もとよりである。したがって、古来多くの恥ずべく、忌むべく、おそるべき極悪・重罪の人が、死刑に処せられたのは、事実である。けれど、これと同時に多くのとうとぶべく、敬すべく、愛すべき善良・賢明の人が死刑に処せられたのも、事実である。そして、はなはだ尊敬すべき善人ではなくとも、またはなはだ嫌悪すべき悪人でもない多くの小人・凡夫が、あやまって時の法律にふれたために――単に一羽の鶴をころし、一頭の犬をころしたということのためにすら――死刑に処せられたのも、また事実である。要するに、刑に死する者が、かならずしも極悪の人、重罪の人のみでなかったことは、事実である。
石川五右衛門も国定忠治も、死刑となった。平井権八も鼠小僧も、死刑となった。白木屋お駒も八百屋お七も、死刑となった。ペロプスカヤもオシンスキーも、死刑となった。王子比干や
スペインに宗教裁判がもうけられていた当時を見よ。
こう見てくれば、死刑は、もとより時の法度にてらして課されたものが多くをしめているのは、論のないところだが、なんびとかよく世界万国有史以来の厳密な統計をもとにして、死刑はつねに恥辱・罪悪にともなうものだと断言しうるであろうか。いな、死刑の意味する恥辱・罪悪は、その有している光栄もしくは冤枉よりも多いということすらも、断言しうるであろうか。これぞ、実に一個未決の問題である、とわたくしは思う。
故に、今のわたくしに、恥ずべく、忌むべく、おそるべきものがあるとすれば、それは、死刑に処せられるということではなくて、わたくしが悪人であり、罪人であるということにあらねばならぬ。これは、わたくし自身が論ずべきかぎりではなく、また論ずる自由をもってはいない。ただ死刑ということ、そのことは、わたくしにとって、なんでもない。
思うに、人に死刑にあたいするほどの犯罪があるであろうか。死刑は、はたして刑罰として当をえたものであろうか。古来の死刑は、はたして刑罰の目的を達することにおいて、よくその効果を奏したか、ということは、学者のひさしくうたがうところで、これまた、未決の一大問題として存している。けれども、わたくしは、ここで死刑の存廃を論ずるのではない。今のわたくし一個人としては、その存廃を論ずるほどに死刑を重大視してはいない。病死その他の不自然な死が来たのと、はなはだ異なるところはない。
無常迅速・生死事大、と仏家はしきりにおどしている。生は、ときとしては大いなる幸福ともなり、またときとしては大なる苦痛ともなるので、いかにも事大にちがいない。しかし、死がなんの事大であろう。人間の血肉の新陳代謝がまったくやすんで、形体・組織が分解しさるのみではないか。死の事大ということは、太古より知恵ある人がたてた一種のカカシである。地獄・極楽の蓑笠つけて、愛着・妄執の弓矢をはなさぬ姿は、はなはだものものしげである。漫然と遠くからこれをのぞめば、まことに意味ありげであるが、近づいて仔細にこれを見れば、なんでもないのである。
わたくしは、かならずしもしいて死を急ぐ者ではない。生きられるだけは生きて、内には生をたのしみ、生を味わい、外には世益をはかるのが当然だと思う。さりとてまた、いやしくも生をむさぼろうとする心もない。病死と横死と刑死とを問わず、死すべきのときがひとたびきたなら、十分の安心と満足とをもって、これにつきたいと思う。
いまやすなわち、そのときである。これが、わたくしの運命である。以下すこしくわたくしの運命観を語りたいと思う。